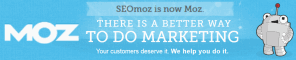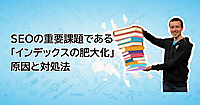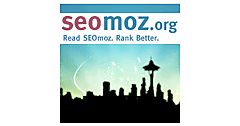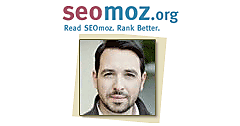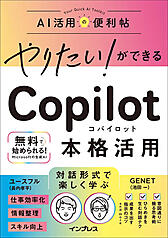YOUmozに載せるのが適当かどうかわからないけど、このコミュニティに来て間もない人には有益な情報に違いないと思い、投稿することにした。おそらく間違っているところもあると思うので、各項目の内容に文句がある人もいるだろう。間違いや抜けを指摘するコメントは歓迎だ。
数字
- 301
- 恒久的なサーバーリダイレクト。Apacheサーバーの.htaccessファイルに記述したウェブページのアドレス変更のこと。正規版サイト公開時のURL変更問題を処理するのにも便利。
A
- AdWords
- アドワーズ広告を参照。
- AdWordsサイト
- MFAと同義。GoogleのAdWords広告掲載プログラムAdsense用に作成したページのこと。広告掲載だけを意図して設計したウェブサイト。必ずしも悪くはないが、一般的には良くない。テレビ番組なんかは、多くの場合広告目的だね。
- altテキスト
- 代替テキストを参照。
B
- B2B
- 企業間の商取引。
- B2C
- 企業と消費者間の商取引。
C
- CGC
- ユーザー生成コンテンツを参照。
- CGM
- ユーザー生成コンテンツを参照。
- CMS
- Content Management Systemの略。コンテンツ管理システムを参照。
- CPC(Cost Per Click)
- クリック単価の略。掲載した広告のクリック数で料金が発生する広告システムの広告料単価のこと。
- CPM(Cost Per Thousand impression)
- 広告露出回数に基づいて料金が発生する広告システムの広告料基準のこと。Mとはローマ数字で千を表す。
E
- eコマースサイト
- 小売業を専門に行うウェブサイト。
F
- FFA(Free For All)
- 関連性のない外部サイトへのリンクを多数掲載したページやサイト。独自のコンテンツがあったとしても、それはごくわずか。リンクファームは検索エンジンのスパイダーだけを対象にしたもので、人間にはほとんど価値がない(それすらもしあればの話)。そのため、検索エンジンの注意は向かず、ペナルティーを受けることもある。
「Free For All」は文字通り訳すと「どなたさまでもご自由にどうぞ」という意味。
G
- Googlebot
- Googleのスパイダープログラム。ボットも参照。
- Googleジュース
- 信用、オーソリティ、PageRankの総称。Googleから受け取る信用あるいはオーソリティのこと。外部向けリンクを通じて、他のサイトにも移っていく。
- Googleダンス
- Googleがデータベースやアルゴリズムを更新することにより、検索結果の順位が変動すること。ウェブマスターが検索結果を見て、強い不安を感じたりびっくり仰天するのはこれのせい。または、Googleのデータセンター間でデータが一致しない際、Googleのインデックス更新が発生している期間のこと。
- Google爆弾
- 複数のウェブマスターが力を合わせ、Googleの検索結果に変化を与え、一般的にはユーモラスな効果をもたらすように取り組む行為のこと。「miserable failure(ダメ人間)」でジョージ・ブッシュや、「greatest living American(もっとも偉大な存命のアメリカ人)」でスティーブン・コルバートといった例が有名だ。
- Googleボウリング
- あるサイトのランクを下げるため、わざと「悪い隣人」からリンクを張ること。スクールバスから降りるときに、友達に向かって「えんがちょ!」と叫ぶようなもの。果して本当に影響があるのか、ただのSEO的な都市伝説なのか、議論が絶えない。
- GYM
- Google、Yahoo!、Microsoftの頭文字。要するに検索業界の大手3社。
H
- HTML
- ハイパーテキストマークアップ言語の略。インターネットで用いるプレーンテキストに、フォーマットやウェブ機能を与える指示子または「マークアップ」の集合。HTMLは、検索エンジンにとって母語といえる。一般論として、ウェブページは厳格にHTMLだけに準拠するべきだ。
L
- LSI(Latent Semantic Indexing)
- 潜在型意味的インデックス化。この長ったらしい言葉は、検索エンジンが文書中にある一連の言葉を結びつけてインデックス化することを指す。SEOではこうした単語の集合を「ロングテール検索」という。検索語の大部分は3単語以上のフレーズだ。ロングテールも参照のこと。「抵当 (mortgage)」という言葉で上位ランクを得るのはほとんど不可能かもしれないが、「大型トラックチームに融資する第二順位抵当(second mortgage to finance monster truck team)」というフレーズならとても簡単というわけ。面白いね。
M
- METAタグ
- HTMLページのHEADセクションに記述するタグで、ページに関する情報を記すもの。METAタグの情報は検索結果画面に現れる可能性があるが、そのページ自体には出てこない。METAタグで記述するタイトルと説明は、独自性がありなおかつ正確な情報にすることが非常に重要だ。なぜなら、検索エンジンがそのページの内容を判断するのに、これをいちばん頼りにするからだ。またこの情報は、検索結果において第1印象をユーザーに与えるものでもある。
- MFA
- 広告用に作成したページやサイトという意味。根本から完全に広告掲載用として設計したページのこと。必ずしも悪くはないが、一般的には良くない。広告目的の好例がテレビ番組。
「MFA」は「Made for AdSense」、つまり「アドセンスのために作られた」という意味で、情報を公開するためではなく広告をクリックするためだけに作られたサイトを指す。
N
- nofollow
- ウェブページのHEADセクションに配置するMETAタグや、リンクタグに記述できるコマンド。検索エンジンスパイダーにそのページのリンク、あるいは特定のリンクを辿らないよう支持するもの。リンクコンドームの一種。
- noindex
- ウェブページのHEADセクションに配置するMETAタグや、リンクタグに記述できるコマンド。検索エンジンスパイダーに、該当のページやリンク先をインデックス化しないよう指示する。リンクコンドームの一種。
P
- PageRank
- PRとも表記する。Googleのアルゴリズムによって決定する与えられる0から1の値。リンク人気度と信用度を他の(独自の)要素とともに定量化する。ツールバーページランクと間違われることがたまにある。
この解説はMichael Martinez氏の助言により改訂した。 - PPA(Pay Per Action)
- 成果報酬型広告の略。クリック課金とよく似ているが、クリックがコンバージョン(何かしら具体的な消費者行動)につながった場合だけ料金が発生する。
- PPC(Pay Per Click)
- キーワード広告と同義。クリック課金広告の略。ユーザーが広告をクリックした数に合わせて、広告主が(Googleなどの)広告サービス業者に広告料を支払う。検索連動やコンテンツ連動を含むキーワード連動型広告で一般的な仕組み。Yahoo!(オーバーチュア)のスポンサードサーチやグーグルのアドワーズ広告がクリック課金広告の代表選手。
R
- RLT
- 地域的ロングテールを参照。
- robots.txt
- ウェブサイトのルートディレクトリに配置するファイル。検索エンジンスパイダーの動作の制限や制御を行う。
- ROI(Return On Investment)
- 投資対費用効果の略。解析ソフトウェアの用法の1つは、投資対費用効果を定量化し、方法ごとのコスト/利益を割り出すこと。
S
- SE(Search Engine)
- 検索エンジンの略。
- SEM(Search Engine Marketing)
- 検索エンジンマーケティングの略。ウェブサイトの露出をできるだけ多くするために、ウェブサイトの調査、提案、検索エンジンにおける地位向上などに伴う活動を指すことが多い。SEMには、検索エンジン最適化や有料登録など、ウェブサイトの露出とトラフィックを増やすための、検索エンジン関連サービスおよび機能などがある。
- SEO(Search Engine Optimization)
- 検索エンジン最適化の略。検索結果で高位ランクを得て、ウェブサイトへのビジターを増やす作業を指す。検索結果でウェブサイトの表示順位が高ければ高いほど、ユーザーがそのサイトにアクセスする可能性が高くなる。インターネットユーザーは多くの場合、検索結果の最初の数ページに出ているリンクしかクリックしないため、上位の表示順位を獲得することは、サイトのトラフィック獲得に欠かせない。SEOは、サイトを検索エンジンにとってアクセスしやすくし、インデックス化と上位ランクの獲得を手助けする。
- SERP(Search Engine Results Page)
- 検索エンジンでの検索結果ページ。
- SMWC(Slapping Myself With Celery)
- ぷっと何か吹き出すような極端なリアクションのことだが、そこに完全菜食主義の風味を上乗せした言葉。他の感嘆的な略語と組み合わせることが多い。たとえば、「何だそれ」のWTFと組み合わせてWTF/SMWCとか、「大爆笑」のROTFLと合わせてROTFL/SMWCといった具合。
- SMM(Social Media Marketing)
- ソーシャルメディアマーケティングの略。ソーシャルメディアを通じてウェブサイトやブランドの宣伝を行うこと。
- SMP(ソーシャルメディア汚染)
- Rand Fishkinの造語。競合相手をスパム屋に見せかけるための、(多くの場合不正な)悪質な技術のこと。たとえば、競合相手の名前やブランドを使って、ブログにコメントスパムを送ることなどが相当する。
SEOに対してキーワード広告(PPC)のことをSEMという人もいるが、本来の意味では、「SEM」はSEOやキーワード広告などの検索エンジン関連のマーケティングを総称するもの。
U
- URL
- ページを特定する文字列のこと。ページアドレスともいう。
W
- Web 2.0
- 新たな時代のウェブ活用方法を指す概念的な言葉。Web 2.0の世界を特徴付けるのは、ユーザー参加を促すウェブサイト。
あ行
- アクセス解析
- ウェブサイトの利用状況を収集して分析するためのプログラム。多機能で無料の分析ツールとしては、Google Analyticsの人気が高い。
- アストロターフィング
- 全面公表の反意語。ソーシャルグループで、偏向のない草の根の参加者を装いながら、商業的あるいは政治的な宣伝活動を意図した行為に走ること。天然芝と人工芝(アストロターフ)の対比から生まれた表現。ブランド構築、顧客獲得、広報活動といった本来の目的を隠しつつ、ユーザーフォーラムに参加することを指す。
- アドワーズ広告
- Googleのキーワード(検索もしくはコンテンツから自動抽出したもの)連動型クリック課金広告プログラムのこと。基本的なウェブ広告として非常に一般的な手段。
- アフィリエイト
- アフィリエイトサイトとは、手数料を見返りとして受け取るために、実際には別のウェブサイトや会社が販売している商品やサービスを宣伝するサイトのこと。
- アルゴリズム
- 検索エンジンが用いるプログラムで、任意の検索クエリに対してどのページを返すかを決定するもの。
- アンカーテキスト
- ユーザーの目に見えるリンク文字列。検索エンジンはアンカーテキストで参照サイトの関連性や、ランディングページのコンテンツへのリンクの関連性を解釈する。この3つが共通して同じキーワードを持つのが理想的。リンクテキストも参照。
- インデックス
- 検索エンジンが持つ、ウェブページとそのコンテンツのデータベース。
- インデックス化
- ウェブページを検索エンジンのインデックスに追加すること。
- インデックス済みページ
- サイト上で、すでに検索エンジンのインデックスに入っているページ。
- インプレッション
- ページビューともいう。訪問者がウェブページを閲覧した回数。広告用語的には各広告の露出回数。
- インリンク
- 被リンクや到達リンクともいう。関連性のあるページから得るリンクは、信用度とPageRankの源になる。
- ウィジェット
- 第1に、ガジェットやギズモなどと同じ。ウェブページ上で、アクセスカウンタやIPアドレス表示など、特定の機能実装に用いる小さなプログラム。この種のプログラムは優れたリンクベイトになる。第2に、経済学から借用した用語で、「製品または日用品」を指す。
- オーガニック検索結果
- 広告リンクなどの料金が発生する検索結果を除く、アルゴリズムのみによって生成された検索結果。SEOの目的は、この検索結果で上位を得ることにある。
- オーガニックリンク
- 自然発生的なリンクのこと。ウェブマスターがユーザーにとって価値があるという理由だけで張ったリンクを指す。
- オーソリティ
- 信用度、リンクジュース、Googleジュースと同義。特定の検索クエリについて、そのサイトが持つ信用度。オーソリティや信用度は、別の信用度の高い関連性のあるサイトから得た被リンクによって発生する。
- オーソリティサイト
- 関連する多数の専門サイトやハブサイトから被リンクを得ているウェブサイト。信用度の高いハブが同時的に引用しているため、オーソリティサイトは信用度やPageRank、そして検索結果の表示順位が高い。Wikipediaがオーソリティサイトの代表格。
HTMLでいうところの<a href="~">ここの文字</a>のこと。
か行
- 外部向けリンク
- 外部サイトに対して張ったリンク。
- 外部リンク
- 外部サイトからこちらへ張られたリンク(サイト内部のリンクは「内部リンク」という)。
- ガジェット
- ギズモを参照。
- キーワード
- ユーザーが検索エンジンに入力した語句。
- キーワード広告
- PPC(Pay Per Click)を参照。
- キーワードスパム
- キーワードの詰め込みと同義。キーワード密度が不適切に高いこと。
- キーワード調査
- どのキーワードが最も目的に適うか判断する、つらい作業。
- キーワードの相殺
- 同じサイト内の多くのページで、同じキーワードを過剰に繰り返して用いること。これをやると、ユーザーや検索エンジンは、あるキーワードについて、どのページが最も高い関連性を持つのかわからなくなってしまう。
- キーワードの詰め込み
- キーワードスパムと同義。キーワード密度が不適切に高いこと。
- キーワード密度
- ウェブページにおける特定のキーワードが登場する割合。この割合が不自然に大きいと、検索エンジンからペナルティを受ける。
- ギズモ
- ガジェットやウィジェットと同義。ウェブページに特定機能を実装するための小さなアプリケーション。アクセスカウンタや、IPアドレス表示など。ギズモは優れたリンクベイトになる。
- クローキング
- 人間用に表示するものとは異なるコンテンツを、検索エンジンスパイダーに見せる手法。こうした悪質な策を弄すると、検索エンジンに目を付けられ、検索結果からそのサイトやドメインの排除という事実上の死刑宣告を受ける。
- クローラ
- ボットやスパイダーと同義。リンク構造を辿ってウェブの世界、すなわちウェブサイトを巡回し、データを収集するプログラム。
- ゲートウェイページ
- ドアウェイページと同義。検索エンジンから引き込んだトラフィックを、別のサイトやページにリダイレクトする目的で用意したページ。ドアウェイページはクローキングとまったく同じではないが、人間のユーザーと検索エンジン用にコンテンツを分けるという点で、実質的に同じこと。
- 現金化
- サイトから収入を得ること。AdSenseはウェブサイトを現金化する簡単な方法だ。
- 検索エンジン
- 略称はSE。ユーザーのキーワードに対し、適合する関連性を持ったドキュメント、またはその集合を探し出し、最も関連性が一致するものを返すプログラム。GoogleやYahoo!などのインターネット検索エンジンは、インターネット全体を検索して関連性が一致するものを探し出す。
- 検索エンジンスパム
- 検索エンジンにとって、不適切だったり関連性の低い結果として抽出してしまうように作られたページ。SEO業者は、時に検索エンジンスパム屋だという不当な評価を受けることがある。まあ、その通りのこともあるにはあるのだが。
- コードスワッピング
- リンクベイトを仕掛けてトラフィックを得て、高い検索結果ランクを獲得した後にコンテンツを変更すること。
- コメントスパム
- 別サイトへのリンクを付加する目的で、ブログにコメントを投稿すること。リンクコンドームを使うブログが多いのはこれを防ぐため。
- コンテンツ
- テキストやコピーなどとも言う。ウェブページの中で、ユーザーにとって価値があり、興味を誘う部分。広告、ナビゲーション、ブランド、決まり文句などはコンテンツと見なされない。
- コンテンツ管理システム
- CMSともいう。日常的なウェブ管理作業とコンテンツ作成作業を切り分け、サイト運営者が面倒だと思えば、コーディングスキルを習得したり理解することなく、ウェブを能率的に作成できるツール。WordPressなどがこれにあたる。
- コンテンツ連動広告
- キーワード連動広告の一形態。コンテンツからキーワードを自動的に抽出し、キーワード連動広告のメカニズムに従って掲載広告を選択する。
- コンバージョン
- 目的の達成とも言う。ウェブサイトにおいて、定量化可能な目標のこと。広告クリック、ユーザー登録、売買成立などがコンバージョンにあたる。
- コンバージョン率
- コンバージョンに至ったユーザーの割合。コンバージョンを参照。
さ行
- サイトマップ
- ウェブサイトにおいて、ユーザーがアクセス可能なすべてのページにリンクしているページまたは構造化されたページの集合で、ユーザーにとってサイトのデータ構造を見えやすくし、サイトの使い勝手向上に寄与するよう意図したもの。また、検索エンジンスパイダーがサイトの全ページを見つけやすいようにする目的で、XML形式のサイトマップをルートディレクトリに置く例も多い。
- サンドボックス
- Googleにおいて、新しいサイトは一定期間が経過するまでサンドボックスに入り、高位のランクが獲得できないという議論や憶測がある。こうしたサンドボックスの存在や実際の動作について、SEOの間では広い支持を得られていない。
- スクレイピング
- サイトからコンテンツをコピーすること。自動化したロボットプログラムで行うこともある。
この解説はMichael Martinez氏の助言により改訂した。 - スパイダー
- ボットやクローラと同義。ウェブページを見つけてインデックスに登録するため、検索エンジンが使用する特殊なボットプログラム。
- スパイダートラップ
- スパイダープログラムを「罠にかける」ことができる、自動生成リンクの無限ループ。自動スクレイピングや電子メールアドレスの収集を防ぐ目的で意図的に用いることもある。
- スパマー
- スパムを利用して目的を達成しようとする人。
- スパム広告ページ
- AdSenseや広告用に作成したページで、スクレイピングで得たコンテンツや自動生成したコンテンツしかなく、ユーザーにとって価値がないページ。スパマーはこんなサイトを何百も作る。
- スプラッシュページ
- テキストコンテンツが少ない、アニメーションやグラフィック主体の扉ページ。スプラッシュページは人間の眼に訴求する目的で作成するものだが、SEOに注意を払わないと、テキストリンクしか追えない検索エンジンスパイダーにとっては、行き止まりのように見えてしまう。出来の悪いスプラッシュページは、SEO的に問題があり、ユーザーにとっても目障りなことがある。
この解説はMichael Martinez氏の助言により改訂した。 - スプログ
- スパムブログの略。人間にはほとんど無意味な内容で、たいていはコンピュータで自動生成したか、スクレイピングで得たコンテンツからなる。
- 正式版問題
- 複製コンテンツ問題とも言う。特にWordPressのようなCMSを使う場合、複製コンテンツを避けるのはほとんど不可能だ。それは検索エンジンから見て、www.site.comと、site.comと、www.site.com/index.htmは、おそらくどれも複製と見なされるためだ。そんなことを区別できないほど洗練されてないというのは、少々信じ難いが。ただし、この問題をうまく処理する方法がいくつかある。たとえば、正式版でない複製版には、METAタグでnoindexと記述したり、正式版への301サーバーリダイレクトを設定するなどだ。
- 静的ページ
- 動的コンテンツや、セッションIDのような変数を持たないウェブページ。静的なページは検索エンジンスパイダーから見てわかりやすいという意味でSEO向きだ。
- 相互リンク
- リンク交換やリンクパートナーと同義。2つのサイト間で互いにリンクし合っている状態。相互リンクは互恵的で、互いに密接な関係がある可能性があるため、通常検索エンジンは相互リンクの価値を低いものと見なす。
- ソーシャルブックマーク
- ユーザーがブックマークを登録して公開する、ソーシャルメディアの一形態。
- ソーシャルメディア
- 情報や視点を共有するためのオンライン技術の総称。ブログ、ウィキ、掲示板、ソーシャルブックマーク、ユーザーレビュー、評価サイト(DiggやReddit)などは、すべてソーシャルメディア。
- ソーシャルメディア汚染(SMP)
- Rand Fishkinの造語。競合相手をスパム屋に見せかけるための、(多くの場合不正な)悪質な技術のこと。たとえば、競合相手の名前やブランドを使って、ブログにコメントスパムを送ることなどが相当する。
- ソーシャルメディアマーケティング(SMM)
- ソーシャルメディアを通じて、ウェブサイトまたはブランドの宣伝を行うこと。
- 測定指標
- 解析プログラムで用いる測定標準。
- ソックパペット
- 直訳的には靴下人形の意味。SEO的用法としては、その人の本当の素性を隠したり、複数のユーザープロファイルを作るため、架空の人格を多数用意する行為を指す。
た行
- 代替テキスト
- 画像タグに付記する説明文。普段は表示されないが、画像を表示できないときや、ブラウザが画像を表示しない設定になっているときに出てくる。代替テキストが重要なのは、検索エンジンが画像を認識できないため。代替テキストは、スパイダが人間のユーザーと異なる情報を取得できる唯一の要素だ。しかも代替テキストは人間のユーザーもアクセスできるので、適切に使えば、画像の正確な説明になる。目の不自由な人用の特別なブラウザでは、画像があれば代替テキストを読み上げるので、画像コンテンツのアクセシビリティを確保できる。
- 地域的ロングテール
- Online DevelopmentのChris Paston氏の造語。都市または地域名を含む複数単語の語句からなるキーワード。サービス業界で特に有用性が高い。
- 直帰率
- サイトにアクセスしてきたものの、そのサイトの別ページを見ることなく去ってしまったユーザーの割合。バウンス率ともいう。
- ツールバーページランク
- Googleのアルゴリズムによって決まる0から10の数値。ページの重要性を定量化したものだが、PageRankとは異なる。ツールバーのページランクは年に数回しか更新されず、最新状況を示したものとはいえない。PageRankと混同することがたまにある。
この解説はMichael Martinez氏の助言により改訂した。 - 定着性
- バウンス率の低さとも言い換えることができる。ユーザーに長く滞在してもらい、より多くのページを見てもらえるようにウェブサイトを変更することが、定着性の向上につながる。
- ディレクトリ
- ディレクトリページに特化したサイト。Yahoo!ディレクトリなど代表例。
- ディレクトリページ
- 関連性のあるウェブページへのリンクを集めたページ。
- テキストリンク
- グラフィックや、FlashおよびJavaScriptなどの特殊なコードとは関係しない、単純なHTMLリンク。
- ドアウェイ
- ゲートウェイと同義。検索エンジンからトラフィックを集める目的で作成したウェブページ。ユーザー(スパイダーではない)を別のサイトやページにリダイレクトするドアウェイページはクローキングの実施に他ならない。
この解説はMichael Martinez氏の助言により改訂した。 - 当社独自の方式
- たわごとや、いんちきと同じ意味。SEO業者がよく使う営業用語。当社独自の方法で「ランキング上位10位」を達成できると吹いたりする。
- 閉ざされた庭
- 相互リンクを貼っているページの集合で、他のページからリンクを得ていないグループ。こうしたページの集合は、サイトマップがあればインデックス化されるが、おそらく非常に低いPageRankしか得ることができない。
- トラストランク
- 価値の高いページとスパムを区別する方法。人間が評価したページから始めて、リンクの関係性を定量化する。
は行
- バウンス率
- 直帰率を参照。
- バックリンク
- 被リンク、インリンク、到達リンク。他のサイトやページから、自分のサイトまたはページに貼られたリンク。
- ハブ
- 信用を得ているページで、コンテンツの質が高く、関連ページへのリンクがあるもの。
- パンくずリスト
- メインコンテンツの上にある、水平のサイトナビゲーションバー。グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」で、主人公が迷子にならないよう、道すがらパンくずを落としたという話に由来する。これがあると、ユーザーは今サイト内のどこにいるのか、トップに戻るにはどうすればよいか理解しやすい。
- 非相互リンク
- サイトAがサイトBにリンクしていて、BがAにリンクしていない場合、リンクは互恵的でないと見なされる。サイト同士の結託の可能性が小さいため、検索エンジンは非相互リンクに重きを置く傾向にある。
- ヒット数
- かつては一般的なウェブトラフィックの判定基準だったが、現在はページビューすなわちインプレッション数に取って代わられ、あまり意味がなくなった。ヒット数は、サーバーがオブジェクト、つまりドキュメント、画像、インクルードファイルなどを送信するたびに発生する。そのため、1ページビューでも多くのヒット数を生むこともある。
- 被リンク
- インリンクや到達リンクともいう。関連性のあるページから得るリンクは、信用度とPageRankの源になる。
- フィード
- 特別なウェブサイトやニュースアグリゲータなどのプログラムから利用者に配信されるコンテンツ。
- 複製コンテンツ
- 他のウェブサイトやページに明らかに似ていたり、まったく同じコンテンツ。複製コンテンツを持つことでペナルティは受けないが、検索エンジンがオリジナルと見なすコンテンツに比べて、得られる信用は、たとえあったとしても少ない。
- 不正クリック
- 広告掲載サイトやその手先が、クリック課金広告から不当な利益を得る目的でクリックを行うこと。不正クリックは、Googleのような広告サービス業者にとって、大きな問題だ。なぜなら、この行為は広告主が広告料金に見合う価値を得ているという確信を失わせるからだ。
- ブラックハット
- Google Webmaster Guidelineなどが示す模範的手法とは真逆の検索エンジン最適化手法。
- フレーム
- 複数の文書を単一画面内に表示するウェブページデザインの1種。フレームを用いると、スパイダーが正しくサイト内を捜索できないことがあるため、SEO的には良くない。また閲覧者にとっても、小さなモニタが2つあるように見えるうえに、どちらも情報のあるページ全体をいっぺんに表示しないので、嫌う人が多い。
- ブログ
- コンテンツをおおよそ時系列順に並べたウェブサイト。コンテンツは速報的なものもあれば、そうでないものもある。ほとんどのブログは自分でウェブページを作成せず、WordPressなどのコンテンツ管理システム(CMS)を使っている。そのため、ブロガーは難解なコードに悩まされることなくコンテンツ作成に集中できる。
- 分析ツール
- アクセス解析を参照。
- ページ滞在時間
- ユーザーが、1つのページに滞在した時間。品質や関連性の指標になる。
- ポータル
- いろいろな機能を提供し、ウェブにおける「ホームページ」として使うようユーザーに勧めているウェブサービス。iGoogle、Yahoo!、MSNなどがポータルの代表。
- 補足インデックス
- 補足結果と同義。Googleの場合、検索クエリには適合しても、PageRankが非常に低いページは、補足結果として表示することが多い。Googleの担当者によると、これはペナルティを示すものではなく、単純にPageRankが低いためだという。
この解説はMichael Martinez氏の助言により改訂した。 - ボット
- ロボット、スパイダー、クローラなどともいう。ある程度自律的にタスクを実行するプログラム。検索エンジンはボットを使ってウェブページを探し、検索インデックスに追加している。スパマーはボットでコンテンツをスクレイピングし、サイトを偽装して悪用しようとする。
- ホワイトハット
- ブラックハットの反語。最適化に関する最良ガイドラインに忠実で、無節操なゲームを仕掛けたり、検索結果を操作しようとしないSEO技術。
RSSやAtomなど。「ウェブフィード」とも呼ばれる。
スパムなどの手法を使うことを厭わない悪質な手法のこと。
ま行
- マッシュアップ
- 主として単一目的を持ったソフトウェアなどの小さなプログラム(ギズモやガジェット)、または場合によってはそういったプログラムへのリンクで構成されたウェブページ。マッシュアップは短期間で簡単に作れるコンテンツでユーザーに人気があり、なおかつ優れたリンクベイトになる。ツールを集めたページもマッシュアップということがある。
- ミラーサイト
- 別アドレスのページ群と同一内容のページ群。
本来マッシュアップとは、ある機能と別の機能を組み合わせることで新しい価値を生み出すこと。他サービスが提供しているAPIを使って実現することが多い。
や行
- 有料登録
- ウェブサイトを検索エンジンやディレクトリに登録する際、料金を徴収する手法。非常に一般的だが、技術的にはGoogleによる有料リンク排除を避けるための迅速処理報酬だ。
- ユーザー生成コンテンツ
- ソーシャルメディア、Wiki、Folksonomies、ブログなどは、ユーザー生成コンテンツに強く依存している。Googleはウェブ全体をユーザー生成コンテンツとして利用し、広告売上を得ていると見なすことができる。
ら行
- ランディングページ
- 検索結果で表示したリンクをクリックしたときにつながるページ。
- リダイレクト
- サイトが新ドメインに移ったときや、ドアウェイを仕掛けるときに、ランディングページを変えるために取る方法の1つ。
- リンク
- ウェブページの要素の1つ。クリックするとブラウザは別のページや同じページの他の場所を表示する。
- リンク交換
- 互恵的なリンクの方法。ディレクトリページに注力するサイトが促進している。リンク交換は質の低いサイトに結びつきがちで、それ自体に得るものは何もない。質の高いディレクトリは、品質を保証するため手作業で編集するのが一般的だ。
- リンクコンドーム
- リンクジュースを別のページに送らないよう防いだり、悪質サイトに外部向けリンクを張ったために悪い結果を招いてしまうのを防いだり、ユーザー生成コンテンツ内のリンクスパムを阻止したりするのに使う方法。
- リンクジュース
- リンクを通じて伝わる信用度、オーソリティ、PageRankのこと。
- リンクスパム
- コメントスパムとも。ブログのコメントのような、ユーザー生成コンテンツが含む望ましくないリンク。
- リンクテキスト
- アンカーテキストともいう。ユーザーの目に見えるリンク文字列。検索エンジンはアンカーテキストで参照サイトの関連性や、ランディングページのコンテンツへのリンクの関連性を解釈する。この3つが共通して同じキーワードを持つのが理想的。
- リンク人気
- そのサイトにリンクしているサイトの数と質に基づいた、サイトの価値評価指標。「リンクポピュラリティ」ということもある。
- リンクパートナー
- リンク交換や相互リンクと同義。リンクし合っている2つのサイト。互恵的という性格上、検索エンジンはこれを重要なリンクと見なさない。
- リンクビルディング
- 積極的にサイトの被リンクを増やすこと。
- リンクファーム
- すべてが互いにリンクし合っているサイトの集まり。
この解説はMichael Martinez氏の助言により改訂した。 - リンクベイト
- リンクを集める目的で作成したウェブページ。こうしたリンクは、ソーシャルメディアを介して集めることが多い。
- リンクラブ
- リンクコンドームによる一切の妨げがなく、信用度を引き渡す外部向けリンク。
- リンケラティ
- リンクベイトで最も成果を見込めるインターネットユーザー。リンケラティには、ソーシャルタグの利用者、掲示板に投稿する人、リソース管理者、ブロガー、コンテンツ作成者、などがあてはまる。リンクを張ったり、リンクを生み出すトラフィックを生成する(これはソーシャルネットワークユーザーの場合)可能性が非常に高い人たち。lorisaの提案による。
- ロングテール
- 長くてより具体的な検索クエリは、短くて広範に当てはまるクエリに比べて、ターゲットになることが少ない。たとえば、「ウィジェット」で検索すると、非常に幅広い結果が出てくるが、「逆スレッドを持つ赤いウィジェット」はロングテール検索になる。ロングテール検索は、検索全体の大きな割合を占める。
「<a rel="nofollow"」のようにして、リンクのタグにnofollow属性を指定することを指すことが多い。
- この記事のキーワード