生成AIの進化により、生活者の情報探索や購買体験が劇的に変化する中で、ブランドサイトには新たな施策が求められている。急速に変化する消費行動にどう応えるべきか。
「デジタルマーケターズサミット 2025 Summer」に登壇したFaber Companyの月岡克博氏は、生成AIエンジン(Generative AI Engine)において、自社のコンテンツがより多く参照・引用され、上位に表示されるように最適化を行う「GEO(AI SEO/LLMO)」を軸に、施策の最新動向と実践のヒントを解説した。
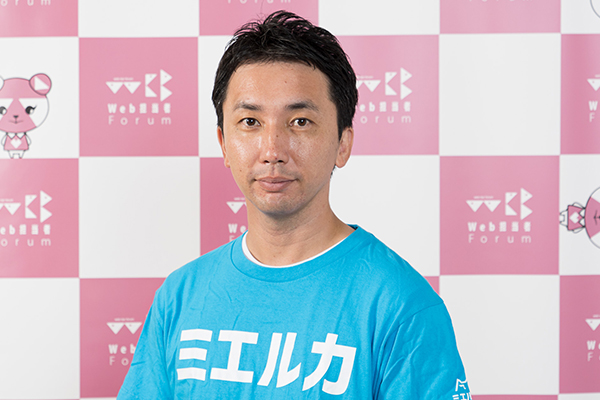
Googleは終わったのか? AI検索とGEOの現在地
ラテン語で「職人」を意味する名を持つFaber Companyは、デジタルマーケティング領域のプロフェッショナルが集う、Webマーケティング支援企業だ。代表的なツールに「ミエルカSEO」「ミエルカヒートマップ」などがある。
同社で執行役員を務める月岡克博氏は、プロダクトマネジメントやマーケティング全般を統括する立場として活動している。
そんな月岡氏がテーマに選んだのは、いま注目を集めている、AI検索対策手法とされる「GEO(Generative Engine Optimization:生成エンジン最適化)」だ。近年、急速に利用者が増加しているChatGPTなどのAIを用いた検索は、自然文で質問を重ね、条件を絞り込みつつ有用な情報を提供し、購入リンクまで表示する。そこに優先的に自社ブランドが表示されることは、今後のマーケティング活動において重要な意味を持つ。
もはや「Google検索は終わったのか?」と言及されることも多いが、様々な調査を見る限りGoogleは検索エンジンとしていまだ圧倒的シェアを持ち、ChatGPTなど生成AI検索は数%程度に留まる。さらに月岡氏は、Googleの検索エンジンとしての歴史や技術的優位性にも触れ、そう簡単にGoogle検索が終わるようなことにはならないだろうと語った。
2025年5月末に開催されたGoogleのイベント「Google I/O」では、AI検索「AI Mode」のデモが公開されている。たとえば「子どもとキャンプに行きたい」という質問に対し、リンク先が並ぶ従来のスタイルではなく、生成AI検索と同じような形式で情報提供される。
現在、Google検索結果の上部にはAI要約である「AI Overviews」が表示されているが、今後はこのAI Modeにシフトしていく可能性もある。2025年8月21日にGoogleは日本を含む世界180か国以上でAI Modeの段階的な提供開始を発表した(2025年9月9日に、日本語でAI Modeでの検索が可能になっている)。
AI検索で意識すべき「マルチモーダル」と「クエリ・ファンアウト」
AI OverviewsとAI Mode、GoogleもAI対応していく中で、マーケティング担当者は何を意識しておくべきなのか。月岡氏は押さえておくべき2つのトピックを紹介した。
キーワード①マルチモーダル
1つ目が「マルチモーダル(Multimodal)」というキーワードだ。Googleのジョン・ミューラー氏がGoogle Search Centralのブログで発表した8項目にわたるAI エクスペリエンスで成果を上げるためのヒントを、月岡氏は以下の3つに要約した。
- 価値あるコンテンツでユーザーによい体験を提供すること
- Google(システム・AI)にわかりやすい構造にすること
- テキストだけでなく画像や動画などさまざまなフォーマットのコンテンツ(マルチモーダル)を発信
テキストだけでなく、動画、PDF、ポッドキャストなどさまざまなフォーマットのコンテンツを、ユーザーの消費スタイルに合わせて提供し、マルチモーダルな情報発信がより重要になってきます(月岡氏)
キーワード②クエリファンアウト
2つ目が、「クエリファンアウト(Query Fan-Out)」というキーワードだ。AI OverviewsやAI Modeの裏側で動くこの技術は、入力されたメインクエリに対して、複数のサブクエリを作り出し、それらの検索結果を要約して結果を生成する。今までユーザーが複数回検索して情報を集める手間を省き、AIが一括して回答を提供する仕組みとなっている。
このような変化に対応する1つの考え方として、より綿密な「トピッククラスター」の構築が重要になると月岡氏は強調する。たとえば、「おいしいお米」というトピックなら、品種、産地、食べ方、炊き方などの情報(インフォメーションクエリ)、品種ごとの比較や価格、評判(比較検討層向け)、購入方法や購入場所(トランザクションクエリ)など、さまざまな角度からの情報を、サイト全体として提供することが求められる。
AI検索の基本的な施策はSEOの延長線上にある
Google検索セントラルにも、「AIの表示方法」というセクションに「Google検索全般と同様に、AI機能にも基本的なSEOのベストプラクティスが適用される」と公式に述べられている。
AI検索対応の基本的な施策はSEO施策の延長線上にあると考えてよいでしょう(月岡氏)
そして、月岡氏は、AIとGoogleの共通点として「(自分たちのブランドの)情報を勝手に発信したりはしてくれない」点を指摘した。
ブランドが自ら情報を発信し続ける必要があり、自社のWebサイトやSNSでの発信内容はもちろんのこと、より他社(者)にどのように紹介、レコメンドされるかも重要になってきます(月岡氏)
他社(者)サイトとして、とりわけメディアは信頼性という観点でも重要であるが、各種生成AIによって参照されやすいメディアの傾向が生じる可能性もある。そのため、どのようなサイトに自社の情報が出ているのか、掲出するかどうかを確認・検討する必要もでてくるだろう。
こうした活動も通じて、自社ブランド・製品・サービスが「◯◯といえば、(自社サービス名)だ」という認知を形成していき、その領域におけるブランド確立を図っていくことが欠かせない。
巷に流れるLLMO施策はほぼ意味なし。大切なのは「計測・ギャップ分析・改善」のサイクル
それでは、今後はどのような取り組みを進めていくべきなのか。月岡氏は「今のところGEO/LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)に積極的に取り組む意義は薄い」と語る。様々なAI検索対応手法がSNSなどで流通しているが、その効果は疑問符のつくものも多く、意味がない施策も少なくないと警鐘を鳴らす。
生成AIは急速に進化しており、今日有効だとされている施策が明日も有効とは限りません。SNSなどで見かけた現時点での特定の対応方法やハックする手法を鵜呑みにしないほうがいいでしょう(月岡氏)
また、投資対効果にも疑問符がつくという。Faber Companyが管理する一部のWebサイトのPV数をまとめると、AIからの流入は1年前と比較して約12倍に増加したものの、オーガニック検索流入と比較すると0.1%程度(1:1千の比率)に過ぎないという。このため、AIからの流入増加を目的とした施策は、短期的な投資対効果が極めて低いことになる。
インパクトが小さく、対応方法も確立されていないため、現時点でAI対策に特化した施策を行う意義は薄い。ただし、特別な施策はないとしながらも、GEO施策としては「計測→ギャップ分析→施策立案」という一般的なPDCAを踏襲すべきだと月岡氏は提唱する。たとえば、特定のプロンプトを投げた際に自社ブランドの露出数が競合より少ない場合、競合との情報発信状況の差を分析し、そのギャップを埋める施策を立案・実行するというわけだ。
月岡氏は、ある領域でYouTube動画が生成AIに採用されやすいと判明した事例を紹介した。しかし、登録者数も再生数も少ないYouTubeチャンネルでは十分な効果が期待できない。一定の登録者数と再生数を持つチャンネルを構築する必要があるが、これにはかなりの時間がかかる。それが1年後に分かったところで時すでに遅し、競合との圧倒的な差がついてしまっている、ということも起こりかねない。現状を知ることで、今から準備を始めるかどうかの判断が可能になる。
AI検索で変化に気づける環境づくりをミエルカで構築する
現在、Faber Companyでは、ChatGPTとGemini、Claude、そしてGoogleの検索結果画面(現在はAI Overviews)を計測対象としているという。
たとえば、ChatGPTで“おすすめ系のプロンプト”を投げた際に、自社ブランドがどのように紹介されるか(=ブランドメンション)、その他のプロンプトで情報源として自社サイトがどのように採用されているか(=採用率)などを確認する。AI Overviewsでも同様に、検索クエリに対するブランド名の露出と、情報源として採用されているWebサイトを計測する。
これらの計測を通じて、ターゲットユーザーが投げそうなプロンプトやクエリに対する自社の露出状況を把握し、その変化に気づける環境を整えることが必要です(月岡氏)
現在、ミエルカSEOでは、AI検索 と AI Overviewsにおける流入・露出状況を計測できる環境を提供しているという。具体的には、GA4連携によるAI流入状況の可視化(オーガニック検索とAI検索の割合、各種生成AIからの流入状況、コンバージョン状況)に加え、AI Overviewsの露出状況(登録キーワード群におけるAI Overviews表示の割合、自社ブランドと競合ブランドの露出状況比較)などの確認が可能だ。
またミエルカSEOでは、登録キーワードの検索順位を取得して可視化する機能が備わっている。その中でAI Overviewsについて、キーワードごとの自社と競合のメンション状況を取得し、比較することも可能だ。
そして、AI Overviewsだけでなく、ChatGPT、Gemini、Claudeの中で、自分たちのブランド名がメンションされている状況を可視化する「LLMモニタリング機能」がローンチされたばかりだという。これは各生成AI検索において、特定プロンプトを投げた際の応答内容(テキスト)と引用URLなどを網羅的に調査し、ブランド露出状況や自社サイトの採用状況を把握するというものだ。
月岡氏は、GEO施策の支援事例として、お米の贈答品を扱う「八代目儀兵衛」の取り組みを紹介した。同社は、結婚内祝いや出産内祝いなどで自社製品が推薦されるか、自社コンテンツが引用されるかどうかを調査分析し始めたところだという。分析結果をもとに各種施策の提案を実施、これから実装が開始される予定だ。
さらに、ミエルカSEOでは、コンテンツ作成におけるAI活用についても強化中だ。AIに全面的に任せるのではなく、あくまでアシストとして活用する方針。ペルソナ作成や構成提案などの機能、グラウンディングやファクトチェック機能も追加されている。これにより、ミエルカSEOのAIが提案した内容がどのような情報源に基づいているかを確認でき、ハルシネーション(幻覚・誤情報)への対応も可能である。
また、ミエルカヒートマップにもAI機能が搭載され、ヒートマップの画像データをAIが解釈し、「ファーストビューからの離脱率が高い」などの問題点を自動で提案してくれるという。月岡氏は、「これらの機能を通じて、Webマーケターの生産性向上にAIを活用することに力を入れている。GEO施策だけでなくミエルカのAI機能強化に期待してほしい」と改めて強調した。
























