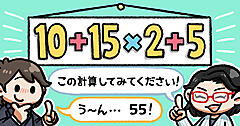AIが普及・進化し検索行動が変化する中で、AIに「選ばれる」ための施策として「GEO(Generative Engine Optimization)」に注目が集まっている。はたしてSEOはGEOに取って代わられるのか。「デジタルマーケターズサミット 2025 Summer」では、AI時代の検索の「現在地」と「未来」について、サイバーエージェントの木村氏が語った。

オーガニック検索からのアクセスが3割減? ゼロクリック増加と新たな最適化
GEOとは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIに最適化し、自社サービスやサイトを優先的に掲載してもらうための施策だ。GoogleのAIプロダクトである「AI Overviews」や「AI Mode」への対応もこれに含まれる。木村氏によると、LLM(大規模言語モデル)だけでなく「生成AI全体に最適化する」という広い意味で、木村氏が在籍するサイバーエージェントのSEOラボでは「GEO」という言葉を用いているという。

このGEOが重要視される背景には、ユーザーの検索行動の劇的な変化がある。木村氏は自身のシンガポール旅行の体験を共有した。かつて旅行先の情報収集は、ブログ記事などを参考にしていたが、AI Overviewsの登場以降は、それが提示する回答だけで完結する場面が多発したという。「SEOを仕事にする自分でさえ、その利便性の虜になっていた」という無意識の行動変容こそ、AIがもたらすインパクトの大きさを示している。
この体験は、Ahrefs社が発表した「AI Overviewsが表示されるとオーガニック検索へのアクセスが34.5%減少する」というデータとも符合する。木村氏は「日本ではそこまで顕著ではないが、確実にゼロクリック検索は増えている」と指摘した。
AI Overviewsの仕組みと、SEO担当者が今とるべきスタンス
従来のWeb検索からの流入を奪う存在と目されるAI検索だが、Google自身は、AI OverviewsやAI Modeを「あくまでWeb検索の延長線上にあるもの」と位置づけている。木村氏は、その影響がクエリの性質によって一様ではないと解説した。




「AI Overviews」の仕組みとオーガニック検索との意外な関係
AI Overviewsには「Search」「Gemini」「Query fan-out(クエリファンアウト)」「Grounding」などの技術が使われている。
Query fan-outは、一つの検索クエリから潜在的な疑問(サブクエリ)を予測し、包括的な回答を生成する技術のこと。たとえば「固定資産税」と検索すると、「固定資産税とは?」「いつ払う?」といったサブクエリの答えもまとめて提示する。Googleが言うところの「包括的な情報提供」は、この技術によって実現されていると思われる。

そしてGroundingは、LLMがWeb検索結果と自らの回答を照合してファクトチェックを行う技術である。これにより、AIによる偽情報を抑制し、回答の正確性を高めている。この技術の性質上、AI Overviewsは事実情報を求めるInformationalクエリで特に機能しやすく、サイバーエージェントの調査では、AI Overviewsが出現するケースの77%がInformationalクエリであったと報告されている(2025年6月時点)。
では、参照されるオーガニック検索の結果はどのように選ばれているのか。分析によると、1位サイトの引用率は約50%と低い一方、2位から7位のサイトは80%以上と高い確率で引用されているという意外な結果が出た。
木村氏は「CTR(クリック率)が高い1位をAIでも引用するとクリックが偏るためではないか」という仮説を提示しつつも、「オーガニック検索のCTRは依然として高いため、あえて2位を狙う必要はない」と断言。結論として「AI Overviewsを過度に意識するより、通常のSEOを磨き上げる方が良い。AI Overviews向けのGEOは、すなわちSEOそのものだ」と述べた。

「AI Mode」と「生成AI」、それぞれに求められる対策とは
「AI Mode」対策はまだ時期尚早か
AI Modeは、対話型のAIに近い回答が表示される仕組みで、木村氏は「Geminiにリンクがついたような感じ」と評する。オーガニック検索順位との相関は一定数見られるものの、1位サイトの引用率は20%程度と低く(2025年7月時点)、Geminiへの依存が強いと推測される。

将来的にはショッピングや予約機能と統合され「コンシェルジュ化」する計画もあるが、現状ではAI Modeへの導線が弱く、ユーザー行動を大きく変える段階には至っていない。このため木村氏は「状況が激変しない限り、現時点で専用の対策を深く検討する必要はない」とし、「まずは基本的なSEOをしっかり行うことが、間接的な備えになる」と述べた。
「生成AI」はプロダクトを“推薦”させる専門GEOが必要
一方、ChatGPTなどの生成AIへの最適化は、SEOとは全く異なるアプローチが求められる。生成AIはWebサイトを検索するのではなく、プロダクト(製品やサービス)を直接推薦する性質を持つからだ。実際、「おすすめの求人サイト」という問いへの回答と、オーガニック検索の順位には全く相関が見られなかったという。
そのため、GEOの目的はサイトへの誘導よりも、「『おすすめの〇〇』という問いに対し、自社のプロダクト名をいかに上位に表示させるか」が最重要となる。

AI時代でもSEOの本質は不変。未来を勝ち抜くための重要戦略
AI Overviews、AI Mode、そしてChatGPTのような生成AIへの対策(GEO)は、結局のところ、従来のSEOをより深く、より本質的に追求することに他ならない。AIという新たな潮流に慌てるのではなく、今こそ地に足をつけ、SEOの基本に立ち返るべきだと強調する。次に木村氏が示した「AI時代にさらに重要度を増す4つの戦略」を紹介する。
① クロールとインデックス:すべての施策の礎となる技術的基盤
SEOやGEOを語る上で、大前提となるのが「クロールとインデックス」の最適化だ。検索エンジンや生成AIにコンテンツを正しく認識させなければ、いかなる施策も意味をなさない。
木村氏が特に警鐘を鳴らすのは、大規模なデータベース型サイトなどで見られる品質の混在だ。Googleは、インデックス品質に満たないURLのパターンを学習すると、そのパターンに合致するページのクロール頻度を下げてしまう性質がある。これにより、本来は高品質でインデックスされるべきページまでクロールされないという機会損失が発生しかねない。
対策として木村氏は、「インデックスできるURLとできないURLを明確に分けること」の重要性を説く。たとえば、URLを品質に応じて「/high/」「/low/」のようにディレクトリで分け、低品質なディレクトリをrobots.txtでクロール制御するなどの方法が有効だ。サイトに割り当てられた「クロールバジェット(クロール量)」は有限であり、このリソースを価値ある重要ページに集中させることが大切である。

② トピッククラスター:サイト全体で専門性を示し、AIの理解を促す
かつてSEOの主流だった「1ページで全ての情報を網羅する」という考え方は、今や進化を遂げている。木村氏は、サイト全体で一つのテーマを体系的に完結させる「トピッククラスター」構造の有効性を強調した。
この構造は、SEOとGEOの両面で大きなメリットをもたらす。SEOの観点では、特定のキーワードを含む関連ページ数が多いほど、サイト全体のテーマ性が強化され、ランキング向上につながる傾向が強まっている。
一方でGEOの観点では、AI Overviewsなどで用いられるQuery fan-out技術への対応に有利に働く可能性がある。Query fan-outは、一つの検索クエリを複数の潜在的なサブクエリに分解して回答を生成する仕組みであり、トピッククラスターによって各サブクエリに対応する専門ページを用意しておくことで、AIに引用されやすくなるというわけだ。


③ サイテーションとエンティティ強化:ブランドこそが最強の資産となる
被リンク獲得施策の効率が低下している現在、木村氏が次に挙げる重要な要素が「サイテーション(言及)」と、それによる「エンティティ(実体・概念)強化」だ。
サイテーションとは、SNSでのメンションや指名検索などを指す。重要なのは、ブランド名と関連キーワードが同時に言及される「共起」である。たとえば、「ヤマハのレンタルバイクでツーリングに行きたい」という言及が増えることで、Googleは「ヤマハ」「レンタルバイク」「ツーリング」というエンティティ間の関連性が強いと判断し、「レンタルバイク」などの検索でヤマハが上位表示されやすくなる。同社の調査では、この「キーワードとブランドの共起メンション」が、特にTransactionalクエリにおいて最もランキングへの影響度が高い要素だったという。
これは、生成AI対策においても同様だ。「おすすめの〇〇」を尋ねた際に自社製品が推薦されるかどうかは、オーガニック検索順位とは相関せず、オンライン上でのブランド力(サイテーション数やメンション数)と強く関連していることがデータで示されている。

④ プロダクトの質:すべての施策を成功に導く最終条件
そして、これらすべての戦略の根底にあるのが、揺るぎない「プロダクトの質」である。木村氏は、サイテーション獲得のプロセスを「きっかけ作り→プロダクト体験→感動・満足→拡散・定着」と説明する。CMやSNSでのバズはあくまで「きっかけ」に過ぎず、ユーザーが実際にプロダクトに触れ、満足し、自発的に他者に紹介したいと思わなければ、持続的なサイテーションにはつながらない。
これは、SEO担当者だけの努力では達成できない領域であり、製品開発やWebサイト制作、マーケティングなど、部門を横断した連携が不可欠となる。

最高のWebサイトと最高のプロダクトを
講演の最後、木村氏は本セッションの核心を突くメッセージで締めくくった。
当面は慌てることなく、地に足をつけて最高のWebサイトと最高のプロダクトを作ることに集中すべきだ(木村氏)
この言葉が示すように、AIの登場は小手先のテクニックの終わりを告げ、コンテンツの質、技術基盤の健全性、そして何よりもブランドとプロダクトの価値そのものが問われる時代の到来を意味している。これまで「当たり前」とされてきたことを、誰よりも深く、当たり前のようにやり切れる者こそが、これからのAI時代の検索を制するのだろう。
【特別付録】SEO重要項目TIPS
最後に、本講演で語られた結論の根拠となっている、木村氏のチームによる大規模なデータ分析の一部を紹介する。これは、どのような要素が検索順位と相関しているかを「Informationalクエリ」と「Transactionalクエリ」のクエリタイプ別に示したものだ。時間の都合で講演内では詳細に触れられなかった、貴重なTIPSとなる。