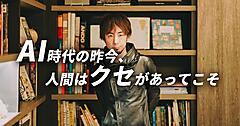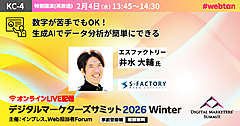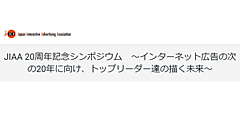「ヒットを生み出すアイデアを導くために重要なのは、センスではなく、データの裏に潜む『顧客の“ホンネ”=インサイト』を的確に掴む“型”を身につけることだ」と語るのは、電通の佐藤氏。「デジタルマーケターズサミット 2025 Summer」に登壇し、著書である『センスのよい考えには、「型」がある』を基に、思考プロセスを解説した。

インサイトの探索に必要なのはセンスではなく「型」
優れた事業やマーケティングアイデアには、ほぼ必ず「インサイト」があるといわれる。そのインサイトの定義にはさまざまあるが、佐藤氏は「人を動かす隠れたホンネ」あるいは「言葉にして自覚できていない欲望」のことだと話す。
「どうしたら自社の商品をもっと買ってくれるだろう?」「どうしたらもっと店舗にお客様に来てもらえるだろう?」といったマーケターの課題を解消するには、まずインサイトを掴まなければならない。にもかかわらず、インサイトというものは極めて曖昧なものである。
コカ・コーラの事例で「インサイト」を理解
佐藤氏は、まずインサイトを掴んだことで大成功を収めたコカ・コーラの広告キャンペーン事例を紹介した。
アンケート結果の裏に隠れたホンネはどこにある?
キャンペーン担当者が渡された資料のなかに、「コカ・コーラはどんなときに飲みたくなるのか?」という質問に対するアンケート結果があった。そこには「暑いとき」「ハンバーガーを食べたとき」という、ある意味、当然の結果が1位と2位を占めていた。
しかし、この結果を見た担当者は、「本当か?」と疑問を抱いた。自分の実感と違うように思えたからだ。加えて、アンケート結果は「その他」の回答が非常に多かった。
ホンネの仮説を立てて、検証してみる
「その他」の回答に、ホンネが隠されていそうだと感じ、改めて、身近な人たちに「コカ・コーラを飲みたくなるのはいつか」と聞いた。すると、「不意に、突然」「なんとなく急に……」といった曖昧な回答が目立った。ということは、「コカ・コーラは、突然、無性に、飲みたくなるもの」なのではないか。
この仮説を検証すべく、別のアンケート調査を実施。コカ・コーラを炭酸飲料やお茶、清涼飲料水などと一緒に並べ、「このなかで無性に飲みたくなるものはどれか?」と聞いた。結果、コカ・コーラと回答した人が圧倒的に多かった。
こうしてインサイトに辿り着き、「No Reason ココロが、求めてる」をキャッチフレーズにしたキャンペーンが生まれ、大ヒットにつながったのだ。
それって、本当にインサイト?
「このようにインサイトは“超強力”だけれど、見つけるのは“超難しい”」と語る佐藤氏。その理由のひとつが、「インサイトはこれだ」と客観的に判断できる指標がないからだという。しかし、以下の5つの条件を満たしていれば、それはインサイトである可能性が高い。
- SURPRISE:聞き手の内面に気づかせ、ハッとさせる、新たな発見や驚きがあるか?
- INSPIRATION:人の発想を広げるインスピレーションを感じさせるか?
- COMMITMENT:自分が心から腑に落ちているか?
- WORDING:1行で言い表せ、誰もが理解できる明確な言葉になっているか?
- ESSENTIAL:人間らしさ、人間の本質はあるか?
また、インサイトと混同されがちなものとして、佐藤氏は「ファインディングス」をあげた。ファインディングスの中には、一見、インサイトのように見えるが、当該プロジェクトのゴールに関係がないもの、すなわち“人を動かさない”隠れたホンネが含まれることがある。「エスノグラフィー調査で陥りがちなので、十分に注意してもらいたい」と佐藤氏は述べる。

感情を起点にインサイトを見つける「出世魚モデル」
次に佐藤氏は、インサイトを見つけるための具体的な方法論「出世魚モデル」を紹介した。出世魚モデルとは、連続した思考プロセスと対話によって、気づきや違和感をインサイトへ育てていく思考の「型」のことで、次の5つのSTEPで成り立っている。

STEP①:日常のなかの違和感に目を向ける。直感や観察に基づいて「気づき/違和感」をもつ(感性力)
STEP①におけるポイントは次のとおり。
- 日常で感じる自分自身の感情に目を向けて、違和感やモヤモヤを思い出す。
- 第一印象は、自分のオリジナルな可能性が高い。自分だけが「ん!?」と引っかかったことを大切にする。
- 感情は、「こうなると思っていたのに、全然違う結果になった!」というような「予測誤差」が大きいときに生まれる。
- ネガティブな感情には人を動かす力がある。ドロドロした感情、コンプレックスなど相反した感情、不満や文句など、誰もが目を背けたい感情のなかにこそ、インサイトの卵は埋もれて隠れている。
さて、なぜ感情を起点にインサイトを探索するのだろうか? 佐藤氏は次のように語った。
私たちがビジネスで生み出したい“価値”とは、“嬉しさ”という感情のことだからだ。この感情を満たせば、購買という意思決定に大きく近づけられる。だからこそ、自分の感情には常に意識を向けて、日々の気づきや違和感に敏感であることが大切だ(佐藤氏)
STEP②:違和感を抱いたのはどんな常識か? 日常のなかの「常識/定説」を改めて明確に把握する(常識把握力)
STEP②におけるポイントは次のとおり。
- その違和感やモヤモヤは、いったいどんな「常識/定説/当たり前」に対して抱いたものなのか?
- 大発見! と思ったのは自分だけ。実はみんなの常識かも。時代によって変わる価値観には要注意。
- インサイトへと成長していく「気づき/違和感」には、常識や定説に対するアンチテーゼが含まれている。
STEP③:常識の裏には、どんなホンネが隠れているのか? 当たり前だと思われていることに「疑問/問い」をもつ(問題提起力)
STEP③におけるポイントは次のとおり。
- 良い問いとは、どんな「常識」に疑問をもつかで決まる。
- 誰もが疑わなかった「常識/定説」に自分の感覚で「疑問/問い」をもてるか。
- 「リフレーミング」「フカボリ」「ユサブリ」などの問いかけのテクニックを活用する。
STEP④:隠れたホンネを自分の納得いく言葉にする。自分の目で改めて世界を捉え直した「仮説/推論」を立てる(言語化力)
STEP④におけるポイントは次のとおり。
- インサイトは言語化が9割。自分の感情に、よりピタッとハマる言葉を見つけていく。
- 似ているようで違う曖昧な感情を明確にする「類義語」。類義語の共通する部分と異なる部分を明確にしていく。
- 反対の言葉でモヤモヤの輪郭を明確にする「対比表現」を活用する。

- ターゲットにインタビューをするなかで、「強い感情を表す言葉(好き、嫌い、嬉しい、苦痛など)」や「思わずホンネが露見する言葉(実は、個人的には、正直にいうとなど)」が出てきたら、近くにインサイトが潜んでいる可能性が高い。
- 「ザックリした言葉」で絶対に満足しない。言語化とは、飾った言葉を「思いつく」ものではなく、精緻に言葉を「選りすぐる」ものである。常套句、専門用語、流行ワードに安易に飛びつかない。
- 「対話」の力で、自分やみんなの感覚にピタッとハマる言葉を見つける。自分の言葉の世界に閉じていると、同じ言葉を使いがち。他者との対話を通じて、自分のなかにはない語彙(=ズレ)を探してみる。

STEP⑤:自分の言葉をみんなに信じてもらう。客観的に誰もがわかるように「確認/検証」する(説得力)
STEP⑤におけるポイントは次のとおり。
- 「定量調査」で、自分やターゲットの“N=1だけではない”と証明する。
- 「定性調査」で、イキイキとした具体的なシーンを引き出す。
- 「事例や関連事象」を列挙する。
「出世魚モデル」の実践例:スマドリバー渋谷
最後に、佐藤氏は、2023年5月に開催された「第15回 日本マーケティング大賞」でグランプリを受賞した「飲めない人の視点から新文化創造に挑戦『スマドリバー渋谷』」の事例を紹介しながら、出世魚モデルの活用方法を紹介した。
「スマドリバー渋谷」は“飲めない人のためのバー”で、自身も飲めない人として佐藤氏が日頃から抱いていた違和感が起点となっている。出世魚モデルのプロセスにならい、飲めない人のインサイトについて、以下のように解説した。
STEP①:気づき/違和感の思考
- 違和感①:飲み会の仲間に、「飲めないのに、遅くまで付き合わせてごめんね」といわれる。
- 違和感②:飲める人のメニューは100種類近くあるのに、飲まない人の分は数種類のソフトドリンクだけの場合が多い。
- 違和感③:そもそもソフトドリンクが、子ども扱いされている気がする。
これらの違和感を一言でまとめると、「飲めない人は、飲める人から、いろいろと決めつけられている」だ。
STEP②:常識/定説の思考
「飲めないのに、遅くまで付き合わせてごめんね」という飲める人の発言の裏には、「飲めないあなたは、お酒の場に無理しているんだよね」という思い込みが透けて見える。だが、ある調査結果によると、お酒を飲めない人のなかで飲み会がキライな人の割合は65%で、残りの約1/3は飲み会が好きと回答していた。
つまり、飲める人のなかには「飲めない人は、飲み会がキライ」という決めつけがある。
STEP③:疑問/問いの思考
【常識/定説】飲めない人は、飲み会がキライ
これに対するアンチテーゼとして、次のように問いを立ててみる。
【疑問/問い】飲めない人は、本当に飲み会がキライなのか?
好き/キライで聞かれたらどちらかで答えるしかない。しかし、好き/キライでは表せない(本人も気づいていないような)“隠れたホンネ”があるのでは?と考えた。
さらに、リフレーミングをしてみたところ「お酒が飲める/飲めない」の先にある目的は、「仲良くなることではないか?」「お酒が飲めようと飲めなかろうと、楽しめる社会が理想では?」などが提起された。
STEP④:仮説/推論の思考
言語化するために対比表現してみる。「飲める人は飲み会が好きで、マジョリティ的立場でメイン顧客」だが、「飲めない人は飲み会がキライで、マイノリティ的扱いで“その他”の客」といったことが、常識/仮説として浮かび上がってきた。
さらに、チームメンバーで話していくなかで、「飲める人ばかり楽しんで、ずるいと思う」という発言が出てきて、これがホンネではないかと皆がハッとした。これがインサイトではないかと考えられる。
STEP⑤:確認/検証の思考
飲めない人に「飲める人ばかり楽しんで、ずるい!」と感じる具体的なシーンを挙げてみると
- 飲める⼈はお酒がストレス解消になるけど、飲めない⼈にはそれがない!
- ロックやストレート、⽔割りなど、⾃分なりの飲み⽅を楽しんでみたい!
- お酒の強い相手にもっと付き合いたい!
といったイキイキとしたシーンの数々が浮かび上がった。
そこで、飲めない人も楽しめるようにすればよいのではないかと、「度数に頼らずに、気分がアガるドリンク体験を提供」する場を設けることにした。そして具体的に、飲めない人が集まって、さまざまなノンアルコールドリンクを楽しめる「スマドリバー渋谷」がオープンしたのだ。
「インサイトはどう見つけるのか?」をさらに知りたい場合は、『センスのよい考えには、「型」がある』(佐藤真木・阿佐美綾香:著 サンマーク出版:刊)を読んでみるといいだろう。