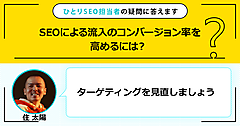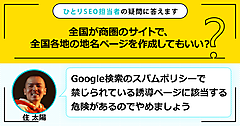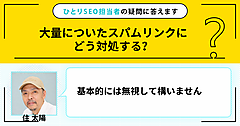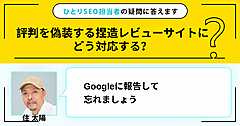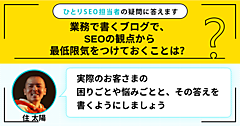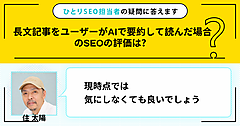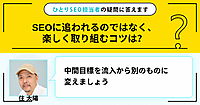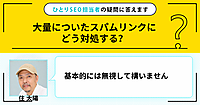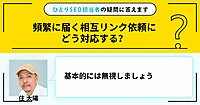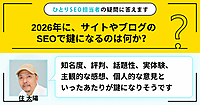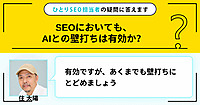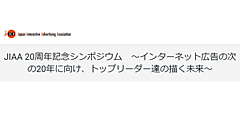ひとりで頑張るSEO担当者さんの悩みに答える本連載。今回の質問は「上司にスパム的なSEOを指示されたときの対応は?」です。
この回答は「上司の指示が会社の方針に沿っているか確認しましょう」です。
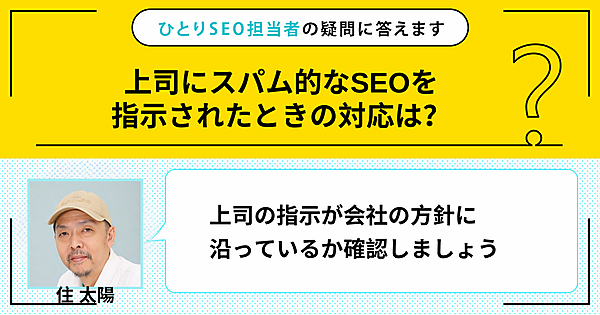
に対する回答は
「上司の指示が会社の方針に沿っているか確認しましょう」です
スパムは見込み客を騙すこと
今回の質問は「上司にスパム的なSEOを指示されたときの対応は?」というものです。ペンネーム「まるもち」さんが寄せてくださいました。Googleマップのクチコミ購入や、既存のサテライトサイトを管理するよう指示を受け、ペナルティのリスクや効果の限定性を説明しても指示が撤回されず、どう対応すべきか、というのが質問内容です。
スパム的なSEO手法を使うときの意識は「検索エンジンを騙して出し抜いてやる」というようなもので、相手が検索エンジンだと考えていればそれほど悪質とは思えないかもしれません。とはいえ、検索エンジンの向こうには検索ユーザーがいますから、検索エンジンを騙すというのは言い換えれば検索ユーザー、つまりは自社の見込み客を騙すことでもあります。
これはスパム的な手法が露見したときのことを考えればわかりやすいと思います。たとえばGoogleマップのクチコミ購入が露見したとして、見込客や顧客がどう思うか考えてみましょう。おそらく「騙された」または「危うく騙されるところだった」といった感想になることでしょう。スパムで騙しているのは見込客なのです。
スパム的な手法が正解(⁉)になるケース
まるもちさんの会社がもし、検索ユーザー、つまりは自社の見込客を騙すことを是とする会社なら、スパム的な手法もまた是であることでしょう。極端な例ですが、消費者の無知につけこむ悪徳商法的なビジネスや、脱法薬物などを当局の規制が入るまでに売れるだけ売るビジネスなら、スパム的な手法も手段のひとつになり得ます。
こうした場合、まるもちさんが「スパムにはリスクがあるうえに商道徳的にも問題がある」と考えたとしても、その考え自体が会社の方針とは合わない可能性があります。その会社にいる限りは、社の方針に従うほかなさそうです。
まっとうなビジネスならスパムは避ける
まるもちさんの会社が商道徳的に問題のない、真摯な姿勢でビジネスをしている会社なら、スパム的な手法を指示する上司個人に問題がありそうです。会社として見込み客を騙す意図がないなら、集客にスパム的な手法を使うことは会社の方針に合わず、その上司の独断である可能性が高いからです。
上司のさらに上役に、検索エンジンとその向こうにいる見込み客を騙すやり方が、会社の方針と合致するかを確認しましょう。長く続いている会社や、これからも長く続けるつもりの会社なら、スパム的な手法で見込み客を誘引することは方針と合致しないはずです。
まとめ
スパム的な手法は商道徳上の問題で、普通の会社なら採用は見送るものです。上司の指示が会社の方針に沿っているとは限りません。また、会社によっては商道徳自体を軽視している場合もあります。まるもちさんも自社の方針をよく確認し、そのうえでどうするかを判断するのがいいでしょう。
P.S.
本コーナーでは、読者の質問にお答えしています。誰にも聞けずに困っていること、現場で感じるふとした疑問など、どしどし質問をお寄せください。

ひとりSEO担当者の疑問や悩みを募集しています。応募したい方は以下からお願いします。
疑問・悩みを応募する