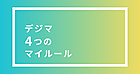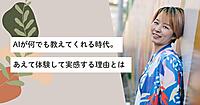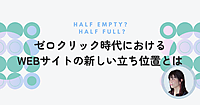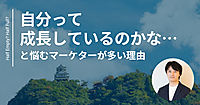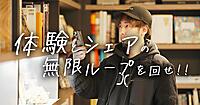最近、「何かを始める」ことのハードルが下がっていると感じる場面が増えました。
私は先日24時間ジム「Fit Place 24」に入会しました。24時間ジムか、ピラティス、パーソナルトレーニングかと迷っていたものの、「自分の好きなタイミングで運動できる方が続く」と思い、24時間ジムに決めました。
以前通っていたジムでは、入会手続きが紙ベースで、スタッフのいる時間帯に来店が必要。支払いは口座引き落としのみで銀行印での捺印も求められ、始めるまでに手間がかかりました。
今回は、すべてがスマホで完結。メール登録、プラン選択、顔写真アップロード、アプリのダウンロードを終えた時点で、もう利用可能な状態になっていました。「始めたい」と思った瞬間に行動へ移せる――まさに「始めやすさ」を実感しました。
同じように「始めやすさ」で感動したのが、TVerで日本シリーズを見たときです。
10月30日、日本シリーズを見ていた私はテレビを子どもに取られてしまい、「ほかに野球を見られる方法はないか?」と検索。すると、TVerとABEMAがヒットしたので、TVerを試してみたところ、数回の質問に答えるだけで視聴が開始できました。会員登録すら不要。「見たい」と思ってから「見られる」までほんの数分。野球は数分で試合展開が変わるかもしれないスポーツなので、すぐに見られて本当にありがたかったです。
なぜこんなに簡単なのか? 背景にある「ユーザーオンボーディング」の思想
この「始めやすさ」の背後には、マーケティングやプロダクト設計で重要視される「ユーザーオンボーディング」の考え方があります。
オンボーディングとは、ユーザーがサービスを使い始める最初の体験の設計のこと。特にSaaSやアプリでは、「Time to Value(価値実感までの時間)」という指標が重視されます。ユーザーが興味を持ってから、価値を感じるまでの時間が短いほど、定着率は高まります。
TVerはその典型例です。CMが収益源であるため、登録という障壁をなくし、視聴開始までを最短化しています。ユーザーが求めているのは「会員になること」ではなく「番組を見られる」という価値。その価値提供に最適化されたUXが、TVerの成功を支えています。
一方でFit Place 24も、興味深い体験設計です。入会をアプリで完結させることで、ユーザー側のハードルを下げつつ、ジム側の事務コスト削減にも貢献しています。ただし、プランによっては解約時にペナルティを設けるなど、「入口は簡単に、出口は慎重に」という戦略的デザインが見えます。
継続させる仕組み:Duolingoに見る次のステップ
もちろん、始めやすさだけではサービスは続きません。使い続けてもらうためには、「継続の仕組み」が欠かせません。
STORES では、10月1日に内定式を実施しました。そのとき、2026年入社予定のエンジニア職の内定者4名と「RubyKaigi 2026に参加しよう」という話になり、「英語で話せたらもっと楽しめるね」という流れから英語学習の話になりました。
私と内定者1名がすでにDuolingoを使っていたこともあり、「みんなでやろう!」という流れに。その場でアプリをダウンロードし、Duolingo上で友だちになるまで、ほんの数分。始めるハードルの低さが、「やってみたい」という一歩を後押ししてくれました。
Duolingoが秀逸なのは、その後の「続ける仕組み」です。
「フレンズ連続記録」という機能があり、友だちと学習の連続日数を競えます。内定者たちと一緒に挑戦している私は、「言い出しっぺとしてやめられない」というプレッシャーも感じながら、毎日アプリを開くようになりました。1日数分でも記録が続くので、小さな成功体験が積み重なります。
そして友だちの進捗が可視化されることで、「みんな頑張ってるから自分も」という気持ちになり、自然とモチベーションが維持されます。Duolingoは、「始めやすさ」と「続けやすさ」を両立させた好例といえます。
最初の一歩と、その先を設計する大切さ
Fit Place 24、TVer、Duolingo。――この3つに共通しているのは、「ユーザーが本当に求めている価値に最短でたどり着けるように設計されている」という点です。
TVerは「番組を見たい」、Fit Place 24は「運動を始めたい」。「Time to Value」を短くすることは、単なる効率化ではなく、ユーザー体験を尊重する姿勢そのものです。会員登録や紙の手続きは企業側の都合であって、体験価値を遠ざける要素になり得ます。
そしてDuolingoが教えてくれるように、「始めやすさ」の次には「続けやすさ」を設計する段階があります。
続ける理由を提供し、達成感を積み重ね、仲間とのつながりでモチベーションを維持する。そこまで設計されてこそ、サービスは習慣として定着します。
「始めやすさ」と「続けやすさ」――私たちが日々何気なく使っているアプリやサービスは、意識せずともこの2つの設計思想の上に成り立っています。
自社の製品やサービスのオンボーディングを考えるときは、まず自分が「つい使い続けている」ものを観察してみる。そこにこそ、始めやすく、続けやすい体験をつくるヒントがあるはずです。