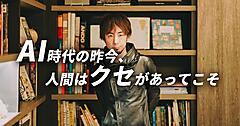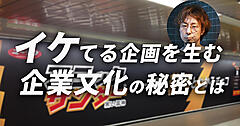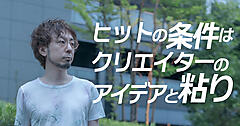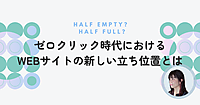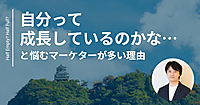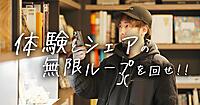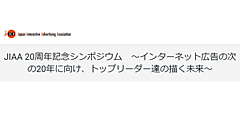こんにちは、エンタメのマーケティングやプロモーションの仕事をしている明坂です。
みなさんは、XやTikTok、InstagramなどのSNSを日常的に利用しますか? 私は一応仕事ということもあり、意識的にTikTokやYouTube Shortsなどを見る時間をつくるようにしています。今や大半の方が、何かしらのSNSを日々利用していると思いますし、それは企業においても同様で、発信によるプロモーションはもちろん、消費者の反応調査など、日常的に活用されていることでしょう。

さてTikTokを眺めていて、近年特に興味深い現象に気づきます。大々的に公式をうたっていないサブアカウント(サブ垢)や、企業が行っているけれどファンアカウント風に見えるアカウントからの投稿が、公式アカウントからの投稿に比べて圧倒的にバズっているケースが増えてきていることです。
しかも、それは単に「踊ってみた」「日常」「インタビュー」系にとどまりません。実際のタレント本人が登場しているにもかかわらず、なぜか“公式”っぽいことがネックになるという、逆説的な構図が見えてきます。

とりわけアイドル系のアカウントではこの傾向が顕著です。たとえば、“Rain Tree”や“#Mooove!”といったグループにおいては、出演しているメンバー自体は公式アカウントと同じなのに、サブ垢での投稿のほうが高い反応を獲得しています。コメントでは「誰この子?」「どこかのアイドル?」というような、素直な称賛が飛び交っています。
これを単なる偶然や編集スキルの差と捉えるのは短絡的です。むしろそこには、TikTokというプラットフォームの構造的な性質、アルゴリズムの働き、そして現代の若年層の“見方”が複雑に絡み合っています。
つまり、表層的には「アカウントの違い」に見えるものの、その背後には、SNS時代特有の“コンテクストの設計”という本質的な要素が潜んでいると考えます。今日は少しこの「公式感より文脈が大事なのはなぜか」というテーマでこの現象を深堀っていきましょう。
公式アカウントが“効かない”理由
TikTokにおける企業公式アカウントの弱さは、単なる演出や運用の問題ではありません。むしろ、その“立場”そのものがノイズになっている可能性があります。
学校でたとえると、いわば、公式アカウントの発信は「ホームルーム(朝礼)」的な性質をもっており、信頼性や一貫性は担保されているものの、どこかよそよそしくなってしまいます。情報としての正しさはあっても、通常そのままでは、UGC(ユーザー生成コンテンツ)のような感情としての“近さ”に欠け、さして話題にもなりません。

たとえば、アイドルが公式アカウントで可愛く振る舞ったとしても、「まあ、アイドルだから可愛いのは当たり前だよね」と、無意識にハードルが上がってしまいます。それに加えて、投稿者の人格が見えにくく、誰が投稿しているのかの解像度が低いため、ユーザーが感情移入しづらいということもあります。これがエンゲージメントの低下につながる理由の根幹だと考えます。
休み時間型コンテンツの魅力
それに対して、サブ垢は「休み時間」のような場を演出します。誰かのもとに自然と集まり、共感や雑談を交わすような、感情的で“素朴”なつながりが創出できるわけです。たとえば先述したアイドルグループ、#Mooove!のTikTok「クラスのマドンナ」、Rain TreeのTikTok「推しを自慢してみるなど。」といったサブ垢は、あえて学校や日常会話といった文脈をもたせ、UGCに見える設計になっています。

この手法は単なる演出ではなく、「管理された本物らしさ(マネージド・オーセンティシティ)、くだけていうと、あえて広告っぽくなくすること」を武器に、素人風の語り口と自然な編集で、ユーザーの心理的ガードを下げます。結果、視聴完了率や保存数、コメント数など、TikTokアルゴリズムに効く指標が大きく伸びる構造になっています。
TikTokのアルゴリズムとユーザー心理
この戦略がなぜここまで効果を発揮するのでしょうか。背景には3つの要素があると考えます。
ひとつはTikTokのアルゴリズム。視聴時間・完了率・保存・共有といった“能動的な行動”に重みづけされる設計は、没入感のある短尺ストーリーと極めて相性が良いです。
次に、ユーザーの深層心理。TikTokの主要ユーザー層であるZ世代は、広告や“公式感”に敏感です。自分に近い立場の人間が発する言葉のほうが信頼できるし、そっちの方が“推せる”と感じます。
最後に、ストーリー(文脈)の設計。「誰が投稿しているのか」「この子は何者なのか」「なぜこの動画を上げたのか」といった背景が、明示的には語られないまま暗示されています。これが視聴者の想像力をかき立て、能動的な“補完”を促します。まるでショート動画が、ドラマの予告編のような役割を果たしているわけです。
模倣と陳腐化の危機。そしてバズるだけでもダメ
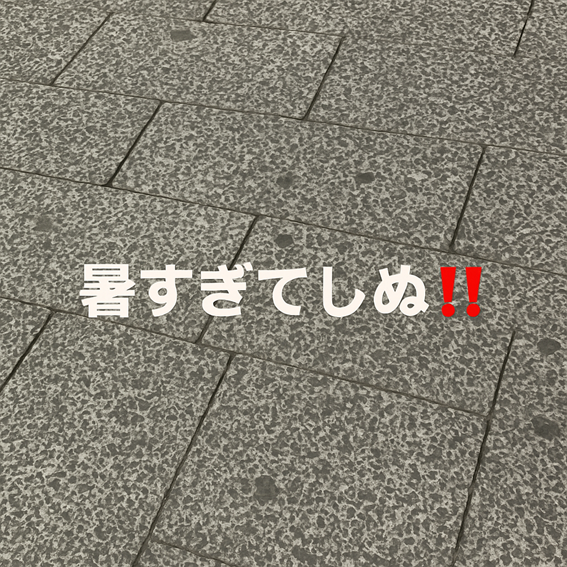
ただし、この手法にもリスクがあります。それは、構造が発見された瞬間に模倣が広がり、飽和&陳腐化が容易に起こりえることです。SNS、とくにTikTokをはじめ、ショート動画SNSにおいては、目新しさが消えた瞬間に価値が半減します。素人風の演出、UGC風のナレーション(XXX過ぎて死ぬ!とか)、テロップのテンプレ化。これらはすでにコモディティ化の兆しを見せ、同じ構造の“量産型”が急増します。
結果として、「またこのフォーマットか」と思われた時点でバズらなくなります。しかも、サブ垢がどれだけバズったとしても、本体アカウントやライブ・物販などの本業ドメインに流入しなければ最終的には意味がありません。しかし、サブ垢としてやっていたアカウントが、ある日いきなりゴリッゴリに宣伝をし始めたら興ざめになってしまうのは容易に想像できます。

Rain Treeが示した“接続”の工夫
この点、Rain Treeのアカウントでは少し工夫が見られます。彼らはバズらせたサブ垢から、いきなり公式アカウントに誘導するのではなく、「文脈を滑らかにつなぐ」仕掛けを敷いています。
たとえば、オフショット風の動画の使用楽曲に、新曲をさり気なく登場させています。そして、その動画が別のファンに引用され、今度は振り付け動画につながっていきます。気がつくとユーザーは、Rain Treeというグループの世界観に、自然に足を踏み入れている、というわけです。これは一見バズとは関係のないようでいて、ファンベースを構築する上で、極めて重要な導線設計だと思います。
もういくつか事例を出します。
ももいろクローバーZの妹分グループであるスターダストプロモーション所属”TEAM SHACHI”の秋本帆華さんがやっているTikTokアカウント「待ち合わせに、飽きもと。」は、「流行りの楽曲のダンスを渋谷や名古屋駅など人通りの多い中でやって、待ち合わせをしている友だちに見つけてもらう」という、友人同士の悪ふざけのような文脈をずっと行っているアカウントです。
ここでは、普段の流れに沿ってシームレスにTEAM SHACHIの楽曲を使ったり、待ち合わせシーンではなくTEAM SHACHIのライブやリリースイベントの様子を流したりなど、普段の文脈とうまく接続しています。ちなみに「TEAM SHACHIの秋本帆華です」と名乗っているアカウントよりサブ垢のほうが、多くのフォロワーがいます。

また、大ちゃんの曲でバズった”ちゃんぴおんず”や、カリスマと信者でおなじみの”リンダカラー∞”が所属するワタナベエンターテインメントが運営する「ネタ以外も見てみたい。(仮)」というアカウントでは、街頭インタビューのようなテイで、これからライブに出演する芸人さんのライブ以外での日常を映し出しています。
ちゃんぴおんずのアカウントのように、固定の人が出たり定番のネタがあったりするわけではありませんが、アカウントのフォロワー数やエンゲージメント力はちゃんぴおんずと近いレベルまでになっていて、まだ知名度が高くない芸人さんを露出するいい仕組みになっていると思います。
一時のバズではなく、構造の設計を
改めて最後にまとめとして強調したいのは、「バズったかどうか」ではなく、「どのようにバズったか」「どこに連れていくつもりか」という視点の重要性です。
アイドルやタレントが“友だちっぽい距離感”で投稿することが一時的に受けるのは確かです。しかし、それだけで継続的なファンになるわけではありません。公式とサブのアカウント同士が断絶していては、世界観が分断されてしまうわけです。
だからこそ、ホームルームと休み時間、すなわち公式とサブの二層構造をどう行き来させるか。そのデザインこそが、今後のTikTokをはじめとするショート動画ひいてはSNSのマーケティングにとって肝となります。バズを点で終わらせず、線に変え、面に広げていく。その視点をもてるかどうか、そしてその視点を仕組みやクリエイティブに落とし込めるアイデアの引き出しがあるかどうかが、明日のバズの“持続可能性”を決めるのではないでしょうか。
とまぁ安易にバズとかいいまくっていますけど、そんなに簡単にバズれたら苦労しません。いろんなアイデアを試しまくる他ないです。すなわち日々、さまざまなクリエイティブを見て、できるだけ多く打席に立ちましょう。私のXアカウント(https://x.com/dr_akesaka)でも主に興味深いプロモーション事例や、好きなアイドルの話題など発信していますので、面白い事例があればぜひリプライをください。