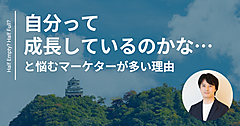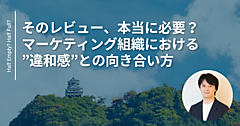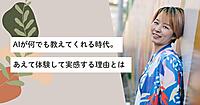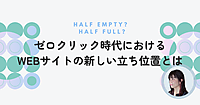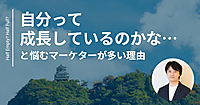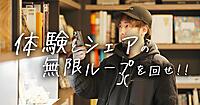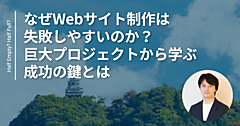みなさん、こんにちは。瀬川(@motoy0shi)です。
私がいるBtoBマーケティングの現場は、いつも施策で溢れています。検索広告、SEO、Webサイト改善、ウェビナー、展示会──。日々の施策をどう最適化すれば成果を上げられるか、常に頭を悩ませています。
そんな日々の中で、ある会議のワンシーンを今でも覚えています。「来月のウェビナーの集客目標をどうするか」という議題のとき、ふと誰かが口にしました。
……そもそもこのウェビナー、何のためにやるんだっけ?
その場が一瞬、静まり返りました。気づけば、私たちは「どうやるか(How)」ばかりを考え、「なぜやるのか(Why)」を語れていなかったのです。
この記事では、自戒も込めて、マーケターが「Why」から施策を始めることの重要性について考えていきたいと思います。日々の施策に追われている方にこそ、読んでいただけたら嬉しいです。
アクセス数が増えたのに、なぜ資料請求数は増えなかったのか?
以前、ある注文住宅メーカーの話を聞きました。
その会社では、資料請求数を増やすために「どうすればWebサイトのアクセス数を増やせるか」に頭を悩ませていました。コンテンツマーケティングの一環として、毎週コラム記事を更新したところ、アクセス数は増えていきました。しかし、肝心の資料請求数は思ったように増えなかったのです。
原因を調べてみると、アクセスの多くを集めていたのは「絵画をどう壁にかけるか」という記事。当然、この記事を読む人の多くは、注文住宅を検討しているわけではありません。「アクセス数」という指標は伸びても、目的である資料請求にはつながっていなかったのです。
その後、同社は方針を見直し、二世帯住宅など、もともと問い合わせが多かったテーマに注力することにしました。その結果、記事からの資料請求が着実に増加していったのです。
Howに追われるマーケティング。見失われた「Why」
なぜ最初から気づかなかったのか?
このように思うかもしれません。しかし、私たちの身の回りにも同じような「Whyの欠如」は数多く存在します。
新規リード獲得が目的のセミナーなのに、メルマガを打ちすぎて、申込者の多くが既存顧客だった
リードの質を重視して施策を最適化した結果、全体のリード数が激減した
広告のCPA改善に注力していたが、実は問題はLPにあった
私たちは施策を実施する際に、「何をやるか(What)」と「どうやるか(How)」に集中しがちです。その方が前に進んでいる感覚があり、仕事をしている実感も得やすいからです。
だからこそ、「なぜやるのか(Why)」が後回しになってしまうのです。
ゴールデンサークル理論に学ぶ、「Why」の重要性
では、なぜマーケティングにおいて「Why」が重要なのでしょうか。
ここで紹介したいのが、サイモン・シネック氏の提唱する「ゴールデンサークル理論」です。この理論では、人や組織の行動は、次の順序で考えるべきだとされています。
Why(なぜ)→How(どのように)→What(何を)
しかし多くの人や組織は、逆に「What → How → Why」の順に考えてしまう。シネック氏はこう述べています。
大半の組織や人間が、円の外側から内側に向かう順番で、つまりWHATからWHYの順番で考え、行動し、コミュニケーションをはかっている。(中略)私たちは、自分のWHAT(していること)は説明できる。とくには、HOW(手法)も説明できる。ところが、そうしているWHY(理由)を説明することはめったにない。
マーケティングでもまったく同じです。
私たちは「どんな施策をやるか(What)」「どう実行するか(How)」には敏感でも、「なぜその施策をやるのか(Why)」は忘れがちです。
そして、目的こそがもっとも重要です。なぜなら、Why次第で、その後のWhatやHowは大きく変わるからです。
たとえば、オフラインイベントを企画するとしても、目的によってすべきことは大きく異なります。次の表は、開催目的別に適したコンテンツと集客方法を整理したものです。
| 目的 | コンテンツ | 集客 |
|---|---|---|
| ①新規リードの創出 | 業界トレンドなど | Web広告など |
| ②既存リードからの商談創出 | 自社サービスの活用事例など | メールマガジン 営業からの個別連絡 |
| ③既存顧客(ユーザー)との関係強化 | 他社の活用事例など | カスタマーサポート担当からの個別連絡 |
このように1つのイベントであっても、目的(Why)次第で、そこから導かれる施策(What、How)は大きく変わります。だからこそ、施策の出発点に「Why」を置くことが欠かせないのです。
Whyから始めるための3ステップ
ここまで、Whyの重要性について考えてきました。では実際に、マーケティング施策の中でどう「Why」を考えればよいのでしょうか。
私は、施策の前・中・後の3つのフェーズで整理することをおすすめしています。
ステップ①施策を実施する前に「Why」を言語化する
最初のステップは、施策を始める前に「Why」を言語化して、記録しておくことです。GoogleドキュメントやNotionといったサービスを使い、次の2つを簡潔にまとめておきます:
- なぜこの施策をする必要があるのか
- どんな課題や背景があるのか
実際、私のマーケティングチームでは、タスク管理ツールでマーケティング施策を管理していますが、施策を立てるタイミングで「目的」や「施策背景」を記載して、上長にレビューしてもらうフローにしています。
きちんと目的が定まれば、自然と「ターゲット」や「KPI」「訴求するメッセージ」なども迷いなく考えられるようになります。
ステップ②施策中に、「Why」からずれていないか確認する
次のステップは、施策を進める中で定期的に「Why」を参照して、施策内容がズレていないかを確認することです。実際、マーケティング施策を走らせていくと、施策の目的がすり替わってしまうことはよくあります。
たとえば、ターゲットを絞ったメールマガジンを書いていて、「せっかくだから」と配信数を増やすためにターゲットリストを増やした。その結果、開封率は上がらず、むしろターゲット外の方からの配信停止(オプトアウト)が増えてしまった。こんな経験がある方も多いのではないでしょうか。
だからこそ、次のような問いを、定期的にチームで確認することが重要です。
そもそも、この施策は何のためだったのか?
同時に、この「そもそもの問い」を安心して発言できる文化をつくることが、マネージャの大切な役割だと思います。
ステップ③施策後に、「Why」に立ち戻って振り返る
最後のステップは、施策後の振り返りのタイミングです。
施策の振り返りでも、「結果が良かった・悪かった」だけでは十分ではありません。目的に照らし合わせたときに、次の2つまで振り返ることで、はじめて施策の振り返りは成立するのです:
- 本来狙っていた効果は得られたのか
- 目的は達成できたか
ここで振り返りを行うためには、きちんと目的が言語化され、記録されていることが必要不可欠です。だからこそ、ステップ①にある「施策前の言語化」が重要なのです。
おわりに
この記事では、マーケティング施策において「Why」から始めることの重要性について紹介しました。Whyを起点に考え行動すれば、施策はブレなくなり、結果として成果を出せる確率はずっと高くなるはずです。
まずはあなたも一度手を止めて、ぜひ1つでもWhyを考えてみてください。それが、施策をドライブさせる第一歩となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。