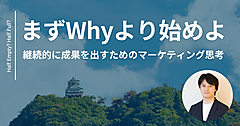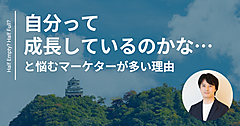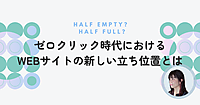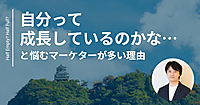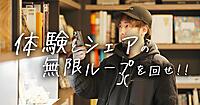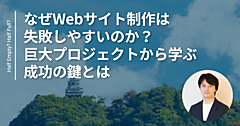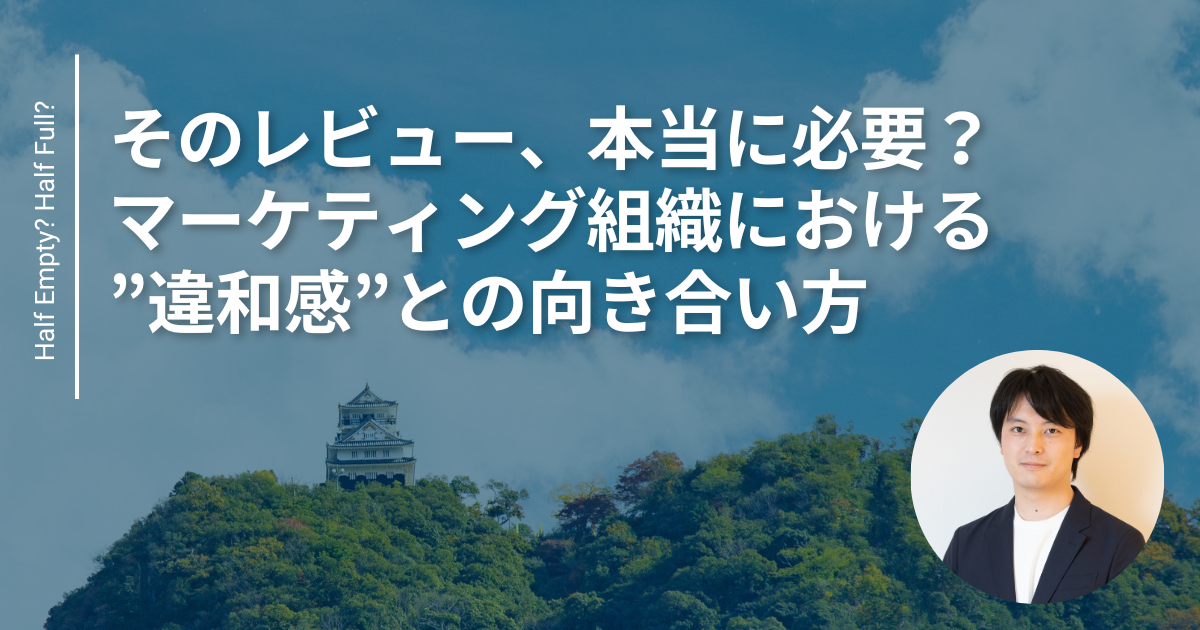
数年前、私がマーケティング組織を任されていた頃のこと。
ある日、チームメンバーのAさんが、ウェビナーの告知用に作成したメルマガ案を持ってきてくれました。
画面を覗くと、その内容は、以前に送ったメルマガとほとんど同じ。そこで私は思わず尋ねました。
このメルマガって、どういう意図でつくったの?
Aさんの答えは、こうでした。
前例を踏襲してこれにしました。
その瞬間、小さな違和感を覚えた私は、思わず少し強い口調でこう言ってしまいました。
考えた結果、前回と一緒なら問題ないよ。でも、ただ前例を踏襲したってことは、深く考えてないということだよね。マーケターとして、思考を放棄したらダメじゃない?
Aさんは黙り込み、トボトボと席に戻っていきました。
あれから数年が経った今、「あのレビューは、本当に必要だったのだろうか?」と自問することがあります。
マーケティングの現場では、レビューが日常的に行われています。クオリティを高めるため、成果を最大化するため、そしてメンバーを成長させるために。
しかし、レビューの仕方次第では、相手の創造性を奪い、改善するマインドを削ぎ、その人らしさを失わせてしまうことにもなりかねません。場合によっては、信頼や関係性にヒビが入ってしまうこともあります。
現在、私はマーケティングチームで、施策の企画や実行をリードしています。組織をつくり、業務を進めるうえで、レビューは避けて通れません。だからこそ、私は日々悩むのです。「この“違和感”を相手に伝えるべきか」と。
そこで今回の記事では、かつての自分の失敗や学びを振り返りながら、マーケティング組織における“違和感”との向き合い方、そしてレビューのあり方を考えてみたいと思います。
その“違和感”はどこから来るのか?
レビューをするとき、成果物が明確に「良い」「悪い」と判断できるのであれば、そこまで悩むことはありません。
実際の現場では、「良い」とも「悪い」とも言い切れない曖昧な領域に悩むのではないでしょうか。
- 方向性は間違ってはいないが、あまり刺さらなさそうな広告コピー
- 内容は問題ないが、デザインがしっくりこないバナー画像
- 経験的にはイマイチだと思うけど、明確に間違いでもないメルマガ構成
こういった成果物のレビューに、頭を抱えている人も多いのではないかと思っています。
そこで考えてみたいのが、その違和感の原因です。私の経験からすると、大きく分けて以下の3つに分類できると考えています。
① マーケティング理論や型
1つ目は、マーケティング理論や型からズレているケースです。
たとえば、「商談アポイントを今すぐ増やしたいのに、ウケ狙いで話題の登壇者をアサインしたセミナーを企画する」といったケースです。
確かに認知や集客にはつながるかもしれませんが、AIDMAやAISASなどの購買ファネルで見ると、「認知」は初期ステップであり、「検討」からはほど遠いため、今すぐの商談アポイントを増やす目的であれば、あまり有効な打ち手とは言えないでしょう。
ただし、理論や型から外れているからといって、それが必ずしも間違っているとは言えないのが難しいところです。
② 過去の経験に基づく直感
さらに難しいのが、2つ目の自分の“経験則”とズレているケースです。
業界経験が長くなってくると、さまざまな施策を経験しているため、自分の中に良し悪しのモノサシができてきます。
たとえば、「メルマガにおけるリンクは、テキスト形式よりもボタン形式の方が、クリック率が高い」といった経験則です。
確かに効果があることも多いですが、どんな場合でも適用できるとは限りません。
実際、私信風にレイアウトしたメールマガジンの場合は、ボタン形式よりも通常のテキスト形式リンクの方が、効果が高いこともあります。
だからこそ、自分の直感として違和感はあるけれども、どこまでレビューで指摘すべきかは非常に難しいのです。
③ 自分の感性や流儀
もっとも難しいのが、3つ目の自分の感性や流儀とズレているケースです。
たとえば、広告バナー画像に対して「自分ならこの配色を使わないな」と思うような場合です。このケースでは、レビューの基準がかなり主観的であり、良し悪しの判断が付きづらくなります。
自分の感性とズレていて違和感があったとしても、「間違いだ」とも言い切れないため、レビューはより困難になるでしょう。
違和感はまず言語化してみる
ここまで3つのケースを見てきましたが、重要なのは、違和感を覚えたときに「なぜ自分はそのように思ったのか?」を自問し、できるかぎり言語化してみることだと思っています。
言語化してみる中で、自分の思考が整理され、その違和感がどこから来るのかを意識できるようになるはずです。
もしうまく言語化できないのであれば、あえてその部分はレビューせずにいることも手かもしれません。なぜなら、レビューは相手を成長させることも、ダメにすることもできる両刃の剣であるからです。
レビューの功罪:伝えることで得られるもの、失うもの
多くの場合、レビューは「良い目的」のために行われます。
- より良い成果物をつくるため
- 炎上などの企業リスクを回避するため
- メンバーに気づきを提供し、成長を促すため
実際、私自身も、レビューを受ける中で、異なる視点からの気づきや学びを得てきました。
一方で、レビューする側は伝え方を誤ると、自分の思考や思想を相手に押し付けてしまうことになりかねません。
場合によっては、レビューが相手の良さを奪ってしまったり、相手を萎縮させてしまったり、「自分で考えなくなる」状況を作り出してしまったりします。
かつて私も失敗したことがありました。
メンバーの書いた記事原稿を添削したときのこと。私は「良かれ」と思って、記事の内容から表現まで、細かく赤(修正のコメント)を入れた結果、原稿は真っ赤になりました。
その原稿を見たメンバーは自信をなくし、記事を書くモチベーションまで失ってしまったのです。
このように、たとえ善意のレビューであったとしても、間違った形で伝わってしまうと、むしろ逆効果になってしまうことがあります。だからこそ、感じた違和感を適切な方法で取り扱わないといけないのです。
その成果物は誰のため? レビューの目的を忘れない
最後に、レビューを考えるうえで欠かせない視点があります。それは「その成果物は誰のためのものか」という視点です。
ここで、マーケティングディレクターであり、私の友人でもある稲田英資さんが書いた記事の一節を紹介します。
「Webコンテンツを評価するのは自分や上司じゃなくて顧客」
ぼくはこの考え方にかなりこだわっています。
(中略)
Webコンテンツの有益性を決めるのは上司ではありません。顧客です。その意味で社内の誰も答えを持っていません。たとえ社長でも。あるのは仮説です。その仮説に答えを出してくれるのが顧客です。Webコンテンツでぼくたちがやれることは仮説を立てて顧客に渡して評価してもらうことです。
「Webコンテンツを評価するのは自分や上司じゃなくて顧客」という言葉は、レビューの本質を突いています。
本来、レビューは良い成果物を作り、事業を伸ばすためにあります。すなわち、レビューは、事業成長を叶えるための手段に過ぎません。
そして、その成果物の価値を決めるのは、自分でもなければ、社内の誰かでもなく、顧客です。極論、自分に違和感があっても、顧客が高く評価していれば、良い成果物なのです。
もし顧客の評価ではなく、社内の「正解」を追ってしまえば、レビューは自己満足になってしまいます。
だからこそ、自分の違和感でなく、「顧客にとって価値あるアウトプットであるか」が重要なのです。
おわりに
この記事では、マーケティングにおける違和感との向き合い方、レビューのあり方について考えてきました。
レビュー時に感じる“違和感”は、決して悪いものではありません。むしろより良いアウトプットを作り、組織を成長させるためには必要なものです。
一方で、その”違和感”の取り扱い方を間違えると、信頼関係を壊したり、組織の成長を妨げたりすることにもなりかねません。
私自身、いまだにレビューの「正解」はわかりません。「違和感を言語化して伝える」ことと、「あえて言わずに見守る」ことの間で、今後も迷いながら正解を探り続けていきたいと思っています。
もしあなたが、レビューで違和感を覚えたなら、まずはこのように自問してみてください。
- 「この違和感は、顧客視点から生じたものなのか、自分の感性からなのか?」
- 「この人はどういう意図で、こうしたのだろうか?」
こうした小さな問いかけが、レビューの質を少しずつ高めてくれるはずです。
皆さんは、どのように“違和感”と向き合っているのでしょうか? ぜひXなどで、お考えを聞かせていただけたら嬉しいです。