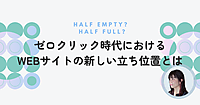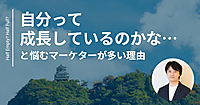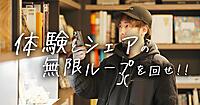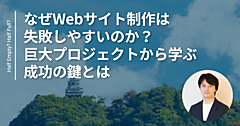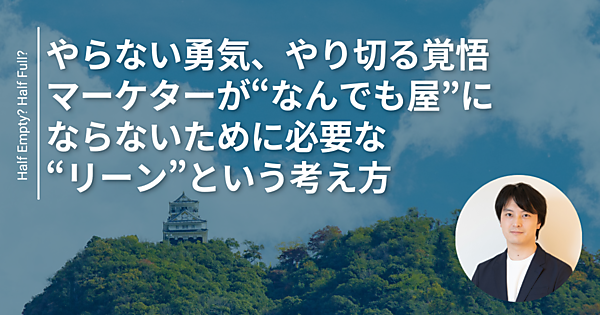
みなさん、こんにちは。瀬川(@motoy0shi)です。
突然ですが、マーケターのみなさん、やることに追われていませんか?
マーケターは、とかく「何でも屋」になりがち。Webサイト運用、広告運用、ウェビナーや展示会の企画、ホワイトペーパー制作、MA運用などなど。やらなければならないことは無限にあり、社内からも頼まれることが多いはずです。
一方で、ほとんどの会社では、社内にマーケターと呼ばれる人は多くても数人。大量のタスクに追われて、気づけば今日が終わり、今週が終わり、今月が終わる。そのうち「そもそも何のためにこの仕事をやっているんだろう」と、自己嫌悪に陥る。もしかしたら、そんな人もいるかもしれません。
じつは私もかつて同じような経験をしました。そして思ったのです。「すべてを自分で、うまくやろうとすることを諦めよう」と。
忙しすぎるマーケターこそ、「やらないこと」を決めることで、より大きな成果を生み出せる。今回の記事では、そんな「リーン(Lean)」思考について考えていきます。
ひとりで抱え込んだ結果、動けなくなったあの日
しばらく前のことです。
私は、大型のプロジェクトの責任者として、日々忙しく働いていました。当時の私は、「自分が一番わかっているから」と、何でも自分でやろうとしていました。
とはいえ、どれだけ努力をしても、膨大なタスクはなかなか減りません。次第に、タスクは遅延し、残業は続き、日に日に疲れ果てていきました。
ある日のこと。夕方まで勤務したのですが、どうも頭が回らなくなってきたので、いったん仮眠をすることに。在宅勤務だったので、「とりあえず20分だけ……」と、アラームをかけて目を瞑りました。
20分後。アラームの音を聞き、「仕事しなきゃ」と体を起こそうとしたものの、どうにも力が入りません。数メートル先の机に向かおうとしても、まったく動けなくなりました。
そしてようやく気づいたのです。「あ、本当に疲れているんだ」と。
“任せる怖さ”を超えた先に見えたもの
あの経験は、私の思考を180度変えました。
それまでの私は、何でも自分でできるし、人よりも上手にできると思っていました。かつて個人事業主として働いていた経験もあるので、どこかで自分の努力を過信していたのかもしれません。
しかし、それは傲慢でした。結局、自分ひとりには限界があるし、大きな成果を上げることはできないのだと、今さらながら気づいたのです。
そのときから、「チーム」でどうすれば成果を最大化できるかを考えるようになりました。
ただ、チームとして働くうえで一番苦労したのが、「タスクを手放す」ことでした。
何でも自分でやってしまう性分の私は、人に任せることがとても苦手だったのです。でも今思えば、その根本には、相手をどこか信じきれていなかったのかもしれません。
しかし、誰かに任せなければ、状況は何ひとつ変わりません。だから、思い切って任せるようにしました。
もちろん、任せた結果うまくいかないこともありました。しかし、その原因はたいてい自分のほうに問題があることが多かったのです。たとえば、意図をきちんと伝えていなかった、丸投げをして途中経過を見守らなかった、などです。そういった経験を通して、自分自身のマネジメントスキルが身についていったように感じます。
そうして少しずつ任せるようになると、当然自分のタスクは減っていきます。そうすることで、以前よりも自分が価値を出せる仕事に集中できるようになってきました。
また、任せることでチームメンバーのスキルや知識、持ち味が発揮され、全体としてより良いアウトプットができるようになっていったのです。
以前の私は、「自分がどれだけ頑張ったか」が重要でした。しかし今は、「いかに自分が頑張らなくても、全体として成果を上げられるか」を大切にしています。
マーケティングで重要な「リーン」という考え方
みなさんは、「リーン」という言葉をご存じでしょうか。
リーンとは、「無駄がない」「無駄をなくす」という意味の英語です。そして、マーケティングの仕事においても、この「リーン」という概念がとても大切なのです。なぜなら、私たちは誰もが24時間しか持っていないからです。
私が好きな書籍『エッセンシャル思考』(グレッグ・マキューン著、かんき出版)では、「より少なく、しかしより良く」というフレーズが出てきます。
マーケティングでも同じです。「より少ない施策を、より良く実行」することが重要なのです。すべての施策に取り組む必要はありません。
しかし、マーケターは気づいたら“何でも屋”になりがちです。
- とりあえず出席しているけど、まったく発言していない会議
- 以前に頼まれたから報告しているけど、誰も見ていないレポート
- やることが目的化して、振り返りもまったくしていないセミナー
こういったものが積み重なり、本当に集中すべきことに集中できていないことも少なくありません。
やったほうが良い施策は山のようにあります。しかし、多くの場合、今やらなくてもよいことは意外に多いのです。むしろ10個を中途半端にやるくらいなら、3個を最後までやり切るほうが、ずっと成果は大きいものです。
だからこそ、忙しいときほど立ち止まって、「何をやらないか」を決めることが重要なのです。
「やめる勇気」を持つための3つの判断軸
では実際に、何を「やらない」と決めるか。それにはいくつかの判断軸があります。
私が「やらないこと」を決めている判断軸は、以下の3つです。
- ①自分でなくてもできること
- ②事業成長やお客様のためにならないこと
- ③「今やるべきだ」と本気で思えないこと
実際、私は①の判断軸に従って、自分がこれまで担ってきた業務を少しずつ他のメンバーに委譲しはじめています。たとえば、SQLを書いてダッシュボードを構築する仕事は、私が入社当時から取り組んでいた業務でした。しかし最近は、入社してきたメンバーに譲り、その成果を見守っています。
中には、自分として取り組むのが好きな仕事もありました。しかし、自分がいつまでも抱えていては、自分のキャパシティはいっこうに増えません。だからこそ、あえて“やらない”ことを決めたのです。
また、ウェビナーについても、とにかく新規コンテンツを作ることをやめました。これまでは新規コンテンツを作ることが重要だと考えていましたが、かなりの工数を取られていました。そこで、アタリの良いコンテンツを丁寧に企画し、成果が出たものをアーカイブとして再配信することで、労力を最小限に抑えながら成果を伸ばすことができました。
おわりに
今回の記事では、マーケターにこそ重要な「リーン」という思考について考えてきました。
あなたが今取り組んでいることの中に、「本当に今、やるべきこと」はどれくらいあるでしょうか。また、その中で「手放してよいこと」はどれくらいあるでしょうか。そして、手放すことで生まれる“余白”には、何を注ぎたいですか?
「やらないこと」を決めることは、自分にとっても、組織にとっても、大きなプラスになる決断です。
この機会に、ぜひご自身の業務を棚卸ししてみてください。