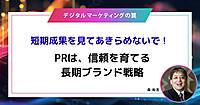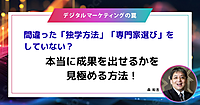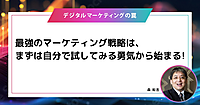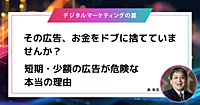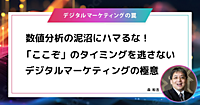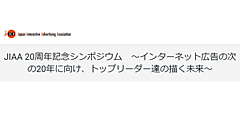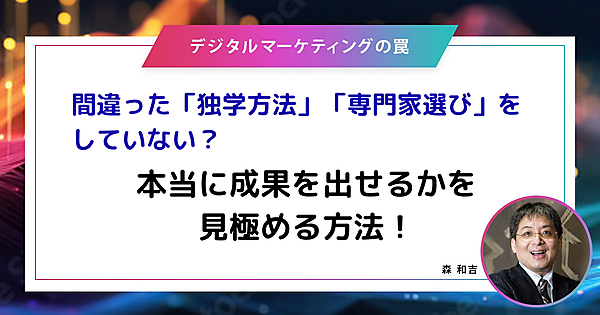
こんにちは。Webコンサルタントの森和吉です。
デジタルマーケティングは進化が速い。だから、常に学び続けなければならない
みなさんは、日々そう感じながら、書籍やオンライン記事、セミナーなどで必死にインプットを続けていることでしょう。その姿勢は、間違いなく正しいものです。実際、ほんの数年前の常識が、今や全く通用しないのがこの世界です。
しかし、ここで一つの「罠」について考えてみてください。
あれほど学んでいるのに、なぜか成果が出ない
知識は増える一方なのに、実務で何から手をつければいいのか、いつも迷っている
もし皆さんがそう感じているとしたら、それは、独学の罠に陥っているサインかもしれません。学べば学ぶほど、なぜか成果から遠ざかる。その努力が、ぐるぐる間違った方向に向かってしまい、貴重なリソースを浪費してしまう危険性です。
そして、その独学の限界に気づいた先に、さらに深刻な次の罠が待ち受けています。今回は、なぜ真面目な独学が失敗に終わるのか、その限界をどう突破すべきか。そして、最大の難関である「本物の専門家」と「経験に基づかない偽物の専門家」をどう見極めるか、という話をします。
失敗事例1 オウンドメディアの独学が「負債」になる瞬間
「独学が間違った方向に向かう」とは、具体的にどういうことか。ここで、私が相談を受けたあるBtoB企業A社の事例をご紹介します。
A社のWeb担当者になったBさんは、非常に真面目で勉強熱心な方でした。入社直後から「これからはオウンドメディアだ」と独学で学び、自社ブログを立ち上げました。彼は夜遅くまでSEOに関する本を読み漁り、「とにかく記事を量産することが重要だ」と理解。「これで会社に貢献できる!」と意気込み、残業を厭わず取り組んでいました。
彼が学んだのは、以下のような数年前の「古いSEO」の知識でした。
- 間違った戦術① キーワードの詰め込み:学んだ情報に基づき、記事タイトルやh1タグに、対策キーワードを不自然なほど詰め込みました。
- 間違った戦術② 低品質なコンテンツの量産:ユーザーの検索意図や悩みを深く考えるよりも、質より量という古い考え方を信じ、似たような内容の記事を次々と公開していきました。
- 間違った戦術③ スパム的なリンクビルディング:外部リンクが重要と学び、自動でリンクを増やすような、今では明確にスパムと判定されるツールに手をだしてしまいました。
Bさんは半年間、上記のような間違った学びに基づいて、ひたすら記事を書き続けました。しかし、成果は一向に出ません。それどころか、ある日のGoogleのコアアップデートを境に、サイト全体の検索順位が圏外に吹き飛んでしまいました。Bさんの半年間の努力は、成果ゼロどころか、ペナルティという負債を生み出してしまったのです。
なぜBさんは失敗したのか? 「真面目さの罠」の本質
Bさんの悲劇は、彼が怠惰だったから起きたのではありません。むしろ、彼が真面目な独学者だったからこそ起きたのです。独学の最大の危険性は、手にした情報が、現在の正解なのか、過去の正解なのか、その賞味期限を判断できない点にあります。
Bさんは「How(どうやるか)」、つまりキーワードを詰め込む、記事を量産するといった「戦術」は学びました。しかし、Googleがなぜそのような戦術を(かつて)評価したのか、その背景にある「Why(なぜやるか)」、すなわち「ユーザーの利便性を第一に考える」という「原則」を理解していませんでした。だから、Googleがその「原則」をより追求するために「戦術」(アルゴリズム)を変更した際、Bさんは対応できなかったのです。
これが独学の限界です。表面的なノウハウ(How)ばかりを追いかけ、普遍的な本質(Why)を見失うと、努力はすべて無駄どころか、マイナスにさえなり得るのです。
失敗事例2SNS運用で起きた「アルゴリズムの落とし穴」
似たような罠は、SEO以外でも起こります。たとえば、私の知るある中小企業C社の事例を紹介しましょう。Dさんは独学でX(Twitter)運用を始め、「バズるためのハッシュタグ活用」を本や記事から学びました。毎日、投稿を繰り返し、トレンドタグを詰め込み、フォロワーを増やそうと奮闘。
しかし、Xのアルゴリズム変更(2024年の大規模アップデート)で、突然エンゲージメントが激減。半年の努力が水の泡となりました。Dさんもまた、短期的な戦術に囚われ、「ユーザーとの本物のつながり(Why)」を軽視していたのです。この事例からも、独学の賞味期限切れリスクが、どんなチャネルでも共通していることがわかります。
失敗事例3助けを求めた専門家が「偽物」だった
さて、A社のBさんはオウンドメディアの失敗で独学の限界を痛感し、外部の専門家(コンサルタント)にSEOを依頼することにしました。しかし、ここにさらに根深く、見抜きにくい罠が潜んでいます。それは、助けを求めた専門家が、「実体験」を持たず、「ググった情報」や「他人の成功事例のコピー」だけで語る偽物である可能性です。
Webコンサルタントは、弁護士や医師と違い、資格が必要ありません。極端な話、誰でも今日から「Webコンサルタント」と名乗れてしまうのです。このような偽物の専門家は、Bさんと同じ穴に落ちています。彼らは「独学者のBさんより、少しだけ先にググった人」に過ぎません。
たとえば、彼らはこんな提案をしてきました。
A社さんの問題はE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)が低いことです。すぐに著者のプロフィールを整備し、専門家の監修を入れましょう
一見、最新のSEOの知識を反映した正しい指摘に見えます。しかし、彼らはA社の顧客について一切質問しません。
- 「御社の顧客が、本当に解決したい課題は何ですか?」
- 「競合ではなく、御社を選ぶ理由はどこにありますか?」
- 「その顧客は、普段どんな情報に触れていますか?」
こうした本質的なヒアリング(診断)をせず、いきなり「E-E-A-T対策をしましょう」と手段(処方箋)から入る。これは、ろくに問診もせず「とりあえず最新の薬を出しておきますね」という医者と同じです。彼らの知識は、A社のビジネスの成功ではなく、アルゴリズムの機嫌を取る(最適化する)ことにしか目を向けていません。彼らもまた、Bさんと同じく「アルゴリズムに踊らされている」だけなのです。
「偽物」と「本物」を見極めるチェックリスト
では、どうすれば「ググっただけの専門家」と「経験豊富な本物の専門家」を見分けられるのでしょうか。私が商談の場などで意識しているポイントを、チェックリストとして共有します。
| チェック項目 | 偽物の専門家(ググっただけ) | 本物の専門家(経験豊富) |
|---|---|---|
| 提案の切り口 | 「SEO対策をしましょう」「AIを活用すべきです」(手段・戦術から入る) | 「御社の顧客は誰ですか?」「ビジネス上の課題は何ですか?」(ヒアリング・戦略から入る) |
| 実績の示し方 | 「大手企業の支援実績多数(社名非公開)」(曖昧で検証不可能) | 「前職のC社ではXXという課題に対し、△△の仮説を立て…」(プロセスが具体的) |
| 使う言葉 | 「絶対に儲かります」「3か月で売上2倍」(根拠なく断言・誇張する) | 「この施策のリスクは〇〇です」「まず仮説Aを検証しましょう」(現実的で、プロセスを提示する) |
| 議論の焦点 | アルゴリズム、最新ツール、バズワード | 顧客の課題、カスタマージャーニー、ビジネスモデル |
| 契約への態度 | 質問をはぐらかし、契約を急かす | 疑問に丁寧に答え、スコープ(業務範囲)を明確にする |
もし、あなたが相談している相手が「左側(偽物)」の特徴に多く当てはまるなら、いくら最新のバズワードを口にしていても、注意が必要です。
解決策「本物の専門家」とは何か?
「本物の専門家」は、戦術(How)ではなく、「戦略(Strategy)」と「原則(Why)」を語ります。彼らの価値は、ググればわかる知識を教えることではありません。彼らの頭の中にある、多様な業界での「成功体験」と、それ以上に価値のある「失敗体験」のデータベースこそが、彼らの価値の源泉です。
私が過去に支援した成功事例、あるいは同業者のすばらしい事例には共通点があります。
- カスタマージャーニーマップの作成:ある電機メーカーでは、専門家を招き、まずカスタマージャーニーマップの作成から着手しました。これは顧客を理解するという戦略そのものです。
- 専門家と一体になってPDCAを回し続ける:ある大手企業では、伴走型の支援を行う専門家を選び、一体になってPDCAを回し続けました。納品して終わりではない、本物のパートナーシップを築きました。
- 顧客視点への徹底的な転換:ある消費財メーカーの場合は、単なるカタログ型のサイトを、ユーザーが目的別に探せるように再構築しました。これも顧客視点への徹底的な転換です。
本物の専門家は皆、「SEO対策」や「広告運用」といった手段から始めません。「顧客理解」という「戦略」から始めるのです。また、本物の専門家を雇う最大のメリットは、短期的な成果を得ることではありません。彼らとともに働くことで、成果の出し方そのものを、自社の組織に根付かせることなのです。
あなたの「独学」をリテラシーに変えよ
ここまで読んで、「もう独学はやめて、全部専門家に丸投げしよう」と思った方。それこそが、大きな罠です。マーケティングで成果を出している企業は、必ず自社内のリーダー(担当者)自身が深くコミットしています。外部への丸投げは、最も典型的な失敗パターンです。独学が無意味なのではありません。
あなたが必死に独学で学ぶべきなのは、あなた自身がスーパープレイヤーになるためではありません。あなたが独学で得るべきなのは、「偽物の専門家」を見抜き、「本物の専門家」の力を最大限に引き出すための「リテラシー(読み書き能力)」なのです。
自社に基礎的な知識がなければ、外注先との連携は円滑に進みません。リテラシーがなければ、「絶対儲かる」という偽物の甘言に騙されます。たとえば、「カスタマージャーニーマップを作りましょう」と提案する本物の専門家の価値がわからず、まずはSEO対策という手段を用いようとするBさんと同じ過ちを繰り返してしまいます。
独学は、本物の専門家と仕事をするための前提条件なのです。明日から、小手先の戦術を追いかけるのは、やめましょう。なぜ顧客はあなたを選ぶのか? 顧客が本当に解決したい課題は何か? その「Why」を考えることこそが、あなたの「独学」を、無駄な努力ではなく、未来の成果につながる「リテラシー」に変える、唯一の道なのです。