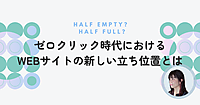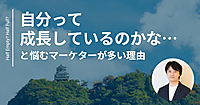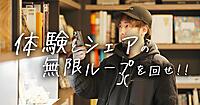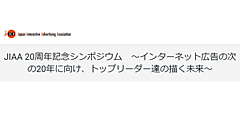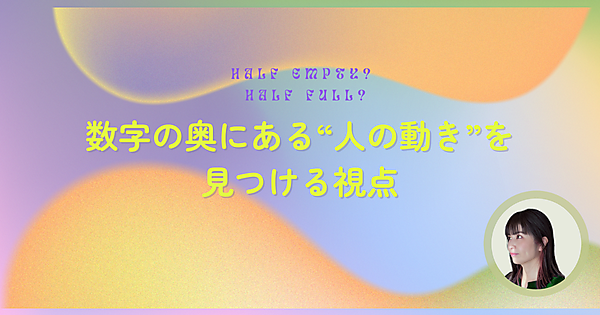
デジタルの現場で忘れがちな「人」の存在
数字が教えてくれるのは、あくまで“結果”
デジタルマーケティングやWebサイト運営、ECサイトでの商品販売や、SaaS型サービスの継続率向上・利用促進に取り組んでいると、KPI(重要業績評価指標)や数値データを主軸にした判断に陥りがちです。CVR(コンバージョン率)、UU(ユニークユーザー数)、直帰率など、明確に可視化された指標は改善アクションを導きやすく、便利な判断材料になります。
しかし、数字が教えてくれるのは“結果”であって、その裏にある“理由”や“背景”までは明かしてくれません。ユーザーの困りごと、迷い、不満、そして行動のきっかけ。そうした要素に目を向けなければ、プロダクトやサービスの改善は本質からズレていきます。
たとえば、店頭でユーザーが商品を探して迷っていたり、使い方がわからず困っていたりする様子を目にすると、体験のデザインがいかに重要かを実感します。一方で、Webサイトやアプリといった一枚のインターフェースを挟むと、そうしたリアルな反応が見えづらくなり、数字の変化のほうが大きく見えてしまうという構造的な難しさもあります。
数字には現れない文脈や目的に目を向ける
数字を指標として活用しながらも、そこで何が起きているのか、なぜそうなっているのかを常に問い直す視点が必要です。
たとえば、BtoBの管理画面を開発している場合を考えてみましょう。店長のような管理者的な立場の人が売上を確認するためにログインするケースと、販促担当者がクーポンやキャンペーンの設定を行うためにログインするケースでは、同じようにダッシュボードを閲覧していたとしても、その背景にある目的や状況は大きく異なります。
ところが、ログデータだけを見ると「ダッシュボード閲覧」という同一の行動としてカウントされ、ユーザーの多様な利用意図が見過ごされてしまう可能性があります。私自身、ユーザーインタビューを実施し、「おそらくこのような課題があるだろう」という仮説をもとに、UIをアップデートしたりしたのですが、明確に変化を起こしたいユーザーの行動を事前に明文化しておらず、結果、「このUIで結局良かったんだっけ?」ということになることもありました。
このように、数字には現れない文脈や目的に目を向けることで、より本質的な改善の糸口が見えてきます。今回のテーマでは、ユーザー体験の全体像をどう捉えるかについて、考えてみたいと思います。
ユーザー行動はサイトの内側だけではない
多くのUI改善や機能追加などのWeb施策や分析は、サイト内でのユーザー行動にフォーカスしがちです。しかし、ユーザーがサービスやプロダクトをどのように認知し、比較し、最終的に意思決定するかというプロセスは、訪問前・訪問中・訪問後を含めた非連続の流れで構成されています。
たとえば、ユーザーが友人から商品名を聞き、それをスマートフォンで検索するとします。まさにここから体験が始まります(訪問前)。その後、サイトをざっと確認し、さらに比較サイトへ移動して情報を集めます(訪問中)。最終的に、Webサイトでは購入せず、実店舗で商品を手に取って購入することもあります(訪問後)。
このように、ユーザーの行動や判断は複数のチャネルやタイミングをまたいでおり、単一のページ遷移やコンバージョン完了といった「点」で評価しても全体像は見えてきません。サービスやプロダクトを企画する初期段階では、マーケティングファネルで、この辺のユーザーの心理の変化やチャネルなども考慮して設計します。
しかし、いざ運用期になるとすっぽりこの考え方を忘れてしまうことがあります。不思議だなぁと思うのですが、皆さんも心当たりはありませんか? サービス全体の“使われ方”を設計し、把握し続けていくことが重要です。
AIOで"サイト訪問前の体験"がさらに重要に
流入前のステップの行動でいうと、検索サイト上でのユーザー行動を想像して、そこを改善することが考えられます。最近では、AIO(AI Optimization)という考え方が浸透してきています。従来のSEO(Search Engine Optimization)が「検索後の最適化」だったのに対し、AIOはより一層「検索前の意図を捉える」ことを重視しています。
ユーザーが検索する前から「自分に合う情報がある」と期待し、検索した瞬間に「自分のことを理解してくれている」と感じ、読み終えたときに「これにしよう!」と納得できる体験を提供することが、AIOにおいては重要です。
これはまさにUXの仕事であり、「どんな情報が・どんな状況で・どんなニーズをもつ人に・どう届くか」を意識した体験設計が鍵になります。
AIとの対話がもたらす新しい検索体験
検索前の意図を捉えるAIO的なアプローチが進む一方で、サイト訪問中の体験そのものもAIの力で進化しています。たとえば、生成AIによる商品検索サポート機能は、訪問中における体験の質を高める新しい手法の一つです。
ECサイトでは以前から、ユーザーの過去の行動や属性に基づいてパーソナライズした情報を提示したり、レコメンデーションによって最適な商品を提案したりする手法が一般的でした。こうした手法は、あらかじめ用意された選択肢から選ばせるアプローチであり、ユーザーがその場で自由にニーズを表現することは難しい側面があります。
一方で、生成AI型のサイト内での検索体験では、ユーザーが自ら背景や状況を入力し、AIとの対話を通じて求める情報へとたどり着くことができます。ユーザー自身の言葉でニーズを表明できるため、状況に応じた柔軟なサポートが可能になり、より個別最適な体験が実現されます。
このような仕組みは、「よくある質問」や「カテゴリから選ぶ」といった静的なナビゲーションとは異なり、ユーザーの意図や課題の解像度に応じてアプローチできる点が大きな利点です。AIOやEEAT(Experience、Expertise、Authoritativeness、Trustworthiness)といった考え方とも親和性が高く、検索前後の接点でユーザー理解や信頼関係の構築をするうえで有効な手段となるでしょう。
AIを活用した体験設計のアプローチは今後も拡張していきますが、本稿ではそのなかでもとくに「検索前」と「検索中」に着目し、ユーザー視点での改善のヒントを探りました。