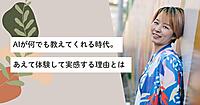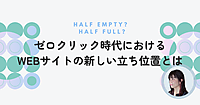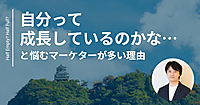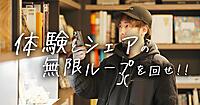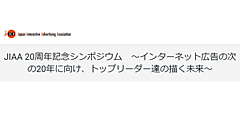安くても売れない? 高くても売れる? 価格と価値の関係をマーケター視点で考察
マーケターによるリレーコラム、今回は花王の辻本光貴氏。今回は価格戦略について考察しています。
2025年4月1日 7:00
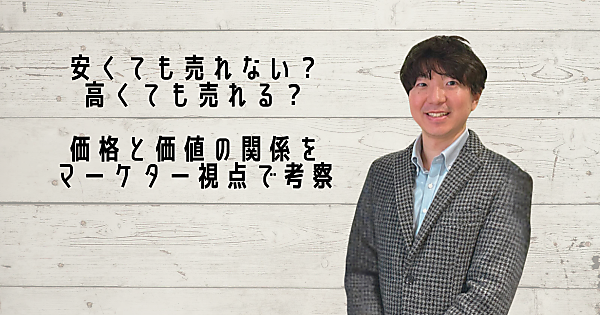
こんにちは、花王株式会社の辻本です。今回は価格について考えます。
物価高騰で人々の生活が変わると同時に、企業の価格戦略は非常に重要になりました。サービスの質が価格に見合っているか、消費者はますます厳しく検討するようになってきたからです。
消費者は見合う価格かを厳しく検討している
例として、私がある論文添削サービスを利用した体験をお話しします。私は数年前にある資格試験に合格しました。その試験には論文試験があり、その対策をしようとネット検索をしたところ、ある企業の論文添削サービスをみつけました。値段は11,000円。オリジナル問題が用意されて2回添削を受けられる講座でした。
この講座を受講するかを検討している際、気になった点がいくつかありました。
論文を郵送するため添削完了まで1か月かかる
この講座は論文を郵送するため、添削結果が手元に戻るまでに2週間程度かかり、合計で1ヶ月くらいの猶予を見ておかないといけません。この1ヶ月という期間は、受験生にとっては長すぎると思います。なぜなら、受験者はあまり勉強時間がとれない社会人が多く、だいたい3~4ヶ月前に勉強を初める人が多いからです。
つまり、多くの人が短期集中型で勉強をするわけです。私もその1人でした。受験勉強にかける3~4ヶ月のうちの1ヶ月を論文添削サービスに割くことになります。これは、勉強期間の1/4の時間です。添削結果をもとに論文をブラッシュアップする時間が少なく、「もう少し時間がほしい」と感じる人もいるでしょう。
添削サービスの11,000円は高いのか、安いのか、適正価格なのか
2025年現在の受験料が7,500円で、参考書は1冊2,000円程度。添削サービスが11,000円。1回の受験に対するお金のかけ具合によって、添削サービスの価格をどう感じるかは人によって異なります。私の場合、すぐに合格をするためにも客観的な視点で自分の論文を見てもらいたかったので、この添削講座を受講することに決めました。
実際に購入して受講したところ、サービスの質も良かったので、結果的には大満足でした。送った論文に対して減点箇所やランク別の合格可能性が書いてあり、受験の参考になりました。しかし、なかには価格や添削結果が戻るまでの期間を理由に、購入を諦めた人もいるかもしれません。
顧客がどのように考えているのかをふまえた価格戦略
そのような経験をふまえて、1回5,000円で、自らが添削する「論文添削サービス」を提供することにしました。私は「文系職種であり、資格の合格者」です。
「早く、安く、高品質な論文添削を行う」「論文の書き方やIT技術者が気づかないマーケティング上の落とし穴を解説できる」という強みを生かしたサービスです。
Wordファイルの論文をネットで送付してもらうため、郵送の時間やお金は不要。サービス提供側の私も、自らが添削を行うので、スキルマーケットの仲介手数料が売上から引かれる程度なので、5,000円でも十分利益がでます。
論文添削サービスを自ら提供:独自性は「文系職種の資格合格者」
また、「文系職種の資格合格者」という点がサービスの独自性につながっています。よくある論文添削サービスはノウハウを教わった“添削担当者”であり、実際の合格者かどうかはわかりません。また、IT技術者がこの試験を受ける場合、彼らは経営やマーケティングの専門知識が備わっているとは限らないため、論文内容が現実に則していないことがあります。
IT技術者の論文を読むと、技術的には可能で、具体的にどのようなシステムであるかを説明する点は上手ですが、事業概要の説明が不足していたり、事業の持続可能性が担保できていなかったりする場合があります。そうした側面を私の添削で補い、合格に導いています。つまり、徹底的に顧客に合わせた添削サービスの提供を行っているわけです。同じ添削サービスであっても、既存の論文対策講座が提供する価値とは異なります。
結果、これまで何度も受注をうけており、確実にニーズがあるものだとわかりました。今後もこのサービスを認知してもらって、より多くの発注がくるように仕掛けていきたいです。
価格を上げるには注意が必要! 顧客の価格受容性を考えよう
さて、話を戻しつつ問題提起です。
「価格と提供価値が見合っているのか、そして交換が成立するのか」という経済活動の基本を考えたときに、売上や利益を伸ばしたいからといって、価格を単純に上げてよいでしょうか。ダメですよね。顧客の価格受容性を考えなければいけません。
仮に売上をもっと上げたいという理由で、5,000円の論文添削サービスを7,000円にしたり、既存の論文添削講座と同じように11,000円にまで引き上げたりしたら、どうなるでしょうか。
「スピードは早くても1回しか添削しないのか、それでこの価格か」
「企業の添削サービスと比べたら添削実績が少ないな、それでこの価格か」
というネガティヴな反応が出てくるかもしれません。しかし、一方で、
「大手とは違って、実際の合格者が文系の視点でも見てくれるから、この価格でも納得」
「レビューに好意的な意見が多くて評価が高いから、この価格でも納得かも」
というポジティブな反応もあるかもしれません。
では、このポジティブとネガティヴの分かれ道に関わる大事なことは何でしょうか。それは、サービスに対するブランドイメージと、顧客の価値観のマッチングです。ブランドイメージと顧客が求める価値のマッチングが成立した商品やサービスであれば、ポジティブな反応をもつ人は多いため、価格は上げやすいはずです。
そのときに、対象市場で求められる価値の優先順位も視野に入れる必要があります。対象顧客が何を優先しているかによって、顧客数も価格受容性も変わるはずです。先ほどの論文添削サービスを例に考えてみると、単純な勝負に置き換えるなら「安心・信頼」vs「早さ」という価値の勝負かもしれません。
つまり、資格試験を受ける人にとって「早さ」が最重要価値の場合、私のサービスの方が戦いに有利で価格を上げやすく、「安心・信頼」が最重要価値の場合、大手サービスの方が戦いに有利で価格を上げやすいというわけです。
ブランドエクイティをふまえた価格設定を
プライシング(価格戦略)というと、テクニカルな感じに聞こえてしまう人も多いようですが、経済学の基礎「交換」に立ちかえると、シンプルにとらえることができます。経済活動の基本は「交換」です。「交換」が成立しない価格まで引き上げたら、顧客が離れてしまいます。
プライシングは、顧客が求めるものを提供できているかという前提条件のなかで、最も売上、利益が最大化できる価格はどこかという議論になります。これは、ブランド論と切り離せません。その前提条件を考えずに、“適正な価格”を議論すると顧客が離反して、売上、利益が最大化できると踏んだ“適正な価格”は的外れになります。
京セラやKDDI、日本航空でお馴染みの稲盛和夫氏は、著書『稲盛和夫の実学 経営と会計』のなかで次のように述べています。
顧客が喜んで買ってくれる最高の値段を見抜いて、その値段で売る。その値決めは経営と直結する重要な仕事であり、それを決定するのは経営者の仕事なのである
深く考慮せずにプライシングをしてはいけないことがよくわかる一言ですね。では、その価格の上げ幅の根拠になるものは何でしょうか。それはブランドエクイティです。
ブランドエクイティとは
ブランドエクイティとは、製品やサービスに与えられた付加価値です。この価値は生活者があるブランドに関して、どう思い、感じ、行動するかに反映されており、心理的価値と財務的価値をもつ重要な無形資産です。
これによって生活者のWTP(Willingness to Pay:支払意向額)が変わっていきます。企業買収に詳しい人は“のれん”という言葉を思い浮かべるとイメージがつかみやすいかもしれません。
つまり、あなたが担当する製品やサービスのブランドエクイティが、生活者にとってどの程度の価値なのか、把握できていないといけません。自分では“価値がある”と思っていても、生活者からみて“価値がない”と判断されていれば、ブランドエクイティを見誤っているわけで、値上げしたら離れてしまいます。その点を調査で明らかにしながら、WTPを探ることが重要です。
多様な価格戦略が世の中には存在する
さらにブランドエクイティに加えて、場所や状況に合わせて戦略的に価格を変えている事例もあります。たとえば、来園ピークに合わせて入園料金を変える遊園地、地域によってメニュー価格が違う飲食チェーン店、雨の日割りなどでうまく価格を変えて購買喚起するアパレル店、使用目的に合わせて複数プランを設けるSaaSを提供する企業など、価格戦略で参考になる事例が数多くありますよね。
私は自分が始めた論文添削サービスでは、「早さ」という価値に着目。通常なら1週間程度で返すものを、追加料金を払えば3日程度で論文添削をする追加オプションも用意しました。また、「塾講師の経験あり」という価値で論文以外の文章問題添削を追加料金で対応したりなど、顧客のニーズに合わせて売上を増やす工夫をしています。
「ブランドエクイティの現状把握と価格設定」は、業界も業態も関係なく経済活動に関わるすべてに共通する論点なのです。厳しい経済環境で、企業や個人はこれまで以上に自分が支払うお金をより真剣に考えています。そうした環境下でのプライシングは、企業が取り組むべき最重要課題の1つともいえるでしょう。