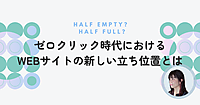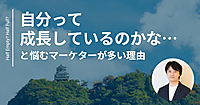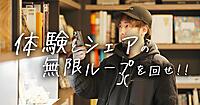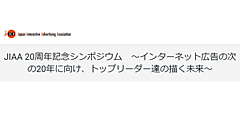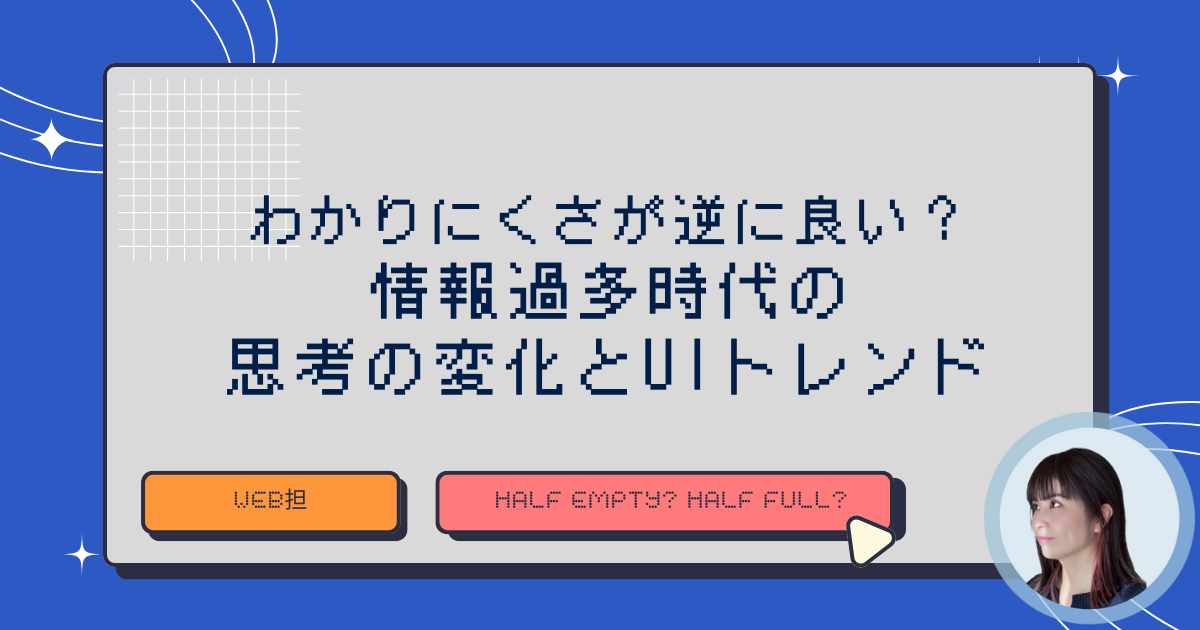
4月上旬、アメリカのトランプ政権が発動した「相互関税」が話題となりました。当初、日本には24%の関税が課されると報じられましたが、その後、90日間の猶予期間が設けられ、最終的には10%に引き下げられました。
このニュースを知って、「24%と聞いていたから、10%ならまだマシかもしれない」と感じた方も多いのではないでしょうか。これは、最初に提示された数値がその後の判断に影響を与える「アンカリング効果」と呼ばれる心理的バイアスの一例です。
こうした先入観は、WebサービスやアプリのUXにも日常的に影響を及ぼしています。たとえば、無料トライアル後に提示される月額料金、最初に選ばれているプラン、セール価格の「元値」表示なども、ユーザーの意思決定に無意識のうちに影響を与えています。
このように、「情報の見せ方」はユーザーの判断だけでなく、体験全体をも変化させます。そうした「伝え方」の影響力をあらためて実感した、個人的な体験をここで紹介します。
スマホから離れて気づいた「アプリ前提」のマーケティング
ある日、スマートフォンとの付き合い方を見直したいと思い、SNSを含む使用頻度の低いアプリを数十個アンインストールしました。もともとSNSは1日30分までと決めており、依存している自覚はありませんでしたが、「なんとなくスマホを触る」という習慣から抜け出してみたかったのです。
私は仕事柄、新しいサービスを体験するために多くのアプリをインストールしています。そのため「仕事に支障が出るのでは」「情報に遅れるのでは」といった不安もありましたが、思い切って削除したことで、思いがけず多くの気づきがありました。
特に印象的だったのは、多くのWebサービスやプロダクトが「アプリありき」で設計されているということです。「アプリがなければ使えない」「通知が届かないと情報に気づけない」、設定や連携が「アプリをご利用ください」で止まってしまうなど、利用者側に制限がかかっている設計が少なくありません。
たとえば、ファーストフード店のモバイルオーダーはアプリからしか利用できなかったり、百貨店のポイントカードもアプリがなければ貯めることも、使うこともできなかったりなどが挙げられます。
こうした体験を通じて、ユーザーの主導権が企業側に握られているように感じることがありました。マーケティングの観点から見ればアプリ経由での接点強化は合理的ですが、ユーザー視点に立ってみると、「使えないなら、それはそれでいいか」と利用自体をやめてしまう判断にもつながりかねません。
これまで、ユーザーが迷わずに目的を達成できる“フリクションレス”なUX設計を重視してきましたが、この体験を通じて、アプリありきの発想にとらわれていたことに気づきました。
現代のラッダイト運動に見る「距離を取る選択」
こうした“スマホから離れる”という選択は、海外でも注目されています。たとえばアメリカでは、「現代版ラッダイト運動」ともいえるティーンエイジャーの間での潮流があります。
ラッダイト運動は、産業革命時代に機械に仕事を奪われるのではないかと危惧したイギリスの労働者が、機械を破壊するなどで抵抗した運動のことを言います。現代版においては、あえてスマートフォンをもたず、フィーチャーフォンや紙の本、手書きの日記などに回帰することで、自分たちの時間や集中力を取り戻そうとしています。
この「現代版ラッダイト運動」は、単なるノスタルジーではなく、テクノロジーに囲まれた日常への問いかけであり、自分の生活を意識的に再設計しようとする意志の表れだと私は考えています。興味深いのは、こうした過去回帰、テクノロジーとの距離感の見直しが、Webデザインの世界にも表出していることです。
Web1.0的な素朴さを意図的に採用、「ブルータリズム」とは
このような潮流のなかで注目されているのが、「ブルータリズム」というWebデザインのスタイルです。
ブルータリズムとは、もともとは建築の用語で、「装飾を排し、素材そのものの質感や構造をむき出しにする」スタイルを指します。Webデザインにおいてもこの考え方が応用され、ボタンやレイアウト、タイポグラフィなどを極限まで簡素化し、Web1.0時代のような無骨なインターフェースをあえて採用します。
このようなデザインは、「インターネット老人会」と自嘲気味に名乗る世代の人たちには「懐かしい!」と感じられるかもしれませんし、「WikipediaのようなUI」と説明すれば、若い人にもイメージしやすいかもしれません。
特徴的なのは、Webフォントを使用せずシステムデフォルトのテキストをそのまま利用したり、リンクがすべて青のアンダーラインだったり、あえて左右非対称のレイアウトにしたりといった点です。一見すると洗練とは対極にあるように感じるかもしれませんが、そこにこそ意図が込められており、視覚的な美しさではなく、構造や思想そのものを体験させることがブルータリズムの本質だといえるでしょう。
「わかりにくさ」を設計に取り入れるという選択
昨今のWebサイトは、スムーズで使いやすい体験を重視するあまり、どのサイトも似通った構成やデザインになりがちになるというのも事実です。その結果、ユーザーは無意識のうちに情報を消費するだけになってしまうこともあります。
ブルータリズムのようなUIは、あえて「わかりにくさ」や「引っかかり」を残すことで、ユーザーに思考を促し、印象に残る体験を生み出そうとします。これは、ブランドの姿勢や世界観を際立たせる手段にもなり得ます。
トレンドに流されず、ユーザーの心理を起点に設計する
今回は昨今の潮流からUIデザインのスタイル「ブルータリズム」に触れましたが、私は引き続き、誰もが迷わずに目的を到達できるために使えるUX設計を基本に据えるべきだと考えています。しかし、「わかりやすさ=正義」という前提に縛られすぎると、かえってユーザーの関心や印象に残らないこともあると気づきました。
ブルータリズムは、すべてのサービスに適した手法ではありません。むしろ、不適切に使えばユーザーが離れてしまうリスクもあります。
それでも、均質化が進む今のデジタルサービスという環境において、「あえて、わかりにくくする」「意図的に粗さを残す」という選択が、かえってブランドの個性を際立たせる有効な手段になる場面もあると感じています。
今後も私は、ユーザーにとってスムーズな体験を設計しつつ、必要に応じて「記憶に残る違和感」や「立ち止まって考えさせる仕掛け」も組み込めるような設計を模索していきたいと思います。