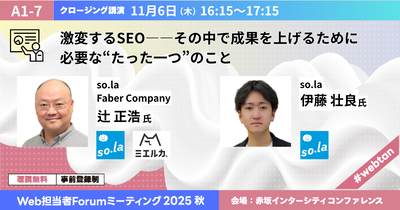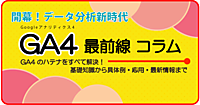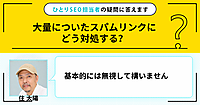最近、「指名検索」自社サービスを直接検索される状態がSEOに重要といわれることが増えてきました。当然、すでに自社のサービスやブランドを認知している指名検索ユーザは、コンバージョン率が高い傾向があり、企業にとって非常に重要な存在です。
しかし、指名検索の数を増やすことばかり注目され、指名検索をした後が考えられることは少ないように感じます。いくら指名検索数を増やしても、そのユーザを適切なランディングページに導き、最終的に成果へつなげなければ意味がありません。
そのユーザの行動を改善するために重要なのが、指名検索の自然検索結果の最上位に表示されることがあるこのリンクです。

通常のタイトル表示の下に並ぶ同じドメインのリンクのことを、Googleは「サイトリンク」と呼んでいます。Googleがユーザの役に立つと判断した場合、サイトリンクが自動で表示されます。
このサイトリンクは、コントロールできないものと考えている人が多いようです。実際、表示が明らかにおかしいまま放置されているサイトをよく見かけます。しかし、サイトリンクはまったくコントロールできないわけではありません。少し工夫すれば、狙ったページを表示させやすくすることが可能です。
指名検索ユーザを成果に導くためには、サイトリンクのコントロールが欠かせません。そこで本記事では、理想的なサイトリンクを作るための方法や考え方について解説します。
なぜサイトリンクをコントロールすべきなのか
サイトリンクをコントロールしないと、大切な指名検索ユーザが他のサイトに流れてしまう可能性が高くなります。
検索意図を絞り切れない指名検索で表示されやすい
サイトリンクは「企業名」や「ブランド名」、「サービス名」のみで検索をした際に表示されることが多いです。 [ミエルカ] [トヨタ] [三井住友銀行] などの検索語句がこれに当たります。そして [ミエルカ] のような語句で検索するユーザの中には、さまざまな検索意図を持ったユーザが混在しています。たとえば以下のような意図です。
- SEOツールの情報収集をしている
- ミエルカを契約しようとしている
- ミエルカのログインページを探している
- ミエルカマーケティングジャーナルを探している など
[ミエルカ ログイン] という検索語句であれば、ミエルカのログインページを探しているユーザが検索していると推測できます。しかし、 [ミエルカ] だけでは検索意図を絞れません。そのため、ユーザ自身が適切なランディングページを選べるように、サイトリンクを調整する必要があります。
サイトリンクの下には同じドメインのページが表示されにくい
サイトリンクが表示されると、検索結果の1ページ目(サイトリンクの下)には、同じドメインのページが表示されづらくなります。つまり、多くの場合はメインのタイトルリンク(通常の検索結果表示)と、それに付随するサイトリンクだけが自社サイトへの入口となるのです。
その入口でユーザの検索意図に応えられず、少しでもスクロールされてしまうと、指名検索ユーザはその下にある比較サイトやクチコミサイトなどに流れてしまいます。そのため、サイトリンクをコントロールして、可能な限り多くのユーザの検索意図に応える必要があるのです。
サイトリンクをコントロールする方法
サイトリンクをコントロールする際、以下の2つの視点から考える必要があります。
- サイトリンクの表示ページをコントロールする
- サイトリンクのタイトル表示をコントロールする
サイトリンクのページをコントロールする
サイトリンクに表示されるページは、 [site:(サイトのドメイン)(検索語句] で検索した際の上位ページとほとんど一致します。
たとえば以下は、[site:https://mieru-ca.com/ ミエルカ] で検索した際の検索結果と、[ミエルカ] で検索した際のサイトリンクです。順番は多少異なりますが、[site:https://mieru-ca.com/ ミエルカ] で検索したときの2位、4~7位のページがサイトリンクに表示されています。

(左)[site:https://mieru-ca.com/ ミエルカ] で検索した際の検索結果
つまり、[site:(サイトのドメイン)(検索語句] の順位をコントロールする施策を行えば、サイトリンクの順番も同じように変動するのです。
[site:(サイトのドメイン)(検索語句] は、検索結果に表示されるドメインが限定されるだけで、順位決定のアルゴリズムは通常の検索とほとんど同じです。そのため、まずは以下のような基本的な施策を行いましょう。
- title要素やページ内に検索語句を入れる
- 内部リンクを集める
title要素やページ内に検索語句を入れる
SEOの基本中の基本ですが、title要素やページ内に検索語句を入れましょう。[site:https://mieru-ca.com/ ミエルカ] で上位を取りたいのであれば、title要素の文頭や前半に「ミエルカ」が入っている方が有利です。また、h要素や本文中にも適宜「ミエルカ」を入れるべきです。
title要素を設定する際は、サイトリンクだけでなく通常のタイトルリンクで表示されるときのことも考えなければいけません。タイトルリンクの作り方の記事を参考にして、[site:https://mieru-ca.com/ ミエルカ] で上位を取りつつ、タイトルリンクも最適化できるtitle要素を目指しましょう。
内部リンクを集める
これもSEOの基本ですが、Googleは内部リンクが集まっているページを重要なページだと判断する傾向があります。サイトリンクに表示させたいページに内部リンクが集まっていなければ、トップページや関連するページ、グローバルナビなどからリンクを張りましょう。
Googleもサイトリンクの質を高める方法として、関連する他のページからリンクを張ることを推奨しています。
サイトリンクのタイトル表示をコントロールする
狙ったページがサイトリンクに並んでいても、それがどのようなページかユーザに伝わらなければ、クリックされません。そのため表示されているタイトルにも気を付ける必要があります。
特にサイトリンクは通常のタイトルリンクよりも文字数が少なく、コントロールも難しいです。全く意図していない文言で表示されてしまうこともよくあります。
サイトリンクのタイトル表示にはなにが使われるのか
サイトリンクのタイトル表示には、基本的にtitle要素やh1要素、リンクのアンカーテキストなどが使用されます。title要素やh1要素が使われることが多いですが、通常のタイトルリンクと比べると、アンカーテキストが使用される場合も多いです。特に、トップページからの動線やグローバルナビ、フッターリンクなど、重要な内部リンクのアンカーテキストは、使用されやすい傾向にあります。
アンカーテキストが使用されている例
こちらは株式会社Faber Companyのサイトリンクです。

4つ目のサイトリンクに、「特長(FaberCompanyの強み)」というタイトル表示で以下のページが表示されています。
このページのtitle要素は「強み・特長 - Faber Company」です。h1要素はなく、唯一のh2要素が「Faber Companyの特長・強みFEATURE」となっています。その他、ページのメインコンテンツ内に「特長(FaberCompanyの強み)」という文言は存在しません。
それでは、どこにこの文言が存在しているかと言うと、フッターリンクのアンカーテキストです。

通常のタイトルリンクでアンカーテキストが使用されることは稀ですが、サイトリンクでは珍しくありません。もしtitle要素やメインコンテンツ内に存在しない文言がサイトリンクに表示されている場合は、まず内部リンクを確認しましょう。
理想的なサイトリンクとは
サイトリンクには、ユーザが求めているページが表示されているべきです。ただし、企業やサービス次第でそれは異なるため、一概にどのページとは言えません。
それでは、どのようにしてユーザが求めているページを特定すればよいのでしょうか。特に参考にするべきなのは以下の2つです。
- メインのページに自然検索流入してきたユーザの行動
- 掛け合わせ語句の検索数
メインのページに自然検索流入してきたユーザの行動
まず、検索結果に表示されるメインのページに自然検索流入してきたユーザが、次にどのページに遷移しているかを確認しましょう。企業名やサービス名のみの指名検索であれば、メインで表示されるページはほとんどの場合がトップページです。

たとえば企業サイトのトップページに自然検索流入したユーザの多くが、次に事例ページに遷移しているのであれば、多くのユーザが事例ページを求めている可能性が高いと言えます。
サイトの回遊データは、GA4の探索レポートの経路データ探索などを使って確認できます。

掛け合わせ語句の検索数
企業名やサービス名との掛け合わせ語句も参考になります。「ミエルカ」を含む検索語句の想定月間検索回数を見てみましょう。
[ミエルカ]:13,200
[ミエルカとは]:2,533
[ミエルカ ヒートマップ]:1,173
[ミエルカ seo]:640
[ミエルカ ログイン]:520
[ミエルカ コネクト]:520
[ミエルカ 事例]:280
[ミエルカ 料金]:147
[ミエルカ ヒートマップ 料金]:120
[ミエルカ ツール]:120
[ミエルカ 会社]:120
[ローカルミエルカ ログイン]:120
[ミエルカ チャンネル]:120
そもそもミエルカとは何かという検索が最も多いです。ミエルカヒートマップやミエルカコネクトといった派生ツール、サービスについての検索も一定数あることがわかります。単純に検索数が多い順に対策すればいいというわけではありませんが、通常のSEOと同様に、検索数は情報ニーズを測る1つの指標になります。
このような方法で、指名検索をするユーザが何を求めているかを調査し、適切なサイトリンクを表示できれば、迷わずにあなたのWebサイトを利用できるはずです。ぜひお試しください。
サイトリンクは定期的にチェックしよう
この記事では、指名検索で表示されるサイトリンクの重要性と、そのコントロール方法について解説してきました。サイトリンクはあまりSEOで語られることは少ないですが、非常に多くの人が利用するとても大切なものです。
私が所属する株式会社so.laでは、お客さまの指名検索結果がユーザにとって最適な状態になっているか定期的にチェックしています。指名検索結果は成果への影響が大きく、そして問題に気付いたときは一般の検索語句よりも改善が容易だからです。
指名検索は、成果につながる可能性が高く、ほぼ確実に1位を取れて、表示状況を容易に改善できます。そのため、本来は最も表示状況にこだわるべき検索語句といえます。
皆さんもぜひこの機会に自社サイトのサイトリンクを見直してみてください。
本記事を執筆した、so.laの伊藤氏と辻氏が登壇!
「Web担当者Forum ミーティング 2025 秋」を2025年11月6日(木)、7日(金)に「赤坂インターシティコンファレンス」で開催します。
お席も少なくなってきました。お早めにお申込みください!