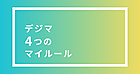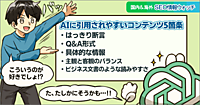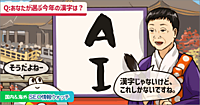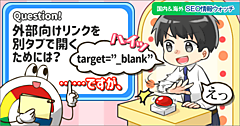前回からほぼ1か月、間をあけてしまった。お久しぶりだ。
今回のピックアップは、「AI向けのコンテンツ作成」の重要なポイントとテクニック。渡辺隆広氏が、基本的な考え方と、学ぶ際に役だつ書籍も紹介してくれている。これはぜひ押さえておきたい情報だ。
今回は、ピックアップを含めて渡辺隆広氏の記事を3本紹介しているほか、AI関係のネタが大量だ。
AI検索のSEO、AI専用サイト、AIモードの日本語提供、さらには生成AIとオーガニック検索のコンバージョン率比較最新版などなど、AI時代のSEO力をアップさせる情報を、今週もまとめてお届けする。
- AI向けライティングの超重要ポイントを渡辺隆広氏が紹介、これは押さえなきゃ損だ
- AI検索時代のSEO: ユーザー中心への回帰
- 「AI専用サイトはSEOに逆効果」の根拠
- Google検索「AIモード」、日本語でいよいよ提供開始
- Bing検索の製品マネージャーがAI検索のSEOをアドバイス
- LLMとオーガニック検索トラフィックのコンバージョン率の比較分析(最新版)
- LLMにリバースエンジニアリングは意味がない
- 2025年9月のオフィスアワー: クロールの統計情報で提示される URL、サイト移転に伴いドメインの評価は分散など
- GBPのビジネスリンクに関するポリシーとガイドラインが更新される
- 帰ってきたSearch Central Live Tokyo、11/7に開催決定!
- Google検索が&num=100パラメータを廃止、SEOに与える影響は?
- Gemini AIをChromeに統合した「Gemini in Chrome」をGoogleがリリース
今週のピックアップ
AI向けライティングの超重要ポイントを渡辺隆広氏が紹介、これは押さえなきゃ損だ
これを押さえておけば基本はOK (SEMリサーチ) 国内情報
「AI向けのコンテンツ作成」の重要なポイントとテクニックを、渡辺隆広氏が明らかにした。
と言っても、その内容は、あなたが期待するものとは違うだろう。渡辺氏が紹介しているのは、「いわゆる古典的な文章術(ライティング技法)、基本的な文章作成技術を学ぶ」というものだ。元記事では、その基本とあわせて、ライティング技術を学ぶ際に参考にするといい書籍を紹介している:
- 『書く技術・伝える技術』 倉島 保美 (あさ出版)
- 『伝わる! 文章力が身につく本』 小笠原信之 (高橋書店)
さて、「AI向けコンテンツ作成のポイントとテクニック」というのは、このコーナーの記事として独自につけた切り口だ。渡辺氏の元記事はそうしたテクニックとして紹介するものではない。元記事の趣旨は、次のようなものだ:
GEO (Generative Engine Optimization) やLLMO (Large Language Model Optimization) といったAI時代のライティング手法が提唱されているが、その内容は99.999%が「結論を先に書く」「平易な言葉で書く」といった、SEOですらなく、古くから存在する普遍的なライティング技法に過ぎない。
かつてSEOライティングは「引越し」と「引っ越し」のような表記ゆれを意識するなど、機械に媚びるような特殊な技術が必要だった。しかし、2013年のハミングバードアップデートなどを経て、「検索エンジンが文脈や検索意図を理解する能力」は飛躍的に向上している。その結果、人間が理解しやすい自然な文章を検索エンジンが評価できるようになった。つまり、「人間にとって理解しやすい文章は、機械(AI)にとっても理解しやすい」ようになってきているのだ。
それにもかかわらず、多くの事業者は「AI」という言葉に惑わされ、共起語を意識するような2014年時点ですら時代遅れとなった手法に今もなお固執している。
渡辺氏は、AIに特効薬のような魔法のライティング術は存在しないと断言し、事業者はバズワードに踊らされず、基本的な文章作成技術を学ぶのが効果的だと主張する。
たしかに、得体の知れない「AI向けコンテンツ術」を意識するよりも、渡辺氏が元記事で紹介している書籍で本質的なライティング能力を身につけるほうが、短期的にも中長期的にも良いことがありそうだ。
なにより、コンテンツ作成に加えて、日常のビジネス(メールや企画書)にも役立つというのは大きい。
- AI SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)
グーグル検索SEO情報①
AI検索時代のSEO: ユーザー中心への回帰
徹底してユーザーのために価値を創造することが唯一の道 (SEMリサーチ) 国内情報
「AI検索・検索エージェントと、SEOやコンテンツマーケティングの影響」と、どう考えてどう対応していくべきかについて、渡辺隆広氏が自身の考えを著した。
AI検索の進化は、2014年の「コンテンツショック」以降、生成AIにより加速した低品質な「ジェネリックコンテンツ」の氾濫と、それが引き起こす「デルフィックコスト」(ユーザーの時間的・認知的コスト)問題へのグーグルの解答であると渡辺氏は言う。
AI Overviewなどの機能は、ユーザーが情報収集から比較検討までをAIとの対話で完結させる未来を示唆しており、キーワードを詰め込む従来型のコンテンツSEOは価値を失う。サイト運営者はAIOやLLMOといったバズワードに惑わされず、広義のSEO、すなわち専門分野での権威性(Topical Authority)を確立し、そのサイトならではの知識や体験を提供して「go-to source」(信頼される情報源)となることに注力すべきであると、渡辺氏は強調している。これは「アルゴリズムのため」から「ユーザーのため」への意識改革であり、究極的にはプロダクトマーケティングと区別がつかなくなるほど優れた製品・サービスがSEOを内包する状態を目指すことが求められるのだ。
要するに、AI検索の進化により、ありきたりなウェブコンテンツはAIに要約され、価値を失う。キーワードを狙うだけの旧来のSEOはもはや通用しない。これからのサイト運営者に求められるのは、「プロンプトにあわせて最適化する」ような小手先のAI対策ではなく、自らの専門分野で「信頼される情報源」となることだ。他では得られない独自の知識や体験を提供し、アルゴリズムではなく、徹底してユーザーのために価値を創造することが、唯一の道となる。
元記事は整理されていて示唆に富む内容ばかりなので、ぜひ全文を読んでいただきたいが、特に印象に残った段落を2つ、紹介しておこう。
その究極は、特別なPR活動をしなくてもユーザーやメディアの注目を集めるような素晴らしい製品を世の中に送り出すことです。SEOを追求すると、プロダクトマーケティングとの区別がつかなくなります。
テクニカルに説明するならば、Topical Authority(ある専門分野における権威性)を目指すことです。そのサイトだからこそ得られる知識や学び、楽しさ、心地よさ(※ サイトにより体験は異なる)を提供するためには、何を、どのようにしたらいいのか。ビジネスゴールと照らし合わせて方針を再考すべきときです。
- すべてのWeb担当者 必見!
「AI専用サイトはSEOに逆効果」の根拠
SEO専門家でない人のSEOアドバイスを鵜呑みにしないこと (SEMリサーチ) 国内情報
博報堂のフォーラムで提唱された「生成AI対策としてAI専用サブドメインを持つべき」という主張に対し、SEOの観点から明確に「不要かつ逆効果になりかねない」と渡辺隆広氏が警鐘を鳴らした。
その根拠として、サブドメインは新規ドメイン名と同様に扱われ、既存サイトが長年かけて築いた信頼性や権威性(オーソリティ)をゼロから構築し直す必要がある点を挙げる。この主張がSEOの知見を持たない外部のAI専門家によるもので、具体的な証拠が何一つ示されていないことも問題視している。
SEOの辻正浩氏も、この件について同様の指摘をしている。
これらの「AI向けに別形式」という考えの多くは、情報収集や購買行動・意思決定をエージェントAIが担うようになるという未来予測を元にされていることが多いです。
— 辻正浩 | Masahiro Tsuji (@tsuj) September 15, 2025
確かに未来はそうなるのかもしれない。でもそれはまだまだ先でしょう。5年?10年?一般層が使うのはおそらくはそれ以上先かと。(3/n)
将来的にどうなるか確実なことは言えないが、少なくとも今後数年に関しては、渡辺氏や辻氏の言うように「AI専用サブドメインにするのは推奨しない」が正しそうだ。
企業は「AIO」といった新語に惑わされず、信頼性の低い新規ドメイン名をわざわざ作るという不合理な戦略は避けるべきだと渡辺氏は結論付けている。
- AI SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)
Google検索「AIモード」、日本語でいよいよ提供開始
積極的に使って実態を確かめよう (Google Japan Blog) 国内情報
Google検索の新機能「AIモード」の日本語での提供を、グーグルが2025年9月9日に開始した。検索結果ページに表示される「AI モード」タブ、もしくは google.com/aimode からアクセスできる。
AI モードはGemini 2.5のカスタム版を利用し、従来複数回の検索が必要だった長く複雑な質問に、一度で包括的な回答を生成する。探求的な質問や旅行計画などに特に役立つという。その背後にあるのは「クエリファンアウト」という技術で、質問をサブトピックに分解し、深くウェブを探索できるのだという。
また、テキスト、音声、画像での質問が可能なマルチモーダル体験が特徴で、たとえば写真のメニューからベジタリアン向け料理を質問するなどできる。
ブラウザ(PCとモバイル)やGoogleアプリでAIモードを利用できる。
たとえば、次のようなクエリをAIモードにしてみた:
京都駅出発で 6 泊 7 日の旅行プランを立てて。伝統工芸とか歴史的な場所を巡るアクティビティ中心のプランで、ディナーでおすすめのレストランも入れて。
その回答は次のように表示される(回答が長いので一部のみ):
いよいよ日本語でもAIモードが使えるようになった。
ハルシネーションが発生するなど懸念点もあるが、まだ試験段階の機能なので改善に期待したい。ウェブ検索にどのような影響を与えるかは未知数だが、積極的に利用し問題点も含めて特徴と変化を自分で体験することを推奨する。
SEOの観点からみると、比較的バランスの良い感じでサイトへ訪問するリンクが提供されているように思われるが、どうだろうか。
- すべてのWeb担当者 必見!
Bing検索の製品マネージャーがAI検索のSEOをアドバイス
グーグルのアドバイスと同じ (Fabrice Canel on X) 海外情報
「AI検索の最適化」について、Bingのプロダクトマネージャであるファブリス・キャネル氏が次のようにコメントした:
SEO担当者が検索やAI、LLMに自分のコンテンツを届けたいのなら、「このうえなく、はっきりさせ」ましょう:
独自で高品質で関連性の高いコンテンツを作成してください。そのコンテンツは、パース(読み取り・解析)しやすいようにしてください。
適切なHTMLタグ、セマンティックマークアップ、CSS、そして必要に応じてJSを活用してください。そうすることで、コンテンツの可視性を高められます。
※SEO界隈で「LLMは構造化データを解釈するかどうか」というトピックが議論になっている流れででた発言だ
グーグルの主張とまったく同じだ。従来のSEOもAI検索のSEOも本質は変わらないことを明確に示している。
Right. SEOs want Search, AI & LLM to get your content? Make it crystal clear: Craft unique, high-quality, relevant content that's easy to parse. Use proper HTML tags, Semantic Markup, CSS, & JS (where appropriate) to boost your content visibility!
— Fabrice Canel (@facan) September 18, 2025
- すべてのWeb担当者 必見!