「インターネット広告創世記〜Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く~」シリーズ第49話。前回の記事はこちらです。

前回のお話では、TwitterとFacebookの台頭によってYouTubeへの流入経路が変わり、YouTubeの広告のあり方が変化したことを紹介しました。また、Twitterが始めた「ネット取引」によって1990年代〜2000年代を通じて続いてきた商習慣に変化が出てきたことを紹介しました。
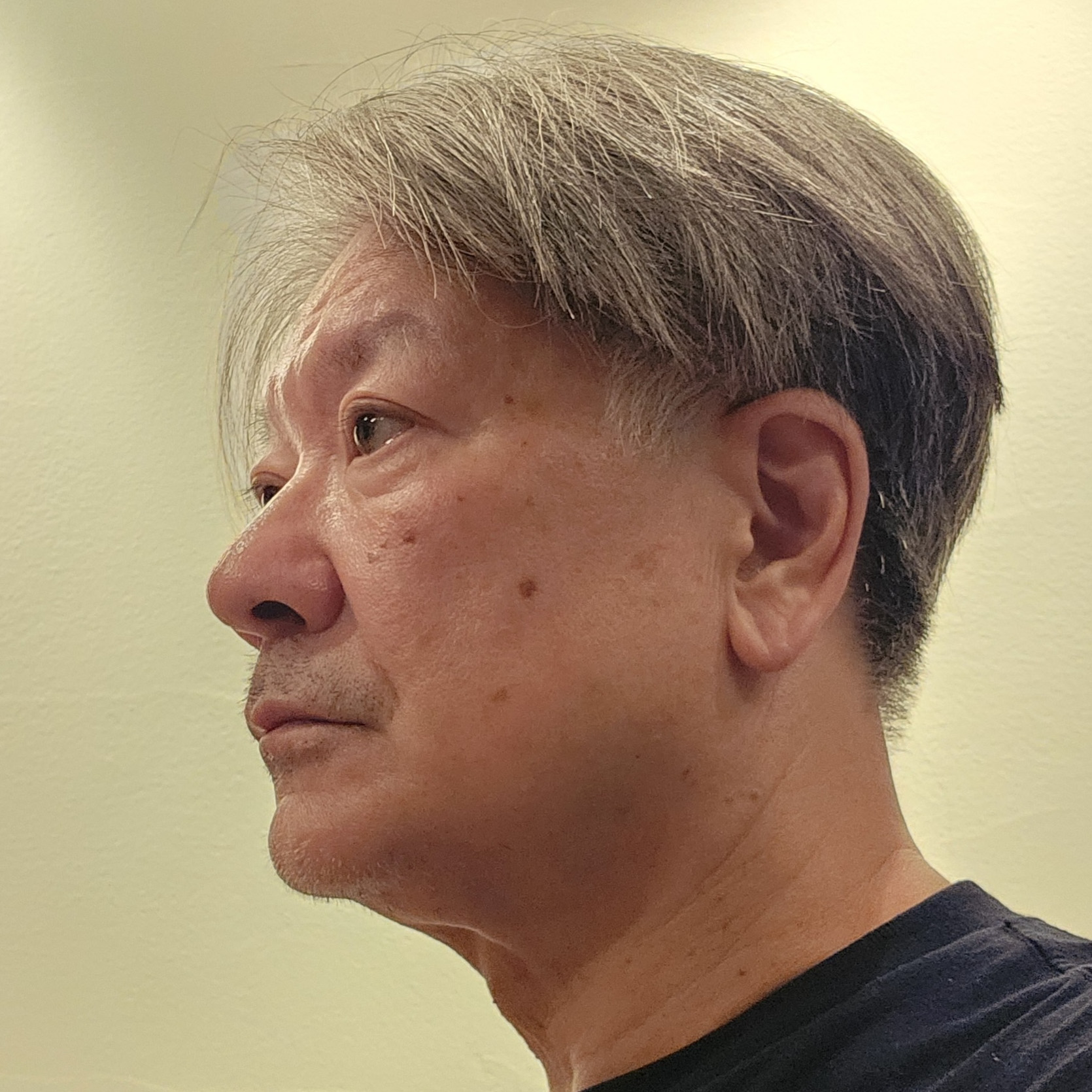
YouTubeの「好きなことで生きていく」CMキャンペーンをきっかけに「YouTuber」が認知されはじめ「インフルエンサー」が登場しました。日本でいち早くインフルエンサーマーケティングに取り組んでいたTHECOO株式会社の平良真人さんと下川弘樹さんにお話を聞くと良いと思います。

はじめまして、ご紹介にあずかりましたTHECOO株式会社のCEOを務める平良真人と申します。、Googleを経て、2014年にTHECOOを創業しました。
Googleに転職するきっかけとなった全番組録画機器
平良:私が在籍していた頃のSONYは、出井伸之さんがインターネットを活用したビジネスモデルの可能性を熱心に啓蒙していました。私はSONYのインターネットプロバイダーサービス「So-net」の海外展開をするチームに所属していて、台湾や香港向けの仕事をしていました。そこで、eコマースなどのインターネットサービスを経験し、収益化の手段の一つとしてインターネット広告に関心を持つようになりました。
ちょうどその頃、パソコンで地上波7チャンネルの全番組を同時に録画できる全番組録画機器が登場しはじめた時期でした。ユーザーはテレビCMをスキップして録画するので、「このスキップした枠に、ユーザーの視聴履歴に基づいてパーソナライズした広告を配信できたら、ソニーにとって大きなビジネスになるのでは」と夢想していました。
Googleへの転職と頭に残ったアイデア
平良:本格的に広告業界のことを勉強してみると、このアイデアが無理だということはすぐにわかったのですが、なんとなくこの時のアイデアが頭の中に残っていて、「もしこのアイデアが実現できるとしたらGoogleしかない」と思い、2007年にGoogleに転職しました。
Googleでは最初、ビジネスデベロプメント(事業開発)の仕事をしていました。検索エンジンのパートナー企業や、AdSenseのパートナー企業との契約の締結や更新などが仕事で、インターネット広告とは直接の関わりはない仕事でした。しかし、頭のどこかでは先程のアイデアを実現したいという思いがありました。当時、Googleにはトップページをユーザーごとにパーソナライズできる「iGoogle」というサービスがあり、「この中で何か実現できることはないか」と考えたりしていたんです。
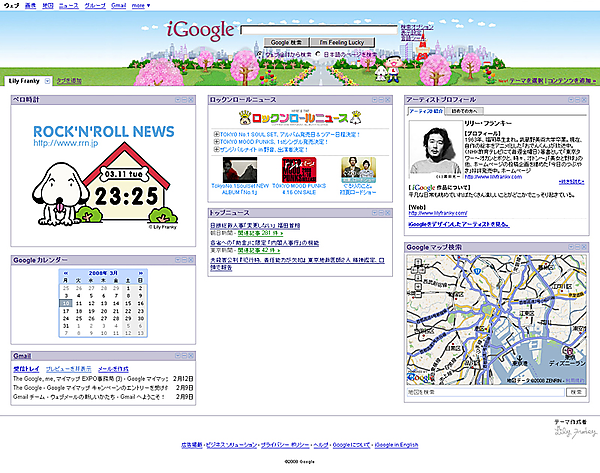
その後、AdWordsの中小企業向けの営業チームに異動して下川弘樹さんと出会い、2013年に一緒にGoogleを退職して、THECOO株式会社の前身となるルビー・マーケティング株式会社を創業しました。

はじめまして、THECOO株式会社で取締役を務めております下川弘樹と申します。現在は経営企画などの部門を管掌しておりますが、創業当初は主に広告運用も含めたデジタルマーケティング部門を管掌していました。私は1979年生まれなのですが、大学生になった頃にインターネットが普及し始めて、インターネットに関わる仕事をしたいなと思い、新卒でNTTに就職しました。
インフラからコンテンツの世界に働く場所を移したいと思ってGoogleに転職
下川:学生の頃、最初は電話回線でインターネットに接続していました。それがADSL、光回線と進化していくうちに、あっという間に通信速度が10倍ほどになり、気づけばテレビではなくインターネットでニュースを見ている自分がいました。そこから、インターネットを支える通信インフラに興味を持つようになったんです。
大学卒業後はNTTに就職し、インターネット回線の販売を担当しました。通信インフラの仕事というのは、ある意味で“縁の下の力持ち”のような存在です。気がつくと、自分たちが築いた「高速道路」の上で、さまざまな新しいサービスが次々に生まれていました。その様子を見て、今度は自分も“その上で走る側”の仕事をしてみたいと思うようになりました。
Googleでの「Don’t be evil」体験
ちょうどその頃、ベストセラーになっていた『ウェブ進化論』を読んでGoogleの本質を知り、その技術力の高さに強く惹かれました。そして2008年、Googleに転職しました。
[amzon:B00E5XATWC]
入社後は、まずAdWords(現Google広告)の中小企業向け営業チームに配属され、広告審査を担当しました。Googleの審査方針を知ったとき、「本当に“Don’t be evil”(Googleの社是の一つ。第31話参照)の精神で運営しているんだ」と感動しましたね。当時の審査ポリシーは、一般的な社会通念よりもずっと厳しく、売上への影響があっても、ポリシーに反する広告は容赦なく却下していました。
その後は、AdWordsのカスタマーサポートや中小企業向けの営業を経て、広告代理店向けの営業も担当しました。そのときに平良さんと出会い、お誘いいただいて起業に参加することになった、というのがこれまでの経緯です。
「海外の『YouTuber』を使って欲しい」と依頼されて
平良:2014年の夏頃のことだったと思います。とあるゲーム関連のお客様から「海外の『YouTuber』を使ってほしい」と言われました。私はこの時点で「YouTuber」という言葉を知りませんでした。
Google所属でも知らなかった「YouTuber」という言葉
それまで、Googleの社内ではYouTuberのことを「クリエイター」または「オンラインクリエイター」と呼んでいたので、心の中で「YouTuberって何?」って思いました。YouTubeの「好きなことで生きていく」キャンペーンが2014年年末で、その時期よりも前の出来事だったので、Googleにいた私でさえも「YouTuber」という言葉を知らなかったんです。
私はその時は知ったかぶりして「YouTubeの『TrueView広告』をやればいいんだな」と思っていたのですが、会社に帰ってから改めて調べてみるとまったく違いました。恥ずかしながら私はYouTubeではミュージックビデオぐらいしか見てこなかったので、「ああ、あのメントスをコーラに入れた動画をあげている人たちのことを海外では“YouTuber”と呼ぶんだな」とそこで初めて気が付きました。
そこで、Google時代の同僚に海外で人気のゲーム実況系YouTuberを紹介してもらい、タイアップ広告をお願いしにロサンゼルスに出張し、お客様のゲームアプリを紹介してもらいました。アプリのインストールを増やすことが目的だったのですが、他の通常の広告チャネルよりも1インストールあたりのコストが安く、結果的にキャンペーンは大成功しました。
インフルエンサーをキャスティングするプラットフォームを模索
平良:私はビジネスの仕組みを考えるのが好きなので、この成功をきっかけに「スケールさせられないか」と考えました。同時に、「Googleが参入したらあっという間にGoogleが本流になってしまうので、このビジネスに将来的にGoogleは参入してくるだろうか」ということも考えました。
この仕事は広告主のビジネスに合致するYouTuberを探し、動画の企画を考え、表現をコントロールする必要があるので実現までにとても手のかかる仕事です。こうした労働集約的な仕事にGoogle自身としては参入してこないだろうと思いました。
また、2007年頃に地上波やケーブルテレビなどのテレビ広告枠をオンライン広告のようにオークション形式で販売・管理する「AdSense for TV」というプロジェクトに携わった経験がありました。しかし、テレビ番組とクリエイティブの親和性をうまく保つことが難しく、実用化には至りませんでした。当時のGoogleは、人間の感性が関わる領域を得意としていない印象がありました。
こうした経験から、GoogleはYouTuberを活用したインフルエンサーマーケティングにはしばらく参入してこないだろうと考え、「iCON CAST」のサービスをスタートしました。

「iCON Suite」のサービス開始
下川:iCON CASTは広告主とYouTuberのマッチングビジネスなので、まずはインフルエンサーに参加をしてもらう必要がありました。ちょうどその頃、HIKAKINやはじめしゃちょーなど、多くのトップYouTuberが所属するマネジメント会社の「UUUM」が設立されたこともあり、業界が盛り上がっていて、数多くの有名なインフルエンサーに参加してもらうことができました。
次に、インフルエンサーの準備が整ったので広告主向けの営業を開始しました。各YouTuberから承認をもらって、APIで各YouTuberの動画の視聴者数やエンゲージメント率などのデータを取得し、広告主がYouTuberをキャスティングしやすいようなデータを整備して、広告主への営業を本格的に始め、多くの広告主に使っていただけるサービスになりました。
当初の目論見では、広告主とYouTuberが直接コミュニケーションをとって自動的に受発注が進んでいくことを想定していたのですが、コンセプト自体が新しかったせいか、私たちが間に立って仲介していく必要が出てきました。ビジネスという観点で言うと労働集約的にはなってしまうのですが、それでもインフルエンサーマーケティング市場の成長率はインターネット広告市場の成長率よりも圧倒的に高かったので、ビジネスとしても大きく成長していきました。
こうしたインフルエンサーマーケティングに特化したプラットフォームは日本では私たちが初めてだったと思いますが、海外ではFameBitというプラットフォームが先行していて、2016年にGoogleが買収をしています。
腹落ちしたインフルエンサーマーケティングの実力
平良:Facebook(現Meta)が買収したInstagramが月間のMAU(Monthly Active Userの略で月間のアクティブユーザー数)でFacebookを上回り、「インスタ映え」という言葉が流行り始めた2017年の終わり頃に『VINYL MUSEUM(ビニール・ミュージアム)』というイベントを表参道で開催しました。チケットを購入すると写真撮影用のフォトスポットに入場できて映える写真が撮影できるというイベントでした。

それまで「iCON CAST」でインフルエンサーマーケティングのサービスを提供しつつも、ひとりのユーザーとしてインフルエンサーの価値を実感する機会はほとんどありませんでした。
「インスタ映え」イベントでの腹落ち
平良:自分でイベントを開催しておきながら「このフォトスポットで本当に映えるかな?」と半信半疑なところもあったのですが、プレオープンの日に若いインフルエンサーを呼んで実際に撮影をしてもらって感想を聞いたところ、「これは映えます!」とポジティブな返事が返ってきました。そして、このプレオープンの日に撮影してもらったインフルエンサーの投稿をきっかけにチケットがあっと言う間に完売してしまいました。
自分の感性との違いにすごくショックを受けたりもしたのですが、この時にひとりのユーザーとしてもインフルエンサーマーケティングの力を腹落ちして理解することができました。ふと気がついてみると、いつのまにか自分もレストランを探す時にInstagramの投稿を見たりしています。広告はスキップするけど投稿を見てしまうんですよね。商品やサービスがクリエイティブの良し悪しでこんなにも変わるのかと驚きましたね。
インフルエンサーマーケティングの潜在的な力はもっとある
下川:現在、インフルエンサーマーケティングは企業のマーケティングチャネルのひとつとして十分に認知されたと思うのですが、まだまだそのポテンシャルは活かしきれていないと感じます。その理由のひとつに計測の問題があると考えています。
YouTubeの動画やInstagramの投稿には計測用のタグを埋め込むことができないので、動画や投稿を見たユーザーがどの程度売上に貢献したかを可視化することが難しいんです。実際のビジネスへの貢献度合いとしては、オンラインの売上にもオフラインの売上にも貢献していることを肌感覚として日々感じているのですが、データがきれいにつながらないので、通常の広告プラットフォームに比べて大きな金額の投資に踏み切りづらいというジレンマがあると思います。ここが解決するとまた違った展開に広がっていく可能性があると思っています。
現在はインフルエンサーの数もジャンルもとても増えたので、ニッチな商材を扱う広告主にもフィットするインフルエンサーがかなり増えてきています。「iCON Suite」では30万件以上のインフルエンサーデータを収録していますし、インフルエンサーマーケティングはこれからさらに発展していくのではないかと考えています。
広告とコンテンツの境界が曖昧になり始めた
佐藤:これまで、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌などの広告はもちろんのこと、Google 広告やMeta広告などのインターネット広告でも基本的には広告とコンテンツは別のものという考え方で発展してきました。インフルエンサーマーケティングの登場によって、少しずつ広告とコンテンツの境界が曖昧になってきたことは、インターネット広告の歴史の中でひとつのターニングポイントであったと思います。
2026年1月15日をもちまして、本連載は無事に完結いたしました。これまで温かく見守り、並走してくださった読者の皆様に、心より感謝申し上げます。連載中に設けておりました情報提供フォームも、あわせて受付を終了いたしました。
現在、2026年6月の刊行を目指して書籍化の準備を進めております。さらにパワーアップした内容を皆様にお届けできる日を、どうぞ楽しみにお待ちください!































