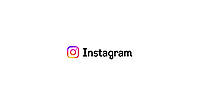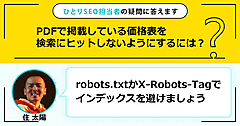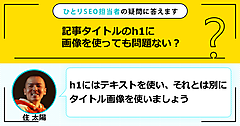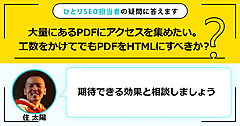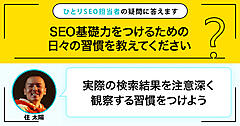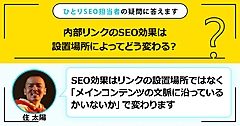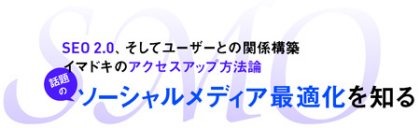
ソーシャルメディア最適化の16のルール
Web 2.0に関連して「ソーシャルメディア」という言葉が話題に上ることが多くなったが、最近ではその影響力を利用してトラフィックの向上やクチコミの伝播を狙う「ソーシャルメディア最適化」、略して「SMO」という言葉も聞かれるようになってきた。ここでは、ソーシャルメディアとは何か、そしてSMOとは何かについてまとめる。
住 太陽
情報が相互に流れるソーシャルメディア
主導権がユーザーにあるメディア
ソーシャルメディアとは、情報や知識を共有するコミュニティを中心に展開されるメディアの総称で、具体的なサービスの種類としては、ソーシャルブックマーク、ソーシャルニュース、フォトシェアリング、ビデオシェアリング、ブログ、SNS、Wikiなどが代表的だ。従来のマスメディアでは情報の出し手と受け手がはっきりと分かれており、情報の流れが一方通行だったのに対して、ソーシャルメディアでは、コンテンツの制作も流通も主導権はユーザーコミュニティの側にあるのが特徴だ。
ここでのキーワードは、ユーザー間での「共有(シェアリング)」だ。SNSは人脈を共有しようとするものだし、Wikiはコンテンツそのものを共有しようとするものだ。また、コンテンツに対する評価を共有しようとするのがソーシャルブックマークやソーシャルニュースだ。ブログやフォトシェアリング、ビデオシェアリングなどのサービスは、個人がコンテンツを発信して共有するのを容易にするだけでなく、同じような趣味趣向を持つ者どうしてつながっていく仕組みも持っている。このような、さまざまな情報や知識をコミュニティ内で共有していくためのサービスがソーシャルメディアと呼ばれ、Web 2.0の中心的なサービスとして話題を集めている。
さまざまな種類のソーシャルメディア
ソーシャルメディアといってもたくさんの種類があり、それぞれに複数のサービスがひしめき合っている。これらのサービスを使ったことがなければ、ソーシャルメディア最適化が今後いかに大切になるかは理解できないだろう。初めて聞くという人もぜひ試してみてほしい。
●ソーシャルブックマーク
ユーザーが気にいったページをオンラインでブックマークするサービス。ブラウザの「お気に入り」はサイトのトップページを登録することが多いが、ソーシャルブックマークでは「記事」の単位で登録されるのが基本だ。

http://b.hatena.ne.jp/オンラインで軽快に使える情報整理ツールとしてだけでなく、旬の話題を効率的に得られる情報サイトとしても人気を集めているソーシャルブックマーク。
ブックマークする際には、簡単なコメントを残したり、「タグ付け」と呼ばれる分類を同時に行ったりでき、その情報をユーザー同士で共有できるほか、単位時間あたりのブックマーク登録数を元に自動生成される人気記事ランキングによって旬の話題を知ることもできる。
国内では「はてなブックマーク」が代表的だが(図1)、米国のサービスである「del.icio.us」を利用する日本人も多い。現在はちょっとしたブームになっており、国内では大手ポータルのほとんどすべてが同種のサービスを提供している。
●ソーシャルニュース
ユーザーが気になるニュースを収集し、そのニュースに対するユーザーの評点を使って「みんなが気になるニュース」を抽出するサービス。評点の際には簡単なコメントを付けられるものが多い。

http://newsing.jp/米国では「Digg(ディグ)」が代表的なソーシャルニュースだが、日本ではnewsingがソーシャルニュースのさきがけだ。
海外では米国の「Digg」が大ブレイクし、新聞社などを含む数多くのニュースサイトよりも人気があるといわれる。国内では「newsing(ニューシング)」がさきがけ的な存在だ(図2)。この種のサービスは、世の中にあふれる数多くのニュースの中から、注目度の高いニュースだけを効率よく取得できるメリットがある。
●フォトシェアリング
自分で撮影したデジタル写真をサーバーにアップロードし、不特定多数に公開したり、招待したユーザーによるコミュニティ内だけに公開したりできるサービス。アップロードした写真には分類を表すタグを付けたり、短いコメントを付けたりできることが一般的。このタグやコメントを元に他のユーザーが写真を探して閲覧したり、評点やコメントを付けたりできるものある。
海外のサービスでは米Yahooが昨年買収したFlickrが代表的だ。英語サービスだが日本語によるタグ付けやコメントも可能で、日本人のユーザーも多い。日本では、ポータルが運営するlivedoor PICSやSo-net Photo、OCNフォトフレンドなどのサービスがある。
●ビデオシェアリング
自分で撮影・編集した動画をサーバーにアップロードし、他のユーザーと共有できるサービスで、いわばフォトシェアリングの動画版。タグ付けやコメント、評点などの機能が備わっているほか、評点や再生回数を元にしたランキングもある。また、気に入った動画を自分のウェブサイトやブログに貼り付ける機能も提供している。
最大手は米国のYouTubeで、インターフェイスのほとんどは英語だが、部分的には日本語を含む6カ国語に対応しているため、国内のユーザーも多い。国内のサービスとしては、サイバーエージェントによるアメーバビジョンや、フジテレビラボLLCによるワッチミー!TV、Ask.jpによるAskビデオなどのサービスがある。
●ブログ
基本的にはオンラインで簡単に更新できる時系列の日記のような形式のサイトだが、トラックバックやコメントなどの機能が実装されていることにより、他のブログ著者や読者と議論を交換するようなコミュニケーションが可能になっている。書かれている内容は、著者の身辺雑記から専門性の高い内容までさまざまだ。近年ではブログを中心に議論される話題も多く、ブログ著者らによる社会をブロゴスフィアなどと呼び、1つの言論圏とされることもある。
●SNS
ソーシャルネットワーキングサービス。ユーザーが持っている人間関係の維持や構築を支援するサービスで、人と人とのつながりや関係性をオンラインで展開する会員制のコミュニティサイト。新規にユーザーになるためには、既存のユーザーからの招待が必要になるサービスがほとんど。
日本ではmixiが代表的。その他、GREEやフレパ、Yahoo! Daysなども多くのユーザーを集めているほか、自分専用のSNSを作成できるサービスも増えており、こうしたサービスを用いて作られた小規模でネットワーク密度の高いSNSも多数出現している。
●Wiki
ブラウザ上から誰でもコンテンツを作成・編集できるコンテンツサイトの仕組みの総称。多数のユーザーが共同でコンテンツを作り上げていくことができる。代表的なサービスはWikipediaで、フリーな百科事典をみんなで作るという世界的なプロジェクトが進行しており、日本語を含む33カ国語に対応している。
- この記事のキーワード