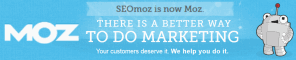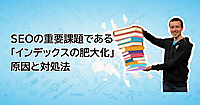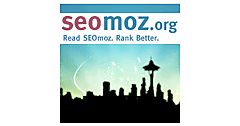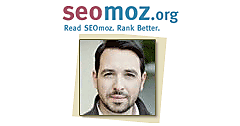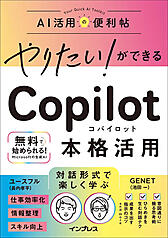将来のSEOに備えるための17のヒント(前編)
「ヘルプフルコンテンツアップデート」「経験に基づくコンテンツ」「強引すぎるSEO」「ブランドオーソリティ」などなど、激動の2024年をふまえ、2025年に意識すべきSEOのヒントをリリー・レイ氏がお届けする。
2025年3月3日 7:00
2024年はSEO業界にとって目まぐるしい1年だった。アルゴリズムの大幅な変更やSERPをめぐる熾烈な競争だけでなく、独占禁止法に関する訴訟もあって、だれもが息もつけないほどだった。
多くのSEO担当者からすると、2024年の激動は「今後どう進めばいいのか」という疑問を投げかけるものだった。
- ヘルプフルコンテンツアップデート(HCU)の影響
- Redditのようなユーザー生成コンテンツ(UGC)プラットフォームの台頭
- グーグルによる最新のアルゴリズム変更
これらの変化と格闘しているのは君だけではない。
この記事は、リリー・レイ氏によるオンラインセミナーを元にしたもので、これらの課題に対処し、2025年に向けて強靭なSEO戦略を計画するための実践的な戦略を紹介する。
- 筆者のリリー・レイ氏によるMoz実践マーケターセミナー「将来のSEOに備えるには」を観るにはこちら(ウェビナー・オンデマンド・無料・登録制、英語のみ)
- ヘルプフルコンテンツアップデートに関する質問
- ヘルプフルコンテンツアップデートやコアアップデートによってウェブサイトへのトラフィックが急減した場合、トラフィックを回復させるために推奨する最初のステップは?
- ヘルプフルコンテンツアップデートは、「経験に基づくコンテンツ」を優先しているように見える。E-E-A-Tの観点から、組織内で経験に基づくコンテンツを推進するにはどうすればいいか?
- ヘルプフルコンテンツアップデートでトラフィックが減少している顧客に対して、「オフサイトでの取り組み」を推奨するか? 同僚の1人は、「ブランド」と「ヘルプフルコンテンツアップデート」の強い関連性を指摘している
- より「定着しやすい」ブランドを生み出すには、どうすればいいか? 特定の課題について想起されるようなブランドを作るには?
- 古いコアアルゴリズムや競合他社の取り組みに原因があるのに「ヘルプフルコンテンツアップデートによって打撃を受けた」と誤解している人が多いと思うか?
- 「強引すぎるSEO」とは、どういうことか?
- 寄生SEO
- グーグルの内部文書流出とブランドの力
- Redditという難問
- 検索エンジンの活動
- オーディエンスからの質問
- 「SERPが大幅に変更されクリック率やトラフィックが低下したことで、クライアントやステークホルダーとの間に摩擦が生じている」という話を見聞きしているか? その場合、どう対処しているか? (後編)
- 「クリック率を上げる」というのは、具体的にはどのような作業になるのか?(後編)
- 「実店舗が複数あり、予算が限られているビジネス」が優先すべきSEO施策を3つ挙げてほしい (後編)
- SEO担当者が2025年に取り組むべき最大の「意識改革」は何か?(後編)
- 2024年のアルゴリズムアップデートとAIのせいで、私の会社の検索トラフィックは壊滅的な状態になった。一般的な対策はすべて実施しているが、さらに減少し続けている。他に何ができるか?(後編)
- 最後に、「未来の検索」についてSEO担当者に1つアドバイスするとしたら、何と伝えたいか?(後編)
- 結論
ヘルプフルコンテンツアップデートに関する質問
将来のSEOに備えるためのヒント #1
ヘルプフルコンテンツアップデートやコアアップデートによってウェブサイトへのトラフィックが急減した場合、トラフィックを回復させるために推奨する最初のステップは?
私だったら、まず「トラフィックの減少を引き起こしたアップデートの種類」を把握する。2023年9月のヘルプフルコンテンツアップデート(HCU)は、通常のコアアップデートとは異なる形でサイトが影響を受けたうえに、回復も難しかったという点で際立っている。
影響を受けたコンテンツのパターンを特定する
特に大きな影響を受けたサイトのセクションやコンテンツの種類を調べる。パターンを特定することで、重点的に改善すべき箇所が浮き彫りになる。
包括的なアプローチを適用する
サイトを回復させるには、次のようなアクションが必要だ:
- コンテンツの品質を改善
- テクニカルSEOを改善
- サイトアーキテクチャを改善
- スパムの可能性がある要素を削除
これは大変な作業であり、時間もかかる。私の会社Amsiveが回復時に行う監査は網羅的なもので、そのチェック内容は通常100ページ~150ページにものぼる。
ただ待つだけではいけない
今後のアップデートで影響が元に戻るのを期待するのは現実的ではない。ただ待つのではなく、複数の問題に同時に対処することで、今後のアップデートに備えてサイトの基盤とレジリエンス(回復力)を強化しよう。
将来のSEOに備えるためのヒント #2
ヘルプフルコンテンツアップデートは、「経験に基づくコンテンツ」を優先しているように見える。E-E-A-Tの観点から、組織内で経験に基づくコンテンツを推進するにはどうすればいいか?
E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)のなかでも「経験に基づくコンテンツ」は、人工知能(AI)で生成されたコンテンツとは一線を画すものとして、今後さらに重要になる可能性が高い。グーグルが常に正しく理解できるとは限らないが、一般に、実体験を含むコンテンツは時が経つにつれてパフォーマンスが向上する。
経験に基づくコンテンツを推進するアプローチとしては、次のようなものが考えられる:
AIの限界を認識する
AIツールを使えばコンテンツ制作の規模を拡大できるが、本物の専門家だけが実際に経験している情報は得られない場合が多い。
独自の企業リソースを活用する
次のものを中心にコンテンツを構築しよう:
- オリジナルデータ
- オリジナルの知見
- オリジナルの視点
次のように自問してみるといい:
独自の新しいアイデアとして、どのようなものを発信できるか?
たとえば、旅行サイトを運営しているなら、従業員たちに自身の旅行体験について書いてもらおう。「私も行ったことがあります。ここで体験したことのトップ5をご紹介しましょう」といった具合だ。
そうすることで、AIコンテンツにはあまりない本物らしさが加わり、ブランドの信頼性も高まる。
将来のSEOに備えるためのヒント #3
ヘルプフルコンテンツアップデートでトラフィックが減少している顧客に対して、「オフサイトでの取り組み」を推奨するか? 同僚の1人は、「ブランド」と「ヘルプフルコンテンツアップデート」の強い関連性を指摘している
ヘルプフルコンテンツアップデートでトラフィックが減少しているのならば「オフサイトでの取り組み」つまりサイト外でのアクションを進めることは、推奨する。
次の2つには、確かなつながりがある:
- ブランドの強さ
- ヘルプフルコンテンツアップデートなどのアップデートに対する回復力
ブランドが強力で、ナビゲーション検索のボリューム(そのブランドに特化して検索する人)が多いサイトは、アルゴリズムの変更もうまく乗り越えられる傾向がある。ユーザーが積極的に君のブランドを検索しているのならば、「信頼性」が築かれているということで、グーグルはその信頼性を重視する。
たとえば、「luxury cars(高級車)」を検索する人は、BMWのようなブランドが表示されると予想するだろう。グーグルは「ユーザーが特定のブランドを特定の業界と関連付けていること」を理解しているため、検索結果でそれらのブランドを優先することでユーザー体験を高めている。同様にブランドを関連付けることで、検索で自分の表示位置を上げられる。
オフサイトでの取り組みとしては、本格的なブランド構築に重点を置こう:
- 屋外広告
- パートナーシップ
- ブランドマーケティング
従来のリンクビルディングだけでは逆効果になるおそれがある。長期的な安定性を確保するには、ブランドの存在感をSEO以外にも拡大することが賢明な戦略だ。
将来のSEOに備えるためのヒント #4
より「定着しやすい」ブランドを生み出すには、どうすればいいか? 特定の課題について想起されるようなブランドを作るには?
「1-877-Kars 4 Kids」の歌を知っているだろうか。米国では多くの人が知っていて、耳に残るジングルだ。好きか嫌いかに関係なく、だれもが覚えてしまう。なぜなら、わかりやすい形でブランドと結びついているからだ。
ここで重要なのは、自分のブランドを「記憶に残りやすく」「すぐに認識してもらえるもの」にする方法を見つけることだ。必ずしもSEOを利用する必要はない。他の方法で大きな注目を集めることもできる。
「アレをやった面白いブランド」として知られるようになるにせよ、耳に残るジングルを使うブランドになるにせよ、印象に残るブランドにするための独創的なアプローチはたくさんある。そうした手法は、大企業にしかできないわけではない。小さなブランドでも、これらのテクニックを使って記憶に残るつながりを生み出せる。
将来のSEOに備えるためのヒント #5
古いコアアルゴリズムや競合他社の取り組みに原因があるのに「ヘルプフルコンテンツアップデートによって打撃を受けた」と誤解している人が多いと思うか?
確かに多いと思う。そういう状況をよく目にする。
ヘルプフルコンテンツアップデート(HCU)は非常に特殊な事象であり、多くのサイトがそれぞれ異なる形で影響を受けた。自分のサイトがHCUの影響を受けたという人は、2023年9月15日から9月20日の間に検索順位とトラフィックが明らかに低下したはずなので、すでに認識しているだろう。
厄介なことに、このアップデートの前後には、2つの別のアップデート(2023年9月と10月に実施されたコアアップデート)がリリースされている。そのため、これらのコアアップデートの影響を受けた多くのサイトは、HCUの影響を受けたと思っているかもしれない。しかし実際のところ、HCUは一連のコアアップデートの1つにすぎない。
どのアップデートの影響を受けたかを判断するには、Google Search Status Dashboardを利用するのがいい。各アップデートのロールアウトの具体的な日付と詳細を確認し、検索トラフィックが変化した時期と照らし合わせて確認してほしい。
回復について言えば、私のチームでは通常、さまざまなSEO改善策を含め、すべてのアップデートで同じアプローチを用いている。しかし、とりわけHCUの影響を受けたサイトでは、「強引すぎるSEOコンテンツが見つかって調整が必要になる」ことが多い。
回復のステップは包括的で多面的なSEOのアプローチに従って進められる(具体的なアクションはサイトによって異なるが)。
将来のSEOに備えるためのヒント #6
「強引すぎるSEO」とは、どういうことか?
「SEOのゴールドラッシュ」とも呼べる時期が2019年頃から2023年半ばにかけてあり、大小さまざまなパブリッシャーが生成AIを使ってコンテンツを次々と増やし、莫大な売り上げを得ていた。パブリッシャーがSEOを活用し、「専門知識や実体験」よりも「コンテンツの量」を重視することが多かったという点で、この時期は特筆に値する。
「強引すぎるSEO」とは現在は一般に、検索ボリュームのためだけに大量のコンテンツを作成することを指す(その反対が「真の知見を共有すること」だ)。
こうしたコンテンツには、次のような特徴がある:
- 検索結果に表示されることを主な目的として作成されているため、実体験に欠ける
- 自動最適化で「キーワード」「サイト内リンク」「見出しタグ」などを処理しているが、読み手よりもアルゴリズムを重視した書き方になっている
このアプローチは2023年初めまで有効だったが、グーグルがアルゴリズムを更新すると、多くのサイトでビジビリティが低下した。
寄生SEO
将来のSEOに備えるためのヒント #7
サイトの評判を不正利用する手法として、寄生SEOが挙げられることがある。ペナルティを受けないために、SEO担当者がこの手法を特定して回避するには、どうすればいいか?
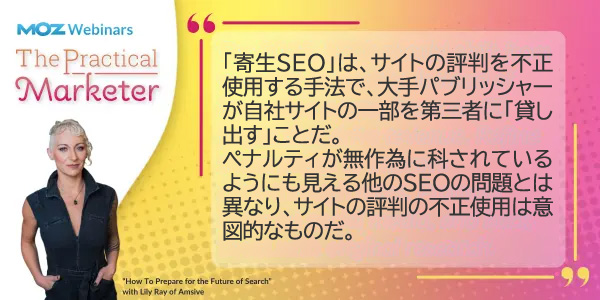
「寄生SEO」とは、サイトの評判を不正使用する手法だ。具体的な手法は、次のようなものだ:
大手パブリッシャーが自社サイトの一部を第三者に「貸し出す」ことで、そのパブリッシャーが持つSEOのオーソリティを利用したアフィリエイト記事やクーポンページなどのコンテンツを、第三者が公開できるようにすること。
大手メディアサイトがサイト内の一部分で「厳選CBDグミ」の記事やプロモーションコードを掲載しており、その多くが外部の企業によって作成されている場合を考えてみよう。これらのセクションが検索結果の上位に表示されるのは、コンテンツのオーソリティが高いからではなく、大手パブリッシャーのドメイン名が持つSEOの強さを活用しているからだ。
グーグルは2023年、付加価値をもたらすことなくドメインオーソリティに「便乗」しているサイトセクションのビジビリティを引き下げるために、この手法を対象としたスパムポリシーを導入した。これを受けて、こうしたパートナーシップから売り上げを得ていたパブリッシャーが影響を受け、戦略の再考を迫られた。
ペナルティを科されないようにするため、SEO担当者やパブリッシャーは、オーソリティを「借りている」ように見えるパートナーシップを回避するべきだ。ペナルティが無作為に科されているようにも見える他のSEOの問題とは異なり、サイトの評判の不正使用は意図的であるため、ブランドに合った価値の高いコンテンツに注力することで回避できる。
グーグルの内部文書流出とブランドの力
将来のSEOに備えるためのヒント #8
特に競争の激しいニッチ市場で、予算が限られている小規模なウェブサイトが、「認知度が高く信頼されるブランドオーソリティ」を築くにはどうすればいいか?
小規模なウェブサイトにとって、ブランドオーソリティは必ずしも多額の予算をかけた取り組みである必要はない。従来の広告を使わずに認知度と信頼を築く方法はある。
私なら、次のような方法で取り組む:
地域の出版物やイベントのスポンサーになる
地域の出版物やイベントのスポンサーになって、自分のブランドを宣伝することを検討しよう。多額の予算をかけずにビジビリティを高める、すばらしい方法だ。
ソーシャルメディアでチームを紹介する
撮影されるのが好きな人がチームにいたら、自社のTikTokやYouTubeチャンネルで紹介しよう。たとえば、害虫駆除会社を経営しているなら、メンバーの日常を紹介すれば人々の共感を得られるかもしれない。動画の効果は非常に大きく、個人的な趣向を加えることで大きな違いが生まれる。
最高のコンテンツを動画にする
SEOでうまくいっているアイデアやトピックを動画で再現しよう。YouTubeに投稿し、そのコンテンツをTikTokでも使おう。グーグルはYouTubeの動画に高い順位を付ける傾向があるので、オーガニックトラフィックを獲得しやすくなる。
人々がどこを見ているかを追跡する
私は個人的に、グーグルではなくTikTokやInstagramでレビューを見ることが多いと思う。小規模なクリエイターから直接知見を得たいと思うのは、大手ブランドより信頼できると感じるからだ。動画は非常に重要であり、2025年を迎えるにあたって、ぜひ戦略に組み込むようみんなに勧めたい。
この記事は、前後編の2回に分けてお届けする。後編となる次回は今回に引き続き、Redditや検索エンジンの活動について、リリー・レイ氏からのアドバイスを紹介する。→後編を読む