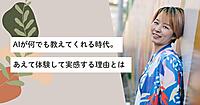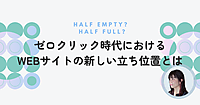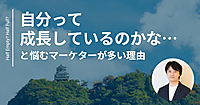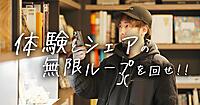ウェブサイトを成長させるウェブ解析士マスターの心得と手法とは?
マーケターコラム、今回は大日本印刷株式会社の田口佳央莉さん。ウェブサイトそれぞれに適した成長の道筋をつくる方法を紹介します。
2024年6月18日 7:00

皆さま、はじめまして、田口佳央莉と申します。
大日本印刷株式会社(以下DNPといいます)にて、自社サイトの解析、SEO、ユーザビリティ向上のために日々奮闘しているウェブ解析士マスターです。
「Web担当者Forum」では2020年に、DNPのオウンドメディア「Discover DNP」について取材を受けた記事が掲載されました。
「Discover DNP」とは、DNPが取り組む社会課題や最新の技術について幅広く発信していくメディアです。むずかしい印刷知識も、「へぇ~」と思いながら楽しんで読んでいただけるよう日々工夫をこらしております。
あれから4年、「Discover DNP」を含むDNPのウェブサイトは順調に成長を続け、全体で当時の約20倍のアクセス規模になっています。
このたび、マーケターコラムに寄稿する機会をいただきましたので、第1回ではウェブサイトを成長させるウェブ解析士の心得についてお話しします。
ウェブ解析士マスターとは?
冒頭でさらっとお伝えした「ウェブ解析士マスター」。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、一般社団法人ウェブ解析士協会が認定する資格です。私は2017年に取得しました。
ウェブ解析における技術能力、コンサルティング能力の両面においてロールモデルであることが求められるウェブ解析士マスターは、現在(2024年5月24日時点)、ウェブ解析士全体の10%未満といった、貴重な生命体となっています(大切に扱ってください)。
ウェブ解析士マスターの役割は?何ができるの?
ざっくり言うとウェブ解析士マスターは、次世代のウェブ解析士を育てることが役目です。ウェブ解析やウェブマーケティングの基礎知識を有する「ウェブ解析士」、より実践力をもってウェブマーケティング施策を立案することのできる「上級ウェブ解析士」、この両方の人材を育成し、資格認定を行うことができます。
私も、主にDNP社内で、デジタルマーケティング教育やウェブ解析士認定講座を開催しており、毎年新たなウェブ解析士をこの世に生み出しています。さらに、みんなでお勉強をがんばっていることを会社の偉い人たちに猛アピールしたら、毎日たくさん褒めてもらえるようになりました。お給料アップにウェブ解析士、おすすめです!
求められているのは、ウェブサイトを成長させるための道筋
現在、私はDNPのコーポレートコミュニケーション本部にて、自社サイトの運営に従事していますが、かつてこの世が平成だった2011年から2018年まで、多くの得意先のウェブサイト解析を担当していました。
EC/金融/メーカーなど、約150社のさまざまな形態のウェブサイトのアクセスデータを分析し、コンテンツ改善やウェブサイトリニューアルに向けた解析レポートを作成していました。
そこで大変身に染みてわかったことは、解析レポートを見たお客さまが本当に欲しいのは、アクセス数値の増減報告ではなく、「ウェブサイトを成長へ導くための道筋」だということです。自社のウェブサイトが目指すべき理想の姿はどのようなものか、そこに辿りつくためには何をするべきか、具体的なアドバイスを求めています。
ウェブサイトというのは各社各様で、どんなサイトにも当てはまる成長の道筋はありません。そこで、サイトそれぞれに適した成長の道筋をつくるために、これまで私がウェブ解析士としてどのような支援をしてきたか、その方法を少しお話ししたいと思います。
デジタルメディアの中長期計画を立てる
最近は「ワイドモニター」や「ウルトラワイドモニター」と呼ばれる横長ディスプレイを使う方が増えてきました。
そんな時代の視聴環境に合わせて、ウェブサイトのデザイン面、機能面を刷新して、「そろそろリニューアルしたい」「かっこよくしたい」と考えるのはウェブ担当者としては当然で、すばらしいことです。大変激しく同意でございます。
しかし、いざ金額面を考えると、ポケットマネーでは済みません。通常のリニューアルで数千万円、システム改修を伴う大規模リニューアルであれば数億円が必要になることもあります。そしてリニューアル後には必ず、さまざまな「で、どうする?」がやってきます。
「誰が運用するの?」
「新しいコンテンツ枠を立ち上げたけれど、誰がコンテンツを更新していくの?」
「何を目標にするの?」
そこで必要になるのが「デジタルメディア3ヵ年計画」です。
オウンドメディア、ソーシャルメディア、ペイドメディア、それぞれで3年後に達成したい目標を立て、どのような方法でそこに辿りつくかの進路を描くものです。
どうやって描けばいいかって? 簡単です。全メディアの担当者が集まって、メディアごとに3年後の理想を語りあい、ホワイトボードに付箋を貼って、発表しあいましょう。そのあとにコンサルタントの方や広告代理店の方に相談し、形を整えていくのです。

理想の組織図をつくる
次につくるべきは「オウンドメディアのウェブ戦略書」です。
これはおおまかに言うと、リニューアル後のサイトの運営方針や、運営に携わる部門の組織体制、各部門のKPI、KGI、KSFを設定し、ツリー構造にした組織体制図です。
組織図は、攻めと守りから構成されていて、認知拡大や新しいコンテンツ制作を行っていく「攻めを担う部隊」と、サイトの基盤管理や新しいツールの導入といった「守りを担う部隊」で役割を分けます。
部門ごとの目標にまで落とし込めれば、目指すべきゴールに向けた登場人物それぞれの役割と重要性が見えてきます。
お客さまとのコミュニケーション動線を設計する
どのようなメディアでも最も重要なのが、お客さまとのコミュニケーションです。
発信をメインとするオウンドメディアではつい忘れてしまいがちですが、来訪してくださるお客さまは必ず目的を持っています。ランディングページから離脱ページまでの理想のルートを設計し、主要動線をつくっていきましょう。
ここがまさに解析士の腕の見せどころです!
たとえば「問い合わせをしたお客さま」が辿った最短ルート、適切な情報収集ルートなどをゴールデンルートとして設定し、その経路で必ず通っているキーコンテンツを探しあてましょう。そして、キーコンテンツを多くの人に見てもらえるようバナー配置を検討することで、お客さまを目的達成へと導くことができるのです。
これらのルートと実際に辿ったルートを比較することで、お客さまに向けたコンテンツが、はたして興味深く見ていただけているのかを検証できます。
社内で褒めあう文化をつくる
ウェブ関連業務に従事する方は日々感じていると思いますが、ウェブサイトの各コンテンツの施策効果は比べるのが難しく、良し悪しを評価しにくいです。
DNPも各事業部門やグループ会社ごとにコンテンツを管理しているため、最初は部門ごとにレポートを作成しておりました。
しかし、コンテンツごとにアクセス増減をまとめても、それが良いのか悪いのか基準がないと評価しにくいというのが課題でした。
そこで、サイト全体から見たときに個々のコンテンツが良いのか悪いのか状態を評価するために、「コンテンツ通信簿」という成績表をつくりました。これは、アクセス数、検索流入数、問い合わせ数を100点満点で評価するレポートです。
3ヵ月に一度まとめて発表し、アクセス増加につながる施策を行った部門には施策内容を発表してもらう、会を開催するようにしました。年度末には最も集客できた部門、多くのお問合わせに導いた部門を経営層が表彰し、担当者のモチベーション向上につなげています。
おわりに
今回はウェブサイトを成長させるために、ウェブ解析士がどのような心得で、どのような仕事をしているのか、私の経験に基づいてお話ししました。ウェブに携わる方も、そうでない方も、日々の生活やお仕事の中で何か1つでもヒントになれば幸いです。
次回からもウェブ解析士目線で、日常のさまざまな事象を分析していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ご意見、ご感想、ファンレター(笑)もお待ちしています!