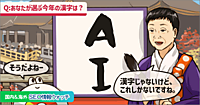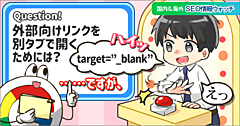グーグルの指名検索シェアは実市場シェアの先行指標になる?
グーグル検索SEO情報②
グーグルの指名検索シェアは実市場シェアの先行指標になる?
検索シェアと市場シェアには高い相関関係あり (住 太陽 on X) 国内情報
興味深いデータを住太陽氏がXで共有した。「グーグルでの社名の指名検索のシェア」と「市場のシェア」ほぼが一致しているというのだ。
こちらは住氏が作成した、ファストフード大手3社と牛丼チェーン大手3社の指名検索シェアと市場シェアの円グラフだ。
どちらも見事に一致している。
元ネタは、効果測定の専門家レス・ビネット氏による分析データに基づく発見と見解だ。2020年10月14日に開催されたIPA(広告実務者協会)主催のEffWorks Global 2020カンファレンスで発表されたものだ。ビネット氏は、新しい指標として「Share of Search(検索シェア)」を発表した。この指標は、ブランドの健全性と広告効果を、迅速・低コスト・予測的に追跡することを目的としている。
検索シェアは、特定のブランドに対するグーグルのオーガニック検索クエリの総数を、そのカテゴリ内の全ブランドに対する検索総数で割って算出する。
「自動車」「エネルギー」「携帯電話端末」の3つのカテゴリで検索シェア定理をビネット氏はテストした。研究から10の重要な発見が得られ、そのなかには次のものが含まれる:
検索シェアは3つのカテゴリすべてで市場シェアと相関関係があった
これは市場シェアの先行指標となり、検索シェアの変化が市場シェアの同様の動きに先行する
検索シェアと市場シェアの差は、市場シェアの動きを特に強く示す指標。「Extra Share of Search」(ESOS、超過検索シェア)と呼ばれる
検索シェアから市場シェアへの先行時間は長くなることがあり、自動車の場合は最大1年に及ぶ
特にCOVID-19のパンデミック中に消費者行動がオンラインへとシフトし、業界の予算がひっ迫している状況で、ブランドの健全性と広告効果を予測する費用対効果の高い指標としてのESOSの可能性をビネット氏は強調した。つまり、検索シェアを知ることで市場シェアの将来を見通せるから、広告予算を効果的に配分できるというのだ。
SEOに直接関わるものではないが、SEOは検索エンジンを舞台にしたマーケティングだ。検索シェアの調査はビジネス計画立案のデータとして利用できるかもしれない。
- 検索エンジンマーケティングがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)
titleタグとh1タグは一致させるべきか?
ユーザー視点で決めることだが、揃えることをオススメ (Google SEO office-hours) 海外情報
titleタグとh1タグに関連する質問が、2024年6月の英語版オフィスアワーで取り上げられた。次の質問だ:
titleタグとh1タグは、同一の内容しておくべきでしょうか?
ゲイリー・イリース氏は次のように回答している:
いいえ、ユーザーの視点から意味が通じることを優先するのがいい。
実は、この話題に関する公式ドキュメントもある。ぜひ確認してほしい。
検索結果のページタイトル(「タイトルリンク」と呼ぶ)の生成の仕組みをグーグルは2021年9月に大幅に改良した。最も目立つ変更は、titleタグではなくh1タグなど見出しタグで指定された見出し、あるいはHTMLで指定されていなくても見た目に大見出しと認識できる要素を積極的にタイトルリンクに利用するようになったことだ。
こうした変更を念頭に、titleタグとh1タグを一致させるべきかどうかを質問者は尋ねたのではないだろうか。
基本的な考え方は、イリース氏が回答したように、次のとおりだ:
titleタグもh1タグもユーザー視点で付けること。
しかし筆者としては、titleタグとh1タグを揃えることを勧めたい。両者が一致していれば、タイトルリンクの修正に備えることができる。それに、検索結果で見たタイトルリンクとページに訪問したときに目に入る(h1で指定された)見出しが一致していれば、ユーザーは正しいページに訪問したと認識できる。揃えることのデメリットを思いつかない。
イリース氏が言及したタイトルリンクに関するドキュメントはこちらだ。あなたが最後に読んだときから更新が入っているかもしれないので、再度読んでおくといいだろう。
- すべてのWeb担当者 必見!
新ドメイン名が検索結果に表示されない! どうすればいい?
まずSearch Consoleにサイトを登録 (Google SEO office-hours) 海外情報
ドメイン名を購入したばかりですが、キャッシュがリセットされておらず、検索結果に表示されません。どうすれば解決できるでしょうか?
2024年6月の英語版オフィスアワーで取り上げられたこの質問に、グーグルのゲイリー・イリース氏が次のように回答した:
まず、Search Consoleで新しいサイトを登録し、そこでのデータを確認して、次のステップを決定することを強くお勧めする。
他の人が以前に所有していたドメイン名であっても、一般的に問題はないはずだ。
あなたがすべきことは、質の高い有益なコンテンツを公開し、インデックスされるのを待つことだ。途中でエラーが発生した場合は、それを修正し、これまでの作業を続けてほしい。
Search Consoleに登録するとわかることがある:
もし、そのドメイン名が以前にも使われていて、しかもスパムサイトだった場合は手動による対策を受けている可能性もある。手動による対策がまだ継続していたとすれば、Search Consoleで警告が残っている。滅多にあるケースではないが、絶対にないとは言い切れない。
次に、インデックスレポートでページがインデックスされているかどうかを調べられる。正常にインデックスされているのであれば、単純に検索に引っかからず表示できていないだけだろう。
本当にインデックスされていないとしたら、その次はクロールレポートで、クロールの状況を調べる:
クロールされているのにインデックスされていないとしたら、コンテンツの品質の低さが原因かもしれない。
クロールエラーが発生していれば、インデックス以前の問題だ。技術的な問題を疑った方がいい。
Search Consoleは、このようにSEOのトラブルシューティングに欠かせないツールだ。このコラムの読者は当然、サイトを登録しているはずだが、SEOのスキルを上げるには各ツールやレポートの場面に応じた使い方もマスターしたい。
- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)
GBPの放置はもったいない! 積極的な管理で集客アップの成功事例
電話が81%⤴️ サイトクリックが50%⤴️ ルート検索が26%⤴️ (Darren Shaw on X) 海外情報
グーグルビジネスプロフィールを積極的に管理・最適化して、次のような成果をあげた事例を紹介する(数字は対前年比):
- 電話問い合わせ: 81%増
- 合計アクション数: 51%増
- ウェブサイトへのクリック: 50%増
- ルート検索: 26%増
ローカルSEOの専門家であるダレン・ショー氏のクライアントの事例だ。実行した具体的な施策もショー氏は共有している。次のようなものだ:
クライアントのプロフィールに、新しいコンテンツを含む投稿を毎週公開
新しい写真や動画を定期的にアップロード
クライアントと協力してレビュー戦略を策定して実行し、レビューを継続的に獲得
すべての新しいレビューに迅速に対応
Q&Aに情報を追加し、質問に応じて更新
プロフィール項目の変更に即時対応(GBP管理ソフトウェアを活用)
クライアントより不当に上位に来ているスパム プロフィールを定期的にチェックして報告
グーグルビジネスプロフィールを積極的に管理することで、2つの良いシグナルをグーグルに送ることができるとショー氏は言う:
プロフィールの情報を常に最新にしていることを示し、これを怠っている90%の競合他社との差別化を図る
GBP上の新鮮で魅力的なコンテンツは、ユーザーのインタラクションを促進する。ユーザーがプロフィール上で多くの時間を費やし、さまざまな要素をクリックすればするほど、グーグルはその結果を好ましいと判断し、ランキングが向上する可能性が高まる
ショー氏は次のように締めくくっている:
グーグルビジネスプロフィールを放置してはいけない。積極的に管理すれば、大きな成果を得られる。
- ローカルビジネスを運営するすべてのWeb担当者 必見!
hreflangを他のlink要素と同居させてはいけない
別々に記述する (Gary Illyes on LinkedIn) 海外情報
多言語・多地域サイトに関するドキュメントをグーグルが更新した。hreflang要素を他のlink要素と組み合わせて使ってはいけないことを明記した。
たとえば、携帯向けのサイトを「m.」のサブドメインURLで配信しているとする。この場合、次のようには記述できない(hreflangとhandheldが1つのlinkタグの中にまとめて記述してはいけない)。
<link rel="alternate" media="handheld" hreflang="en-GB" href="https://m·example·com/gb/en/page1" />次に示すように、別々に記述する必要がある。
<link rel="alternate" hreflang="en-GB" href="https://m.example.com/gb/en/page1" /><link rel="alternate" media="handheld" href="https://m.example.com/gb/en/page1" />
仕様が変わったわけではなく、以前からこのようだった。グローバサルサイトのウェブ担当者は知っておこう。
- グローバルサイトを管理するすべてのWeb担当者 必見!
 海外SEO情報ブログの
海外SEO情報ブログの
掲載記事からピックアップ
SEOアドバイスとモバイルファーストインデックスに関する記事をピックアップ。
- GoogleからのSEOアドバイス:素晴らしいコンテンツが最優先、それを上手にプロモーションする
ランキング要因に振り回されてはいけない
- すべてのWeb担当者 必見!
- PC向けサイトのSEOはモバイルファーストインデックスでは無視していいのか?
MFI完全移行だからといってPCを無視していいことにはならない
- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)