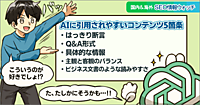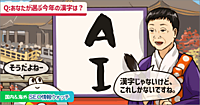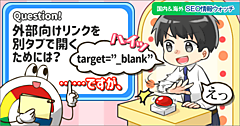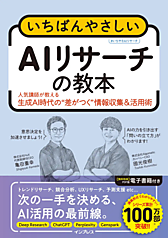海外&国内SEO情報ウォッチの、2023年最後の投稿だ。今回は、2023年に取り上げたSEO記事やWeb担当者向け記事から、おさらいしておきたい注目トピック10件を選りすぐってお届けする。
- 生成AIチャットボット元年、検索エンジン企業がChatGPTに対抗
- Google検索×生成AIの「SGE」が日本上陸
- AIで作ったコンテンツはSEOでどのように評価されるのか?
- グーグルのインデックス条件がますます厳しくなった2023年
- 「E-A-T」が「E-E-A-T」へと進化、経験も重要視
- Google Discoverのランキング要因はブラックボックス? 最適化は難しい
- あれから1年、グーグルの寄生サイト対策はどうなった?
- ニュースサイト向けSEO情報が豊富だった2023年
- リニューアルして再始動したGoogle検索オフィスアワー
- Search Central Live Tokyo開催! 3年半ぶりの対面イベント
コラム読者のみなさんへ筆者より:
2023年もこのコラムをご愛読いただき、ありがとうございました。2024年の初回更新は1月12日の予定です。引き続き、みなさんのお役に立てる情報を共有するので、来年もコラムを読みにお越しください。
みなさんが健康に2024年を迎え、2023年のSEOも成功することを祈っています。
素敵なクリスマスと良いお年を!
2023年は生成AI元年(1位~3位)
生成AIチャットボット元年、検索エンジン企業がChatGPTに対抗
ユーザーの検索行動にどのような影響を与えるのか?
2023年は、生成AIが一気に市民権を得る拡大を進めた年でもあり、検索エンジンがその動きに対抗していった都市でもあった。
ChatGPTをOpenAI(オープンエーアイ)が公開したのが2022年11月。対話形式でさまざまなやり取りができる生成AI(ジェネラティブAI)を基盤としたチャットツールで、わからないことをなんでも教えてくれるので大ブームとなった。
危機感をあらわにしたのは検索エンジン企業だ。人びとが何か知りたいときに生成AIを使うようになれば、検索エンジンの利用機会を奪われてしまうからだ。AIチャットは、検索エンジンとは異なり、その場で回答してくれる。検索エンジンのように、検索結果に出てきたコンテンツにアクセスして、内容を自分で確かめる必要がない。しかも生成AIは、回答結果に重ねて対話をすることで知りたい情報にたどり着くのも容易だ。
そこで、マイクロソフトはいち早くBingチャット(現Copilot)を2023年2月にリリースした。ChatGPTと同じように、Bingチャットも対話形式でやり取りできる。日本語でもリリース時点で利用できた。Bing検索と融合しているのは、ChatGPTにはない特徴だ。
一方でグーグルは、完全に出遅れた。対抗馬としてBardをリリースしたのはBingチャットよりも1か月遅れの3月だ。しかも、完全公開ではなく、順番待ちリストに登録し、順次という形だった。日本語で利用できるようになったのは、さらに2か月後の5月だ。
出だしは遅れたグーグルだが、リリース後は継続的にBardを改良している。7月には音声読み上げや画像アップロードの機能を追加した。9月には、回答の長さや口調の調整、グーグルのアプリとサービスへの接続も可能にした。さらに、満を持してグーグルが公開した次世代の大規模言語モデルGemini(ジェミニ)も年末に搭載した(Geminiの詳細は次回以降に)。
現在、多くのユーザーがBardを利用しているようだ。どのような目的でBardをユーザーが利用しているかのデータをグーグルは公開した。トップは「調べもの」目的だったとのことである。その次には、専門的なトピックの相談、プログラミング、翻訳と続く。
ただし、検索エンジン代わりにBardなどの生成AIを利用する場合は注意が必要だ。理由は“ハルシネーション”と呼ばれる「完全な嘘回答」の現象が付きものだからだ。Bardに限らず、ChatGPTもBingチャットも、大規模言語モデルをベースにしたAIチャットは、事実とは異なる回答をでっちあげることがあるのだ。ハルシネーションの完全な回避策はまだ見つかっていない。
とはいえ、利用方法やハルシネーションに注意すれば、AIチャットは作業効率化やアイデア出しなどに非常に有効なツールとなる。
12月に入ってから、Bardのプロモーションにグーグルは力を入れている。
Netflix 話題作のあんなシーンやこんなシーンで、#Bardに聞いてみた
— Google Japan (@googlejapan) December 9, 2023
あなたなら、Bard になに聞いてみる?#なんでも聞けるGoogleのAI #Bard pic.twitter.com/4mmvUTU3El
2024年もBardの改良は続くだろう。SEOにも賢く利用したい。
- すべてのWeb担当者 必見!
Google検索×生成AIの「SGE」が日本上陸
検索トラフィックに与える影響は未知数
Bardとは別に、SGE(Search Generative Experience、検索生成体験)と呼ぶ生成AIツールもグーグルはリリースした。BardとSGEの違いは次のとおりだ:
- Bardは、検索機能とは切り離された、独立のAIチャット
- SGEは、検索機能の一部
SGEは5月には米国の英語ユーザーを対象に試験公開された。日本で利用できるのは当分先だろうと筆者は予想していたのだが、予想に反して2番目のサポート国/言語として日本でも8月に試験公開された(インド/ヒンドゥー語も同時)。この辺りの舞台裏もインタビュー記事で明らかになっている。
知りたい情報が検索結果ページでうまく入手できるのが、SGEの最大の特徴だ。検索結果に表示されたページにユーザーはアクセスする必要がなくなるし、たいていは検索結果のトップに掲載されるので、ChatGPTやBard以上に検索トラフィックに影響を与える可能性がある。Bard同様に、2024年のSGEの進化にも注視したい。
なお、ヤフーも、検索に生成AIを用いた機能を準備している。どのような機能になるのかこちらからも目が離せない。
- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)
AIで作ったコンテンツはSEOでどのように評価されるのか?
役に立つならAIが作ったかどうかは問題にならない
ChatGPTの登場以後、生成AIに記事を書かせることが容易になった。結果として、AIが書いた記事のグーグル検索での扱いが関心の的となった。
グーグル検索における生成簡潔にAIの扱いは、簡潔に言えば次のとおりだ:
- コンテンツを書いたのがAIか人間かは、重要ではない
- 重要なのは、コンテンツがユーザーの役に立つかどうか
ユーザーの役に立つものであれば、AIが作ったコンテンツでもなんら問題ない。逆に、人間が作ったコンテンツだとしても役に立たないコンテンツならば、必ずしも検索で評価されるとは限らない。
とはいえ、AIに作成を丸投げしたコンテンツではそのままでは、今の段階では有用性の点でも信頼性の点でも劣るケースが多い。生成AIが書いたゴミコンテンツがウェブを汚染し始めている現状が明らかになっている。
ChatGPTだけで書いたような記事では、そもそも上位表示は難しい。まっとうなコンテンツにしようとすれば結局は専門家の手を借りる必要があるので非効率だと指摘するSEOスペシャリストたちの声も紹介した。
一方で、Googleマップに投稿された口コミへの返信に上手にChatGPTを活用している事例も紹介した。
使い方次第で、良質なコンテンツ作成の支援にも使えるし、低品質なコンテンツを撒き散らすだけのスパムツールにもなりうるのが、生成AIだ。
- すべてのWeb担当者 必見!
4位~6位
グーグルのインデックス条件がますます厳しくなった2023年
対処法をエキスパートが指南
グーグル検索にインデックスされない
インデックスされてもすぐに検索から消えてしまう
こうした悲鳴にも似たインデックスに関する悩みを、2023年も頻繁に聞いた。事実グーグルは、インデックスするコンテンツの条件を年々厳しくしているようだ。「ウェブに公開すればどんなコンテンツでも無条件でインデックスされる時代」は、とうに終わりを迎えている。
検索エンジンがコンテンツをインデックスするのを促進する施策を2つ、2023年は紹介した。1つは、グーグル公式の検索セントラルヘルプコミュニティのプロダクトエキスパートたちによるもので、もう1つはso.laの辻正浩氏によるものだ:
インデックスに関して2023年にトラブルを経験した人は読み返しておくといい。
- インデックスがうまくいかないすべてのWeb担当者 必見!
「E-A-T」が「E-E-A-T」へと進化、経験も重要視
経験コンテンツが上位表示され始めたか?
グーグル検索の品質を人間の評価者が評価する際に用いられる検索評価ガイドラインに登場する「E-A-T」が「E-E-A-T」へと拡張されたのは、2022年末だった。
従来のE-A-Tは、次の3要素の頭文字をとったものだった:
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trust(信頼性)
ここにもう1つのEが加わった。Experience(経験)だ。
新しい「E」のExperienceとはどういったものかを、JADEの伊東氏が簡潔に説明している。伊東氏によるまとめを押さえておけば、一般のウェブ担当者にとって十分なExperienceについての知識を得られる。
Experienceも含めて、E-E-A-Tを徹底的に理解したいならば、住太陽氏が著した解説記事がオススメだ。SEO担当者なら一読しておく価値がある。
2023年8月のコア アップデートではExperienceを示すサイトが実際に評価されるようになったという分析もある。Experienceとはどういったコンセプトなのかを理解し、経験を示せるコンテンツ作りにも励みたい。
- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)
Google Discoverのランキング要因はブラックボックス? 最適化は難しい
まことしやかなエセ情報がはびこっている
Discover からのトラフィックは、予測可能性や信頼性が低い。偶発的な要素を含むので、キーワード検索のトラフィックの補完的なものと考える必要がある。
Discoverのドキュメントに、このような注意書きをグーグルが追加した。Discoverにコンテンツが掲載される要因もこのドキュメントでは解説されている。検索のランキング要因との共通点も多いのだが、サイト側ではコントロールできないものばかりだ。掲載されるかどうかは、ほぼグーグル任せと言ってもいい。熟練したSEOのプロですら、Discover最適化は実に難しい。したがって、トラフィック獲得の主軸にDiscoverを据えるのは危険だ。
実際問題として、Discoverの掲載要因はウェブ検索と比べると公式情報が少ない。これも手伝って巷にはDiscover最適化の間違ったノウハウが出回っている。うかつに取り入れてしまうと、Discover以外も巻き込む悪影響がでることもある。
グーグルによる情報公開の乏しさと、間違った施策が出回っている状況には、辻氏も不満を漏らしている:
Discoverの情報開示の少なさは問題。ユーザ数すら5年前の名称変更時発表時にMAU8億と公開されたっきり。それから誘導量は数倍になってるから、ユーザ数は驚くほどになってるはず。
— 辻正浩 | Masahiro Tsuji (@tsuj) December 16, 2023
それくらい影響があるのに「もともと不安定なものだから」という説明で良いと思ってるGoogleが信じがたい。
- Discoverがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)
7位~10位
あれから1年、グーグルの寄生サイト対策はどうなった?
着実に効果をあげていると思われる
昨年(2022年)のまとめでトップピックアップに選んだのは寄生サイトの横行だった。サイトの一部をサブディレクトリやサブドメインといった形式で第三者に貸すやり口だ。この手法自体に罪はないのだが、低品質なアフィリエイトサイトがこのやり方で高品質なニュースサイトなどに寄生し、検索品質を低下させている実情があった。
グーグルは、低品質な寄生サイトの対策を2023年も継続してきた。寄生サイトを絶えず監視してきた辻氏は、寄生サイトの順位下落をたびたび目撃している。ときには、手動対策もグーグルは与えているようだ。また、海外でも寄生サイトのランキングダウンは発生している。
11月下旬にはゲイリー・イリース氏に筆者がインタビューして、役に立たない寄生サイトに対する対策をグーグルが本当に講じていることと、今後も対策を継続することを直に聞いてきた。
また、ヘルプフル コンテンツ システムを説明するドキュメントに、第三者のコンテンツをホストするやり方に関する注意事項が追加されたことも、注目に値する。
悪質な寄生サイトが完全に撲滅されたわけではないが、検索結果で目にする数は着実に減少している。2024年はさらに突っ込んだ対策を期待したい。
- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)
ニュースサイト向けSEO情報が豊富だった2023年
動画解説のベストプラクティス
ニュースサイトのSEOは、ウェブ検索のSEOと比べると公式情報が少ない。しかし2023年は違った。Googleニュースに関するベストプラクティスをグーグル社員が解説した動画が公開された。
動画は3本ある。
1本目は、2022年に公開した英語版に日本語字幕を付けて2023年に公開された。ニュースサイト向けのSEOをテーマにダニー・サリバン氏とゲイリー・イリース氏が解説している。ニュースサイト運営者には確実に役立つ内容だ。20分少々の動画でボリュームがある。
2本目と3本目は、ダニエル・ウェイズバーグ氏とチェリー・プロマウィン氏が登場する動画で、10分程度の長さだ。こちらはさらに基本的ではあるが、確実に押さえておきたい基本でもある。
ニュースサイト管理者でまだ視聴していなければ、これを機にグーグル公式のニュースSEOベストプラクティスを学んでおこう。
また、ニュースコンテンツの評価に影響する「トピックオーソリティ」という名前のランキングシグナルの存在も、2023年に明らかになった。「特定の分野や地域について関連性と専門性が高いニュースコンテンツ」をウェブ検索とグーグルニュースで上位表示するように、トピックオーソリティは機能する。
こちらはすぐに何か大きな成果をあげられるものではないが、意識しておくと中長期的に違いがでてくるだろう。
- ニュースサイトのすべてのWeb担当者 必見!
リニューアルして再始動したGoogle検索オフィスアワー
新体制ではあんな氏が1人で切り盛り
グーグル内部の事情で休止を余儀なくされたオフィスアワーだったが、「Google検索オフィスアワー」という名称で再スタートした。新体制では、あんな氏が1人で切り盛りしている。内容自体には大きな変更はなく、事前に送られた質問にあんな氏が1つひとつ丁寧に回答してくれる。
あんな氏主演の新オフィスアワーは、5月10日公開の回を皮切りに7本が公開された。再生リストがあるので、見逃した回があれば視聴しよう。
自分1人では解決できない問題や疑問があれば、質問フォームから送っておこう。次回以降にあんな氏が答えてくれる。
- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)
Search Central Live Tokyo開催! 3年半ぶりの対面イベント
当日は大盛り上がり
2023年6月16日に、渋谷のグーグルオフィスでSearch Central Live Tokyoが開催された。検索関連の対面イベントは日本では、2019年11月に開催されたWebmaster Conference以来、実に3年半ぶりだ。約150人が参加し、グーグル社員によるブレイクアウトセッションや&Aセッション、選抜者によるライトニングトークなど非常に盛り上がった。
セッション内容の有用ツイート(X投稿)をこのコラムでまとめた。また、Q&Aセッションは検索オフィスアワーに組み込まれてYouTubeで録画が公開されている。ほとんどの内容は今でも古くなってはいない。参加できなかった人はチェックしておこう。
2024年もSearch Central Liveが日本で開催されるかどうは現時点では不明だが、開催されると信じて待ちたい。
- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)