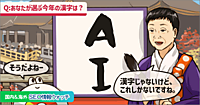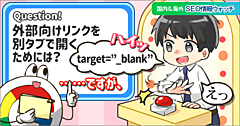絶対に許せない! AI進化版コンテンツファームで月間数億のアクセスを稼ぐメディア
グーグル検索SEO情報②
絶対に許せない! AI進化版コンテンツファームで月間数億のアクセスを稼ぐメディア
あざといやり口だがグーグルが見抜けていない (Josh Tyler on X) 海外情報
ある超大手メディア企業のインハウスSEOとして誘いを受けたSEOコンサルタントの投稿を紹介する。
その企業のCEOとの面談で、記事作成の現在のプロセスを教えてもらったそうだ。次のようなものだった:
ウェブ上でトレンドになっているトピックを常にスキャンするアルゴリズム(AIではない)を持っている。「どんなトピックを記事として扱うか」を、そのアルゴリズムが選択する。
トピックが選択されると、次のアルゴリズムが「他の人がそのトピックで書いたタイトルと記事」をスキャンする。その情報を使用して、記事のタイトルを考え出す。
その記事のタイトルは、順番待ちリストに入っているライターにランダムに割り当てられる。「タイトル」と「書くべき内容の基本的なアウトライン」をアルゴリズムがライターに提供する。
完成した記事を編集者がレビューし、多少修正する。画像はアルゴリズムによって提案された画像から選択する。
記事が公開される。
このプロセスについて投稿者は次のようにコメントしている。
このプロセスは何度も繰り返され、特定されたトピックでできるだけ多くの記事を生成し、ついには、そのトピックの記事を氾濫させて支配し、競合するコンテンツを排除する。
アルゴリズムによって設計され、ライターは空白にコンテンツを埋めるために作業するだけだった。
ライターに指示するアウトラインをアルゴリズムがどのように作成するかを私は詳しく調べようとした。私が収集した限りでは、基本的に、他のサイトの誰かがやったことをコピーするだけだった。または、他のサイトのいくつかの異なる記事を組み合わせてアウトラインを作成していたかもしれない。
この会社のサイトはペナルティを受けたことがなく、現在、グーグル検索、ニュース、Discoverでかつてないほどに好調だ。月に何億回も閲覧されている
この方法では、多くのコンテンツをすばやく作成できるだけでなく、安価に作成できる。1人の編集者が数十人のライターを処理でき、ライターは第三世界の人を雇っているため、支払う料金は安い。これは、自動化されたシステムによって、決まった形式どおりに記事を書けばよく誰でもできるようになったためだ。
Had a meeting with the the CEO of one of the biggest and most well known content farm media companies.
— Josh Tyler (@joshtyler) January 14, 2025
He wanted me on his team, so he answered all of my questions about how his company produces content.
Now I’m going to tell you.
まさしく「検索エンジンのため」に作ったコンテンツだ。非常にあざといやり口ながら、現状ではかなりうまくやっているようだ。もちろん、手段はともあれ検索ユーザーに価値を提供するコンテンツを作れているのならば、まったく問題はないのも事実だ。とはいうものの、実際にはそうではない可能性が高い。
そして、「今、うまくいっている」からといって、筆者たちが模倣するべきやり方では決してない。別トピックで取り上げたリリー・レイ氏の警告のように、グーグルが気づいて検索結果から排除してほしいのものだ、それも早急に。
- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)
AI生成コンテンツからバックリンク→明らかなリンクスパム
SEO業者の施策に注意 (John Mueller at Bluesky) 海外情報
次のような懸念を投稿した人がいた:
自分のプロジェクトのWebサイト関連のサポートを、ある企業に提供してもらっています。
その企業がSEOの被リンク獲得をアウトソースしている外部企業が「あたかも私のプロジェクトが書いたかのように、生成AIを使ってウェブページやブログ記事を作成していた」ことを、今日知りました。
そもそも私が書いたと示すのは事実に反していますし、私の仕事の倫理観にも反しています。
Today I learned that the company providing my project’s web support has been outsourcing SEO ‘back link’ provision to a third party that’s used gen AI to create web pages and blog posts as if authored *by my project*. Not only are they factually incorrect, but also in ethical opposition to my work
— Becca Harrison (@beccaeharrison.bsky.social) January 8, 2025 at 3:35 AM
外部のSEO業者が「SEO施策」と称して、生成AIで作成したコンテンツを別のサイトで公開し、そこから本サイトにリンクを張っているというのだ。しかも筆者名を偽ってだ。
グーグルのジョン・ミューラー氏はこの投稿を読んで、次のようにコメントを返した:
聞くだけでもイライラしますね。削除できましたか? これはほぼ確実にグーグルのスパムポリシーにも違反しています。
It's frustrating to hear - did you manage to get it deleted? This is almost certainly against Google's spam policies too. :-(
— John Mueller (@johnmu.com) January 8, 2025 at 3:54 AM
ミューラー氏が指摘するように、ほぼ完全にリンクスパムだ。手動対策の対象になる。AIによる無作為なコンテンツ作成は大量生成されたコンテンツの不正使用に該当するかもしれない。
自作自演リンクのスパムを自ら実行する人は今の時代にはいないと思うが、業者のなかには存在しているようだ。外部のSEO業者に依頼するときはくれぐれも注意してほしい。どういった行為がスパムポリシーに違反するかを、発注者として把握しておこう。
- すべてのWeb担当者 必見!
レンダリング戦略とは? グーグル社員がわかりやすく動画で解説
それぞれのレンダリング戦略に長所・短所あり (Google Search Central on YouTube) 海外情報
「Google検索でうまく扱われるために、CMSやウェブアプリのレンダリング戦略に関して知っておくべきこと」を、Google検索リレーションズチームに所属するマーティン・スプリット氏が動画で解説した。
SEO業界の人は「レンダリング」というとGoogle検索側のJavaScript/CSSレンダリングのことをイメージするかもしれない。しかしこの動画で解説しているのは、「ブラウザに表示される内容の構築」であり、「ページ内容の構築をサーバー側で行うか、ブラウザ側で行うか、Webサイト管理者が決めるシステムの仕組み」に関することだ。
動画では、次のようなことを解説してくれている:
- レンダリングとは
- プリレンダリング
- サーバーサイドレンダリング(SSR)
- クライアントサイドレンダリング(CSR)
- どのレンダリングを選ぶか
- まとめ
レンダリングにはいくつかの方法があり、それぞれに長所と短所がある。こうしたことにも触れながらスプリット氏は説明している。コンテンツ生成にJavaScriptを多用しているサイトの管理者に特に役に立つ内容だ。
なお、スプリット氏は動画で話しているが、日本語字幕を利用できる。
- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)
- 技術がわかる人に伝えましょう
「SEOスパムしていない」=「上位表示できる」とは限らないよね? 当たり前だけど
公式チェックリストでの自己評価は必須 (Martin Splitt on Bluesky) 海外情報
グーグル検索リレーションズチーム所属のマーティン・スプリット氏が、ぼやきとも受け取れるメッセージをBluesky(ブルースカイ)に投稿した。
こんな風に私に連絡してきた人がいる:
このサイトは絶対にスパムではないのに、検索ランキングが低い
そのサイトを見てみたら、本当に質が低いものだった。その人がそのことに気づいているかどうかはわからない。
自分のウェブサイトがどのようなものだと思っているのかを聞いてみようかと考えている。純粋にこれを理解したいんだ。
Someone reached out to me with their website "definitively not being spam" not ranking and I looked at it and boy was it low quality. I'm not sure if they know that. I'm considering asking them what they think their website is. I genuinely want to understand this.
— Martin Splitt (@divingfor.fun) January 14, 2025 at 5:43 AM
「スパムしていない=上位表示できる」ではないことは、言うまでもない。役に立つ高品質なコンテンツがグーグルからの評価を得る大前提なのだが、問い合わせた人にはその視点が抜けているように思える。
とはいえ、自分が作成したコンテンツを客観的に評価するのが難しいのも確かだ。少なくとも、グーグルが提供するコンテンツ品質チェックリストに照らし合わせて自己評価はすませておきたい。できれば、第三者にも査定してもらいたい。
- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)
中央省庁のサイトがオンラインカジノに!? 放置サイトのハッキングには要注意
忘れられたサブドメインがないか調査 (NHK) 国内情報
国土交通省や総務省など複数の中央省庁の一部ウェブサイトにセキュリティ上の不備があり、ハッキングを受けていたとNHKが報じた。
次のような状況だったという:
国土交通省が公共交通機関の利用実態を調査するために使っていたウェブサイトが、タイのオンラインカジノにつながる広告サイトに一時流用されていた。
総務省が新型コロナ対策の特別定額給付金用にかかわるウェブサイトをドメイン名「kyufukin.soumu.go.jp」で2020年に開設していたが、サイトを閉鎖したあと必要な対策がとられていなかったため、第三者が不正利用できる状態になっていた。
こうした話題は以前ならば「官公庁の使っていた汎用.JPドメイン名が、サイト終了後に悪用される」だったが、今回は「放置されたサイトが攻撃を受けて.go.jpドメイン名のまま悪用される」という、非常に問題のある状態だ。
NKKの取材に対して辻正浩氏は次のようにコメントしている:
公的機関や大企業などのドメインは信頼性が高いため、検索の上位に表示されやすく、広告料を目的としたサイトに使われたのだとみられる。ドメインは信頼性を示すものなので、今回は、国の信用を悪用できる状況にあったと言え、非常に大きな問題だ
省庁などの政府機関が利用するドメイン名は「go.jp」だ。評価の優劣をドメイン名だけでグーグルがつけることはないが、政府機関はコンテンツの質だったりリンクの数だったりとさまざまな要素で信頼性が高い。つまり上位表示しやすいのだ。ハッキングのターゲットとしてはもってこいだろう。
今回のケースのようにサブドメインで運用していた別サイトが放置されているケースは少なくない。CMSやプラグインのアップデートが実行されずに脆弱性をつかれてハッキングされやすい。前任者や別部署が過去に運用していたサブドメインサイトが放ったらかしになっているケースもある。
放置されたサブドメインサイトの危険性については、名高いSEOコンサルタントのグレン・ゲイブ氏も警鐘を鳴らしている。
複数部署でサイトを利用している企業のウェブ担当者は、忘れ去られたサブドメインがないかどうかを調査しておこう(ゲイブ氏の記事が役にたつ)。
- すべてのWeb担当者 必見!
 海外SEO情報ブログの
海外SEO情報ブログの
掲載記事からピックアップ
URL検査ツールのスクリーンショットについてと、2025年のグーグル検索の進化についての記事をピックアップ
- URL検査ツールのスクリーンショットはGoogleが実際に見ている表示
最終的に頼るべきはHTMLコード
- ホントにSEOを極めたい人だけ
- Google検索とAIは2025年にどのように進化するのか?
AIがさらに浸透する
- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)