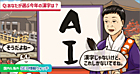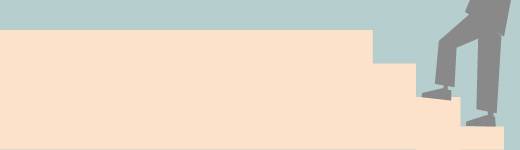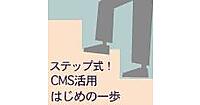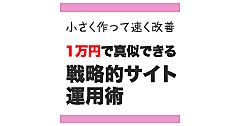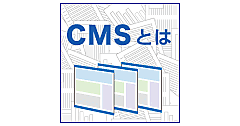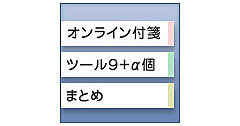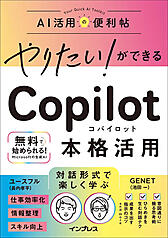CMSの費用対効果(ROI)をKPIで体感しよう!
CMS導入前の費用対効果算出や、運用開始後の効果測定に使えるKPIの立て方について検討する。
2009年5月27日 10:00
作業効率に関するKPI
CMS導入の費用対効果(ROI)は、社内提案を通すための必殺技だといえる。CMSはコスト削減につながるのか?それとも必要なインフラへの設備投資なのか?まず重要なのは、導入効果を数値化することだ。自社の事情に合った目標を立てて、計測を開始しよう。今回は、導入前の費用対効果算出、または運用開始後の効果測定に使えるKPIの立て方について、具体的に検討する。
CMSを導入する結果、何が変わるのか?仮説を立てて、それぞれについてKPI(Key Performance Indicator=重要指標)を設定してみよう。まず、「CMSを導入することにより、コンテンツをより効率よく管理できるようになる」ということを数値化してみる。効率が良くなるため、より多くのコンテンツを作ったり、更新できるようになるはずだ。CMSから取り出しやすい指標として、次の3つを段階的に見ていこう。
- 新規作成または更新されたコンテンツのページ数
- 承認まで完了したワークフローの本数
- 生産性=新規・更新ページ数÷作業者全員の合計作業時間
新規作成または更新されたコンテンツのページ数
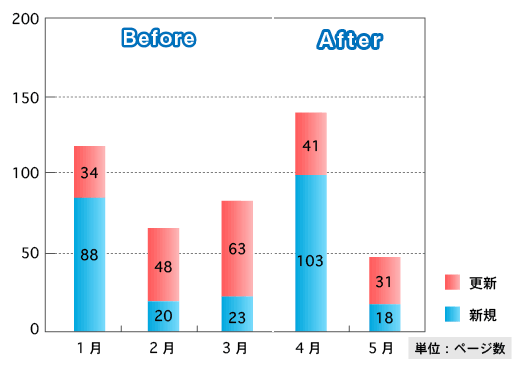
1月と4月にページ数が増えているのは、時期的な要因だ。また、ページ数が多ければ作業量も多いとは一概に言えない。たとえば「©2010」など、共通フッタにおけるコピーライトの年号表記を変更すると、全ページが更新されることになる。
どうも、この指標はCMS導入のROIとして使うには適切ではないようだ。
承認まで完了したワークフローの本数
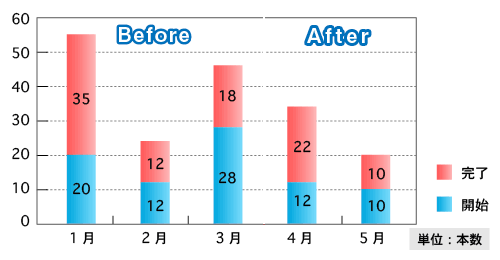
制作の作業とワークフローは、公開のタイミングよりも前に仕込んでおくことがあるため、先ほどの「新規作成または更新されたコンテンツのページ数」よりも時期が前にズレこんでいる。
いずれにせよ、ページ数やワークフロー本数のようなボリュームに関する指標は、マーケティングの力の入れ具合や年度末などの季節要因、人員の増減などによってブレてしまう。
この指標も、CMS導入のROIを表しているわけではなさそうだ。
生産性=新規・更新ページ数÷作業者全員の合計作業時間
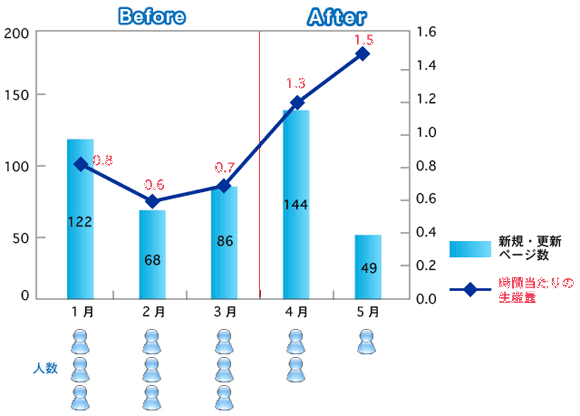
そこで、1人当たりの生産性、に注目してみよう。たとえば、デザイナーやデベロッパーは1時間あたりに何ページを生産したのか? などだ。例では、CMS導入後にアサインするスタッフ数を減らしたため、生産性が上がっていることがわかる。
これでようやく、CMSの導入効果が見えるようになってきた。