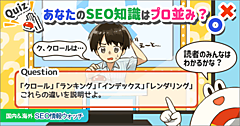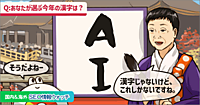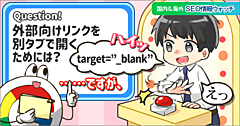2022年1月のオフィスアワー: 監修者情報を検索エンジンに伝えるには? リンクの表記を統一させるべきか、ほか
Web担当者に役立つ最新情報
2022年1月のオフィスアワー: 監修者情報を検索エンジンに伝えるには? リンクの表記を統一させるべきか、ほか
だれが書いたかはランキング要因ではない (グーグル ポリシー オフィスアワー) 国内情報
グーグルの金谷氏とあんな氏がポリシーオフィスアワーを開催した。2022年の1回目だ。
2人が回答した質問は次のとおり:
- 「他の人はこちらも検索」と検索キーワード(4:03)
- リンクの表記を統一させるべきか(7:39)
- 除外された記事をインデックスさせたい(11:31)
- Search Console: 検出 - インデックス未登録(16:11)
- 『ページにリダイレクトがあります』検出条件(18:43)
- 「Aggregate rating」構造化データ(20:08)
- サブディレクトリで無関係な記事ページを作成(27:42)
- URL パラメータツールと robots.txt の違い(35:53)
- 記事コンテンツの一部を無断転記して高順位に(41:09)
- 著作権侵害による一括削除の依頼(45:05)
- 監修者情報を検索エンジンに伝えたい(48:19)
気になる質問の回答をダイレクトに確認できるように再生時間にリンクしてある。
個人的には、最後の「監修者情報を検索エンジンに伝えたい」のやりとりはぜひチェックしてほしい。質問者は記事を監修した人を検索エンジンに伝える方法を質問者は知りたがっているのだが、金谷氏は「だれが書いたかはランキング要因ではない」と明言し、検索エンジン相手ではなくユーザーにとってわかりやすく紹介することが重要だと説明している。詳しくは動画で確認してほしい。
なお、パブリッシャー ポリシーに関する質問も1つ出ている:
- ブログのコメントに対価を支払うのは違反か(51:42)
こちらも、ぜひすべてのサイト管理者が把握しておいてほしい内容だ。
- すべてのWeb担当者 必見!
ガイドライン違反がバレずに上位表示しているサイトがある、ウチもやらないと損?
見つかったときの代償が大きすぎる (John Mueller on Twitter) 海外情報
「よくある質問(FAQ)の構造化データ」を悪用するSEOに関して、ユーザーがツイッターで指摘した。
具体的には、ユーザーがページで見ることができないコンテンツをFAQとして構造化マークアップし、検索結果にリッチリザルトとして表示させているサイトがあるというのだ。
この手法はFAQ構造化データのコンテンツ ガイドラインで明確に禁止しているものだ。
質問者はSEOのプロとして「この手法はNGだ」とクライアントに説明しているのに、そうしたやり方で検索結果の良い場所にFAQを表示しているサイトがあるのだという。そうした状況を苦々しく思い、グーグルのジョン・ミューラー氏に訴えた形だ。
こうした指摘にミューラー氏は次のようにコメントした:
OK、把握した。
だが、どんなガイドラインでも同じなのだが、ズルいことをする人はいるし、ルールを破る人もいる。わざと破る人もいて、それがバレずに見落とされたままになるときもある。
だからと言って、それが賢いやり方だということではない。
I get that -- but that's the same for any of our guidelines. Sneaky people are sneaky, people break rules, sometimes on purpose, and sometimes don't get caught, but that doesn't make it a good practice.
— 🐄 John 🐄 (@JohnMu) January 20, 2022
ミューラー氏は「今すぐに対処する」といった名言はしていない。しかしその発言からは、「いままで把握できてなかった」「もう把握したから安心して」というニュアンスを読み取れる。
よくある質問のリッチリザルトに限らずに、グーグルが定めるガイドラインに違反し、うまいことやっているサイトは常に存在する。しかし、だからといって、
あのサイトがやっていて大丈夫だから、自分のサイトも
と考えて行動するのは、まったくおすすめしない。絶対に見つからないという保証はないし、発見されたときの代償(順位下落や手動の対策)が大きすぎる。
「おかしいな」「この手法はダメなのに」という場合にとれる最善の方法は、グーグルの人に確認することなのかもしれない(たとえばグーグル ポリシー オフィスアワーの質問として聞くのが最もやりやすいだろう)。
- すべてのWeb担当者 必見!
ドメイン名に関する4つの質問にグーグル社員が回答
SEO初級者からの質問っぽい (#AskGooglebot on YouTube) 海外情報
ドメイン名に関する4つの質問に、グーグルのジョン・ミューラー氏が動画で簡潔に回答した。一般のサイト管理者から寄せられた質問だ。
Q1. example.space というドメイン名よりも example.com というドメイン名を使ったほうがいいか?
- 「.space」などの新しいTLD
- 「.com」などの古典的なTLD
回答:
好きなものを選んで構わない。
SEOの観点からは、新しいTLD(トップレベルドメイン名)は、ほかのTLDと等しく扱われる。
Q2. wwwありとwwwなしのどちらをドメイン名に使うべきか?
回答:
どちらでも好きなほうを使っていい。グーグルがどちらかを優遇するということはない。
技術的な事情でどちらかを選ばなければならないときもあるが、通常は好みの問題だ。
Q3. 異なるドメイン名のURLに対して rel="canonical" タグを設定できるか? たとえば「.com」ドメイン名のURLを「.co.jp」ドメイン名のURLに正規化できるか?
回答:
できる。
rel="canonical"で指す先のURLは、別のドメイン名でも問題ない。
Q4. ccTLD(国別トップレベルドメイン名)でもグローバルで上位表示できるか?
回答:
できる。
ccTLDは、「その国が対象だ」とグーグルが理解する手助けになるものであり(限定するものではないので)、世界中で上位表示が可能だ。
唯一の制限はそれ以外の国に(Search Consoleの)インターナショナルターゲティングを設定できないことだ。たとえば、
- フランス向けの「.fr」ドメイン名をグローバルサイトに使う
は可能だが、
- フランス向けの「.fr」ドメイン名を明示的にブラジルにインターナショナルターゲティング設定する
ことはできない。
どれも、SEO初級者からの質問のようだ。それでも、上級者であっても過去に抱いたことがある疑問のようにも思う。
- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)
サイトのURL変更をうまくやる4つのステップ
これをやらないと評価が失われる (#AskGooglebot on YouTube) 海外情報
公開してある程度リンクなどの評価もついているサイトのURLを変更する必要が生じたときには、どんなことに気をつけなければいけないのだろうか?
検索エンジンはページをURL単位で管理している。元のURLから新しいURLに評価を移すには、適切な方法が必要だ。さもなくば、評価は失われてしまう。完全にサイトを作り直すのなら構わないが、そうでないなら移転のための正しい設定が必須となる。
そこで、SEOを考慮に入れた、URL変更をともなうサイト移転について、グーグルのジョン・ミューラー氏が動画で簡潔に説明した。
ミューラー氏は次の4ステップで移転を進行するようにアドバイスしている:
リサーチ: 移転には時間がかかるしランキングへの影響もあるので、選択肢と潜在的な効果を調査する。実行するタイミングも考慮する。
新旧のURLのリスト作成: 元のURLと新しいURLのリストを作成する。移行後の変化を追跡しやすくなる。
移行開始: 移行したら、旧URLから新URLへと301リダイレクトを設定する。
さらに、次の内部要素のURLを新しいものへと更新する:
- リンク
- フォーム
- 構造化データ
- サイトマップ
- robots.txt
- など
監視: すべてのページへのアクセスが適切にリダイレクトしているかチェックする。Search Consoleでは、重要なページはすぐに移転されているのがわかる。残りのページの移転はゆっくり進む。
最後に、注意すべき点としてミューラー氏は次の2つに言及している:
- たいていは、移転完了に数か月かかる
- リダイレクトは少なくとも1年は継続する
※筆者注: リダイレクトの1年継続の推奨については別の動画で理由をミューラー氏は説明している。
なお、サイト移転の手順をグーグルは検索セントラルサイトで詳しく解説している。サイト移転の際には必ず読んでおくようにしてほしい。
- すべてのWeb担当者 必見!
グローバルサイトの構造化データは全言語のページにマークアップすべきか?
グーグルは魔法をかけるようには転送してくれない (Google SEO office-hours) 海外情報
グローバルサイトを運営していて、さまざまな言語や地域に対応するページをそれぞれ公開しているとき、構造化データの扱いは次のどちらが正しいのだろうか?
- 全言語のページに構造化データを含める必要がある
- メインとなる1言語向けページにマークアップしておけばいい
「グーグルは優秀だから、メイン言語のページに構造化データを入れておけば、ほかの言語向けページにも適用してくれるのではないか」と考える人もいるかもしれない。
しかし、グーグルのジョン・ミューラー氏によれば、すべてのページにマークアップする必要があるそうだ。あるページから別の言語向けページへ魔法をかけるように構造化データを転送することはないとのことである。
多言語・多地域に向けたグローバルサイトのウェブ担当者は知っておくべき情報だ。
- グローバルサイトのすべてのWeb担当者 必見!
 海外SEO情報ブログの
海外SEO情報ブログの
掲載記事からピックアップ
検索結果の変化とSearch Console新機能を今回はピックアップ。
- GoogleがPC検索結果にサムネイル画像を表示。テスト? 正式導入?
検索結果のCTRに影響するかも
- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)
- PCページのページエクスペリエンスレポートをSearch Consoleが提供開始
PC版ページエクスペリエンス アップデートの導入開始は今月
- すべてのWeb担当者 必見!