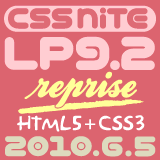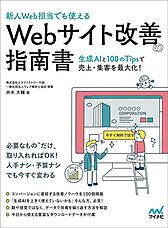Aggregator
Instigator Blogから失敗するスタートアップ企業の特徴を紹介。起業する前の人はこうならない反面教師に、起業したけどイマイチうまくいっていない人は軌道修正箇所の確認に、スタートアップ企業への転職を考えている人は転職しない方が良い会社の参考に?!してみてください。 — SEO Japan
以下のような道を下っていくスタートアップ企業をどれくらい見たことがあるだろうか?
数人であるアイディアを思いつき、興奮する。すっかり興奮する。
競争相手のことや、誰かがその計画を盗むのではないかと心配し、口を閉じる。
何かを作り始める。この時大抵は、小さな暗い部屋に閉じこもり、大量のカフェインを摂取している。
すぐに資金を集める。とにかく設立するためにシードラウンドであることが多い。
大量のコードが書かれ、大量のアイディアがホワイトボード上にあり、みんなワクワクしている。そして、銀行にはお金がある。
開発に予定よりも時間がかる。重要な仕様の変更が知らぬ間に忍び寄っている。見積もりと合わない。しかし、もう後戻りはできない。
追加で1人か2人を雇い、物事を迅速化しようとする。
資金は尽きるが、モチベーションはいまだに高い。
設立完了!さあ、後はお祝いと成功を待つだけだ。
誰にも相手にされない。
さて、この時点で、もしくはステップ8くらいで、若干慌て始める。それは、設立者がどれくらいやみくもに走っているかということや、全てがうまくいくと思いこむことにどれくらい成功しているかによって大きく左右される。
1つの大きな問題点は、失敗の数がこれらのステップを先に進むほど増えていくということだ。失敗点やリスクを解消しているのではなく、追加しているのだ。
スタートアップ企業の立ち上げに向かうこの道筋を私はスタートアップD.O.A(Death on Arrival)と呼んでいる。つまり、即死が確定しているスタートアップだ。最低だ。見るのもつらい。憂鬱で苛立たしいことだ。そして、極めてよくあることでもある。
ここに、数多くのスタートアップ企業が直面する3つの重大な問題を紹介する。
1. 早い段階の系統だった検証が十分ではない
スタートアップのアイディアを検証することは、それ自体がとても大きな難問だ。しかし、ある程度の系統だった検証がなければ、全くの当てずっぽうでやることになる。中には他に比べて系統的に検証するのが難しいアイディアもある。例えば、企業・消費者間(B2C)のウェブアプリは検証が難しい。Twitterが世の中に出る前、Twitterの検証などどうやって出来ただろうか?しかし、そのような場合でも、もっぱら希望と祈りだけを頼りにしていたら、D.O.A(即死)の可能性は非常に高くなるのだ。私たちはこういった失敗についての話しよりも、成功した話しばかり多く耳にする。
どうか、どうか、どうか、検証する方法を見つけて欲しい。共同設立者と腰を下ろし、このことについて徹底的に話し合うのだ。どうすれば検証ができるのか考え、誰に話をするべきなのか考えるのだ。臆病になってはいけない。出来るだけ早く、拒絶への恐れを克服するのだ。
どうか、どうか、どうか、厳しく検証をし、積極的に「私たちは系統的な検証プロセスを通過し、これは当てずっぽうではないのだ。スタートアップD.O.Aになる前に、今すぐに問題点はつぶしてしまおう。」と言って欲しい。
2. 資金が十分ではない
もし、6ヶ月間で資金を集めるのなら、次の日には行動を開始しなければならない。その理由は、資金調達には最大6カ月はかかるからだ。もし、立ち上げや、その後のけん引力やかなり重要な節目を積み重ることを繰り返すのに十分な時間を取らなければ、多くの資金を調達するのにひどく大変な時間を過ごすことになるだろう。これは必ずしも最初からから大量の資金を集めるための議論ではなく、資金の正しい使い方を理解し、なるべく早く立ち上げ(そうすればより重要な節目を達成する時間の余裕ができる)、仕様変更に圧倒される大量のシステムを作ろうとする中で身動きがとれなくならないようにするための議論だ。小さな問題をきちんと解決すること。小さく始め、集中し、曖昧さのない価値ある提案をすること。頻繁に使用する製品をつくること。
3. 事業経営の仕方を知らずにいる
初めて起業家になる人は、一般的には企業運営の仕方を知らない。それは今までにやったことがないからだ。ただ単に気が付いたら自分がその環境にいたというのが現実なのだ。スタートアップ企業の経験がある人でさえ、この問題を抱えている場合もある。とても難しいものなのだ。助けが必要だ。出来るだけのことをすること。良い助けを得ること。自分が何をしているのか分からないということを認め、誰が助けてくれるのかに気が付くこと。
スタートアップD.O.Aになるのは最悪だ
自分の信念と魂を(たくさんの血と汗と涙と、そしてお金も!)注いで立ち上げて、失敗し、やり続けるためのリソースも金も力もなくなってしまう。しかし、これを変えることができる方法もあるのだ。そして、たとえそれがあなたの戦略やチームやロードマップなどを大幅に変更することになったとしても、今こそそれを実行する時なのだ。良くなるのを期待して待っていてはダメだ。何百万もの人があなたのサイトを訪問し、お金を支払ってくれることを期待して待ってもダメだ。必要な修正を早くすればするほどチャンスは高まるのだ。
この記事は、Instigator Blogに掲載された「Startup D.O.A.」を翻訳した内容です。
最初のくだりの10番目「誰にも相手にされない。」には思わず笑ってしまいました。確かに自分で考えたアイデアをスゴイと思われない限り起業することもないでしょうが、自分の考えたアイデアを変に疑心暗鬼になって立ち上げるまで誰にも言わないまま進めてしまった所、思ったほど受けず結局誰にも使われないままで終わってしまった、、、というケースは起業してまでやるかはともかく良くある話ですよね。誰か信頼して相談できる人がいることが大事かもですね。最も、自分がスゴイと思っていても実際誰かが盗んでまで真似したいかと思うアイデアなんて滅多にないわけですし、どんどん人に話して意見を聞きながら進めていく、とやり方もあるでしょうけど。別に起業して成功するには、革新的なビジネスアイデアがないといけない、なんてことは全く無いわけですし、意見を聞きながら市場で受け入れられるようブラッシュアップしながら進めていくという方法の方がより今風というかネットビジネス的かもしれませんね。
後は現実的な話ですが起業する時はある程度の資金は準備してから始めた方が確実とは思います。新規事業の立ち上げが予定通りに進むことなんてまずありえないわけですし、早々にお金がなくなってその場しのぎの本来やりたくない仕事をやって結局本来やりたいことができないままズルズル時間だけ立ってしまう、、、なんてケースもあるでしょうし。予定通りに進むことなんて滅多にないということでいえば、それをあらかじめ予期してお金は最低限で回すことも大事でしょうね。。。ビジネスプランを考える時はついお金をかけてビジネスの立ち上げを加速化させたプランになりがちですが(=人を雇いすぎる&ビジネスの検証をする前から広告費など無駄なことにお金をかけすぎる)、その通りに回らなかった場合、資金が足りなくなったら一発アウトですからね。なんて偉そうにいっている私も新規事業や投資事業で過去に何度か痛い目にあいました。
スタートアップをつぶさないためには、どれだけ良いビジネスアイデアだと思ったとしても最初の1年はビジネスの可能性を検証する時間として最低限の資金で回す方が無難かと思います。一度加速し出したら後には戻れませんからね。。。スタートアップの場合、軌道修正して立て直す程の余裕があるケースは余りないですしね。
最後は個人的な雑談のようになってしまい恐縮です m(_ _)m — SEO Japan
米インターネット利用者の7人に一人は動画を投稿
米検索エンジンの検索語数の平均は3なのに、何故Facebookでは平均が2なのか
パブリッククラウドサービス、過半数がセキュリティへの不安
RTmetricsのAuriQ Systemsが新会社を設立
2010/6/3のオーリック・システムズのリリースから。http://www.auriq.co.jp/press/2010/det/0603.htmlhttp://www.auriq.co.jp/press/2010/det/0603_2.htmlモバイルマーケティング事業に特化した100%出資子会社としてmaqs(マックス)株式会社を設立。新機軸のモバイルマーケティング事業を展開していく。その第一弾として、今年7月より、新しいモバイル広告マーケットプレイスを提供開始する予定。以下がその説明文。単なるツールベンダーからマーケティング支援企業への進化が必然の流れなのか。オーリックが独自開発した「リアルタイム・スコアリングエンジン」により、サイトの特性から広告主が求める条件とマッチングを行い最適な広告を配信します。広告掲載料は、広告主による入札方式で決定され、クリック単位で課金されます。
Google AdWords セミナー情報ページが新しくなりました
Posted by オンラインビジネスソリューションチーム
AdWords オンライン教室 では、今までどおりのライブでのオンラインセミナーの最新情報はもちろん、多くの皆様からご要望をいただいていた、オンデマンドのビデオセミナーもご用意しています。
現在は、下記の 8 種類のオンデマンドセミナーをご視聴いただけます。
· AdWords スタートガイド
- アカウント管理画面でできること [受講]
- 広告が表示されない理由 [受講]
- AdWords 広告 5 つの必勝法 [受講]
· アカウント パフォーマンスの改善
- アカウント構造の最適化 [受講]
- キーワードターゲット広告表示回数の最適化 [受講]
· 費用の管理
- コンバージョンオプティマイザー活用 [受講]
· アカウント パフォーマンスの理解
- コンバージョントラッキング導入 [受講]
· 広告掲載範囲の拡大とターゲットユーザーへのアプローチ
- コンテンツターゲット広告の最適化 [受講]
これらのオンデマンドセミナーはいずれも、20~30 分間の短いセミナーで、皆様のご都合に合わせて、いつでもご受講いただけます。
基本から復習したい方も、さらに掲載結果を向上させたい方も、ぜひこの機会にAdWords オンライン教室 をご利用ください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
[ツール]今までのアクセス解析ツールの「不満」を取り除いた、韓国生まれの「X-log」レビュー
今回は株式会社ジャスネットが提供する、アクセス解析サービス「X-log」を紹介いたします。不正クリックを追跡して、ユーザーのアクセスを遮断出来る機能がウリとの事で使って見ましたが、実はそれ以外にも機能が豊富な、骨太アクセス解析ツールでした。 注意: 1)ツールの使用時間は15時間ほどです。一部の機能や設定を見逃している可能性があります。 2)過去のツール紹介記事と同様「広告記事」ではありません*1 ※ツールのレビューを希望される会社様・個人の方は「こちら」をご覧下さい。 X-logの概要 X ...
JIAA、10周年記念懸賞論文の受賞作品を発表
最優秀賞は博報堂の亀谷政晃氏。7月にはインターネット広告推進協議会のウェブサイトで受賞論文が公開されるようだ。
コカコーラ+メントス=ロケット自動車
メキシコ湾で原油が大量に流出していることを考えれば、コカコーラがこれくらい無駄になってもよかろう。
アクセス解析チェック項目一覧表(チートシート) - どのデータをいつ分析するべきか [アクセス解析tips]
Web担当者Forumの2010/6/3の記事をどうぞ。http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2010/06/03/8098関連リンク:<リサーチ/データのリテラシー入門>社会人に必要なリサーチ/データリテラシー5原則 適切な調査対象者の抽出(サンプリング)とは? サンプル数や回答数よりも回収率が大事な理由 調査方法に潜む罠とチェックの重要性 集計方法と指標の定義: さまざまな平均値/中央値/最頻値 外部要因を意識したデータの読み解き方<データをざくざく処理するためのグラフの読み方、使い方> 「一つのグラフには一つの主張」の罠 代表的な4つのグラフの使い分けのポイント 円グラフの使い分けを論理的に考える わかりやすい棒グラフ作成のポイントと棒グラフの限界 折れ線グラフの伸び率を大きく見せるトリックとは? ひと目でわかる2軸グラフの作り方のコツとは?
最近よくいただくお問い合わせ(FAQ)
最近よくいただくお問い合わせをこちらにまとめました。
- CSS NiteではUSTREAM配信を行わないのですか?
- アップルストア銀座でのマンスリー版などがUSTREAM配信にもってこいだと思いますが、現状、アップルストア銀座では、USTREAM配信が許可されていません。
有料版は、ビジネスモデルとしてどうなのか?という問題よりも、出会いの場としての意義を重要視しているため、今のところ、行う予定はありません。 - 有料でも、あとでビデオを見れるようにして欲しい。
- 現状、コストと手間的に難しいです。
- 有料版のお申し込みの際、複数枚を一括で購入できるようにして欲しい。
- たとえば、受講票を送付する場合、「山田太郎さん」が2名いらっしゃると、混乱のもとです。会社によって、いろいろご事情があると思いますが、実際にセミナーに参加される個人名とメールアドレスでそれぞれお申し込みくださいますようお願いいたします。
「Yahoo! JAPAN クリエイティブアワード2010」公式サイト公開!
最近よくいただくお問い合わせ(FAQ)
最近よくいただくお問い合わせをこちらにまとめました。 CSS NiteではUST... CSS Nite実行委員会
CSS Nite LP, Disk 9.2(reprise)にご参加の方へ
今週の土曜日(6月5日)にベルサール九段で開催されるCSS Nite LP, Disk 9.2(reprise)にご参加される方へのお知らせです。
- 受講票は、6月2日に送信しました。早めにご確認ください(前日や当日に、届いていないと言われても、対応難しいです)。最悪、名簿でチェックしますので、届いていたけど、忘れた、等の方は、とりあえず会場にお越しください。
- 開場は12:00、開演は12:30です。
- カウントダウンメールにて、懇親会のお知らせをご案内しています。残り16名になっています。ご参加希望の方は、事前登録をお願いします。
- その他、こちらのページもご一読ください。
会場はLP9のときのベルサール神田とは異なります。ご注意ください。
CSS Nite LP, Disk 9.2(reprise)にご参加の方へ
今週の土曜日(6月5日)にベルサール九段で開催されるCSS Nite LP, ... CSS Nite実行委員会
被リンク構築を成功に導く2010年版の5大理論
サーチエンジンランドから被リンク構築の話題を。2010年版の5大理論とは大げさなタイトルを付けてくれたものですが、その内容はいかに? — SEO Japan
リンク構築は常に変化している。ここ数年間で、質の高いリンクを数多く持つ質の高いコンテンツの能力の大半、もしくはオーガニックな見返りの大半が失われてしまった。ウェブサイトのオーナー達による自発的な共有はすっかり影をひそめるようになった。ウェブ上の競争は加熱し、ノイズは増える一方である。さらにリンクを巡る金銭的なインセンティブが加わり、良質なコンテンツがなかなか注目を集めることが出来なくなっているのだ。現在、たとえ質の高いコンテンツであっても、注目を集めるためには助けが必要な状態なのだ - しかも、ちょっとやそっとの助けではどうにもならないケースもある。
ウェブのリンクグラフは大きく2つのタイプに分類される: 自然なリンクグラフと商業的なリンクグラフだ。この2つは結びつき、持ちつ持たれつの関係であり、なかなか見分けがつかないが、意図に関しては正反対である。
リンクの歴史
ブログが登場し、広がるにつれ、ウェブでのリンクの供給量が急激に上昇した時期があった。しかし、ブログとリンクと共にnofollowが台頭し、ウェブのリンクグラフは崩壊した。その後、ソーシャルメディアが浮上すると(特にここ2年間)、リンク構築のコンセプトはさらに進化していった。URLの短縮サービス、ツイッターおよびフェイスブックのようなサイトがさらに必要以上に展開を早めていく。オリジナルのコンテンツを持つパブリッシャーは、懸命に努力しても手に入れることが出来るリンクの本数は減る一方である。リンクに飢え、リンクが飽和した状態が続いているのだ(ソーシャルサイトにおいて)。
インターネットの離れ小島に隔離されてしまうコンテンツのタイプや量を説明するのは不可能である。誰も訪れないし、誰にもその存在を知られていない。そして、誰も気にも留めてくれないのだ。
2001年、「それを作れば、彼らは来る」と言う格言があったが、2010年、この格言は「それを作っても、構ってもらえない可能性がある」に変わった。価値の高い、ユニークでしかも注目に値するアイテムであっても、魔法のようにリンクを獲得することが出来るわけではない。スポットライトを浴びるには、世話係、賛同者、プロモーター、プラットフォーム、もしくは財源が必要なのだ。時には、ゆっくりと自然に広げていくために、熟成させる必要もある。コンテンツのタイプによって異なる戦略が必要になるのだ。
このウェブ新時代に対して、私は以下の5つの理論をリンク構築の概念化のフレームワークとして提唱する:
1. 良質なコンテンツであってもリンクは保証されない。 質の高いコンテンツが必ずしもリンクを魅了するわけではない。以上。それを作っても、無視することが出来ないように巧みに、画期的な方法で提供することが出来なければ、誰も気にも留めないだろう。
2. リンクは必ずしも価値に結びつくわけではない。 ページもしくはサイト全体のリンクの量は、質、信頼性、もしくはオーソリティを示唆するものではない。多くのリンクを持つサイトやリソースは高いランキングを獲得する可能性はあるが、必ずしも質が高いわけではない。有料リンクがオンラインのコンテンツの質を悪化させ、質の低いコンテンツをオーガニックな検索で上位に押し出すようになったからだ。
劣悪なコンテンツであっても高いランクを獲得し、大量のリンクを手に入れられる可能性がある、と言い換えることも出来る。
3. リンクが金銭を反映することがよくある。 実際に金銭的なインセンティブが内在するため、リンクが金銭を反映して然るべきである。事実、お金に換算されていることが多い。これは倫理観を映し出すものではなく(判断は皆さんに任せよう)、あくまでも実利主義、そして、オープンな商業マーケットを考慮した理論である。
4. 姿を消す実力主義。 ウェブサイトのオーナー達が、自由に、そして、無邪気にサイトの能力をベースにリンクを交換する関係はその姿を消しつつある。これは、ツイッターのようなソーシャルメディアのサイトが台頭してきたことも理由の一つである。ソーシャルメディアはブログのパブリッシャーを中抜きしているのだ(ソーシャルに共有するだけなら、ブログは必要ない)。また、悪気はないものの、ウェブサイトのオーナー達が持つ検討違いのnofollowへの不信感も理由の一つだ。これに加えて、リンクの価値における意識が全体的に上がったことも理由に挙げられるだろう。売ることが出来るのに、無料で与えるのは勿体ないと言う考え方が根付きつつあるのだ。
5. リンクが商品化されつつある。 有料リンクは、量産された詐欺的なコンテンツと共にウェブの全体的な質を落とした張本人である(その最近の代表格がディマンド・メディア)。そして、ブログが広がったこともこの傾向を加速させた原因の一つだと個人的には思っている。ノイズが増え、シグナルを圧倒し、急流での競争上の利点を得る戦いが激化した。ここで前に進むために利用する出来ることはすべて利用する土台が築かれたのだ。有料リンクは多くのサイトにとって救命胴衣の役目を担っており、事実、多くのサイトは有料リンクがなければ溺れてしまうだろう。
オーガニックなリンクの競争における利点
自然に、そして、知的にリンク構築する取り組みは、長期間におよぶプロセスである。しかし、これでは“大至急欲しい”と言うウェブ(および一般的な社会)の概念とは相いれない。これは多くのサイトが誤って大規模な有料リンク戦略を採用してしまう理由の一つだと私は思う。有料リンクでの行動は必ずしも均等ではなく、多くの場合、広範囲に悪影響が出てしまう。条件は公平ではない。オフラインの世界のように、ブランドが大きければ大きいほど、リスクを乗り越える能力も高まるのだ。
だからと言って、今年はリンクを構築することが出来ないと言っているのではない。むしろその反対だ。事実、私たちは過去数年よりもリンク構築で大きな成功を収めている。かつてないほど選択肢が豊富に用意されているのだ。見る場所さえ分かれば、ウェブは潜在的なリンクの供給源で満ち溢れていると言えるだろう。
このような状況で、オーガニックなリンクは競争における確かな利点になった。類まれな洗練された検索エンジンとなったグーグルは、皆さんのリンクプロフィールを熟知している。グーグルは皆さんが抱えているリンクをすべて把握し、皆さんが下した決定の記録も持っている。リンク戦略を策定する際は、この事実を肝に銘じておこう。
クライアントとリンク構築に関して話し合うとき、私たちは考慮するべき3つの主要な原則を紹介するようにしている:
結果を把握する。 ウェブサイトが取るすべての行為が何かしらの結果が生む。
リスクの許容度を計測する。 有料リンクを購入すると危険度は上がる。リスクの許容範囲を把握し、検索エンジンの利益に明らかに反する行為を行うことで得られる見返りを計算しよう。
長期的な視点で見る。 リンクプロフィールは現在に至るまでの選択の記録である。
2001年は良質なリソースを構築することが最も重要であった。2010年は、良質なリソースを作り、影響力を及ぼし、そして、知的に良質なコンテンツを徹底して売り込む取り組みが必要になる。
この記事の中で述べられている意見はゲストライターの意見であり、必ずしもサーチ・エンジン・ランドを代表しているわけではない。
この記事は、Search Engine Landに掲載された「5 New Paradigms For Link Building Success」を翻訳した内容です。
This article on Columns: Industrial Strength first appeared on Search Engine Land.
c Copyright Third Door Media, Inc. Republished with Permission.
5大手法ではなく、5大理論なだけに現状の状況説明といった内容でした。流石サーチエンジンランド、内容はどれも納得できますね。しかしこれを読むと米国でも有料リンクは日常化しており、リンク獲得の手法や努力もコンテンツの品質を超えた部分で過度に行われていることがうかがえますね。以前、商用サイトが堂々と行っていたり、有料の複数ディレクトリ登録サービスが人気を集めていたり(&もちろんリンク販売のみを行っているSEO業者が幅を利かせていたり・・・)と日本の有料リンクの現状の方が海外よりひどいかも、というコメントを書きましたが、実際の所はこの記事を読んだり、また少し調べていくと米国も似たような状況ではあるようですね。
リンク中心の検索アルゴリズムが主要な以上、仕方ないといえば仕方ないのですが、、、ソーシャルウェブやリアルタイムメディアの普及で検索アルゴリズムも新たな進化が問われる今後の数年かとは思いますが、ソーシャル・リアルタイム共にリンクを評価概念にある程度取り入れることは必要と思われますし、どのように検索エンジンが進化し、そしてSEO業界が対応していくのか注目していきたいです。 — SEO Japan
SONY α「Focus Your Love」
SONYの一眼レフカメラαのスペシャルサイト「Focus Your Love」。浅野忠信・北川景子がαと共に旅をする。iPadのおかげでまたカメラが面白くなっ...
Re: E-Book製作環境としてのCMS+IA:問題の設定
6/22に開催されるEB2研究講座に向けた「E-Book製作環境としてのCMS+IA:問題の設定」への返信です。
鎌田様
今回はよろしくお願いいたします。
意味や価値を読むとは?
まず、デジタル以前の成功体験を踏まえた上で議論を積み重ねるため、出版社がこれまでコンテンツ・コンテクスト・読者からどのような意味を読み取り、創造性と品質を高め、読者とのコミュニケーションをレベルアップしてきたのか、について具体的に知りたいと思っています。
Webに関しては、整理するためにダイアグラムをより具体化してみました。
図:コンテンツとユーザーのコンテクストを解析する: ユーザーのコンテクストがUX コンテンツのコンテクストがIA ...
米モバイルでソーシャルネットワークアプリ利用者が1年で3.4倍に
2009年のヨーロッパのインターネット広告、年4.5%成長に留まる
2010/6/2のIAB Europeのリリースから。 http://www.iabeurope.eu/news/europe2007年は対前年比4割増、2008年は同2割増だったが、2009年は4.5%にとどまった。フォーマット別では、検索連動型広告の割合が45.8%で、ディスプレイ広告が30.9%となった。検索連動型広告の伸びは二桁増となっている。 下図で全体の伸びが4.9%となっているが、リリース本文では全体の伸びは4.5%と書いてあって整合性がないようだ。関連リンク:2010年米インターネット広告費、10.8%増に(eMarketer)米2010Q1インターネット広告は59億ドルで、対前年同期比7.5%増(IAB)米2009年インターネット広告は227億ドルで、対前年比3.4%減英インターネット広告費、9年間で23倍に2009年モバイル広告は前年比112.9%(電通)
新着記事
編集部からのおしらせ
新人Web担当者必読『Webサイト改善の指南書 ―生成AIと100のTipsで売上・集客を最大化!』を3名様にプレゼント 1月23日 10:00 行動データからみる深層インサイト分析/人が“つい”反応してしまう行動経済学【2/4水 無料セミナー】 1月23日 7:05 生成AIで成果を出す! デジタルマーケターのための実践活用術 1月22日 7:05 顧客心理を読み解くヒートマップ分析とMEOで実現する店舗集客とは/生活者・AI双方のニーズに応えるオウンドメディア戦略など【Web担当者向け講演】 1月22日 7:05 生成AI×GA4×ClarityでWebサイト時短PDCA改善術/画面をAIに投げる簡単分析術【データ分析講演2つ】 1月21日 7:05
すべて見る