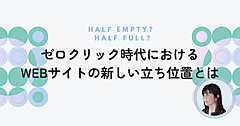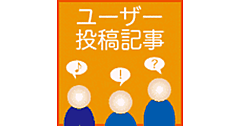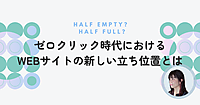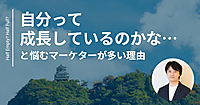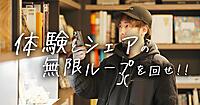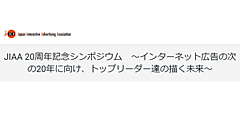テクノロジーが切り拓く新たなユーザー体験
マーケターコラム、今回は村石怜菜氏。ユーザーのタイパ重視傾向に合わせ、テクノロジーによる新たなユーザー体験を探ります。
2024年4月2日 7:00

みなさん、こんにちは。村石怜菜です。突然ですが、あなたは最近どこで洋服を買いましたか?
「最近どこで洋服を買った?」からはじめるユーザーリサーチ
「最近どこで洋服を買いましたか?」は、私がよく尋ねる質問の1つです。親しい友人や家族だけでなく、同僚や初対面の人にも投げかけます。この質問の目的は、相手の消費行動や趣味を理解したいからです。同時に、リアル店舗を選ぶのか、ECサイトを選ぶのかの基準や理由を確認したいからです。
では、なぜ洋服なのでしょうか? 洋服に焦点を当てる理由は、アパレルのEC化率が年々上昇傾向にある一方で、出勤や通学、休日といった外出着などの衣料品は、物理的な商品を見て購入したいという需要が依然として存在します。
ECで購入しやすい無形商材や消費財よりも、衣料品や家電製品などの耐久財をどこで買うかを尋ねたほうが、ECサイトでの購入に伴う心理的障壁の変化に気づきやすいです。
洋服は購入先によって、その人の消費行動や好みが鮮明に現れます。たとえば、ユニクロで毎回同じ型の商品しか買わないという人もいれば、ZOZOTOWNや他のECモール、ブランドのECサイトでのショッピングを好む人もいます。
さらに、環境問題や衣類の過剰生産に興味を持つ人は、メルカリやセカンドハンドショップでの買い物を好むこともあります。ECサイトで買わない場合には、リアル店舗で購入するのか、その場合はどこの店を選ぶのかなども質問します。
商業施設は減少傾向「わざわざ行く場所」
私は2011年から7〜8年間ほど、ショッピングセンターや百貨店などの商業施設において、ITやデジタルマーケティングの戦略策定・支援に携わってきました。2011年頃は、商業施設の閉店が決まると、それが大きなニュースとして取り上げられており、この業界が社会に与えるインパクトの大きさを感じていました。
しかし、最近ではこのようなニュースがあまり大きく報じられず、閉店時の様子などが取り上げられるだけで、残念ながらそれが日常の一部になってきたように感じます。『SC白書2023~新たな時代に向けて歩み出すSC~』(一般社団法人日本ショッピングセンター協会発行)によると、ショッピングセンターの総数は2018年から4年連続で減少しているようです。
「最近どこで洋服を買いましたか?」という質問を20代に尋ねてわかったのですが、商業施設に行くこと自体が「わざわざ行くイベント」となっている傾向が高いようです。「特別な理由がない限り、休日に混んでいる場所まで行くのは面倒くさい」というわけです。タイムパフォーマンス(タイパ・タムパ)が悪いといったイメージが強いのでしょう。
マーケターの皆さんは、開業したばかりの施設を視察することは頻繁にあると思います。業界や職種が異なると、顧客が同じ首都圏に住んでいたとしても興味関心がまったく異なることを実感されているのではないでしょうか。
テクノロジーが切り開く新しいリアル店舗体験
先日、私は渋谷PARCOの屋上で催された「冬の渋谷の夜空を彩るAR花火イベント ~ MIRAI HANABI in SHIBUYA PARCO~」というAR(Augmented Reality:拡張現実)イベントに参加しました。

スマートフォンアプリ「STYLY(スタイリー)」をインストールし、イベント会場内のQRコードを読み込むと、渋谷PARCOの上空に花火が打ち上げられ、照明や音楽の演出により臨場感あふれる体験ができました。


このイベントの特徴は、「花火の打ち上げが難しい都市部の市街地で、AR技術を駆使してこれまでにない花火イベントの体験を提供できる」という点です。「MIRAI HANABI」を体験する前に、このプロジェクトに関わった方々のトークイベントが開催されたのですが、その中で印象的だったのは、「LBX(Location Based Experience:その場所に行かないと体験できない価値)」という言葉とコンセプトでした。
従来、商業施設は、花火大会のための「浴衣を買いに行く場所」でしたが、今回のAR花火大会では「花火大会を見に行くために訪れる場所」となっています。渋谷PARCOという場所をベースとした、そこに足を運ばないと体験できないエクスペリエンスを、テクノロジーを活用して創り出すというアプローチがとられています。
商業施設のコンテンツとしては、期間限定のコンセプトカフェや催事が一般的でしたが、今後はこのようなテクノロジーを活用し、商業施設という場所や体験を拡張したユーザー体験の創出が増えていく可能性を感じました。
「Apple Vision Pro」の登場で身近になったMR
ところで、ヘッドセット型の空間コンピューティングデバイスを使用したことはありますか? 以前、私はVR(Virtual Reality:仮想現実)ヘッドセットをレンタルして試したことがあります。没入感には非常に感動しましたが、体質に合わなかったのか、頭痛や吐き気で休日が潰れるといった経験をしたため、以降は敬遠してきました。
この苦い経験から、ヘッドセット型のデバイスを十把一絡げに捉え、MR(複合現実)についての情報も積極的にキャッチアップしようとしていませんでした。映画の中で表現されている「MR」の世界しかイメージできず、現実社会においてどのような影響をもたらすのかには理解が及ばなかったことも、積極的になれなかった理由です。
しかし、「Apple Vision Pro」のプロモーション動画を見て興味がわきました。動画を見ることで「これが近い将来実現する世界なのか」と明確にイメージできたからです(残念ながら、実際に「Apple Vision Pro」を体験できてはいませんが…)。
販売後のレビューでは、「ギーク向けの商品だ」「高すぎる」「対応アプリが少ない」といった否定的な意見も見られましたし、現実世界で街中を歩きながら使用するのはまだ難しいようです。ただ、「Apple Vision Pro」の登場により、MRという言葉が身近に感じられるようになったことは事実ではないでしょうか。
リアル店舗でのxRの活用
話を商業施設に戻します。では、商業施設といったリアル店舗では、VRやAR、MRといったxR(クロスリアリティ)は、ユーザー体験にどう組み込まれていくのでしょうか?
たとえば、VRに焦点を当てると、VRコマースが今後も成長するとされつつも、商業施設での具体的な利用にはいくつかの課題が存在します。VRによる仮想の商業施設では、2次元の画面上に存在する世界が臨場感に欠け、購買意欲を高めたり、ブランドへの帰属意識を醸成したりするのが難しいとの感想があります。また、商品情報の不足やデータ化の必要性などもハードルとなっています。
一方で、ARやMRといった技術は、現実世界のイベントや環境に対してリッチでインタラクティブなデジタル要素を組み込み、ユーザーに新しい体験を提供できます。前述の渋谷PARCOの事例だけでなく、商業施設のAR活用事例は多く見つかります。現在は、集客施設としてのイベントという立ち位置が主ですが、スマートグラスなどデバイスの小型化や通信環境の進化により、将来的にはxRによる複合的なアプローチが、一時的な集客だけでなく、継続的なコミュニケーションや購買体験の価値向上など、リアル店舗のユーザー体験を向上させるために活用されるでしょう。
デパート探訪してみませんか?
「わざわざショッピングセンターに行くなんて」というタイパ・タムパ優先勢の気持ちを理解しつつも、リアル店舗を楽しむ方法がもっと拡がって欲しいなと思っています。私は最近ポッドキャストを聞かない日はないくらい聞いているのですが、その中でも好きな番組は、ニッポン放送のラジオ番組「星野源のオールナイトニッポン」です。その番組で放送作家をされている寺坂直毅さんという方がいらっしゃるのですが、生粋のデパート好きとして知られています。
寺坂さんは幼少時からデパートが好きで、これまでにおそらく200以上のデパートを訪れたとのこと(ラジオコーナー説明の情報より)。百貨店愛が高じて、百貨店に関する書籍や記事を執筆されたりもしているようです。同番組内では「寺坂直毅のデパートに愛を誓って!」というコーナーを担当されており、各都道府県の百貨店について熱く語り、そのデパートでの楽しみ方を紹介しています。
寺坂さんのコーナーでは、まるで旅行のガイドブックのように各地の百貨店を取り上げ、その地域ならではの楽しみや特徴をとても魅力的に紹介しています。リスナーにとっては、まるで旅行気分で百貨店めぐりが楽しめるコーナーとなっています。私も同行者が許せば、国内外問わずその地域の百貨店や商業施設を訪れますが、ショッピングセンターよりも百貨店の方が特色が強い気がします。
国内の百貨店でも、フロアの構成が異なり、デパ地下には地域独自の店舗や生鮮食品が並んでいるため、訪れるたびに新しい発見があります。ぜひ、旅行に行かれる際は、地元の百貨店に足を運んでみてください。



ユーザーとの共感を生む、五感に訴えるエクスペリエンス
私は仕事柄、全国の商業施設をいろいろと訪れた経験があります。特色がある商業施設がある一方で、首都圏、地方に関わらず、特にターミナル駅周辺のショッピングセンターはどこも同じようなテナント構成で、味気なさを感じます。コロナ禍を経てリアルへ回帰した今、再びリアル店舗の存在価値を考え直す時期がきていると思います。
先日、家族で外食中に百貨店の話題が出て、「小さい頃は〇〇デパートによく行って、あそこのラズベリーのジェラートが美味しかったよね」「私、今でもジェラートはラズベリーを頼む」と母や妹と思い出話に花が咲きました。帰り道には恋しくなって思い出のラズベリー味のジェラートを食べました。この幼少期の五感と結びつけられた記憶は、リアル店舗ならではの体験ではないでしょうか。
「商業施設=物を売る場所」という固定概念から考えると、「物を売ろう」という意識が強くなってしまいがちですが、「商業施設の来店者=消費者」ではなく、「その施設を楽しみに訪れたゲストまたはユーザー」というような感覚に切り替えることが大事なのではないかと思います。
昨今、オンライン・オフラインだけでなく、商業施設とエンターテイメント施設の境界線は曖昧になってきていると感じています。私の幼少期の思い出のように五感に強く結びついた記憶が、今度はテクノロジーを活用して、リアルとデジタルが融合する新たな体験価値として創出されることを期待しています。