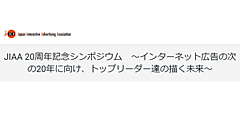技術が発展し、AIを用いたマーケティングなど新しいマーケティング手法が次々と出てくるなか、脳科学をマーケティングに応用している会社があると聞き、さっそく担当の方にお話をお聞きしに行った。
会社の名前はNeU(ニュー)。日立ハイテクノロジーズ(以下、日立)と東北大学が立ち上げた脳科学カンパニーだ。脳科学がどのようにマーケティングに活かされているのか、さまざまな事例をNeUの岡田拓也氏に聞いた。

手のひらサイズのデバイス開発で日常の脳計測を実現
――任天堂DSの脳トレで有名な川島隆太教授が御社のCTOになられていますね。
岡田氏: はい。弊社は東北大学加齢医学研究所川島研究室の「認知脳科学知見」と日立ハイテクノロジーズの「携帯型脳計測技術」を融合して誕生した脳科学ベンチャーです。
元々、川島教授の開発した脳トレを日立の脳計測技術を用いて検証するなど、両者には10年近くの関係性がありました。近年の法改正で国立大学が自らVCを設立し、研究成果に基づく優れた技術を活用した新産業を創出することが可能となったので、2017年8月に弊社が誕生しました。
弊社のミッションは、「脳科学でQuality of Lifeの向上に貢献する」ことです。元来は医療の用途が中心だった脳血流計測器(NIRS)を小型化して産業応用することを進めています。そして、脳科学の知見を活用し、ニューロマーケティングはもちろん、ヘルスケアなどのソリューションを提供しています。
――脳科学とヘルスケアはすぐにつながりそうですが、なぜマーケティング事業につながったのでしょう?
岡田氏: 実は、弊社のニューロマーケティングのコンサルティングサービスは、日立製作所で生まれたブレインサイエンスビジネスユニットが前身です。脳科学の産業応用をテーマとして計測機器の小型化を進め、日常生活の中での一般ユーザーの脳計測を実現したことで、さまざまなソリューションを提供できるようになりました。
最新のデバイスである超小型脳計測装置「XB-01」は、重さわずか30g。大きさ80×40×13mmです。体重や血圧を測るような感覚で身近に脳を測ることができる世界の実現を目指しています。

岡田氏: こういった超小型脳計測器デバイスをはじめ、主に研究用途で用いられる多チャンネル型機器までさまざまなハードウェアを使って、ヒトの本音や潜在意識を明らかにし、マーケティングに役立てる活動を行っています。
たとえば、乗り心地・触り心地や味の満足といった感性評価、脳科学の知見を活かした商品開発の支援と商品企画、広告・宣伝領域での評価や改善などのコンサルティングを提供しています。
世界トップクラスの光を使った脳計測技術
――小型化した計測機器が御社の特徴の1つなのですね。
岡田氏: それと、脳の計測方法として、光を用いた方法(NIRS方式)を採用している点も弊社の特徴です。脳波という言葉はよく耳にすると思いますが、これは脳の電気信号を計測しているものです。弊社のハードウェアは、近赤外光による脳の血流量変化を計測しています。
この近赤外光は人体組織を透過する特性を持っていますが、血液内に存在するヘモグロビンに遮られてしまうという特性があります。
脳の活動にはグルコース(糖)と酸素が必要なのですが、脳はそれらを貯蔵する機能がないため、脳活動が盛んになるとそれだけエネルギー源が必要となり、血流で運ばれていきます。
つまり、脳活動が活発になると、その特定部位部分の血流が増えるわけです。この脳血流量の変化を近赤外光で計測し、脳活動として評価しています。
世界的には、脳を測る際には脳波の研究を扱う場合が多いのですが、光で脳を測るNIRS方式は技術は日本発の技術ということもあって、日立グループを筆頭に日本のメーカーが含めた数社がトップ技術をもっています。世界をリードしており、我々もそれを1つの強みとしています。

――なぜ脳波ではなく、光による脳血流の測定を採用しているのでしょう?
岡田氏: 脳波は電気信号ですから、ヒトの筋肉から生じる電気信号や外部環境での電子機器が計測ノイズとなります。実験室の環境ではともかく、日常生活の中での計測は未だ大きな制約があるというのが現状です。
一方、近赤外光を用いた我々の脳血流計測光法は電気的影響を受けないため、ノイズの影響が少ないという特徴があり、日常空間での計測に適しているという利点があります。
もちろん、脳波からも非常に得られるものは多いです。そのため、計測する内容によっての使い分けや、同時計測可能な機器の開発などにも取り組んでいます。
生体情報を測定し、商品開発や広告・宣伝に活かす
――御社のニューロマーケティング事業について教えてください。
岡田氏: 脳活動を中心として、ヒトが生きていくなかで発するいろいろなシグナル=信号情報を測定し、商品開発や広告・宣伝に役立てています。
脳以外の生体信号。たとえばアイトラッキングはもちろん、心拍、表情、皮膚電位なども活用しています。弊社は脳科学ベンチャーですから、脳計測をもっとも重要なコア技術として、さらに目的に応じたさまざまな生体指標を組み合わせて使っていくという形をとっています。
――こうした指標が教えてくれることは何でしょう?
岡田氏: たとえば、あいまいなもの、感覚的なものは、従来の主観評価では判断が難しいところがあります。「涼しげな」といっても、人によって若干イメージが異なるのではないでしょうか。
車の乗り心地を問われても、AさんとBさんの「良い」というニュアンスの客観的比較はなかなか困難です。また、CMを主観インタビューなどで評価しても、ついつい終わり際のシーンの印象が回答に強く影響します。
脳の反応はその瞬間、瞬間をあらわすものですから、シーンごとのバイアスのない評価が可能になるわけです。
それに、消費者は言葉と行動があまり一致しないというか、本音と建前が常に存在しています。そのため、偽ることが不可能な脳の活動は、消費者の反応をダイレクトに知る大きな手がかりになります。実際に言葉での表現が難しいような感覚的な違い、感性の客観化、定量化を行っています。
感性評価、商品企画でメーカーのモノづくりを支援
――これから実際に提供なさっているソリューションをお聞きしたいと思います。先ほど、ニューロマーケティング事業で提供しているものに車両の乗り心地とか、味の満足といった感性評価があるとお話されていましたね。
岡田氏: そうですね。感性評価に関しては、鉄道や車などの乗り心地や触り心地、車両デザインや空間デザインなど言葉では表しにくいものを定量評価するために、脳を計測しています。他にも作業時の眠気や疲労、集中度合いなど、計測する内容は多岐にわたっています。
――商品企画では、どのような商品に関わられたのでしょう?
岡田氏: たとえばバンダイ様の乳幼児向け玩具「ベビラボ・ブロックラボシリーズ」は、実際に赤ちゃんの脳を計測して誕生した製品ブランドです。発売から数年で年間売り上げが数十億円を突破した人気商品です。
赤ちゃんは、生まれてからの成長過程で脳神経細胞も急激に増加します。特にヒトを認知するという点でも、大きく進化します。たとえば、生まれて半年くらいで、顔の表情変化などを認知するようになります。いないいないばあは、赤ちゃんがその表情変化を学習する一例です。
「アンパンマンのいないばあ」と「見知らぬ人のいないいないばあ」を比較したところ、脳活動計測により「アンパンマンのいないばあ」により注目すること、そしてアンパンマンに注目したときの脳血流変化が強いことがわかりました。この脳科学検証は一例ですが、多々の脳科学検証をもとに、ベビラボ・ブロックラボシリーズが開発されてきています。

――シニア向けの商品もありますね。
岡田氏: 「モトタイル」(セノー)は、「点灯したタイルを踏む」というシンプルだけれど楽しみながら運動ができる商品です。実際に脳を計測すると、きちんとタイルを踏めた人の脳は活動していることがわかります。そして、トレーニングした前と後では、どこに何があるかを覚える分野で成果があがっています。弊社では、こうした認知機能の向上についての検証を行い、商品化へのサポートを行いました。

広告・宣伝系では脳科学に基づいて改善を提案
――広告系では、脳科学をどのように使われていますか?
岡田氏: メーカーさんや広告代理店さんと一緒に打ち合わせをし、必要に応じて計測も行いながら、脳科学に基づく改善のコンサルティングを行っています。たとえば、次のようなチラシの改善提案をさせていただきました。

これはお客様側でご用意いただいたクリエイティブ案をベースに脳科学的な視点を踏まえて改善提案を行いました。
具体的には、視線の誘導やシズルカットの配置などへのアドバイスです。最終的にいくつかのクリエイティブ案を脳活動で評価し、もっとも反応の高かったものを実際のチラシに反映していただきました。改善のプロセスを検討する上では、アイトラッキングも活用しています。
――視線と脳活動を一緒に計測する場合も多いのですね。
岡田氏: そういったシーンは増えてきています。たとえば、同じだけ物を見ていても、覚えているものと覚えていないものがありますよね。その違いは脳活動にあらわれていて、脳活動が高いもののほうが、後日思い出せる率が高くなり、記憶に残りやすいということが先行研究により明らかになっています。
このことは、弊社が実施した新聞15段広告調査などでも同様の結果が得られており、視線と脳活動をセットにした計測から、視線占有率と、その際の脳活動の高さが後日再認率と関係があることを確認しています。
――視線と脳活動の計測は、Webの改善でも使えそうですね。
岡田氏: そうですね。たとえばユーザビリティ評価では、脳活動が低い方がより使いやすいということがあります。脳は前頭前野で情報処理を行いますから、ユーザビリティという視点では前頭前野が活性化しない方が直感的に使えるというわけです。
そこで、先行研究としてエレベーターの「閉じる」ボタンと「開く」ボタンについて実験を行ってみました。脳科学的知見を取り入れたデザイン案を含め、次のようなボタンアイコンを評価した際、主観評価で「どれが押しやすいですか?」と問うと、多くの人が見慣れている一番左を選びました。

しかし、各ボタン300回ずつの試行でどのくらいエラーが出るのか、そのときの脳活動はどうかを測定したところ、主観評価で一位だった定番のアイコンが22回のエラーに対し、顔のイラストが隠れるアイコンの方はエラーが0という結果になりました。このボタンは、ヒトは人間の顔に注目しやすいという顔認知特性をデザインに利用したものです。
また、脳計測の結果でも、顔ボタンの方は前頭前野の脳活動の山が低く、認知負荷がより低い=直感的に使いやすいことがわかります。こうした先行知見をもとに、スマートフォンのユーザビリティなどを検証するサービスも提供しています。
購買行動も脳科学で計測
――脳科学的知見と計測による裏付けを進めているのですね。
岡田氏: 店頭によくあるPOPについても、北陸先端科学技術大学院大学と共同で購買行動への影響を測った実験を行っています。まずは、POPを脳活動で評価し、脳活動が高いPOPと低いPOPを確認しました。次に実際店舗で、それらPOPの有無により売り上げがどれだけ変わるかを測ってみました。
実験では、非計画購買(店頭で選択肢の決定を行う)アイテムである「おにぎり」を対象にしました。結果、脳活動の低いPOPは販売個数にほぼ影響がないのに対して、脳活動が高いPOPはその有無によって販売個数に約2倍もの差が見られました。これは脳活動が高いPOPは購買行動に影響を与えるということを検証した事例と言えると思います。この知見をベースに店頭評価などを実施しています。
――ECでも同じように考えることができるでしょうか?
岡田氏: LPのパッと見のイメージが、脳活動を活性化するかしないかで、購買への影響は出そうですね。脳活動が高いトップページのファーストビューの方が記憶や興味関心に影響し、コンバージョンに影響しているように思います。
A/Bテストは、厳密に要素分解すればするほど、変動要素が無数にありますよね。先ほどのピザのチラシ例のように、シズルカットなども評価が脳計測で行えますから、A/Bテストと一緒に脳の評価も行ってみるとおもしろい結果が得られるかもしれませんね。
――そうすると、海外の人がわかりやすいピクトグラムにも脳計測を利用できますよね。
岡田氏: 脳の構造は世界共通ですから、もちろん利用できます。我々のところには、防災関連での案内表示のわかりやすさ、ピクトグラムがどれくらい人に伝わっているのかというような相談が来ることもあります。
マルチモーダルでより精度を上げていく!
――いま取り組まれていることは何でしょうか?
岡田氏: 視線計測ができるVRのヘッドマウントディスプレイ(FOVE 0)に、我々の脳計測センサーを組み込むことで、脳血流、心拍、視線、まばたきや瞳孔などを同時に取得可能なデバイスを開発しました。

好きなものを見ると瞳孔が開く、集中時には瞬きが減るなど、目からもさまざまな情報が獲得できます。これらと脳活動を組み合わせることで、より確度の高い情報が得られると考えています。
それこそ、VR空間でネットサーフィンしていただきでき、本デバイスで商品の発見から購入完了までを計測すれば、その人がどういうところで購買の意思決定をしたかがすべて明らかになるかもしれません。複数の生体指標を組み合わせることをマルチモーダル化と言いますが、これによって脳科学調査の精度をよりあげていこうというのが今後の目標です。
VRで一例を挙げると、たとえば、自動車の内装デザインの評価をしている例です。右が脳活動および心拍。左下が目の動きですね。これを解析すると、車内のどこに注目し、興味関心を持ったかなどが可視化できます。
脳血流と脳波を組み合わせての計測ソリューションも開発していますし、こうしたマルチモーダル化によって、日常的なシチュエーションでの生体情報を数多く取得し、より正確なヒトの心の動きを把握することを目指しています。
クラウド化が次のフェーズ
岡田氏: マルチモーダル化とともに進めているのがクラウド化です。計測器が小さくなり、日常の中で手軽に計測できるようになりましたので、一般ユーザーに宅配便で送り、指定したタスクのデータをご自身のスマホで計測してとっていただく、ということが実現可能になってきています。
脳科学の分野では、1クラスタ20人程度の計測がスタンダードですが、このクラウド化によって数千人、数万人のデータを集めると、世界中のどこも実現していないようなビッグデータになります。
これと、売り上げや閲覧履歴など世の中にある既存のデータと組み合わせることで、さまざまな発見やブレイクスルーが生まれると考えています。実際に、店舗などに設置したキオスク型の脳セルフチェック端末から、すでに1か月数千人単位で脳活動データの取得をはじめています。クラウド化による脳ビッグデータ収集と活用が、次のフェーズのテーマですね。
――興味深いお話をありがとうございました!
自分自身の脳や五感を客観視してその働きを知る機会はそうそうないこと。お聞きしながら私の脳もフル回転。活性化した時間でした。