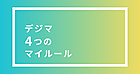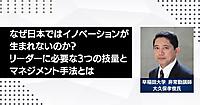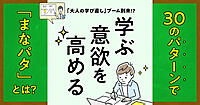日本経済新聞社(以下、日経)では、マーケティング人財育成プログラムを内製し、2022年から実施している。日本のビジネスシーンをリードする日経は、どのようなプログラムを実施しているのか。背景や目的、プログラムの内容について、日本経済新聞社 プラットフォーム推進室の小林秀次氏と福澤由華氏に聞いた。
マーケティング人財育成プログラムの実施背景
日経には、新聞メディア事業以外に、データベースサービス、書籍・出版、教育・研修、イベント、デジタル情報・サービスなど、多様な事業があり、新聞メディアとしての強いブランド力がある。これまでは、「新聞を購読することは社会人の常識」という風潮があり、そうしたブランド力をベースにして他の事業も進めてきた。
しかし、スマホが普及し、ビジネスに関する情報取得チャネルが多様化する中、この先もずっと選ばれ続けることの不透明感が増している。顧客は誰なのか、顧客にどんな価値を提供するべきなのかを考えること、すなわちマーケティングに本腰を入れて取り組む必要が出てきたのだ。そこで、全社的なプラットフォームを整備することをミッションとするプラットフォーム推進室のマーケティング&グロースGが中心となり、2022年からマーケティング人材育成プログラムを実施している。
そもそも、顧客視点や顧客理解を前提とすべきという考え方が定着していなかった。それを大事にしようというメッセージを強く打ち出したのが、この取り組みの大きな特長(小林氏)

マーケティング&グロースG
部長
小林秀次氏
マーケティングとは、『価値の創造、市場の創造』
ナレッジを社内で横展開するためには、ナレッジを構成する概念を共通言語化しておく必要がある。特に、「マーケティング」という用語は対照する範囲が広く、人によって定義が異なる。考え方を統一してからでないと、そもそも会話が成り立たない。
日経の中でのマーケティングでは何を大事にするのか、マーケターの必要要件は何なのか、という定義から決めた。定義が決まっていないと、どこを目指していいかが決まらない(小林氏)
カリキュラムを制作するにあたり、日経における「マーケティング」の定義を『価値の創造、市場の創造』とし、「顧客に対する価値の創造と便益の最大化により、事業の売上、利益を最大化させる」ことができるようになるためのプログラムを作った。
プログラムは3年間で100名に受講してもらう計画で始まった。収益に関わる部門を中心に各部署から毎年1~2名を選出。2年目となる2023年からは一部のグループ会社からも参加者を募っている。3年目の今年は、若手約40名が参加して5~9月に実施される。100人いれば、1つの事業に複数人の受講経験者がいることになる。
一人だと、学んだことを周りに説明しても理解してもらえなくて孤独になりがち。共通言語で話せる人が一緒にいると、そこを基点にして考え方を広めていくこともできると考えた(福澤氏)

部次長
福澤由華氏
今年のプログラムは基礎編と実践編の2階建て
3年目となる今年は、1・2年目の経験から、より実践に即した内容にプログラムをブラッシュアップした。ベースとなる思考法の講座は全員に受講してもらい、その上にスキル(自分の業務に必要な講座を選択して受講)の部分が乗る、2階建ての構造とした。
一番大事なのは思考法。顧客理解の重要性を理解することが何よりも大事なので、すべての講座に貫かれている(福澤氏)
思考法の部分である基礎編では、以下のような内容を学ぶ。
- 【目的志向】常に目的に立ち返って思考する習慣
- 【顧客理解】お客様を深く知り、お客様の本質的な課題に寄り添う姿勢
- 【データリテラシー】ファクトに基づき思考する力、ファクトを集める力、分析する力
- 【共通言語】議論や意思決定のスピードを速め、精度を高める
その上に乗る実践編では、以下のような講座が用意されている。
- 【戦略】顧客理解に基づき、サービスや施策の設計を行うスキル
- 【戦術】目的志向でマーケティング施策をプランニングするスキル
- 【実践・検証】戦略、戦術設計に則り実践し、適切に分析、検証を行うスキル
プログラムの実施フローは、以下のとおり。
- Step1:アセスメントを受講(講座受講前)
- Step2:基礎編講座を受講
- Step3:実践編講座を受講
- Step4:講座修了ワーク
- Step5:アセスメントを受講(講座受講後)
アセスメントは120問程度のオンラインテストで、独自に作成したものだ。受講者には、受講前後で同じテストを受けてもらう。これにより、自身のスキルに欠けている分野を事前に把握したうえで講義に臨めるし、自分がどのくらいレベルアップしたか実感できる。
受講者を送り出してくれた所属部門長には、全プログラム終了後に、メンバーのアセスメント結果2回分を、事後のアンケートや講座修了ワークの結果とともに共有する。アセスメント結果の伸びを示すことで、講座参加の意義や効果を端的に理解してもらいやすい。
外部の汎用的なマーケティング講座などを受講してもらうのではなくオリジナルにこだわるのは、プログラム全体を貫く「顧客理解」の考え方が個々の講座においてもブレないことが大事だと考えたからだ。
プログラムには外部講師を招いている講座もあるが、講座全体の思想に共感していただき、このプログラムに合わせた内容を制作してもらっている。講師には、講師業を専門にしている人ではなく、マーケティングの最前線にいる実務家を選定している。社外の講師に依頼するのは、以下のようなメリットがあると小林氏は語る。
- 外部でその業務に携わっている第一人者の話だと説得力が増す
- 他社事例や現場におけるベストプラクティスも含めて話してもらえる
インプットとアウトプットで受講内容の定着を促進
プログラムには、インプットのコンテンツとアウトプットのコンテンツがある。インプットのコンテンツはいわゆる座学で、マーケティング人財に必要な思考法やスキルを学び、理解する。アウトプットのコンテンツでは、学習したスキルやフレームワークを実際に活用して作業を行う。
座学だけだと、わかった気になるだけでどうしても定着しない。自分でSTP分析を行ったり、カスタマージャーニーを書いたりなど、実際に手と頭を動かしてみるのが大事(小林氏)
実際に一度手を動かしてみると、それを自分の担当している事業でも改めてやってみよう、というきっかけにもなる。ワークショップは受講者からも好評のようだ。
また、全講座を受講した後に実施する「講座修了ワーク」では、講座で得た学び・気づきと、自身が携わる業務・事業の現状を対比して見えてくるギャップから、解決すべき課題を抽出し、具体的なアクションプランに落とし込む作業を各自が行う。
学んだことを活かして、自分たちの事業の現在地とギャップから課題まで出すことで、そのまま使えるアクションプランが作成できる(小林氏)
各自が作成したシートはグループワークで互いに見せ合い、感想や意見を述べてもらう。
これはうちと同じだねとか、こういう気づきは私になかったな、といったことを共有することによって、課題への理解がさらに深まり、実践への意識も高まる(福澤氏)
講座のテーマは4領域12種
講座は、以下のようなテーマが用意されている。
- 【思考法】マーケティング概論、施策プランニング概論、データ活用の攻めと守り
- 【戦略】リサーチ、BtoBマーケティング、CRM、カスタマーサクセス
- 【戦術】SEO、デジタルメディアプランニング、SFA・MAツールの活用
- 【実践・検証】データ分析、パートナーマネジメントなど
講座受講後にはアンケートを実施して、講座のアップデートも行っている。
講座ごとのアンケートを実施し、実務への有用度などを評価してもらっている。また、毎年プログラムが終了した後、上長とも話をし、受講後の受講者の変化や、現場のマーケティング課題についてもヒアリングを行っている。これらの活動を通じて毎年プログラムを改善している(小林氏)
アップデートにより、3年目に追加されたのが「パートナーマネジメントの基礎」だ。「パートナーからよい提案をいただくためのブリーフィングに必要な設計と手段を知る」ことを目的としていて、最終的に、ブリーフィングを適切に行うための与件が整理できるようになる。普通のマーケティングプログラムには含まれていないことが多いが、日経でマーケティング業務に携わる際には押さえておきたい内容だと小林氏は言う。
社内では、制作会社や代理店など社外パートナーとともに施策を進めることが多い。その際のコミュニケーションに課題があるとわかったことで生まれた講座だ。与件を正しく伝え、キャッチボールを適切に行えるようになると、パートナーとともに作り上げる施策や企画の質が必ず向上する(小林氏)
人財育成プログラムを成功させるための3つのポイント
このような人財育成の取り組みを成功させるために押さえておくべきポイントとして、小林氏は以下の3つを挙げる。
- トップ・役員層の後押し、後ろ盾
- プログラムを実行する人たちのパッション、思い
- 受講する人たちの受け入れマインド
トップの後押しがなければ、現場から受講者を出してもらえないかもしれない。私たちに思いがなければ、どこかのプログラムを受けてくださいと言うだけになる。現場に受け入れマインドがなければ、どんなにいいことを言っても浸透しない(小林氏)
受講者の受け入れマインドという意味では、新人ではなく、業務経験があり、現場で課題を感じている人の方がいい。このため、新人研修のような形ではなく中堅どころから始めて、3年目の現在、1~2年の経験がある若手まで受講者が広がったところだ。
福澤氏は、講座を作る軸、中心となる考え方を持っていることが重要だという。
マーケティングができる人財を作ろう、というだけでは、多分うまくいかない。私たちの場合は顧客理解を共通言語にというのがコアの考え方としてある。そこを持っていることが大事(福澤氏)
マーケティングの定義から始めたというのがまさにこれで、何をするプログラムなのかが決まっていないと、そのプログラムが成功したのか失敗したのかを評価することもできない。
最後に小林氏は、「顧客理解を共通言語にするという考え方は、マーケティングだけにとどまらず、会社の文化・風土になるところまで落とし込みたい」と将来的な展望を語った。