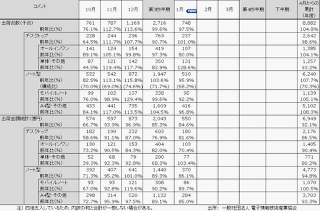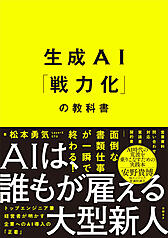13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
テレビ番組「徹子の部屋」を見ていた時に、タモリと黒柳徹子が「倍音」繋がりだったとかいう話を聞いたのが、この本を知るきっかけだった。
書いてある内容は、脳科学から音楽、言葉、文化などまで守備範囲が広い、学際的で非常に面白い本だった。工学部卒でありながら、尺八演奏家・作曲家である著者らしく、科学的でありながら情緒的でもある内容だ。
右脳・左脳、発声、音楽、日本語、日本文化といったキーワードに興味を持っている方には、是非お勧めしたい本だ。目次からは内容が想像しにくいかもしれないが、基本的に「音」をベースにした話。
<目次>
第1章:不思議な現象
第2章:倍音とは何か
第3章:メディアを席巻する倍音
第4章:日本という環境・身体・言語
第5章:日本文化の構造
第6章:超倍音楽器、尺八
第7章:人間にとって音、音楽とは何か
終章:未来の響きに耳を澄ます
発行:春秋社
著者:中村明一
定価:1,800円+税
約250ページ
関連リンク:
書評ページをまとめた

noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
まあ目次を見てもらってもわかるとおり、全体構成もよく考えた上で作られた本だ。天声人語を昔書いていた人が筆者なので頷ける。
今までの沢山の「文章」書き方本は読んできたが、結局自分でアウトプットしていかないと身につかないので、こういう本を直接参考にはしていない。無理してまねてもできないからだ。
しかしたまにいろんな本を読んで、これは自分でやっているなあとか、なるほど、こんな組み立て方もあるのかといった具合に、無理せず吸収できそうなものを少しずつ学んでいる感じだろうか。
文章の書き方といっても、小説を書くのと、評論を書くのと、ビジネス文書を書くのは全然違う。共通な基本的な技法もあるし、共通しないものもあるだろう。個人的には楽しく、気軽に読めた。付箋もそれなりに付いた。
<目次>
一.広場無欲感の巻---素材の発見
広い円
現場
無心
意欲
感覚
二.平均遊具品の巻き---文章の基本
平明
均衡
遊び
具体性
品格
三.整正新選流---表現の工夫
整える
正確
新鮮
選ぶ
流れ
発行:岩波新書
著者:辰濃和男
定価:800円+税
約240ページ
関連リンク:
書評ページをまとめた

noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 9ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
ウェブアナリスト 宏美のブログ。WebAnalyticsの3Cデータと関連情報を提供。一つはcompetitor、市場マクロデータや競合データ。一つはcompany、自社のアクセス解析データ。最後はcustomer、ユーザー行動データ。数値の一人歩きをさせたくないので、詳しくは原典と各調査方法を確認のこと。Unknownnoreply@blogger.comBlogger9007125
Insight for WebAnalytics フィード を購読