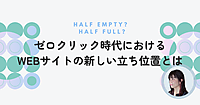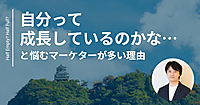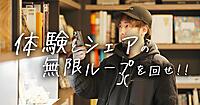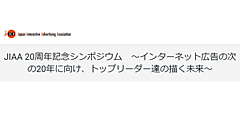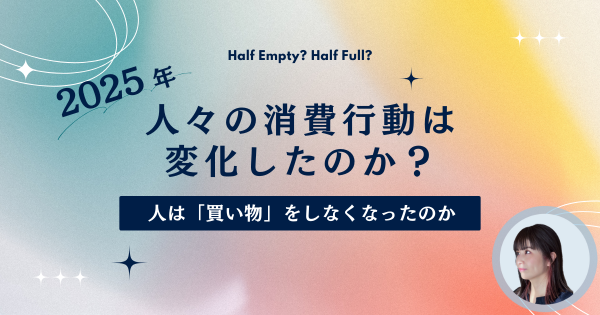
皆さま、こんにちは、村石怜菜です。21世紀になって四半世紀。今年も新しい技術やトレンドが出ると思うと期待と興味が尽きません。すでに2月ではありますが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
年末年始休暇中に「今回のコラムのテーマをどうしようか」と考えていると、「来年は2025年か…。そういえば2025年って何かが起こる年だったような…。本で読んだことがあるな…」と頭に浮かび、そして思い出しました。その本が、望月智之氏の著書『2025年、人は「買い物」をしなくなる』です。
この本を以前読んだ記憶がよみがえり、「そこに描かれていた未来は本当に実現しているのだろうか?」という疑問がわきました。そこで、過去に読んだこの本をKindleのライブラリから引っ張り出し、あらためて読み返してみることにしました。
ただ、この本が出版されたのは2019年11月。中国の武漢市で最初のコロナウイルス感染者が報告されたのは、2019年12月初旬のことです。当時、コロナ禍がもたらす急速なデジタルシフトを誰も予測していませんでした。コロナ禍をきっかけにデジタルシフトやDX(Digital Transformation)が急激に進んだことで、この本で描かれていた未来の予測は、逆にそれを上回る形で実現している可能性もあります。
今回は、この本が示した未来像と現実のギャップ、そしてこれからの消費行動について考えてみました。
デジタルシェルフがもたらす新たな購買体験
この本では、「日常のすべてが商品棚になる」という未来像を「デジタルシェルフ」として描いています。デジタルシェルフとは、ECプラットフォームやデジタルインフラ上で、商品が適切なタイミングで消費者に提示される仕組みを指します。この環境では、消費者は必要な商品にアクセスできるようになります。
一方で、従来の「オムニチャネル戦略」は、リアル店舗、ECサイト、モバイルアプリなど、複数のチャネルを通じて消費者との接点を増やすことを目指していました。しかし、現代の消費者は商品情報や価格、口コミに容易にアクセスできる環境を手に入れており、もはや接点を単純に増やすだけでは不十分です。
消費者にとって重要なのは、「何も考えなくても、必要なものが的確に届く」ことです。買い物に伴う記憶や思考、意思決定のプロセスが簡略化されることが、購買体験をより快適にする鍵となっています。
行動経済学で見る「楽をしたい」消費者心理
消費行動の変化を理解するには、行動経済学の視点が役立ちます。私は行動経済学を学ぶのが好きなのですが、「ヒューマン」と「エーコン」という概念についてはご存知でしょうか。この概念は、人間の意思決定の特性をわかりやすく示しており、消費行動が簡約化される背景にも深く関わっています。
- ヒューマン:現実の人間を指し、脳がエネルギー効率を重視して「楽をする」傾向があり、直感や経験に基づいた簡略化された意思決定を行う。損失回避やアンカリング、現状維持バイアスといった非合理的な行動が見られ、感情や社会的影響に敏感に反応する。
- エーコン:完全に合理的な存在として、すべての選択肢を評価し、常に最適な意思決定を行う。ただし、これは現実にはほとんど存在しない理想的なモデル。
このような人間の特性を踏まえても、選択を最小限に抑え、考える必要をなくすことが、消費者にとってより快適で嬉しい購買体験を提供する鍵だといえます。私たちを取り巻く買い物環境も、こうした消費者心理に対応する形で変化しています。
AIがコンシェルジュとして商品を勧める時代
本書では、「5Gなど通信技術の進化により、現実とバーチャルの境界がなくなり、バーチャルコンシェルジュが常に寄り添う未来が訪れる」と予測されています。個人に最適化された情報やサービスが24時間提供される時代を示唆しているのです。
2025年現在、この予測に近い存在として私が注目しているのが、AmazonのAIショッピングアシスタント「Rufus(ルーファス)」です。2024年11月に日本でベータ版が提供開始されたこのツールは、単なる商品検索ではなく、具体的なシーンや目的に応じた商品提案を行います。
たとえば、「釣りで使える簡単に折りたためる椅子」といったニッチな要望にも対応し、私自身、検索では見つからない商品に出会えることも多々あります。一方で、提案の精度に課題が残る場合もあり、さらなる改良が期待されます。
サブスクリプションで変わる「買うことの価値観」
サブスクリプションサービスは、私たちの生活に欠かせない存在となりつつあります。音楽ストリーミングや動画配信サービスだけでなく、家電や衣類、家具など、あらゆる商品がサブスクで利用できる時代になりました。
私が愛用している「レンティオ」は、その先駆けといえるサービスの一つです。カメラレンタルからスタートし、現在では家電や衣類、さらには振り袖や電動自転車といったアイテムまでレンタルできるようになりました。こうしたカテゴリーの拡大からも、時代のニーズが多様化していることを実感しています。
本書で「人々は買い物をしなくなる」と述べられていますが、私はこれを文字通り「買い物そのものが消滅する」という意味ではないと解釈しています。消費者が商品を利用する手段は、所有ではなくサブスクリプションを選ぶ場合もあれば、通販サイトやAIによるレコメンドによってスムーズに商品を手に入れる場合もあるでしょう。つまり、テクノロジーの進化によって「買い物」と「日常生活」の境界線が薄れていく、ということを指しているのではないでしょうか。
一方で、かつてのように百貨店へ出かけ、実物を手に取りながら商品を選ぶ体験は、今後ますます特別なものになるかもしれません。たとえば、職人技や歴史、ストーリーが込められた工芸品には、これまで以上に高い価値が見いだされるでしょう。このような商品を、店舗で店員との対話を楽しみながら購入する体験が重視される場面も多くなると考えられます。非日常的な買い物体験は、より貴重で特別なものとして消費者に受け入れられるのではないでしょうか。
顧客の利用文脈をさらに分析・理解することが、今後のマーケティングの鍵となる
デジタルテクノロジーの進化に伴い、「デジタルシェルフ」が生活のなかでますます存在感を増しています。しかし、消費者との接点を単純に増やすだけでは不十分です。接点の質や文脈を深く理解し、消費者に最適な体験を提供することが、これからのマーケティングに求められています。
従来のマーケティングファネルに依存するアプローチでは、接点が増え、消費行動が多様化する現在の状況を十分に捉えるのは難しくなっています。既存顧客や潜在顧客にアプローチし続けるだけでは、長期的な成果が期待できないでしょう。消費者が商品を選ぶ背景や文脈を深く理解し、それに基づいた体験を設計することが不可欠です。
実際にECサイトのユーザーをシーケンス分析(一人の行動を分析)してみると、1つのサイト内で購入することに固執せず、Google検索で見つけて訪問し、離脱を繰り返すユーザーが増加傾向にあるように感じます。こうした行動を深く理解し、それに応じたコミュニケーションやUX(User eXperience)を設計することで、そのECサイトは消費者に想起される存在となり、最終的にはECサイトやブランドのファンになる可能性が高まります。
ここで注目したいのが、「カテゴリーエントリーポイント(CEP)」という考え方です。CEPは、消費者が特定のカテゴリーの商品やサービスを選ぶ際の「入り口」となる瞬間や要素を指し、文脈に即したUX設計を通じて、ブランド体験を向上させる概念です。これまでは、企業やブランド単位でUXを設計するのが主流でした。しかし、これからは「体験上の文脈=カテゴリー」に焦点を当て、消費者がそのカテゴリー内でどのように商品を選ぶのか、自社が選ばれる理由を明確にすることが重要です。
CEPの体験設計がマーケティングを変える
CEPの活用により、消費者は単に商品を購入するのではなく、「そのときのニーズや状況にぴったりと合った体験」として購買行動を捉えるようになります。たとえば、忙しい朝に素早く飲めるコーヒーを提案するか、記念日に特別なプレゼントとして選ばれる商品を提供するかといった文脈に寄り添った提案が可能です。このようなアプローチを通じて、ブランドとの結びつきが強まり、競争の激しい市場で優位性を確保できるでしょう。
コンビニエンスストアでのCEPの具体例
たとえば、コンビニエンスストアでは以下のようなCEPが考えられます。
- 朝の通勤中に手軽に朝食…サンドイッチやおにぎりを入口付近に配置し、モバイルオーダーで事前注文を可能にする。
- 帰宅後のリラックスタイムに合わせた提案…夜間限定のデリ商品やスイーツを展開し、特定の組み合わせ割引で購入を促進する。
- 日常使いできるおしゃれアイテム…Tシャツや靴下など、季節に応じたアパレル商品やブランドコラボ商品を展開する。
これらのCEPは、コンビニという枠を超えた新たな顧客接点の構築に寄与しています。日常的な利用ニーズだけでなく、より特別な体験を提供することで、顧客との結びつきを深めています。
昨年ごろから耳にする「ユニファイドコマース」も、CEPを活用するための重要な仕組みの一つと考えます。リアルとデジタルを横断し、すべてのチャネルを統合することで、消費者がどのタッチポイントを利用してもシームレスな体験を提供できます。特に、実店舗での購入履歴やオンラインでの閲覧データを統合してパーソナライズされた提案を行うことで、消費者にとって一貫性のある購買体験を実現します。
2025年、買い物はより生活に溶け込んでいく
『2025年、人は「買い物」をしなくなる 』が示した未来像は、AIやIoTを活用した購買体験の進化や、消費者行動が日常に溶け込む姿を描いています。単なる「購入行為」から「体験」や「文脈」に重きを置いたプロセスへの進化は、今まさに現実のものとなっています。
こうした変化を受け、今後のマーケティングでは、消費者が商品を選ぶ背景や文脈を深く理解し、それに基づいた体験設計がますます重要になります。CEPは、その「入口」を設計するための重要な概念です。CEPを活用することで、ブランドは消費者にとって「選ばれる存在」となり、新しい消費行動に応えることができるでしょう。