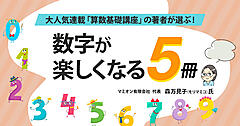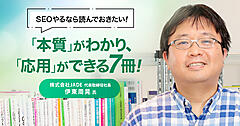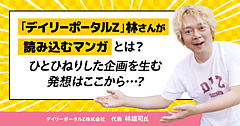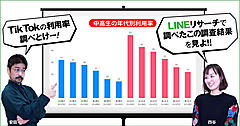業界のトップランナーにオススメの書籍を教えてもらう本連載。今回は、SEOを専門とする神頼(かむらい)の広岡謙さんにお話を聞いた。SEOというとテクニックの話になりがちだが、広岡さんは「SEOに直接関係はしないが、それを取り巻く人や仕組みを考えるのに役に立つ本」を9冊、紹介してくれた。まずは気になった本から手に取ってみてほしい。

偶然SEOと出合い、現在はプラチナプロダクトエキスパートに
SEOを専門とする神頼株式会社 取締役副社長COOを務める広岡さん。SEOに出合ったのは偶然だという。無職だったころ、英語ができる人材募集を見て、応募。その会社がSEO支援事業に取り組んでいたことから、SEOの海外情報の収集や翻訳の仕事をするようになった。
その会社が大手広告代理店の子会社に買収され、移籍。やがて、別の広告代理店のデジタルマーケティングの会社に転職した。転職先には、SEO関連の飲み仲間がたくさんいたことも転職のきっかけになった。
その後、仲間と神頼を創業。広岡さんは、ECサイト・求人サイト・不動産サイトのような大規模データベースで商品管理を行うサイトや、大規模メディアのSEOを得意としている。また、Google 検索セントラルへの回答を続け、現在Googleのプラチナプロダクトエキスパート。Google検索の評価方針を示している「検索品質評価ガイドライン」の私訳・解説もてがけている。

SEOの基本はGoogle公式情報を確認しよう
広岡さんは、開口一番「SEOに関する本については、株式会社JADEの伊東周晃さんが紹介している記事をまずは読んでください」と述べた。
そのうえで、さらに次の3つのGoogle公式情報をチェックするとよいという。
1. Google 検索の仕組み
https://www.google.com/intl/ja_ALL/search/howsearchworks/how-search-works/
もっともシンプルにGoogle検索エンジンの仕組みを解説している。
初心者向けに、わかりやすいたとえで検索エンジンの仕組みが紹介されているので、クロール、インデックス、ランキングなどの一連の流れを理解できます。そのうえで、「Google 検索に関するドキュメント」を読んでみると、より理解が深まると思います(広岡さん)
2. General Guidelines(検索品質評価ガイドライン)
SEOのなかで一番わかりにくい「ウェブサイトの品質・評価」についての公式ガイドである。
こちらは、検索エンジンが表示する検索結果の教師データを作成するためのガイドラインです。その評価の際に、よいWebサイト、よいページと判定するためのポイントが示されています。
Googleがどんな価値観をもっていて、どんなコンテンツを検索結果に表示させたいのかがわかると思います。
私が手掛けた私訳・解説もあるのですが、すでに古いものになっているので原典を読みましょう。ただ英文で180ページ以上あるので、結構大変だと思います。生成AIで翻訳、要約しながら読むのもよいでしょう(広岡さん)
3. Google 検索セントラル のヘルプ コミュニティ
https://support.google.com/webmasters/community?hl=ja
SEO絡みの実務で困ったらこちら。Googleの公式フォーラムである。
SEOを学習していてわからないことがあったり、「自社名で検索しても上位に表示されない」「サーチコンソールのデータに違和感がある」など実務上のSEOの悩みがあったりしたら、ヘルプコミュニティを活用するのがオススメです。SEOのプロが回答してくれることも多いので、回答の質が高いです。自分では完璧な施策をしているつもりでも、他の人から見ると抜けが見つかることがあるので、困ったら相談してみてください(広岡さん)

情報の選抜者(検索エンジン・生成AI)の考え方、その立場の難しさを知るための本
広岡さんは、生成AIで情報を取得するようになっても、以下の3者が連携して情報が循環する構造は変わらないと話す。
- 情報の選抜者(検索エンジン・生成AI)
- 情報の消費者(検索ユーザー)
- 情報の供給者(ウェブサイト運営者)
「この3者の思惑に配慮しつつ、連携を潤滑にするための手助けをするのがSEOの仕事」と広岡さんは捉えており、3者を理解するのに役立った本を紹介してくれた。
まずは「選抜者」の検索エンジン・生成AI。これは、人の声を聞いたうえで、最もよい結果をデータベースから選んで表示する。しかし、選ぶ側が間違えることがあるという「危うさ」もあることを、忘れてはいけない。
1冊目
『日本神判史 盟神探湯、湯起請、鉄火起請』
(清水克行:著 中央公論新社:刊 2010/5/25:初版発行)
帯には、“神慮の名のもとに釜に煮えたぎる湯の中に手を入れ、火傷の状態で判断が下される「湯起請」。赤く熱した鉄片を握る「鉄火起請」。なぜ、かくも過酷な裁判を人々は求めたのか”とある。
一見理不尽に見えるこうしたシステムがなぜ支持され、そして消えていったのか。裁く側・裁かれる側・共同体の思惑から、その理由を読み解く一冊です。「情報を処理し、取捨選択して結論を出す」プロセスの正確さとはなにか? 人はなぜその結果を受け入れるのか? という点を考えるきっかけになります。
検索の「情報の選択者」としてときには裁き、君臨していると批判もうけがちな検索エンジンですが、いかに「民意」「公平性」などに配慮しているか、そして今後もそうした点に配慮したサービスが生き残るはずだ、ということがわかります(広岡さん)
2冊目
『ある首斬り役人の日記』
(フランツ・シュミット:著 藤代幸一:訳 白水社:刊 1987/12/1:初版発行)
本書は、ドイツ・ニュルンベルクの死刑執行人フランツが、1573年から約45年間にわたる執行を淡々と記録した日記だ。心が元気な時に読んでほしい。
日記を読み進めると、ある変化に気づかされます。仕事を始めた当初は克明だった処刑の記録が、後半に進むにつれてどんどん淡白になっていくのです。これは、執行する側の「慣れ」や「鈍感さ」の現れに他なりません。
検索にも、通じるものがあります。多数の情報を処理するほど、一つ一つの情報やその製作者への配慮を万全にすることは難しくなります(広岡さん)
3冊目
『独裁者の言い分: トーク・オブ・ザ・デビル』
(リッカルド オリツィオ:著 松田和也:翻訳 柏書房:刊 2003/9/1:初版発行)
アミン、ボカッサなど、かつて独裁政治をしていた権力者たちにインタビューした、興味深い書籍だ。
自分の過去の弾圧について振り返ってもらった際に「しかたがなかった、些細なこと」と話す人がいることに驚きます。権力が集中すると、「選択者」は鈍感になりがちです。検索エンジン・生成AIがどこに向かおうとしているのか、その先を見て危ういともし感じたら、別の手法を考えることも必要だと思います。
知らない独裁者も多数登場しますが、この本を読んだ後に彼らの事績を調べてみるとおもしろいです。現在の彼らは、自分の過去をどう受け止めているのか…?(広岡さん)
情報の消費者(検索ユーザー)の気持ち・人間像を知るための本
ユーザーは何のために、何を求めて検索をしているのだろうか。広岡さんは、「寝たい」という検索キーワードについて、ある事例を教えてくれた。
「寝たい」と検索する人は、寝たいのに、寝られなくて困っている人です。そのキーワードに対策していたのが、ある「求人サイト」でした。寝たいと検索してしまうほどストレスがかかっている状態の人に、まずは今眠るための方法を、次にその根源にあるストレスを解消する方法を紹介していました。そうした段階を踏まえて、「それでもだめなら、もしかしたら転職したほうがいいかもしれない」という選択肢を示すわけです。
仕事を紹介するのが求人サイトですが、ただ仕事を紹介するだけでは事足りません。紹介する前の段階、紹介した後の段階までフォローして、人の悩みに深く向き合っているサイトは信頼できるなと思いました。
生成AIの登場で検索やSEOはなくなるという極論もありますが、人の悩みや疑問をすべて事前につぶすことはできないはず。そして、そうした悩みや疑問に答える情報、人が求める情報を提供したり探したりする仕事は、なくならないと思います(広岡さん)
人の悩みに向き合った文章として参考になるのが、次の本だ。
4冊目
『毒舌 身の上相談』
(今東光:著 集英社:刊 1994/5/20:初版発行)
今東光さんは、小説家にして、天台宗大僧正、中尊寺貫主を務めた人物。人生相談も得意としていた。本書は、若者向けの身の上相談集だ。
常に相談者に寄り添うわけではなく、たまにはバッサリと切り捨てる時があります。私は「甘い悩みに甘やかす答えを返す人」は信用できないと思います。医者でも、「風邪です」という患者に風邪薬を処方するのはだめな医者で、本当に風邪なのか、患者の言葉の背後にある事情を俯瞰してこ別の病気の可能性を調べる必要があります。
SEOでも「検索クエリに沿っただけ」の浅いコンテンツは評価されにくい。「寝たい」の例のように、眠れない原因を広く想像し、その中で検索者に必要なものを絞って提供することが大事です。
この記事を読んでくださる方には、156ページの「本はどう読むべきか」という問答がオススメです。「本を読むことで、自身の感受性や思考を養いたい」という相談者への、秀逸な回答が心地よいです(広岡さん)

5冊目
『流言・投書の太平洋戦争』
(川島高峰:著 講談社:刊 2004/12/11:初版発行)
流言とは、根拠の無いうわさやデマのこと。太平洋戦争当時、SNSはなかったので人々は新聞に投書をしていた。本書は、戦争が始まったころから終わるまでの間に投書や流言などがどう変わっていったかをまとめている。
「フェイク・ヘイト」を考えるうえで役立つ一冊です。戦戦争が始まったばかりのころは、“「来年には戦争が終わる」と、仙人みたいなおじいさんが言っていた”というような牧歌的な投書が多いです。しかし、戦況が終盤に入ると「この国は〇〇だから勝てる」「スパイや裏切り者が身近にいる」というような悲壮な内容ばかりになります。
特に印象深いのが、終戦間近の内閣情報局の発言(274ページ)。人々が本土空襲に苦しむ中で「空襲というのは損害だが、見方を変えればとてもありがたいことだ」と発言する担当部長の、そのロジックと心理に戦慄します。
検索する人の気持ちは世情によって変わり、フェイク・ヘイトによって扇動されることもあります。「検索クエリに沿っただけ」の対応に慣れてしまっていると、こうした点を見落とすことがあります(広岡さん)
一方で変わらない、普遍的なこともある。それが人は必ず死ぬということだ。6冊目は、作家の山田風太郎さんが、さまざまな人の死に方についてコンパクトに紹介している本だ。
6冊目
『人間臨終図巻1 <新装版>』
(山田風太郎:著 徳間書店:刊 2011/11/15:初版発行)
英雄や武将、政治家など、さまざまな著名人の死にざまを、死んだときの年齢別に記している。
若くして命を燃やして死ぬ人もいれば、若い時は優れた作家だったのに、晩年は同じことを何度も繰り返すような文章を書いて壊れてしまって終わる人もいます。いろいろな年代に対して理解が深まる本です。
ユーザー像やペルソナを考える時に役立ちます。通人間の幅広さ・生きざま・苦悩などを知ることで、クエリの向こうにいるユーザーへの想像力が増します。
「今の自分と同じ年で亡くなった人」を毎年読んでみると、いろいろと考えさせられます(広岡さん)
情報の供給者(ウェブサイト運営者)の陥りがちな過誤を知るための本
次に、情報の供給者としての企業がおかしやすい間違いについて書かれた、戒めにもなる本を紹介してくれた。
7冊目
『珍説愚説辞典』
(J.C.カリエール、G.ベシュテル:著 高遠弘美:訳 国書刊行会:刊 2003/9/20:初版発行)
ローマ法王や学者など、古今東西の教養人の珍説・愚説をまとめた一冊。
過去の知識人・有名人の意見で、現代の知識や常識からみると、珍説・愚説と思われるものをまとめています。こんな感じです。
- 「空を飛ぶことは物理的に不可能」(1888年、当時の科学誌)
- 「日本人は原始人。崇高な作品を生み出すことは未来永劫あり得ない」(1888年、当時の有名な批評家)
どんなに知性豊かで優れた人であっても、誤解・偏見からは逃れられないということを再確認できます。コンテンツを作成する際に、時に立ち止まり推敲・自己批評をすることの大切さがわかります(広岡さん)
今、正しいとされていることも、数年経てば珍説愚説になりえるかもしれないという意識をもつことが発信者としては大事だろう。
Web担読者に読んでほしい2冊
次は、「SEO担当者だけでなく、マーケターやWeb担当者に読んでほしい」と広岡さんが紹介してくれた2冊だ。
8冊目
『株式会社日広エージェンシー企画課長中島裕之』
(中島らも:著 双葉社:刊 2005/7/1:初版発行)
作家・エッセイストの中島らもさんは、かつて広告代理店の敏腕企画課長だった。本書は、当時の企画書を読み解いていく一冊だ。ぜひ、企画書づくりの参考にしてほしい。
この業界にいると「データありきで作った、意志の宿らない企画書・提案書」といったものを見かけがちですが、らもさんの企画は全然違います。生みたい価値・やるべきことが明確にあり、それを伝えるための手段がまたおもしろい。データやロジックも適切に使いつつ、それだけに依存していません。自筆のエッセイ・漫画・プロットなど、適切な手段を柔軟に使いこなします。この人に任せたらおもしろくなるな、と思わせる魅力があるのです。
自分が提案する際に、鑑としている一冊です(広岡さん)
9冊目
『中世実在職業解説本 十三世紀のハローワーク』
(グレゴリウス 山田:著 一迅社:刊 2017/1/19:初版発行)
AIによっていろいろな仕事がなくなるといわれているが、「時代が変われば仕事の内容も変わるので、そう悲観する必要はない」と広岡さんは話す。そのことが実感できるのが本書だ。13世紀とはいえ、人間の仕事が多様であることがわかる。イラスト満載で、まるでゲームのキャラクターのように職業が紹介されているので、見ているだけでも楽しい。
貴婦人に傘をさすだけの仕事、馬の成長を占う仕事、船が嵐にあったときに生贄にされる仕事など、現代では考えられないような仕事があります。AIに今の仕事を奪われても、人が求めることであれば何でも仕事になるので、不安がることはないと思います。
また「Webマーケターになってはみたものの、向いていないのではないか…」と悩んでいる人にもおすすめです。いろいろな人生の可能性が見えます(広岡さん)

知らない本を読み、知らない店に行ってみよう
今回紹介した本の多くは、広岡さんが古本屋で偶然見つけたものだそう。古本屋に行くと、思わぬ本に出会うことがある。タイトルが気になったら、ぜひ買ってみてほしいと広岡さん。
インターネットで見聞きする情報や、Webの本屋では「自分の好きな本・情報」としか出会えません。自分の知っている世界に閉じこもって小さい最適化をしがちです。その点、リアルの本屋には未知との出会いが詰まっています。
私は「ちょっと表紙がおもしろそう」「タイトルが気になる」くらいの理由で、本を読んでみることを大事にしています。割とハズレも引きがちですが、たまに人生を救うかもしれないおもしろい本に出会えることがありますよ(広岡さん)
そしてもう1つは、かつて寺山修司さんが提案した『書を捨てよ、町へ出よう』ということ。本だけでは学べないさまざまなことがあるのが町、そして飲み屋だと広岡さんは語る。
お酒を飲みながらお客さんの語ることをラジオのように流し聴きしていると、本の世界では触れられないようなことに触れられます。
行きつけの根津の「たまゆら」というバーは穏やかな会話と音楽に身をゆだねられる良いお店です。ママの人柄にひかれて、普段の生活では関わらないようなさまざまな人が集まります。そうした会話に耳を傾けると、本には出てこないような価値観があって、みんなのオススメを聞くこともできる。自分の世界を、一歩広げてくれるのです
また、普段行かない酒場に行くのもオススメです。古本を買うのと同じで、自分を広げる出会いやいい気付きがありますよ(広岡さん)
これまで本連載で紹介してきた本とは少し趣向の違った書籍を、テーマに合わせて紹介してくれた広岡さん。検索エンジン、ユーザー、情報発信者のそれぞれの危うさや間違いやすさに気づかせてくれるような本で、SEOの奥深さを感じることとなった。
広岡謙
神頼株式会社 取締役副社長COO
SEO(検索最適化)の専門家として、複数の大規模ウェブサイトのコンサルティングを主導。また、検索需要・検索行動・自然言語処理・AIなどの関連分野の調査や、利活用方法の企画なども行う。趣味は酒・料理・本・折り紙など。敬愛する作家は内田百閒。
Google Product Expert (Search Central, Platinum)