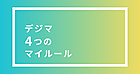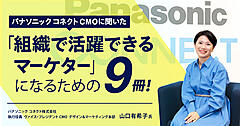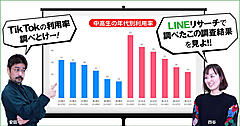野球・サッカー好きの人事が選ぶ、戦略的な「組織運営」を学ぶための5冊!
東大サッカー部のテクニカルスタッフだったというユニークな経験をもつアナグラム人事の小坂さんに、サッカー部での経験と現在の仕事をつなぐ本や、組織運営に関する本を教えてもらった。
2025年4月15日 7:00
業界の第一線で活躍する人たちに、書籍をオススメしてもらう本連載。今回は、アナグラムの経営戦略室人事チーム リーダーの小坂彩さんに組織論やマネジメント論に関する書籍を紹介してもらった。小坂さんは、大学時代にデータ分析でサッカーチームを支援していた経験をもつ。そうした経験も含めて、お話を聞いた。

大学時代は東大のサッカー部でテクニカルスタッフとして活躍
小坂さんは、東京大学の在学時、ア式蹴球部(サッカー部)でテクニカルスタッフとして活動していた。テクニカルスタッフは、自チームのデータを収集して分析し、選手にフィードバックしたりするほか、対戦相手の映像を見て特徴を分析したりする役割を担う。
取得するデータは、選手一人ひとりのパス成功率、クロス成功率のようなミクロなものからチーム全体のパスマップといったマクロなものまで幅広い。
私自身はサッカーをプレーしたことがないので、データは監督や選手と同じ目線で語るためのツールであり、発言の信頼性を担保するものでもありました。日々とっているデータからは、バイアスによって気づけなかった盲点が見つかることもありましたし、映像を見て抱いた仮説をデータで改めて検証することもありました(小坂さん)
もともとスポーツビジネスに興味があり、卒業後、スポーツ用品メーカーに就職した小坂さんは、ECの部署でデジタルマーケティングを担当。その後、運用型広告の代理店であるアナグラムに転職したが、転職のきっかけは意外なところにあったようだ。
アナグラムに興味をもったきっかけは、独自の組織運営をしていると知ったことでした。一般的に「お客様のため」と謳っている会社も、現場レベルでは(お客様のためにならない)売上が重視されていたりしますよね。
しかしアナグラムでは、掲げたビジョンを評価制度や組織体制などの仕組みに反映させ、現場まで落とし込んでいるという記事を読んで、おもしろそうだなと思い、入社を決めました(小坂さん)
運用型広告エキスパートとして経験を積んだのち、現在は、人事チームのリーダーとして、もともと関心の高かった組織作りや採用活動などを担当している。

弱小野球チームがデータを重視して強くなる実話から、データ分析の基本や採用戦略を学ぶ
1冊目
『マネー・ボール〔完全版〕』
(マイケル ルイス:著 中山宥:訳 早川書房:刊)
小坂さんが最初に紹介してくれたのが『マネー・ボール』だ。本書は映画にもなっているので、知っている方も多いだろう。資金が限られている野球チームのアスレチックスが、データを活用して隠れた選手を掘り出し、資金力のある強いチームに勝って旋風を巻き起こしていくという実話に基づくストーリーが展開されている。
小坂さんは、中学生のときにこの映画をみてデータ分析やスポーツビジネスに興味が湧いたそうだが、その後、原作を読んでみて、今の仕事につながるような学びを得たという。
本書からは、データの扱いに関する基本的な考え方を知ることができます。たとえば、「データはデータだけで意味をもつのではなく、そこからどう解釈するかが大事である」みたいな話は、そのまま広告運用にも活きると思いますね。単に「CVRが〇%に下がりました」という話をするのがデータ分析ではなく、なぜCVRが下がってしまったのか、改善するにはどうしたらいいのか? という解釈につなげなければ意味がないので(小坂さん)
もう1つ、小坂さんが本書から学んだのは、メンバーの採用方法だ。アスレチックスでは、ドラフトで多球団から1位指名されるような選手ではなくても、チームの戦略にマッチする人材をデータから探して指名していく。
決して大きな会社ではないアナグラムの採用戦略にも、通じる考え方があります。アナグラムの場合、書類選考と面接の間に独自の適性検査を実施し、「この問題に対してこういった回答をしている人は採用しない」という基準を設けています。
逆にいえば、学歴や職歴が華々しくないがために通常書類で落とされてしまうような人であっても、適性検査を通してマッチする人材かどうかを判断できるということでもあります(小坂さん)

部分ではなく、全体をみて考えることの大切さを知る
『マネー・ボール』をみてデータ分析に興味をもったという小坂さんだが、大学時代のテクニカルスタッフの活動を振り返ると、サッカーはチーム全員がグラウンドで流動的に動くためデータ分析は複雑になり、野球よりも評価がむずかしかったと話す。そうしたサッカーの特徴を考えたとき、「部分に切り分けるのではなく、全体をみて考える」ことが重要になる。その際、参考になるのが次の書籍だ。
2冊目:
『バルセロナが最強なのは必然である グアルディオラが受け継いだ戦術フィロソフィー』
(オスカル・P・カノ・モレノ:著 羽中田昌:訳 カンゼン:刊)
グアルディオラは、2008年にバルセロナの監督に就任すると、ボールをキープし続けるポゼッション戦術を確立し、2009年には史上初の6冠を達成した。メッシを中心に黄金時代を築いた、クラブ史上最も成功した監督の一人である。本書は、バルセロナの強さの秘訣を分析している。
サッカーのような複雑性の高いスポーツでは、単独の要素だけをみて、相互作用を見落すとうまくいかないと紹介されています。
たとえば身体でも、足が痛いとなると足を治療しなければと思いがちですが、実際には足とつながる腰にボトルネックがあった、みたいなことってありますよね。サッカーにおいても、攻撃と守備を分断して捉えたり、プレーヤーの能力を切り分けて考えてしまうと、本質的な改善につながらない可能性があると述べられています(小坂さん)
サッカーの文脈で読んでももちろんおもしろいが、要素還元ではなく、全体をみようという本書の一貫したメッセージは、次に紹介するシステム論の本にもつながる部分であり、組織運営のヒントになると話す。
システム論の考え方を学ぶ
3冊目
『世界はシステムで動く ― いま起きていることの本質をつかむ考え方』
(ドネラ・H・メドウズ:著 枝廣淳子:訳 小田理一郎:解説 英治出版:刊)
3冊目の書籍も要素還元ではなく全体をみることの重要性を伝えた1冊で、小坂さんのお気に入りだという。物事を個々の要素ではなく、それらが相互に関係し合う全体として捉える考え方をシステム論と呼び、組織や社会、生態系、機械など、さまざまな分野に応用されている。そのなかでも特に、多くの要素が相互に影響を与え合い、全体として予測しにくい振る舞いをするシステムを複雑系と呼ぶ。
目的、複数の要素、要素の相互作用という3条件がそろえば、すべてシステムです。そういう意味では会社組織もシステムと捉えることができます。複雑なシステムは、完全な自由(カオス)でも、ガチガチの静的な構造でもうまく機能しません。その中間にあるちょうどいい塩梅をつくることが重要です。
こういったベースの考え方が頭に入っていると、「MVV」「多様性」「心理的安全性」などのフレーズを単なる流行りの手法として捉えるのではなく、「システムを円滑に動かすために、なぜ必要なのか」という根本から理解したうえで適切に導入することができると思います(小坂さん)

世界100万部突破の名著で、システム思考をベースにした組織開発を知る
4冊目
『学習する組織――システム思考で未来を創造する』
(ピーター M センゲ:著 枝廣淳子、小田理一郎、中小路佳代子:訳 英治出版:刊)
4冊目としてオススメするのは、『学習する組織――システム思考で未来を創造する』だ。2006年の初版が発行されて以来、改定されながら版を重ねている。本書は、帯にあるように、<成長と繁栄の最大の鍵となる「組織としての学習能力」はどうすれば高められるのか>について記されている。
著者のピーター M センゲはMITの経営大学院上級講師であり、システム思考で組織開発を行っていく「学習する組織」という理論を提唱した人だ。
すべての組織はシステムであるとした本書は、組織開発の古典的な名著です。20年近く前に発行された本だとは思えないほど、現代にも活かせる理論だと感じます。ただし、厚いです(笑)。全部読むのは大変ですが、具体例を交えながら手厚く説明してくれているので、まずはシステム思考の部分だけでも読むと参考になると思います(小坂さん)
ただし、本書は独自のフレーズが使われているため、読者としては少しとっつきにくく感じられるかもしれないという。用語や分量の観点でハードルが高いと感じる場合は、入門書や漫画版を読んでみるのもよいかもしれないとのことで、参考書として、『「学習する組織」入門――自分・チーム・会社が変わる 持続的成長の技術と実践』も紹介してくれた。

複雑なシステムをリードし、結果を出すための適応型マネジメント論の最新刊
5冊目
『ミネルバ式 最先端リーダーシップ 不確実な時代に成果を出し続けるリーダーの18の思考習慣』
(黒川公晴:著 ディスカヴァー・トゥエンティワン:刊)
本書では、現在のリーダーに必要なシステム思考や対人知性、課題解決といったスキルを、実践可能な18の思考習慣として提示している。マネジメント論を学べる本だが、『学習する組織』とリンクする部分もあり、組織論を学ぶうえでも知っておきたい内容だ。
ミネルバ式とは、2014年に創設されたアメリカの革新的な大学として注目されるミネルバ大学のモデルである。なお、ミネルバ大学での入学選考時の合格率は1〜2%と、ハーバード大学以上に選考が厳しい。著者の黒川さんは、ミネルバ認定講師であり、日本企業向けのリーダーシップ開発プログラム「Managing Complexity」を展開している。
本書は現代のマネジメントに必要な考え方を網羅的に盛り込んでいて、読みやすいと思います。システム思考を大事にしているのは『学習する組織』とも共通する部分なので、合わせて読んでみるとよいでしょう。システム思考に限らず、EQやデザイン思考などさまざまな視点からマネジメントを理解できる本です(小坂さん)
情報ソースは書店や人など
小坂さんは、日ごろから大型書店を目的なく歩き回ることで情報収集をしている。
本屋に行くことが大好きなんです。店内をみて回るだけでもトレンドを把握できますし。なかでも大きい店舗が好きで、書店ごとの陳列やキャンペーンの違いなどを楽しんでいます(小坂さん)
その他、信頼している人がオススメしている書籍や映画はチェックしている。最近では、ラジオやポッドキャストからも情報を得ているという。
特に、長期にわたって良質なアウトプットをし続けている人がオススメする書籍やコンテンツには、自分が興味のない分野でもいったん触れてみることを意識しています。1回きりではなく何年にもわたって質の高いアウトプットを出すには、センスだけではなく良質なインプットをし続けることが必要だと思うからです。 小説家や脚本家、TVのプロデューサー、アーティストなどのコンテンツ制作を仕事にしている人や、長く会社を経営している社長など、さまざまな分野の人を参考にさせてもらっています(小坂さん)

大学時代のテクニカルスタッフの取り組みから始まり、理論的に組織やマネジメントに取り組んでいる小坂さん。基礎知識がしっかりとあったうえで、さまざまな情報に接していることが伝わってきた。
小坂彩(こさか あや)
アナグラム株式会社
経営戦略室人事チーム リーダー
神奈川県出身。スポーツ観戦が趣味で、大学時代はサッカー部の分析官としてデータ分析や戦術を組み立てる日々を過ごす。卒業後はスポーツアパレルの会社でデジタルマーケティング職を経験し、デジタルマーケティングのおもしろさを知る。
その後、アナグラムのビジョンや仕事のやり方に魅力を感じ、2021年1月より参画。
アナグラム株式会社URL:https://anagrams.jp/