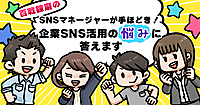オーガニック運用・広告配信・危機管理など、企業のSNS活用のポイント、最新情報を、SNSマネージャー養成講座の講師陣「チーフSNSマネージャー」のメンバーが、それぞれの得意分野を中心に解説します。
今回はカエルコムニス代表でGallup認定ストレングスコーチも務める小杉清香氏が回答します。
 質問
質問SNSをやるべき理由はわかりましたし、情報源もたくさんあるんですが、正直、ちょっとしんどくなってきました……気持ちが乗らないというか……。
 小杉
小杉やるべきことの理解はできても、気持ちがしんどくなること、ありますよね。SNSの本質はコミュニケーションなので、自分のスタイルに合わせるとラクに運用できますし、やりがいも感じられて楽しく続けられますよ。
「SNSは投稿頻度が命!」「こうすれば続けられるよ!」……これらを理解できていても、がんばり続けているだけでは気持ちがシンドくなってしまいます。メンドクサッ!と叫んだり、弱音を吐きたくなったりすることもあるでしょう。続けられない自分を責めて、落ち込んでしまうことがあるかもしれません。
「仕事でSNSをやっているからツラいのは当然!」……そんなことはありません。そもそも、SNSはコミュニケーションです。ツラい気持ちの乗った投稿はなんとなく敬遠されてしまい、なおさらモチベーションも落ちてしまいます。
楽しくSNSを続けるために、自分のコミュニケーションスタイルを運用に落とし込んでみましょう。
あなたはどのタイプ? 4つのコミュニケーションスタイル診断
YESの数を数えてみましょう。当てはまった数が多い順に、以下の4タイプに分けることができます。
- 1、5、9、13、17のうち3個以上 → 【アレコレ思考力タイプ】
- 2、6、10、14、18のうち3個以上 → 【ニコニコ友情力タイプ】
- 3、7、11、15、19のうち3個以上 → 【カリスマ影響力タイプ】
- 4、8、12、16、20のうち3個以上 → 【コツコツ継続力タイプ】

2つ以上のタイプに当てはまる場合は、それぞれの特徴を組み合わせて考えてみましょう。数が少なく当てはまるタイプがなかったときは、1つでもチェックが付いたタイプを参考にしてみてください。
(1)アレコレ思考力タイプ

オススメのSNS運用方法:
情報を集めてシェアするノウハウ提供スタイル
このタイプは考えることそのものが大好きなので、SNSで見かけたリンク先の内容も全部読んでいるのではないでしょうか。全部読んでいなくても、後で読みたいとブックマークに入っていることも多いでしょう。自社の情報はもちろんですが、クライアントが喜びそうな情報や自社にとって有益な情報にもアンテナを立てやすいです。この「たくさんの情報を扱う力」が、このタイプの強み。
もう少し細分化すると、
- 今後を見据えた、未来の情報
- 現状を理解するための、根拠となる情報
- 戦略や戦術の参考になる、他メディアの情報
- 数値的に理解できる、信頼できるデータ
などが、扱いやすくシェアしやすい情報でしょう。
情報源は様々ですが、シェアしたい情報源となるアカウントをリストにしておくと良いでしょう。Twitter なら「リスト」、Facebook なら「お気に入り」の機能を活用します。もし「企業アカウント」として他社の情報をシェアするような運用するのが難しければ、会社の代表となる個人が行うのもオススメです。社長が思考力タイプなら、企業アカウントと絡みながら運用していきたいですね。
なお、SNSマネージャー養成講座の公式Twitter(@snsmanager_tw)は、この「アレコレ思考力タイプ」で運用しています。
- SNS情報に明るいチーフSNSマネージャーのアカウントや各種メディアのアカウントを、情報源としてリストに設定。
- 企業のSNS運用に役立つ情報をコメント付きでシェア。
- 「#SNSマネージャー」のタグ付きツイートを確認、合格の声など一部をリツイート。
- 朝をメインとしたスキマ時間に運用。
- 次の日に残しておく情報ツイートはブックマークで管理。
- 月曜日の朝など思考力が微妙なときは、チーフの金言をピックアップしてリツイート。など
注意したい点
このタイプは、競合の情報すらも共有したくなる性分なので、ソーシャルメディアポリシーを一緒に定めながら「やってはならないNGライン」をつくっておくことが必要です。
また、すでにSNSを情報収集ツールとして使っており、それほどSNSの運用に困っているとは言えないかもしれません。だからこそ、異なるタイプの人を見て「調べればわかることなのに……なんでやらないんだろう?」と思ってしまうことも。世に出ている運用方法はたいてい、思考力系がラクになるやり方です。
思考力タイプでない方は、そもそも自分から情報収集をあまりしようとせず、受け身で入ってくる情報を得ている事が多いので、同じような運用をお願いしても難しい場合があることを理解しておきましょう。もしご自身が思考力系で、SNS運用を支援する側なら、下記の他タイプの運用方法を参考にしてください。
(2)ニコニコ友情力タイプ

オススメのSNS運用方法:
あいさつからはじまる信頼のハートフルスタイル
このタイプは他者を尊重し、困っている人を助けたいと願っています。広く浅いつきあいより、狭くても深いつきあいを好むため、発言はそれほど多くなくても、つながりの強いファンが生まれやすく、エンゲージメントが高い特徴があります。ひとつひとつの投稿が、とても丁寧だからです。
積極的な発言をしない代わりに、ファンになってくれた相手や、自分のお気に入りアカウントを巡回するのが大好きです。毎日何十件といいねを送り、真心からの称賛も労いも惜しみません。だから何の下心もなく返報性の法則が働きやすいのが、このタイプの強み。
- ちゃんと投稿するなら、自分も相手もうれしくなるものにする。
- 朝と夕方にあいさつ投稿するタイミングで、フォロワーのいいね回りも日課にする。
- 自分の投稿よりコメントでのやりとりが多め。
継続できる運用スタイルとして、この3つを意識することがオススメです。投稿に感情が乗りやすいので、リアクションが多いのも特徴です。おすすめポイントが顧客の視座になっていると、売上にもつながりやすいです。
企業アカウントで運用する際には、目的を達成するためのキーパーソンとの関係性を高めていくのがポイントです。たとえば、採用を目的に企業文化を出していきたいのなら、まずはSNSよりも社内交流を深めていくことが先決です。また、顧客との接点を深めることが目的なら、先に挙げたフォロワーの交流を密にする行動の優先順位が上がります。それによってKPIも変わるので、ある程度定量化して判断できるような仕組みを作っておきましょう。
注意したい点
友情力タイプの人はいつも気を遣っているため、仲の良いコミュニケーションができているように見えても、知らない人に声をかけていくことは苦手な場合が多く、営業的な活動ができるとは限りません。
また、良くも悪くも感情に左右されてしまうため、本人が本当にステキだと感じた商品やサービスでないと、違和感のある投稿になって本人もツラくなります。自社の商品やサービスへの違和感は「良くないこと」と思われるかもしれません。会社としても認めにくいかもしれませんが、顧客も感じている印象である場合が多いです。時間がかかるのは否めませんが、そのような違和感は改善やイノベーションのチャンスだと捉えましょう。
さらに、できるだけつながっていたいという思いが強いので、フォロワーが増えても全員に「いいね返し」を続けていると、SNS疲れを起こしてしまいやすいです。時間や件数を決めるなどのルールを決めて、SNS疲れを起こさない環境を作りましょう。
(3)カリスマ影響力タイプ

オススメのSNS運用方法:
持論を展開してファンを率いるリーダースタイル
このタイプは自分の言動によって他者を変えたいという欲求が根底にあり、実際に頼られることの多い人生を送ってきたのではないでしょうか。本来のカリスマ性を出して断言できるので、フォロワーが集まりやすいです。リアルでも大きな影響力を持っていたり、いくつも著書を出されている人は、間違いなくこのタイプ。
ファンが多い分、アンチの絶対数も多いので、ネガティブな感情を割り切れるメンタルがあります(傷つかないわけではありません)。「好きなものは好き!良いものは良い!自分はこう!」と言い切ってブレない潔さを発揮することで、インフルエンサーやYouTuberにもなれる可能性が十分にあります。「こうしたほうが良いと思います」といった弱気な発言ではなく「こうです!」と簡潔に断言できるのが強みです。
本人が納得できる目的とガイドラインを決めておけば、あとは好きなように運用してもらうのが一番ですが、SNSに慣れていない場合は下記のやり方を参考にしてください。
- 師として仰ぐアカウントを5つ選んで、投稿スタイルを自分に取り入れながら独自性を出していく(守破離の発想)。
- 一次ソースとして信頼できる情報源をもとに、わかりやすく説明する。
- 自らの情緒的価値(カワイイ、カッコイイ、信頼できるなど)を磨いて発信する。
また、文章よりも画像や動画のほうが本人の良さを出しやすいことも多いので、テキストベースのSNSだけでなく、InstagramやYouTubeなどの動画も積極的に検討してみてください。
注意したい点
影響力タイプは「自分が正しいから相手を変えたい」というスタンスなので、承認欲求が強いことも少なくありません。認められたい思いをハンドリングできないと、展開する持論が論理的でなくなったり、高圧的だったりして、逆に孤立してしまうこともありえます。これはすごくもったいないことですが、失敗を糧にする反骨精神も強いので、そのときは本人が師とする相手からの言動で反省し成長するチャンスです。ちなみに、本人が尊敬する相手からの言葉でないと響きにくいのも特徴です。
また、企業アカウントで批判的な言動をしてしまうのはブランド毀損につながってしまう恐れがあります。企業の顔で運用するより、ガイドラインを作成して会社の名前を冠した個人での運用のほうがしやすい場合もあるので、影響力タイプがSNS担当になる場合には、会社の目的を共有した上で、本人のやり方をすり合わせましょう。出る杭は真っ直ぐ伸ばしてあげるのがポイントです。
(4)コツコツ継続力タイプ

オススメのSNS運用方法:
やるべきことはやるメンテナンススタイル
継続力タイプは仕事を最後まで成し遂げることが得意な分、「終わらせないとモヤモヤする」という傾向が強く見られます。「仕事なんだからやるのが当然」というスタンスで、SNSの投稿を「タスク」としてこなしていくことに気負うこともありません。朝と夕方のあいさつや、新着情報の更新など、ルールに沿ってルーティーンで進めていくため、飽きることがほとんどないのが特徴です。
なぜ飽きないのかといえば、思考の余地がない仕組みのなかで動くことが得意だからです。継続力タイプの強みはここにあり、「自分が判断しなくてもできる仕事をバリバリこなすのが得意」なので、繰り返しやらなければならない事務作業のような仕事に長けています。数字やその日何があったかなどを継続的に記録していくことも苦にならないでしょう。
そのため、継続力タイプの運用方法は下記がポイントになります。プログラミングをイメージするとわかりやすいでしょうか。
- 投稿内容の情報源、時間、頻度、リアクション条件を明確にする。
- 毎日のフォロー対象の条件と、フォローバックの条件を明確にする。
- イレギュラー対応の確認担当者を決めておく。
- KPIを定点観測し、違和感があったら報告する。
注意したい点
他のタイプの傾向も含まれていれば、「考えながらコツコツやる」「人と関わりながらコツコツやる」「自分のためにコツコツやる」などができますが、この継続力タイプがダントツな場合、自分で考えることも、人に助けを求めることも、自分を大切にすることも苦手な傾向にあります。そのため、他のタイプからあまり理解されないケースが少なくありません。「仕事をまっとうするのはフツウのこと」と思われるかもしれませんが、その実直さや誠実さは「フツウ」の一言では済まされないくらい、命を削って取り組んでいるのがこのタイプです。
本来、100を100として効率的に継続できる能力に長けているので、効率化できていない場合は、本人が抱え込んでしまう前に課題の解像度を上げられるよう、声をかけて運用の条件を改善してください。また、突然の変更や暗黙のルールがないように支援しましょう。「継続は力なり」を十二分に発揮してくれます。
まとめ
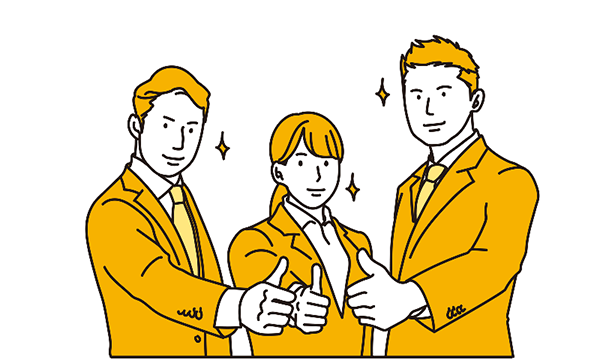
今回のパターン分けは、米国Gallup社の「ストレングスファインダー」(クリフトンストレングス・テスト)をもとに、4つの領域(戦略的思考力、人間関係構築力、影響力、実行力)を簡易的に診断して、それぞれの欲求やコミュニケーション傾向からSNSの取り組み方をまとめたものです。
パフォーマンスアップできる方法は個人によって異なりますが、どのような方法であっても、目的は達成できます。逆に、自分には合わないやり方でやれと言われても、努力した割には成果があまり出なかった、という事態になりかねません。
SNSの運用目的はさまざまですが、企業なら最終的に売上につなげたいという思いはあるでしょう。業務時間の工数を割いているのですから、成果を期待するのは当然の思いです。ただ、SNSでは「情報を得たから欲しくなる」人よりも、「心を動かされたから欲しくなる」人のほうが多いので、「売り手よし・買い手よし・世間よし」という商売の原点に還るような、仕事に喜びを感じられるコミュニケーションを大切にしてみませんか。
商品やサービスに思い入れの強い社長がSNSの担当をするのは王道ですし、効果的です。だからこそ同じように、理念に則った情熱をスタッフにも共感してもらい、SNSの運用をチームで自走させたいですよね。今回の記事を参考に、チームの体制を整えてみてください。
小杉でした(/・ω・)/
2020年より私たちは、「SNSマネージャー養成講座」という資格試験をスタートしました。SNSマネージャーの上位資格である上級講座では、実際に運用しているアカウントをサンプルにして、徹底的に運用目的とKPIなどの必要項目を掘り下げて企画書を作成するワークを実施しています。
この記事を読んで「理屈はわかったけど、実際自社のアカウントに当てはめるとピンと来ない。さてどうしたものか……」とお悩みのあなた。ぜひチャレンジを。
タイトルデザイン、タイトルイラスト:995(Twitterアカウント)
三度の飯より猫が好きなイラストレーター。ゆるくてかわいいイラストが得意です。