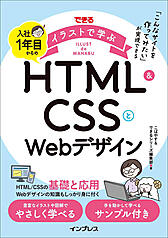Aggregator
Googleがテレビ番組をただのコンテンツに変える日
ページ分割したときの1ページの長さは5スクロール分が最適
- ページ分割したときの1ページの長さは5スクロール分が最適 -
Posted on: 海外SEO情報ブログ - SuzukiKenichi.COM
[基本]アクセス解析活用の「二つの成熟度」
カンヌのサイバー、フォルクスワーゲンなどに栄冠
------------------------------
Volkswagen - The Fun Theory
http://www.adqualifier.com/cannes2010/thefuntheory/
Nike Livestrong Foundation
http://nosharpstuff.com/awardsites/overview/nike/cha/
------------------------------
受賞広告の解説は、福田敏也氏のブログが詳しい。
------------------------------
Cyber Lions 決定!
http://ameblo.jp/toshiyafukuda/entry-10572042785.html
Cyber Lions 金賞受賞作
http://ameblo.jp/toshiyafukuda/entry-10572548449.html
Cyber Lions 金賞受賞作2
http://ameblo.jp/toshiyafukuda/entry-10573116065.html
------------------------------
第一回 “キズナの会” 開催
6月25日の金曜日、予定から1ヶ月ほど遅れて第一回キズナの会@おまっとさん “絆” を実施して来ましたっ!

※みんな酔っ払って顔が真っ赤だったので会場の写真掲載は見送りましたw
この会は、スケダチ高広さんの助言によって企画されたもので(⇒「キズナの会」を開催します)、今回が第一回目。先のブログで告知して、先着約20名の方が参加してくださいました。
特に企画モノなどはしなかったので、本当にただの飲み会になってしまいましたが、1次会が終わっても2割くらいの方しか帰らず、そのまま2次会へ。しかし、前日のサッカー日本代表戦の疲れから、3時くらいにはほぼ全員がグロッキー状態w
皆さまと均等にお話することができなかったことが心残りですが、すっごく楽しかったです!(話題の中心がソーシャルメディアとかマーケティングじゃなく、終始シモネタ方面に向かって行ったのは、僕のせいじゃなく @husaosan と エロヒゲブランディング男 @groundcolor のせいだと思います!)
ご参加頂いた皆さま、ありがとうございました!(この続きはFacebookで!)
第2回目の企画が固まったらまた本ブログで告知致します。皆さん、ぜひ一杯飲み交わしましょう♪
SoftBank 「みんなの味方有吉弘行のホームページ」
Google Analytics 導入セミナーのお知らせ ~ 2010 年 6 月
Posted by オンラインビジネス ソリューション チーム
本日は、6 月 30 日開催予定の無料オンラインセミナー 『AdWords と一緒に使おう! Google Analytics 1 - 導入編』のご紹介をいたします。
Google では AdWords の効果的な運用方法や操作方法などをご紹介するセミナーを定期的に開催しております。来週は、Google Analytics をこれから導入しようとお考えのみなさまを対象に、下記セミナーを開催いたします。すでに導入済みの方の復習にもお役立ていただける内容ですので、是非この機会にセミナーにご参加ください。
『AdWords と一緒に使おう! Google Analytics 1 - 導入編』
2010 年 6 月 30 日 (水) 17:00 - 18:00 [お申し込み]
なお、「AdWords オンライン教室」 にて、いつでも最新の AdWords セミナー情報をご確認いただけますので、あわせてご利用ください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
有吉弘行のホームページ
Google Appsではじめるオフィス・イノベーションを読んだ
プロが教えるGoogle Analytics実践テクニックを読んだ
米メール・マーケティング、独立記念日向けが上昇
新連載3本とイベントのお知らせ
HCD-Netフォーラム2010「User Experienceが切り開くHCDの未来」
2010年フォーラムを開催いたします。
今年のテーマは「User Experienceが切り開くHCDの未来」です。
皆様のご参加をお待ちしております。
●日 時: 2010年6月12日(土)
・フォーラム 午後1時~5時30分
・交流会 6時~8時
●場 所: 東海大学 高輪校舎 4号館2階 4201教室
http://www.u-tokai.ac.jp/info/traffic_map/shared/pdf/takanawa_campus.pdf
●主 催: NPO法人人間中心設計推進機構
●協 賛: ヒューマンインタフェース学会
●主 旨:
「User Experience」(UX)という捉え方が開発者に浸透してきたが、言葉から得られる印象は抽象的で幅が広く、人によって描くイメージは様々である。
UXの現在の主流は、情報やサービスの提供を受けるユーザーがよりよい体験をすることを目指しており、この実現のためには、情報やサービスを提供する側の意識改革や手段の工夫、顧客との連携なども必要である。
UXを通じて高い利用者満足度を達成することが大切であり、「UXの生産性の向上」を意識する時代になったといえよう。その上で、ビジネスにおける顧客満足度の達成、サービス生産性の向上に繋がることが期待される。
こうした状況を踏まえ、さらに産業界の日々の活動にUXを有効に機能させるために、規格から具体的な取り組み方までの最新の話題を提供し、議論する機会を設ける。
●プログラム:
総合司会:安藤 千賀
12:30~ 受付
13:00~13:10 はじめに 早川 誠二 (HCD-Net副理事長)
13:10~14:40 User Experienceとサービス原則 北島 宗雄氏(産業技術総合研究所)
概要:人間の行動選択は、Experiential Processing SystemとRational ProcessingSystemの2つのシステム(Two Mindsと呼ばれる)が状況に依存して生成する反応の結果として捉えることができる。サービスの一形態であるユーザエクスペリエンスによりサービス受容者に高い満足度を経験させるためには、サービス受容時にTwo Mindsがどのように働くのかを適切に理解することが必要である。本講演では、その理解のための基盤であるMHP/RT(Model Human Processor with Real Time Constraints)、ならびにMHP/RTに立脚したサービス受容者理解のための方法である認知的クロノエスノグラフィー(CCE; Cognitive Chrono-Ethnography)を紹介する。また、CCE調査の結果を利用してサービス受容者の満足度に関与できることを示す。
14:40~14:55 総会報告 鱗原 晴彦 (HCD-Net事務局長)
14:55~15:05 パラレルセッション紹介
<パラレルセッションとセッションリーダー・プレゼンター>
【セッションA】 サービス利用者のUX計測・モデル化の事例
15:30~17:30 4201教室
北島 宗雄氏(独立行政法人産業技術総合研究所)
田平 博嗣氏(株式会社U’eyes Design)
概要:顧客の消費体験と満足度との関係を構造的に把握することが、ユーザエクスペリエンスを実現するサービス設計への重要な手掛かりとなる。
本セッションでは、消費傾向や計測条件が異なる2つの集客フィールド(プロ野球観戦と温泉旅行)を中心に、※認知的クロノエスノグラフィー(CCE)を適用した事例を示し、その効果について述べる。
※平成21年度人間工学会「大島正光賞」受賞
※The 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure.
25-30 May 2010,Cappadocia,Turkey.「Best Research Paper」受賞
【セッションB】 ユーザエクスペリエンス(UX)から実利用経験(RUX)へ
- ISO13407からISO9241-210への改訂に寄せて
15:30~17:30 4204教室
黒須 正明(HCD-Net理事長)
安藤 昌也(HCD-Net理事)
概要:Part 1・UXを議論するための基礎として、その歴史的経緯(ユーザビリティ関連とマーケティング関連)を確認する。
・消費者とユーザーという経験者の変化を区別する必要性を述べる。
・ISO9241-11とISO13407とISO9241-210はUXといかなる関係にあるか。
・設計と開発、ライフサイクルというスコープの拡大とUX
・ユーザビリティテストはUXを測定しているのか。
・長期的ユーザビリティという概念とSwedenのUsers Awardの試みについて。
・実利用経験(rUX, realUX)という考え方、その広告業界、製造業・サービス業界などへの波及効果とユーザーの受益性。
概要:Part 2
・実利用経験のUX評価とはどういうものか:最新の研究成果から
・UX評価を高めるための、戦略的考え方
・“ユーザーを導くデザイン”を目指して
【セッションC】 アドバンストデザインにおけるUXアプローチ
15:30~17:30 4205教室
松原 幸行(HCD-Net理事)
畑中 元秀氏(takram design engineering)
石黒 猛氏(石黒猛事務所)
概要:新たな情報による気づきや相互触発による新しいモノコトのアイデア展開をリアルタイムで行う。
畑中氏・石黒氏がアドバンストデザインにおけるアイデア展開作業を公開で行い,提言をまとめる。
オーディエンスは,実際の作業過程を見ることで,アドバンストデザインのアプローチをリアルに体感することができる。
テーマは誰もが身近に感じられる「自転車」と「東京」。エコの時代に注目される自転車を東京で活かしていくための様々なアイデアを展開する。
【セッションD】 アジャイルUXの潮流
15:30~17:30 4206教室
樽本 徹也(HCD-Net理事)
川口 恭伸氏(株式会社QUICK)
概要:Part1はHCD実務家のためのアジャイル開発の入門講座です。代表的な手法である「スクラム」のエッセンスをワークショップ形式で解説します。
Part2ではHCD実務家がアジャイル開発チームとスムーズに協働作業するための基本的な概念と手法について、アジャイルHCDのミニヒストリーや最新情報も交えて解説します。
Part3では総括として、参加者全員で情報共有を行います。
<交流会>
18:00~
交流会の場で各セッションの結果概要を報告します。ふるってご参加ください。
●参加費用:
・フォーラム 会員3,000円 (3500) 一般5,000円 (5500) 学生 1000円 (1500)
・交流会 会員4,000円 (4500) 一般6,000円 (6500)
※参加費は事前振込をお願いいたします。当日支払いの場合は( )内の金額となります。
※参加費支払い方法については参加受付メールでご案内します
※請求書が必要な場合は申込のメールにその旨と郵送先の記載をお願いいたします。
●定員: 150名
●参加申込:
メールタイトルを「HCD-Netフォーラム2010」参加申込み」として
①氏名 ②所属 ③メールアドレス④会員区分(一般,一般学生,正会員,賛助会員,
学生会員)
⑤懇親会の参加の有無、を本文に記入し,
hcdnet_registration@hcdnet.orgまでメールでお申込みください。
※当日申し込みの場合、お席が確保できないことがあります。
辛島です。
フォーラムの際の校舎入口に立て看板をだすならば、
立て看板のサイズはA1判を縦に2列にならべたサイズだそうです。
必要であれば手配いたしますので、文面、レイアウトをお知らせください。
通路に設置する誘導用パネル3枚、各会場入り口に設置する会場用案内パネル4枚は手配いたしました。
Wifiは今のところ難しいです。
マイクについては現状の各部屋ワイヤレスマイク1本、ピンマイク1本計2本以上には増設できないそうです。
御報告まで。
辛島光彦
教授
東海大学情報通信学部経営システム工学科
(東海大学大学院工学研究科経営工学専攻)
TEL 03-3441-1171内線1320
FAX 03-5475-7156
去る6月12日(土)に、東海大学高輪校舎にて、HCD-Netフォーラム2010が開催されました。週末にも関わらず140名を超す参加者がありまし た。フォーラムは、「User Experience(UX)が切り開くHCDの未来」をテーマに、Ⅰ部の基調講演、Ⅱ部のパラレルセッション、Ⅲ部の交流会で構成され、基調講演は、産業技術総合研究所の北島先生から「サービス利用者のUX計測・モデル化の事例」のお話しがありました。また、パラレルセッションは4つのテーマ(下記プログラム参照) に分かれ、ワークショップや討議が行われました。パラレルセッションの各テーマは、後日、個別にセミナーを中心にリピート企画を予定しています。


ネットイヤーグループと電通が業務提携
JIAAが行動ターゲティング広告ガイドラインを公開
JIAA、行動ターゲティング広告ガイドラインを改定
企業のTwitter運営ポリシーを9つの視点から考える
------------------------------
企業のTwitter運営ポリシーを9つの視点から考える(その1)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmg/20100420/214090/
- 1. 自動一斉配信型
- 2. 手動一斉配信型
- 3. 手動雑談型
企業のTwitter運営ポリシーを9つの視点から考える(その2)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmg/20100511/214334/
- 4. パッシブサポート型
- 5. パッシブ雑談型
企業のTwitter運営ポリシーを9つの視点から考える(その3)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmg/20100525/214578/
- 6. アクティブサポート型
- 7. アクティブ雑談型
企業のTwitter運営ポリシーを9つの視点から考える(その4)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmg/20100608/214832/
- 8. 自動パッシブ返信型
企業のTwitter運営ポリシーを9つの視点から考える(その5)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmg/20100622/215086/
- 9. 自動アクティブ送信型
------------------------------
電通、電通ネットイヤーアビームを完全子会社化
------------------------------
電通ネットイヤーアビーム
http://www.dentsu-n-a.co.jp/
電通コンサルティング
http://www.dentsuconsulting.com/
------------------------------
同時に、ネットイヤーグループと電通は、次世代マーケティング領域における戦略コンサルティングサービスで業務提携することも発表。