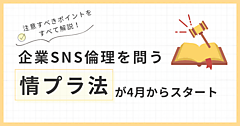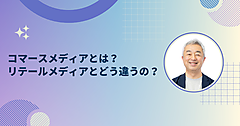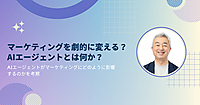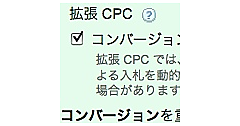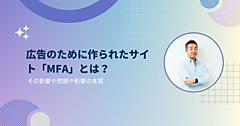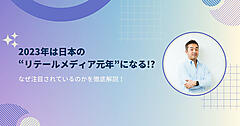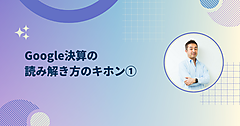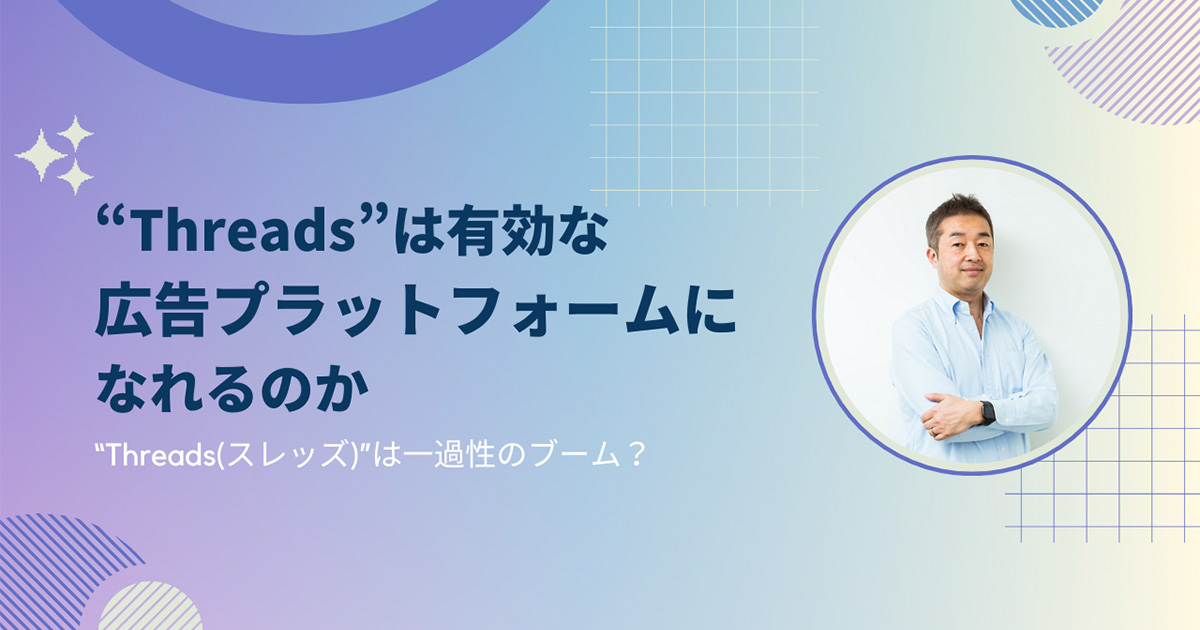
Threadsが早くも1億ユーザーを突破
米Metaが「テキストでつながる新しいアプリ」というコンセプトで、ソーシャルメディア「Threads(スレッズ)」の提供を開始しました。サービス開始からわずか5日間で1億ユーザーを突破しました。OpenAIが提供する「ChatGPT」の公開から2カ月で利用者が1億人に到達したのと比較しても、驚異的なスピードで成長していることがわかります。
これには、Twitterから真剣に乗り換えようとしている人もいれば、大きな話題になっているので乗り遅れないように取り急ぎアカウントだけ作成しておこうという人など、さまざまな背景があると思われます。
ThreadsとTwitterはどこが違う?
ThreadsとTwitterの2023年7月12日時点での機能比較をしてみよう。
| Threads | ||
|---|---|---|
| 投稿できる文字数 | 500文字 | 240文字 |
| 文字装飾 | 不可 | 太字・斜体 |
| リンク | 可 | 可 |
| 画像 | 可 | 可 |
| 動画 | 最長5分 | 最長2分20秒 (ツイッターブルーでは120分以内、8GB以内) |
| 投稿の編集 | 不可 | 不可 (ツイッターブルーで投稿後1時間は可能) |
| 投稿の削除 | 可 | 可 |
| ダイレクトメッセージ | なし(実装予定) | あり |
| トレンド機能 | なし(実装予定) | あり |
| ハッシュタグ機能 | なし | あり |
| 検索 | なし(実装予定) | あり |
| 認証マーク | あり(Instagram経由) | なし (ツイッターブルー他一部アカウントではあり) |
| 他のプラットフォームとの相互運用 | あり (ActivePub実装予定) | なし |
ご覧のように基本的な機能に関しては大きな差はありません。すでに米国の大手の広告主にはダイレクトメッセージ、トレンド機能、検索機能は実装予定と話しているようなので、こちらは時間の問題です。
差別化のキーはFediverseか
ThreadsとTwitterで違う点は、今後実装される予定の他のプラットフォームとの相互運用機能です。Threadsは「ActivityPub」という、非中央集権型の分散 SNS のオープン標準プロトコル(通信手順)を採用する予定です。ActivityPubという共通の仕組みを使うことで、Mastodon、Misskeyなど他のプラットフォームにいるユーザーが行う投稿にいいね!やコメントなどを、あたかも自社のユーザーがやっているように取り扱うことができます。
このように、ActivityPubのような技術や仕組みを用いて互いにつながり合うサーバー同士のネットワークのことを「Fediverse(フェディバース)」と言います。Fediverseは「連合(federation)」と「世界(universe)」を組み合わせたかばん語なのですが、“ソーシャルメディア連合”と呼ぶとわかりやすくていいかもしれません。
- Fediverseについての説明は、こちらの動画がわかりやすいです(英語)Distributed social media - Mastodon & Fediverse Explained
Threads単体としてユーザーを増やしていくことも大事ですが、Fediverseの中心的な存在として他のプラットフォームをどんどん巻き込み、連合体としてのユーザーを増やしていくことでさまざまなユーザーを取り込むことができますし、プラットフォームの活性化に寄与すると思われます。
広告はいつ始まる?
Twitterの広告出稿を取り下げた広告主としては、Threadsにおける広告展開があるのかが気になるところでしょう。
MetaのCEOのマーク・ザッカーバーグ氏は自らのThreadsの投稿で「私たちのアプローチは、他の全ての製品と同じです。まず製品をうまく機能させ、次に10億人への明確な道筋をつけることができるかどうかを確認し、その時点で初めて収益化を考えるのです」と説明しています。
よって、広告展開については確実に行うと考えてよいと思いますが、問題はいつ頃開始するのかになるでしょう。
MetaはFacebook、Instagramの両プラットフォームの収益化を支える強力な広告プラットフォーム、さらには、その営業網をすでに持っています。広告プラットフォームをスクラッチから開発するのには、莫大な費用と時間がかかります。広告を売る営業部隊や広告代理店などの外部パートナーをリクルーティングするのも時間がかかります。この点に関しては他の新興SNSと比較しても大きなアドバンテージです。この観点では実質「いつでも」広告展開は可能ということになります。
冒頭に書いたユーザー数が記録的な勢いで伸びている点は素晴らしいですし、10億人への道筋もある程度立っていると思いますが、ユーザーはたくさんいても、プラットフォームを積極的に使っているユーザーが少なく、フィードも閑散としている場合、広告の掲載場所としては好ましくありません。ですので、10億人は表面的な数字でもあり一つの目安ではありますが、今後、注視していくべきはDAU(デイリー(1日の)アクティブユーザー)またはMAU(マンスリー(月間)アクティブユーザー)の数の推移でしょう。
では、アクティブなプラットフォームをどのように作るのでしょうか。前述のActivityPubによるSNS連合で、プラットフォームを気にせずにユーザー間のエンゲージメントを増やすのは一つの戦略でしょう。Threadsとしても企業やインフルエンサーをいかに取り込んでいくかも推進していくはずです。
Instagramの責任者であるアダム・モセリ氏も、自らのThreadsで興味深いコメントをしています。
Threadsは、Twitterに取って代わることが目的ではありません。InstagramのコミュニティがTwitterを受け入れなかったり、Twitter(や他のプラットフォーム)のコミュニティがあまり怒りのない会話の場に興味を持っていたりする場合に、公共の広場のようなものを作ることが目的です。政治や難しいニュースがスレッドに現れるのは避けられませんし、Instagramでもある程度はそうなっていますが、そこを盛り上げようとは考えていません(アダム・モセリ氏)
Threadsが目指しているのは、ユーザーにとって「怒りのない、やさしい公共の場」である、と捉えることができます。また、Metaの既存の広告主に対して、Threadsというプラットフォームは、ブランドとユーザーがコントロールしあえる場所であると強調しているそうです。自社の広告が、ブランド価値を毀損する不適切な投稿の側に掲載されることは、どの企業も避けたいものです。
つまりThreadsが、ユーザーにとっては「“怒りのない、やさしい”場」であり、広告主や企業にとっては「“ブランドを守り、安全性を確保できる”場」になり得ると仮定すると、広告主にとって魅力的なアクティブユーザー数が担保できた頃が、広告を展開し始める時期になるでしょう。
その世界観を実現するには多くの壁に直面していくと思われますが、プラットフォームがどのように成長していくのか、今後がとても楽しみです。