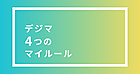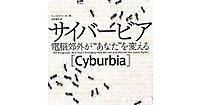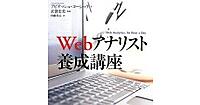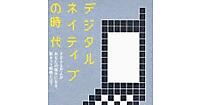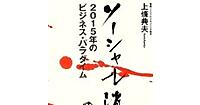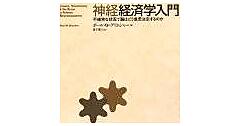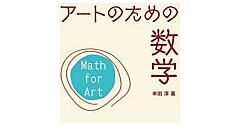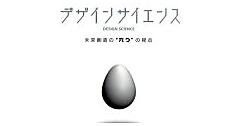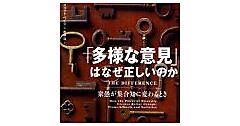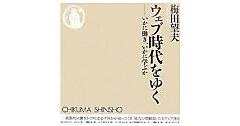BOOK REVIEW ウェブ担当者なら読んでおきたいこの1冊
『ネットはテレビをどう呑みこむのか?』
森山 和道(サイエンスライター)
「放送と通信の融合」が進んだら、何が変わるのだろうか?
来るべき時代をネット視点で見つつ、多くの問題を提起する

- 歌田 明弘 著
- ISBN:978-4-7561-4933-6
- 定価:本体724円+税
- アスキー新書
もし本当に「放送と通信の融合」が進んだら、テレビのコンテンツはネットのほかのコンテンツとまったく同列に配信されることになると本書は指摘する。
YouTubeはワーナー・ミュージック・グループ、NBCユニバーサル、CBSなど大手メディア企業を納得させ、コンテンツの利用を認めさせた。結果オーライのような強引なやり方だが、一般の利用者が大手企業のコンテンツを利用する道をこじ開けつつあることは認めざるを得ない。
一方、民放の広告モデルは崩壊の兆しを見せている。テレビの利用時間も減少傾向にあり、キー局と系列局との間の関係も徐々に変化し始めた。そもそもブロードバンド時代を迎え、テレビモニターに映像を送り出せるのがテレビ局だけだった状況は崩れ始めている。これまでとは異なるビジネスモデルが必要であることは間違いない。
また、ホリエモンが語ったように、スクープや一次情報の経済的価値は暴落し、儲からないものになっている。著者によれば、多くの閲覧者は一次情報を得ることに誰かがコストを払っていることに意識を向けることもなくなりつつあるという。コンテンツ製作者のことは省みられなくなりつつあるのだ。
本書は、雑誌「週刊アスキー」連載を抜粋、まとめたものである。そのため内容のなかには、やや古く感じるものもある。また本書の内容すべてが「ネットとマスメディア」に関わるものとも言えない。特に著者の連続ドラマの見方に関するくだりは贔屓目に見ても単なる個人的思い込みとしか読めず、ブログで読むにはいいかもしれないが、書籍で読むには退屈だ。
しかしながら、現在のメディア環境をネット視点で見た本書は、実に多くの問題提起が行われており、目を通しておくべき一冊である。たとえば電子的なテレビ番組表を出す「リモコン」が手元にあればおもしろいといったネタ的話題に反応する読者もいるだろうし、放送局のビジネスモデルに興味がある読者もいるだろう。
特に、ネット世論との距離感の難しさの話は興味深い。いま、マスメディアは「みんなのネット」に呑みこまれつつある。少なくともそういう見方がある。著者は「直接民主主義的」なネットの世界で報道機関が直接的な反応に耐えられるかと投げかけている。
ネット世論は過熱しやすく、冷めやすい。何よりも怖いのは「『ふつうの人々』の過剰な反応」だという。また急速にネットは狭くなりつつあり、多様性や独立性、分散性を失い、一様な世論を形成しやすい。今やネットリテラシーとは巧みに多数派を形成する、あるいは多数派でいることだと考える学生がいるという話にもうなずける。報道機関がどれだけ主張の正しさに自信を持っていても、感情的猛反発が最初からわかっていたら、どうしても躊躇してしまうのではないか。報道機関といえども部数が伸びなければ経営が成り立たないし、何より個人の集団から成り立っているからだ。
ぶれないでいること、そのためのシステムを作ることは、いつも難しい。