
読者から寄せられた仕事の悩みをウェブパンが代わって解決するパン! 今回はSEO施策の支援側の悩みを解決するパン!
読者からのお悩みを解決するパン!
読者のお悩み
SEO支援会社で働いています。最近思っていることとして「クライアント側の事業者が日常のマーケティング活動をやらないと、SEO(コンテンツSEO)ができない、やる意味がない」というものがあります。実際のところはどうなのか、教えてほしいです。
(ペンネーム: 匿名)

お便りありがとうパン!
SEO支援会社のso.la 代表・辻正浩さんに相談してみるパン!


ウェブパン、いらっしゃい! 私がそのお悩みを解決しましょう!
SEO施策の8つの分類

SEOをやるには、日常のマーケティング活動が必要なのパン?

必ずしもそうとは言えないと思います。まずは、企業のWeb担当者がSEOのために行うことを整理してみましょうか。
検索エンジンとのより良い関係を目指すには、次の8つのSEO施策に分類できるでしょう。
| カテゴリ | SEO施策 | 概要 |
|---|---|---|
| 方針策定 | 全体方針策定 | SEOで行うことの洗い出しや優先度、重み付けなどの策定を行う。 |
| 方針策定 | キーワードマーケティング | 検索ニーズや検索結果状況の把握と成果貢献の予測などを行い、具体的な施策の策定につなげる。 |
| コンテンツ関連 | 新規コンテンツ作成 | 自社の価値やリソース、検索ニーズなどを元に、公開するコンテンツの作成を行う。 |
| コンテンツ関連 | 既存コンテンツ改善 | 自社の価値やリソース、検索ニーズなどを元に、既存コンテンツの改善を行う。 |
| 技術 | テクニカルSEO | 検索エンジンがサイトを適切な形で評価することを主な目的とした、技術面の改善を行う。 |
| Web制作関連 | SEO観点でのユーザ行動改善 | 検索流入の増加や、検索流入後の成果率の向上を目的としたサイト改善を行う。 |
| Web制作関連 | SEO観点でのパフォーマンス改善 | Core Web Vitalsなど、検索エンジンの評価に影響するWebパフォーマンスの向上を行う。 |
| 外部施策 | 外部対応 | 検索エンジンを意識した自社サイト外部の対応をして、ネット上でのサイト評価・ブランド評価の構築を行う。 |

ひとつずつ説明しますね。
方針策定1全体方針策定
さまざまな分析をしたうえで、SEOの方針を決める方針策定です。
方針策定2キーワードマーケティング
自社が関わる領域での情報ニーズの調査と、その情報がどのように探されているかを「キーワード調査」として調べることです。
単なる思いつきや、アクセス解析やツールに頼って発見できるキーワードと、そのかけ合わせだけではなく、幅広い情報ソースから調査したいものです。検索語句に現れる顕在ニーズ量から、潜在ニーズの量を汲み取るような調査もしたいですね。
また、今それらの情報ニーズに自社がどれくらい対応できているのか調査することも、この施策に入るでしょう。
コンテンツ関連1新規コンテンツ作成
新規にコンテンツを作ります。コンテンツとは、記事に限らず動画やシステムの場合もあります。何らかの価値をWebサイトに加えていく作業になります。もしWebサイトに検索されるような価値が足りない場合には必須項目です。
コンテンツ関連2既存コンテンツ改善
コンテンツ自体を修正するだけでなく、コンテンツへの動線を強化することも含みます。既存の価値が十分にあるWebサイトの場合では、新規コンテンツの作成よりも効率的で効果的なことが多い項目です。
技術テクニカルSEO
技術的なアプローチでのSEOです。ページのmeta要素部分の調整やrobots.txtなど小さな部分から、システムの改修など大きな部分まで関わるので、やり方は多様です。特に、データベースと連動した大きなシステムが動いているWebサイトでは技術面が重要です。
Web制作関連1
SEO観点でのユーザ行動改善
Web制作やアクセス解析などの領域として取り組まれるところかもしれませんが、数年前からはSEOにも影響が大きくなった分野です。
ただし「検索流入を上げるうえで重要なユーザ満足の改善ポイント」と「一般的なユーザ満足改善」は異なる場合が多いです。そのため、SEOの視点でも調査・改善に取り組む必要があります。
Web制作関連2
SEO観点でのパフォーマンス改善
サーバーの応答速度や表示、体験についてもSEOに影響します。ここ数年ではCore Web Vitalsだけが注目されがちですが、この指標に出ない領域でもSEOに影響する部分は多くあります。
外部施策外部対応
「被リンク」で注目されがちな部分ですね。昔に比べると影響力は落ちましたが、いまでも大きな指標です。各種SNSやGoogle ビジネスプロフィールなど検索エンジンに影響する外部サービスの活用・連携を行うことも、この領域にあてはまります。
最近ではリンク先で、どのように自社サイト・ブランドが扱われているのか、その視点で取り組む必要もでてきました。

SEO施策では何が重要?

Web担当者がSEOのためにやる施策って、こんなにもあるパンね……。

すべてに取り組むことが理想的ですが、そんなことは現実的に難しいです。私も膨大な数のWebサイトのSEOに関わってきましたが、ぜんぶに取り組めた経験はありません。
だからこそ優先順位が重要になります。重要なものを3つ選ぶとしたら、どれを選びますか?
| カテゴリ | SEO施策 | 概要 |
|---|---|---|
| 方針策定 | 全体方針策定 | SEOで行うことの洗い出しや優先度、重み付けなどの策定を行う。 |
| 方針策定 | キーワードマーケティング | 検索ニーズや検索結果状況の把握と成果貢献の予測などを行い、具体的な施策の策定につなげる。 |
| コンテンツ関連 | 新規コンテンツ作成 | 自社の価値やリソース、検索ニーズなどを元に、公開するコンテンツの作成を行う。 |
| コンテンツ関連 | 既存コンテンツ改善 | 自社の価値やリソース、検索ニーズなどを元に、既存コンテンツの改善を行う。 |
| 技術 | テクニカルSEO | 検索エンジンがサイトを適切な形で評価することを主な目的とした、技術面の改善を行う。 |
| Web制作関連 | SEO観点でのユーザ行動改善 | 検索流入の増加や、検索流入後の成果率の向上を目的としたサイト改善を行う。 |
| Web制作関連 | SEO観点でのパフォーマンス改善 | Core Web Vitalsなど、検索エンジンの評価に影響するWebパフォーマンスの向上を行う。 |
| 外部施策 | 外部対応 | 検索エンジンを意識した自社サイト外部の対応をして、ネット上でのサイト評価・ブランド評価の構築を行う。 |

え、3つ!?
「全体方針策定」を間違えるとムダになりそうだし、アクセスがあっても成果にならないと意味がないから「SEO観点でのユーザ行動指標改善」も重要そうパン。あとはコンテンツ関連や技術面も外せなさそうパン。うーん……。

じつは、明確に「これが重要」と決められるものではありません。重要性はWebサイトによって全く異なるからです。

Webサイトによって、どう異なるパン?

たとえば、数ページしかない小規模なサイトで「テクニカルSEO」を頑張っても成果が出ないことが多く、そういうサイトには「新規コンテンツ作成」が重要です。
検索流入はあるけれども成果につながらないときには、「新規コンテンツ作成」よりも他の施策のほうが重要です。「キーワードマーケティング」が見当外れかもしれませんし、「SEO観点でのユーザ行動改善」が必要かもしれません。
巨大なユーザ投稿型サイトなどでは「テクニカルSEO」が重要になることが多く、「キーワードマーケティング」の重要性は下がります。
「全体方針策定」はたしかに重要ですが、しかしそれがないからといってSEOができないわけではありません。
私は大企業のお手伝いをする際は、全体方針を打ち出す前に、あえて「既存コンテンツ改善」「テクニカルSEO」など、簡単に対応できる施策から始めることもあります。ひとまず成果を上げ、協力が得られるようになってから方針についてディスカッションしたほうが、スムーズに進むんです。

なるほど、Webサイトの種類や現状で重要度は大きく変わるパンね。

ただ気をつけたいのは、優先順位が高い施策に取り組んでいたとしても、ちょっとしたミスで台無しになることもあります。
たとえば、非常に力を入れて「新規コンテンツ作成」をしたものの「テクニカルSEO」がダメで、すべてが無駄になることもあります。
- 全ページにcanonicalの設定を間違えていた
- 本文が検索エンジンが認識しづらい形のJavaScriptで生成されていた
などは、私も数え切れないほど体験しましたし、次のような誤りを何度も見てきました。
- noindexで検索を拒否していた
- robots.txtでブロックしていた
ほかにも「新規コンテンツ作成」をしても、「既存コンテンツ改善」がされていないため検索流入減少のほうが大きくなるメディアサイトは多くありますし、普通は直接の検索流入に影響しづらく軽視されがちな「SEO観点でのパフォーマンス改善」も、極端に悪い数値だった場合には大幅に検索流入を落とすことになります。
「外部対応」が全く考えられておらず、サイト単位の評価が一定以上に伸びず、突然大きく落ちるというケースもコアアップデートのたびに見られます。

Web担当者Forumも既存コンテンツの改善が必要パンね……。

そうなんです。いろいろと例を話してきましたが、まとめると、次の2点になります。
- SEO施策の重要度はその時々で違う
- 重要度は低くても無視して良いSEO施策は滅多にない
SEOは長所を伸ばすべき? それとも短所を補うべき?

話を戻すけど、相談者の「事業者が日常のマーケティング活動をやらないと、コンテンツSEOは意味がないのでは?」という疑問について、辻さんはどう考えるパン?

「日々のマーケティング活動」という表現は広範囲ですが、たとえば自分の商品やサービスが選ばれる最低限の状態になっていないと他の施策が無意味になってしまうことは、たしかです。
Webサイト、もしくはブランドの評価が検索エンジンに伝わっていないと、コンテンツをどんどん作ったとしても良い成果に結びつきづらいものですし、今のアルゴリズムでは順位が伸びづらいものです。
そういった意味で「日常のマーケティング活動がないならコンテンツSEOをやる意味がない」というのは、その通りだと思います。
ただ同様に、次の状況も正しいです。
- 最低限のテクニカルSEOをやらないと他のSEOをやる意味がない
- 最低限の検索されるコンテンツを作らないと他のSEOをやる意味がない
- 最低限の成果率を上げないと他のSEOをやる意味がない
「まずは正常にindexされ、最低限の検索されるコンテンツがあり、最低限のコンバージョン動線がないと、SEO施策を進める意味はない」と言い切って良いでしょう。
ここで重要なのは“最低限”ということ。多くの領域で最低限の部分ができてはじめて土俵に登れるものです。
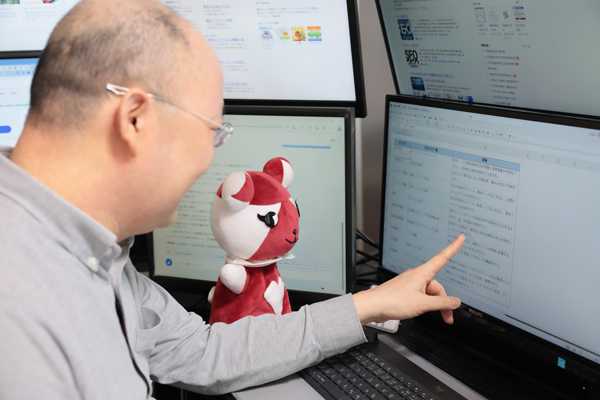

どの施策も最低限行うのがポイントってことパンね。
辻さんは「SEOは長所を伸ばすことと、短所を補うこと」、どっちが大事だと思うパン……?

自信を持って「長所を伸ばすべき」と答えます。
多くの場合、劣っている部分をがんばって競合と同程度にしても大きな価値にはなりません。競合より明らかに勝っている部分をより明確に伝えるように、検索に活かせるようにするほうが効果に結びつくものです。
ただし、極端な短所がないことが前提です。最低限の問題解決をしたうえで、Webサイトや会社にあった長所につながりやすい領域を伸ばしていくべきです。
今回挙げた8つの分類の中で、極端に弱い部分があるのであれば、まずはそこを手当てしていきましょう。そういう部分は、比較的工数が少なめで効果に結びつくことが多いです。
また最初からすべての項目で十分に進められないことも多いと思います。段階的にでも進めていくことをお考えください。

SEOには「これさえやれば伸びる!」といった魔法のテクニックはなく、地道に取り組んでいくしかないパンね。
SEOの支援側の皆さんに、辻さんからのメッセージ

支援側の中には、事業者側の対応が理想的ではないことで悩まれている方もいると思います。
事業者側が動かないのには相応の理由があるものです。事業者側のリソースをもらえるかどうかは、支援側の腕の見せ所です。
私も支援側として入った当初は担当者以外からは“怪しいSEO業者”と警戒されがちですし、あまり協力してもらえずリソースをもらえない状態から始まることも多いです。その状態で事業全体に関わる「日々のマーケティング」を語っても響かないでしょう。
まずは小さくても成果を出すことです。そうすると信頼されるようになって、大きなリソースをもらえるようになるものです。事業にほぼ影響しないWebサイトの細かい部分、ユーザ動線にも影響しない所しか触らせてもらえない状態から、サイト名変更や会社の体制の調整などに踏み込んでいけるようになります。
事業者側に動いてもらえないならば、それだけの説得力をつけるように努力するべきだと思います。どうぞがんばってください。
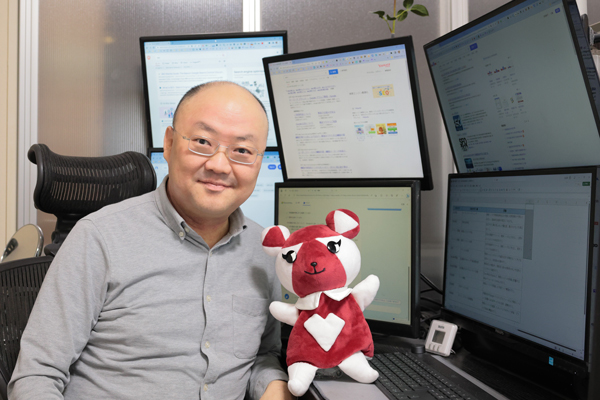

お悩み解決できたかな?
「Web担当者Forum」では今後も読者のお悩みを解決するために頑張るパン!
















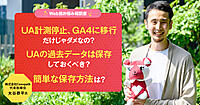

 1974年北海道生まれ。営業、広告・Web制作を経てSEOの専門家として活動を始めた後、2011年に独立。株式会社so.la代表としてさまざまな規模・種別・業界のWebサイトのSEOに関わっている。特に大規模サイトの対応を得意としており、多数の日本有数の巨大サイトのSEO担当として検索流入拡大に取り組んでいる。 Webマスターと検索ユーザー、検索エンジンの三者が利益を受けるSEOを信条に活動中。
1974年北海道生まれ。営業、広告・Web制作を経てSEOの専門家として活動を始めた後、2011年に独立。株式会社so.la代表としてさまざまな規模・種別・業界のWebサイトのSEOに関わっている。特に大規模サイトの対応を得意としており、多数の日本有数の巨大サイトのSEO担当として検索流入拡大に取り組んでいる。 Webマスターと検索ユーザー、検索エンジンの三者が利益を受けるSEOを信条に活動中。









