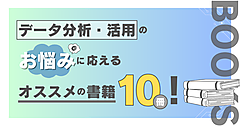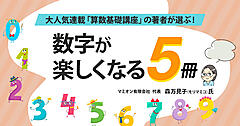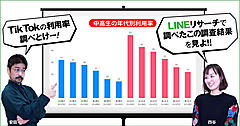業界の最前線で活躍する方にオススメの書籍を教えてもらう本連載。今回は、メルカリでデータアナリストとして活躍している諏訪ひと美さんに、データ分析初心者に向けた「データ活用」に関するオススメ書籍を4冊紹介してもらった。

実務を通じ、書籍を補助的に読んで数字との付き合い方を学んだ
諏訪さんは、「Web担当者Forum ミーティング2023 秋(以下、Web担ミーティング)」で、“「数字が苦手」でもできるデータ分析の第一歩”と題したセッションに登壇。文学部出身のためにデータ分析に苦労した経験から、数字への苦手意識を克服する方法や分析レポートに並ぶ数字の読み取り方、指標をみるときのポイントなどを解説してくれた。
社会人になったばかりの頃は数字が苦手だったという諏訪さんだが、現在はメルカリのデータアナリストとして活躍している。そのきっかけは、新卒で入社したデジタルマーケティングの支援会社で、データ分析を叩き込まれたことだ。OJT(On the Job Training)で先輩と一緒に案件をこなしながら、見様見真似で分析方法を覚え、データ活用に関する書籍を補助的に読んで身につけていった。
そのようにデータ分析のスキルを得た諏訪さんは、自社プロダクトを成長させる仕事がしたいと思うようになってメルカリに転職。メルカリ利用者の行動分析などを行った後、現在は人事データの分析に携わっている。

効果を実感できる「プロセス分析」を学ぶ本
新卒で入社した当時はデータ活用に関する知識がなく苦労したという諏訪さんだが、これから紹介する1冊目の書籍を読み、数字を使って業務を改善する成功体験が得られ、データ分析にのめり込むようになっていったという。
1冊目
『孫社長にたたきこまれた すごい「数値化」仕事術』(三木雄信:著 PHP研究所:刊)
「本書で特にオススメなのは、プロセス分析について書かれている第2章だ」と諏訪さんは話す。
プロセス分析とは、たとえば営業であれば、受注というゴールまでのプロセスを、テレアポ→商談→提案→受注と分けて、それぞれの歩留まり率を計測していく手法です。プロセス分析はシンプルな手法でわかりやすく、しかも効果が抜群です(諏訪さん)
当時、デジタルマーケティングの支援会社でSEOのコンサルティングを行っていた諏訪さんは、さっそく担当企業でプロセス分析を実施したという。
担当企業の顧客の契約継続をゴールとして、契約継続までの段取りをプロセスに分解し、歩留まり率を計測していきました。歩留まり率を見ていくことで、自分が認識していたこと以外にも意外性のあるプロセスにドロップポイントがあることなど、新たな発見が得られ、改善施策を実施できました(諏訪さん)
プロセス分析による改善効果を実感した実務体験から、数字の使い方を学んだ諏訪さん。データ分析担当の初心者にも、ぜひプロセス分析を実際にやってみてほしいと語る。
Web担ミーティングでも「手触り」というキーワードを使いましたが、プロセス分析は、手触り感のある、効果を実感しやすい手法だと思います。たとえば転職やダイエットなどにも、プロセス分析を活用できます。目標に向けてプロセスを分け、仮説を立てながら成果を計測して、プロセス分析の効果を実感してみてほしいです(諏訪さん)

売上を上げるために、どの指標を見るべきかがわかる本
収集したデータをどう見て、どう活用すれば、意味のある分析結果が得られるのかわからないという方もいるのではないだろうか。そんな時にオススメなのが2冊目の本だ。
2冊目
『デジタルマーケティングで売上の壁を超える方法』(西井敏恭:著 翔泳社:刊)
本書は、「特にECサイトを運営している人にオススメしたい」と語る諏訪さん。本書のなかでも、とりわけ第2章の「売上を新規と継続に分解する」を読むと、ECやデジタルマーケティングで使う指標の構造がわかるようになる。
第2章では、新規顧客と継続顧客に分けて売上を分析する手法が具体例をまじえて解説され、継続顧客を増やすことの重要性が語られています。なかには、新規、継続ごとに、ユーザー数、購入単価、購入回数など観るべき指標が比較できる表が示されているので、まずは同じように自社データを整理してみるといいと思います(諏訪さん)
また、売上を指標に分解する図版もわかりやすく、どの指標を上げていくと売上が増えるのかをイメージできるようになるという。
指標がいっぱいありすぎて、何をどう改善していいかわからないという方には、きっと役立つはずです(諏訪さん)
実践しながら読んでほしい! 分析手法を体系的に学べる本
3冊目のオススメ本は、分析手法について体系的に学べる一冊。グロービスビジネススクールの人気講座を書籍化したもので、ビジネスに役立つ要点がまとまっている。少し難易度が上がるので、初心者向けの1冊目、2冊目を読んで数字に慣れてから読んでほしい。
3冊目
『定量分析の教科書―ビジネス数字力養成講座』(鈴木健一:著 東洋経済新報社:刊)
本書のエッセンスは、プロセス、視点、アプローチの3点にあるという。
現在はKindle版で読み直していますが、最初に手にしたのは紙の書籍でした。その表紙カバーのそでに、プロセス、視点、アプローチの3つの図解がのっていたんです。私はその3つの図解部分を切り取って机に貼り、いつでも意識するようにしていました。それくらい重要な図です(諏訪さん)
本書では、定量分析の手法について基礎から応用までがまとめられている。難しく感じた箇所はとばして気になったところから読んでもいいし、実務中、参考のために読み直してみるのもいいだろう。
経験を重ねて再読すると納得できる範囲が増えているのがわかり、レベルアップしていることが実感できると思います。実践しながら読むことで、身についていくはずです(諏訪さん)

相関関係と因果関係を正しく理解するための本
施策を行い、期待通りの数値が得られたとしても、「この施策によって得られた効果だと、手放しに喜んでいいのか疑わしい」と思った経験はないだろうか? そこで知っておくべきは、因果関係と相関関係だ。
4冊目
『「原因と結果」の経済学―データから真実を見抜く思考法』(中室牧子、津川友介:著 ダイヤモンド社:刊)
4冊目として取り上げてくれたのは、相関関係と因果関係の違いがわかるようになる書籍だ。諏訪さんは「データ分析を依頼するマーケターの人も、間違った方向性で依頼しないためにも読んでおいた方がよい」と話す。
初心者から脱してデータ分析に慣れてくると、誤った解釈をしてしまうという落とし穴にはまることがあります。それは相関関係と因果関係の区別ができていないことによる落とし穴です。
本書では相関と因果の2つの違いがわかりやすく解説されていて、あたかも因果関係があるかのようにみえる擬似相関の注意点についても紹介されています。専門用語もありますが楽しく読める1冊で、どういう分析をすれば因果関係を特定できるのか、その手法が解説されています。
因果関係を特定するのは本当に難しい一方、その限界をふまえて何ができるか、を考えていくのは楽しいです。学ぶほどにはまってしまう「沼」だと思います(諏訪さん)
ブログやSNS、コンサルティング会社のレポートで最新情報を取得
最後に、書籍以外にチェックしている情報ソースについても教えてもらった。
諏訪さんは、実務でデータ分析をしている人のブログ、大学で統計学を教えている先生のブログなどをチェックしているという。また、マッキンゼー・アンド・カンパニーやPwCなどのコンサルティング会社が公開するレポートを読むことも多いそうだ。
レポートでは、主に分析手法やデータの可視化の方法を参考にさせてもらっています。レポートのまとめ方なども参考になりますね(諏訪さん)

今回は、初心者向けから中級者向けまで、順番にステップアップしながら読める4冊を紹介してもらった。数字が得意でない方も、今回のオススメ本を読んでデータ分析の力を身に付けてほしい。
諏訪ひと美(すわ ひとみ)
株式会社メルカリ HR System&Data シニアデータアナリスト
東京大学文学部卒業(社会心理学専攻)。株式会社SpeeeでSEOコンサルティングやデータ活用支援事業のマーケティングに従事した後、データアナリストとして株式会社メルカリへ入社。メルカリでは主にWeb・アプリの行動ログやA/Bテストの分析を担当。現在は人事のデータ分析部門にて、人事データの分析基盤の整備から人的資本の分析、データの民主化まで行っている。