Webページ、SNS、ポスター、プレゼン資料を制作するとき、私たちは「あるデザイン」を選択して仕事を進めている。できることなら、上司や自分の好みではなく、顧客に寄り添うデザインかを見極めるだけの根拠がほしい。そこで、Adobe MAX US 2018にも出演し、25年以上制作現場で活躍している鷹野雅弘さんに、「デザイン」をテーマにオススメ本を紹介していただいた。
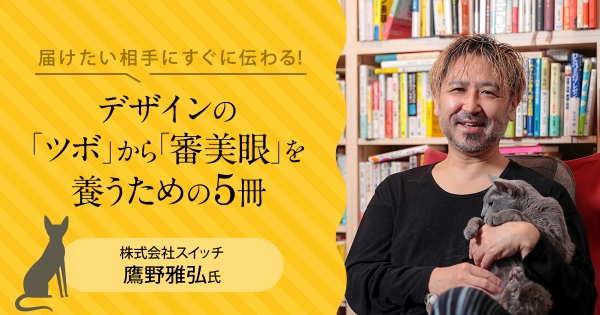
現場ですぐに役立つ「デザインのツボ」がわかる本
1冊目
『とりあえず、素人っぽく見えないデザインのコツを教えてください!』(ingectar-e:著 インプレス:刊)
1冊目は、まさに書名どおり。デザイナーになったばかりの初心者や非デザイナーのための「素人っぽく見えないデザインのコツ」がわかる本だ。「メリハリをつけて主役を目立たせる!」「使っていいフォントは3つまで。」「1色選ぶだけでデザインはできる!」「トリミングで伝えたいことを明確に。」「情報のアイコン化ですっきり注目!」など、まさに現場ですぐに役立つことが、before / afterの例とともに紹介されている。
なお、チャプターは5つ。「まずは情報整理からレイアウトのコツ」「すっきり読みやすい文字と文章」「1色や3色でOK! 配色アイデア」「ひと目で伝わるビジュアル」「もう一歩作り込むあしらいと装飾」だ。Webページはもちろん、プレゼン資料にもすぐに役立つ内容になっている。
基本的な優しい内容をロジカルに説明しているので、読むと「確かにそうだよね」と納得できます。デザインの良し悪しは、カッコイイよりも「伝わる」ことが大切。ビジネス現場では、あまり手をかけずにツボをおさえることが重要なんです。デザインの難しい理論を学ぶよりも、まずはこの「ツボを知る」ことをオススメします。本書には、基本的なツボがたくさん紹介されています(鷹野さん)
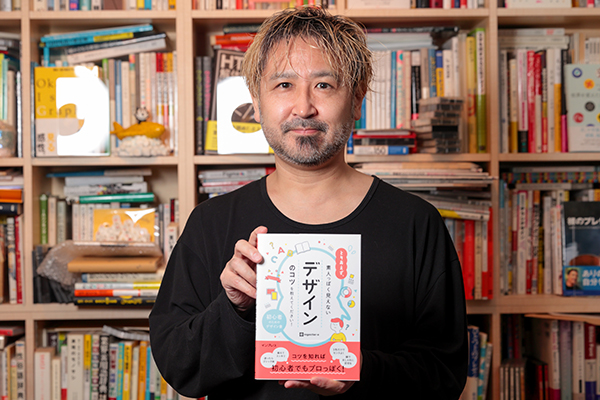
短時間で正確に伝える「文章上のツボ」がわかる本
2冊目
『日本語文章チェック事典』(石黒圭:著 東京堂出版:刊)
2冊目は、デザインという観点ではないが、文章という観点で「ツボ」が書かれた本だ。「表記」「語彙」「文体」「文法」「文章」「修辞」という6つのチャプターごとに、制作現場ならではの事例が、before / afterとともに紹介されている。たとえば、「読みやすいフォントの選び方」「気持ちが伝わる比喩の作り方」といった項目が並ぶ。
なかでも本書で特徴的なのは、「<正しさ>よりも、伝えるための<ニュアンス>をどう考えるべきかが書かれていることだ」と鷹野さんはいう。
たとえば、LINEのメッセージ。末尾に「。」を付けると世代によっては“冷たい”と感じます。伝えて終わりでなく、きちんと「伝わる」ためには、伝えたい相手によってことばのチョイスやニュアンスを変えていく必要がありますよね。チャットやメールでも、デザインメールでもデザイン制作でも同様です(鷹野さん)
本書中の例ではないが、「漢字」で書くか、「ひらがな」で書くかによっても、相手に伝わるニュアンスが変わる。たとえば、「その通り」と「そのとおり」であれば、鷹野さんは「通り」ではなく、「とおり」を使うという。「通り」という漢字を使うと「道のニュアンス」が出てしまうからだ。
「楽に」と「らくに」はどうでしょう? 「楽」は「楽しい」を連想させますから、「らくに」とひらがなの方がいい。さらに「ラクに」とすることで、ポップなニュアンスを残しつつ、読みやすくなります。こうした漢字にするか、ひらがなにするか、さらにカタカナも用いるかは大切です。noteに「なぜ、“ひらく”のか」への考察 として書きましたので、よかったら読んでみてください(鷹野さん)
私たちが制作しているものは、文章で伝えるものが多い。短時間でいかに正確に伝えるかを考えると、デザインとともに文章の表記も重要になる。むしろ、文章も含めて「伝わるためのデザイン」と考えてもよいかもしれない。
ポスターでも、Webページでも、最近では多くの人が文章をじっくり読まなくなっています。キャッチコピーのように、一瞬で理解してもらわないといけません。そこで、文字詰めや表記が重要になります。マーケターの方々が作るプレゼン資料においても、同様に表記の吟味が必要でしょう(鷹野さん)
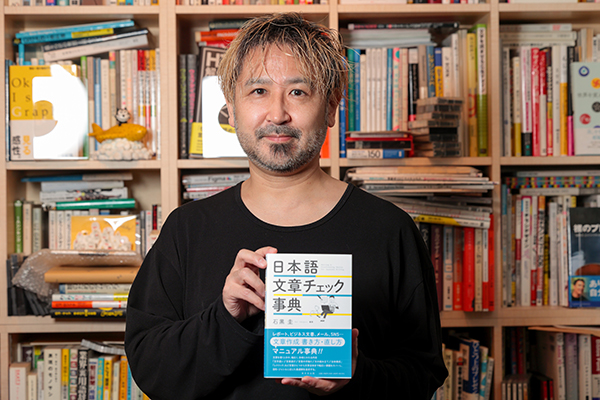
「誰にでも伝わりやすくする方法」がわかる本
3冊目
『見えにくい、読みにくい「困った!」を解決するデザイン』(間嶋沙知:著 マイナビ出版:刊)
3冊目は、ユニバーサルデザインの本だ。2016年に障害者差別解消法が施行され、ユニバーサルデザインへの対応は「取り組みたいこと」ではなく、「取り組むべきこと」になってきている。たとえば、同じ色でも色覚特性によって見え方が異なる。そこを配慮しなくては、伝わらない人が出てきてしまう。ではどのように配慮すればよいのか? それを、具体的な例を用いて説明しているのが本書だ。
赤と緑が見えにくい人がいることはかなり前からいわれていました。しかし、「どうすればいいのか」というところに踏み込んだ本はなかったんです。安全色を用いたりセパレーションを入れたりするなど、デザイナーがどうすればよいのか、具体的な方法が書いてあります。カッコイイと思うデザインでも、伝わらなければ意味がありませんから(鷹野さん)

ユニバーサルデザインといっても「特定の障害者向けのものだと、ことさら考える必要はない」と鷹野さんはいう。誰でも年齢を重ねれば老眼になる。また、重いスーツケースをもてば2、3段の階段を上るのも大変になる。そのため、設計段階から駅の入り口にはスロープを付けておくことが大切になるわけだ。何かを作る際には、ちょっとした配慮で皆が心地よく使えるものになる。一方、配慮に欠けると誰かの「困った!」につながってしまう。
本書には、「<ことば>で困った」ことの解決策も提示している。たとえば、日本で暮らす外国人のために「やさしい日本語」を使うこと、これも伝わるためのデザインの工夫だといっていいだろう。
「ここは海抜2m」と書いてあっても、海外からいらした方は「海抜」の意味がわからないのではないかと思います。その解決事例として、本書では、「海抜」の上に「(うみからのたかさ)」と添え、意味が伝わる表記にした和歌山県海南市のポスターを取り上げています(鷹野さん)
なお、本書には「色」「ことば」のほか、「文字」「図解」「UI」というカテゴリがあり、それぞれに「困ったときの解決法」が書かれている。
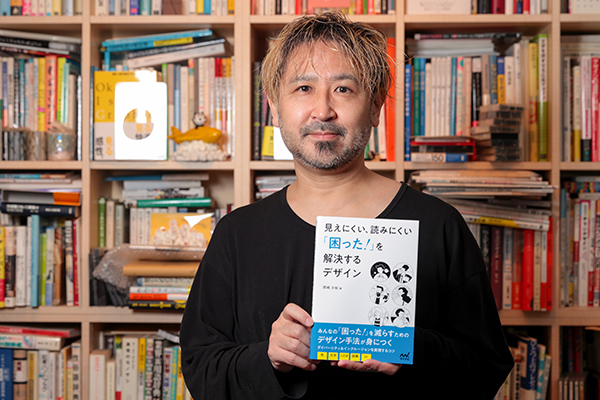
『見えにくい、読みにくい「困った!」を解決するデザイン』
「目的に合った写真の選び方」がわかる本
4冊目
『ネットショップ初心者でも売れる 商品写真の基礎知識とつくり方』(黒葛原道:著 玄光社:刊)
4冊目は、デザイナーが書いた写真の本だ。書名に「ネットショップ」と入っているが、ネットショップに限らず、デザイナーが写真を扱う際のポイントが記された本だという。
最近は素材サイトなどから写真を選ぶことが多いと思いますが、本書には、写真のどこを見て選べばよいのかが書かれています。また、写真撮影を依頼する際の注意点もあるので、デザイナーにこそ読んでほしいオススメ本です(鷹野さん)
なお、本書は「ECにおける写真の重要性」「ECに必要な写真と調達方法」「効率的に写真を用意する方法」「商品別に必要な写真の撮り方」「覚えておきたい撮影の基本」「SNSを活用する」という6つのチャプターに分かれている。
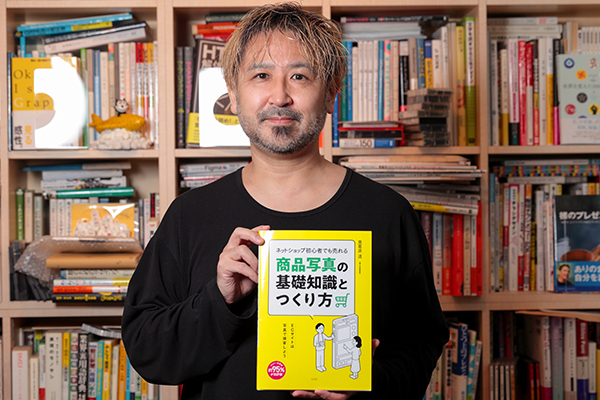
審美眼を養うための本
5冊目
『なるほどデザイン 目で見て楽しむデザインの本』(筒井美希:著 エムディエヌコーポレーション:刊)
本書を手に「この本はすぐには役立ちません」という鷹野さん。ではなぜオススメなのかというと、「良いものに触れて感覚を磨く」のにとても良い本だからだ。副題に「目で見て楽しむデザインの本」とあるように、豊富な実例を見ているだけで、良いデザインがどういうものかが蓄積されていく内容だ。
美しい写真やページを用意すれば商品が売れるわけではないですが、その美しさ、世界観に共鳴する人はいます。世界観を表現するのに、どんなニュアンスを大切にしていけばいいのかという審美眼が本書で養われると思います。休憩スペースなどに置いて、仕事の合間にパラパラとめくり、その時々で目に飛び込んでくるものを吸収してもらうといいですね(鷹野さん)
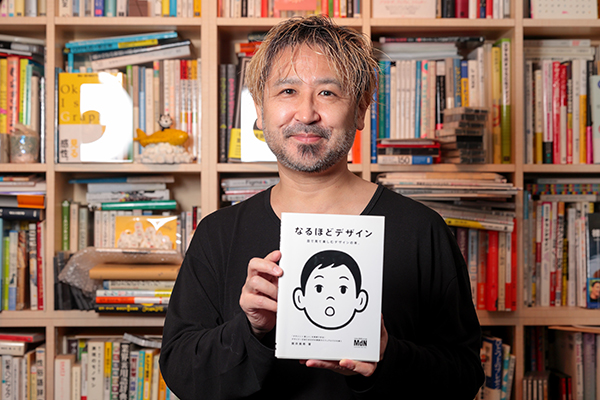
スキルアップし続けるために
最後に、スキルアップするために効果的な方法を伺ったところ、「実はアウトプットこそが一番のインプットになる」と教えてくれた。
人に説明したり、文章に書いてみると、あいまいだったり、理解が浅い部分が見えてきます。次のようなアクションを通じて、表やチャートを作ると理解が深まります。
- 人に説明する:社内勉強会
- 文章に書く:ブログ(note)
私自身、仕事での日々の課題をブログに書くことで、別の解決方法が見えてくることが多々あります(鷹野さん)
デザイン関連でわからないことを書き出していく「課題のネタ帳」を作ることもオススメだという。課題のネタ帳作りについては、「課題のネタ帳」を作りましょうを参考にしてほしい。
また、初心者向けの情報源として、鷹野さんがまとめているTwitterのリストやnote記事は次のとおりだ。
- 【学生向け】最初にフォローすべき人
https://twitter.com/i/lists/1302484744433618944 - 読んでおきたいツイートや記事(マンスリー)
https://note.com/swwwitch/m/md4bf55123077
鷹野さんのオフィスは、BGMに鳥の声、水の音が流れている、とてもゆったりとした空間。しかも美しい猫ちゃんが時折顔を出してくれるというオマケ付き。とてもリラックスしながらお話を伺った。そんな中一貫してお話されていたのは、「届けたい相手に合わせ、すぐに伝わるようにすること」の重要性だった。今回紹介していただいた書籍は、そのための方法をロジカルに説明してくれている。ぜひ読んでみてほしい。
なお、デザイン本ではないが、話の流れで『エバンジェリストの教科書』(西脇資哲:著 C&R研究所:刊)もご紹介いただいた。プレゼンのツボが書かれた本として、鷹野さんも参考にされているという。ビジネス上、プレゼン技術は必須ともいえるので手にとってみてはいかがだろうか。
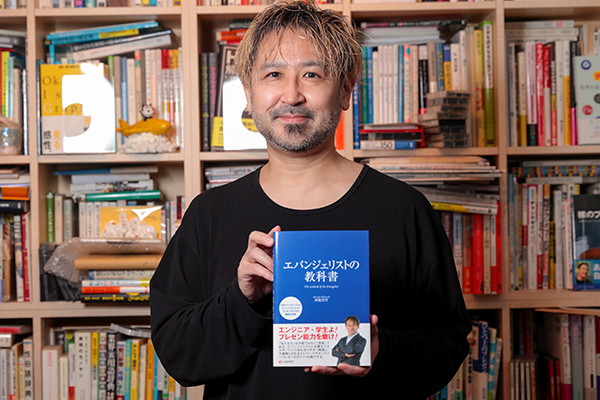
鷹野雅弘
株式会社スイッチ 代表取締役
DTPやウェブサイト制作など、25年以上、第一線で手を動かし続け、「制作→執筆→講演」のサイクルを回す日々。
2015年から大阪芸術大学 客員教授。
2017年からAdobe Community Evangelist。
ウェブ制作者向けのセミナーイベント「CSS Nite」や、DTP制作者向けの情報サイト「DTP Transit」を、それぞれ2005年から継続している。
テクニカルライターとして30冊以上の著書をもち、総販売数は18万部を超える。主に『10倍ラクするIllustrator仕事術(増強改訂版)』(共著、技術評論社)など。
Adobe MAX US 2018に出演。
株式会社スイッチのURL:http://swwwitch.com/



























