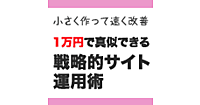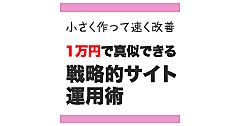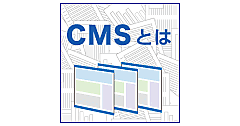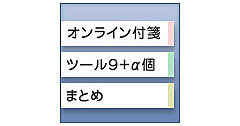作りながら要件を固めて選ぶ(続き)
作りながら要件を固めて選ぶ(続き)
 3. サイトを最適化する
3. サイトを最適化する
どのCMSにするのかを決めたら、CMSの設定、サイト自体の設計を続けて、サイトを完成させよう。評価目的で作ってみたサイトがそのまま使えるなら、さらにブラッシュアップしていく。
a.使えるものは使う
CMSの現状を知らずに設計したサイトは、絵に描いた餅と同じだ。CMSを使って予算内でどんなことができるのかを理解できたので、その範囲でできる最大限のことをしたい。当初は必要とは思っていなかった機能であっても、使えるなら使ってみて、後で効果測定すれば良い。
「システムありきの本末転倒な進め方だ」という考えもあるが、低予算の場合は、ない物ねだりをせずに得られるものを最大限活用するほうが、費用対効果が高くなる。そのために、サイトの設計やデザイン自体も見直して最適化をすれば良いのだ。
どんなプロジェクトにも制約がある。その制約と可能性を十分に理解した上で、最適なバランスを見るけることが重要なのだ。
b.変化に耐えられる体制を
さらにいうと、立ち上げた後でさえ、サイトは常に未完成の状態だといえる。たとえば、3年前にあなたはTweetボタンやFacebookの「いいね!」ボタンが今ほど一般化すると予測できていただろうか?
CMSを一度導入すると、少なくても数年は使い続けることになる。CMSを導入したことで、逆にニーズやトレンドに迅速かつ柔軟に対応できなくなるのは、本末転倒だ。そのため、初期構築の予算に加えて、継続的な改善や変更のための工数(予算)も確保しておくと良いだろう。
まとめ
以上、製品の違いを意識して効率よくシステム選定とサイト設計を同時並行で進める方法を紹介した。
この考え方はCMSに限らず、いろいろなシステムの選定に応用できる。低予算、短納期のプロジェクトは結果的にこうなっているケースも多いが、進め方とポイントについて改めてまとめてみた。参考になれば幸いだ。
参考となる記事
- 【小説】CMS導入奮闘記――吉祥寺和男の挑戦
- CMSの導入はゴールでなくスタート、その「運用」の秘訣とは?
- 企業で使えるオープンソースCMS―挙12種類解説(機能やインストール/管理の難易度評価付き)
- 無料でサイトを構築できるCMS+ホスティング16サービスを一挙紹介
今回の想定真似コスト 10~72時間