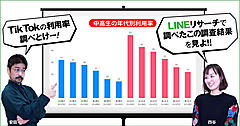「セミナーで営業トークは一切していないのに、終了後、参加者の2割が商談したいと申し込みがありました」と話すのは、国内最大規模のWeb行動ログのデータベースを活用したマーケティング支援を行う株式会社ヴァリューズの齋藤ロベルト義晃氏。
Web担当者Forumでは、年4回実施するイベントで集客・聴講者からの満足度が高いスポンサー企業の講演セミナーを「スポンサー部門最優秀コンテンツ賞」として表彰している。2024年2月に開催されたセミナー「デジタルマーケターズサミット 2024 Winter」で受賞したのは株式会社ヴァリューズ。
受賞を記念して齋藤氏に、商談につながるセミナー作りのコツを伺った。
参加者の課題解決を目指したセミナー。終了後のアンケートでは参加者の20%が「商談したい」

ヴァリューズは、250万人規模のインターネットユーザーのWeb行動ログと属性情報を活用したマーケティング支援のほか、経営課題のコンサルティングから、課題解決、販売促進の支援までを提供している。齋藤氏はデータ分析に基づく施策設計・実施、効果検証を行うデータプロモーション事業の事業責任者を務めている。
今回「スポンサー部門最優秀コンテンツ賞」の受賞を聞き、まず「思いが報われて嬉しい!」と感じたという。セミナーは「申し込んだ方が貴重な時間を費やして聴きに来てくれるもの」ととらえ、常にそれだけの価値を提供できるように努力してきたからだ。
もともと金融系の事業会社でマーケターをしており、その頃は業務時間の隙間を縫ってセミナーに参加していたので、参加者の期待がよくわかるんです。セミナーの内容が営業、宣伝にならないことはもちろんですが、情報提供だけで終わっても『参考になった』という感想で終わってしまいます。参加した方の課題解決につながることを目指して内容を考えています(齋藤氏)
齋藤氏が2018年にヴァリューズに入社して以来、今回が11回目の登壇となる。なお10回目は、シンガポールで開催されたマーケティングリサーチのカンファレンス「ESOMAR」での登壇だったといい、大きな経験となったという。その経験の後日本で初めての講演で受賞したことが嬉しいと話した。
なお、セミナー終了後のアンケートでは20%の参加者が「商談したい」と回答。その後のフォローで、現在はその約2倍の数の企業と商談に進んでおり、「直近でも、かなり手応えがあった」と話す。
他社のセミナーテーマを予測して内容が被らずかつ関心の高いテーマとして認知広告を選定
受賞したセミナーは認知広告の効果測定をテーマにした。生成AIやSEOなどホットなトピックが並ぶ中で、古くて新しいテーマだ。
最新トレンドではなく、マーケティングの本流をテーマにした内容で受賞できたことがよかったです。ヴァリューズは、マーケティングに関わるあらゆるテーマの相談相手なので、たくさんのクライアントと話す中で共通の課題を見つけることができます。その中から、よい問いをたてられる課題をセミナーのテーマにしています(齋藤氏)

受賞したセミナーでは「認知広告施策の妥当なKPIは何か」を問いとして、セミナーの内容を構成した。なおこのテーマは、本イベントが初披露となる。すでに様々なテーマでセミナーを実施している中で、より多くの人に聞いてもらいたいということから、初めてのテーマを選んだという。
セミナーのテーマを考える上では、他社の顔ぶれをみて、どんな内容を話すのかを予測して、重ならないようにしたともいう。
事業会社の事例を聞きたいという参加者も多いでしょう。他のセミナーでは支援会社と事業会社が一緒に登壇するセミナーがあり、リアリティある話が聞けます。支援会社一人で登壇する今回は、事例ではなくクライアントが抱える共通課題を取り上げるべきだと考えました(齋藤氏)
こうしたテーマ選定の戦略が功を奏して、集客数が多くなった。集客にあたっては「登壇者としてイベントに貢献したい」という気持ちから、齋藤氏自身がXでこのセミナーにかける思いなどをポストした。
なおセミナーでは、認知広告のKPIを態度系の指標だけで計測することに対して疑問を呈している。認知度、購入意欲が上がっても実際に行動につながらなければ意味がないからだ。セミナーでは、認知広告接触後にWeb行動ログを分析して行動につながったかどうかを検証する方法を紹介している。その手法が参加者の課題解決になると同時に、セミナー後の商談にもつながる結果となったと齋藤氏は振り返る。
会社として月に1回以上協賛型セミナーに登壇。テーマにあったスペシャリストが登壇し、会社としてのプレゼンス向上をはかる
B2Bマーケティングのセミナー施策として、他社が開催するイベントに協賛して登壇する協賛型セミナーと、自社で開催する自社セミナーがある。同社ではそれぞれどのように活用しているのか。インタビューに同席した、同社の事業企画局 広報G マネジャーの簗瀬太氏から説明があった。
協賛型セミナーは、自社のプレゼンス向上、ブランディング、新規リード獲得を目的に参加しています。協賛型セミナーには、月に1回以上のペースで参加しています。
一方、自社セミナーは基本的にはハウスリストで集客しており、より密接なコミュニケーションにより商談化を目指しています(簗瀬氏)
協賛型セミナーに登壇する場合は、マーケティングチームから、社内のスペシャリストに声をかけ、登壇してもらうケースが多いが、時には事業部から「このテーマで登壇したい」と声があがることもあるという。協賛型セミナーに登壇することのメリットが事業部側にも伝わっており、登壇意欲が高い人材が多いという。
なお、協賛型セミナーのKPIは申込者数、新規リード獲得数、自社セミナーの場合は申込者数、商談化率としている。協賛型セミナーの場合は、自社のセミナーの申込数だけでなく、イベント全体の申込者数についても着目しているという。

冒頭に参加者が共感するエピソードを入れることで、関心を高める
セミナーの資料作りは、マーケティングチームがサポートすることもあれば、登壇者が一人で作成することもある。今回は、齋藤氏が一人で作成した。
一般的に、1時間をベースに講演内容を設計します。1時間は、業務の合間にセミナーに参加できる最大時間ですし、集中して聞ける時間でもあるからです。講演時間が短い場合は、1時間の内容を削ぎ落として調整します。今回は、あえて60分の内容を削ぎ落とさずに、話し方で40分に調整したので、アンケートで『話が早すぎる』というフィードバックがあり、大いに反省しています(齋藤氏)
セミナーの内容を考える時間、資料作成の時間はテーマによって異なるという。骨子を考えるステップが数日間でできるものもあれば、数週間かかる場合もある。今回の場合は、メイン業務の合間を縫いながら、2か月弱セミナーの準備に時間をかけたとのこと。なお、スライド1ページ1分というペースを目安に作成している。
参加者の興味をひくための工夫として、このテーマが自分に関連するテーマだと気づいてもらう話をするようにしているという。
たとえば、自分が事業者側だった頃に悩んでいた体験を伝えると、参加者も『自分もそうだ』と共感してもらえます。どのセミナーでも最初に共感を得るためのパートを用意して、最後に商談につなげる構成にしています。オンラインの場合は、ながら視聴の人も多いので、注目してもらいたいスライドは『大事なのでここだけは見てください』と伝えたり、少し間を開けてみたりという工夫をしています。
参加者に新しい情報を提供することも大切です。私の場合は、2023年にシンガポールで開催された「ESOMAR」というカンファレンスに登壇してからは、海外の情報を入れるように意識し始めています。海外のカンファレンスの内容など、日本には入ってこない情報がまだまだ多いことを実感したので、自分が架け橋になって伝えたいですね(齋藤氏)
自分の話している姿を録画して改善点をみつけよう!
今回のセミナーテーマは、内容をアップデートして自社セミナーでも講演したという。
わかりやすく伝えるためには、自分で講演内容を録画したものを見て改善点を見つけることが重要だと齋藤氏。
喋り方、しぐさ、表情が画面から伝わって、人間の第六感のようなところで、信頼できる、わかりやすいと判断することはあるのではないかと思います。登壇に慣れている方の話はやはりわかりやすいですし、自分と比較してよいところを見つけて改善しています(齋藤氏)
ヴァリューズでは、顧客理解、市場調査、思索設計、実行、効果検証、商品開発など、テーマを限定せずに幅広い顧客の課題と向き合っていることから、今後もさまざまなテーマでの講演活動をしていきたいと考えている。
入社当初は、認知広告をテーマに講演するとは想像していませんでした。これからも次々に新しいテーマが出てくるので、継続的な情報発信にも力を入れたいです。海外の新しい情報も含めてSNSでも積極的に発信していきたいのでご興味のある方は(@Roberto_VALUES)をぜひフォローしてください(齋藤氏)