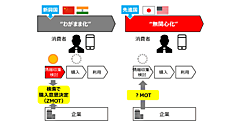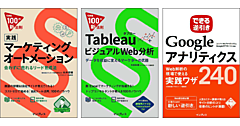広告をやめた企業は、どうやって売り上げをあげているのか。――ビルコム太田氏著の書籍、インプレスが1月31日発売
「企業からの発信ではないこと」「演出がないこと」「マイクロコンテキストをふまえていること」
2018年1月26日 16:16
書籍『広告をやめた企業は、どうやって売り上げをあげているのか。』を、インプレスが1月31日に発売する。著者はビルコム代表取締役兼CEOの太田滋氏。
Amazonなど主要オンライン書店で予約できる。
- 書名: 広告をやめた企業は、どうやって売り上げをあげているのか。
- 著者: 太田滋氏(ビルコム株式会社 代表取締役 兼 CEO)
- 発売日: 2018年1月31日(水)
- ページ数: 208ページ
- 出版社: インプレス
- 価格: 本体1,728円(税込み)
- https://www.amazon.co.jp/dp/4295003085/
広告がかつてのようには効かなくなった。
かけた費用に見合うだけの効果が得られなくなった。
広告の炎上がおそろしい。
そうした、企業の担当者が広告にアタマを抱えるいまの状況は、なぜ起こっているのか。そんななかで企業は、どのように生活者に働きかけていけばいいのか。
著者の太田氏は、大切なこととして、次に示す3つの条件を満たしたところに、「つぎのコミュニケーション」があると説く。
- 企業からの発信ではないこと
- 演出がないこと
- マイクロコンテキストをふまえていること
目次・内容
- はじめに ── どうして「ちがい」が生まれたのか
- 第1章 なぜ「広告をやめたい企業」が増えているのか
- テレビCMは本当に必要か
- 「短い尺」では難しい
- 活動時間の約3分の1は「スマホ」
- 「とりあえず、マス広告」の時代ではない
- 指摘される「広告のリスク」
- 広告はそもそも炎上しやすい
- なぜ、広告をやめられないのか
- 第2章 広告は本当に効かなくなったのか
- 社会が変われば、コミュニケーションも変わる
- テレビCMとウェブ動画広告を比べてわかること
- 「メガコンテキスト」から「マイクロコンテキスト」へ
- 「仕事人生がすばらしい」の危険性
- 「自己本位化」するコミュニケーション
- 「広告のように見えるもの」すら見られない
- 「6秒」の広告でなにを伝えるか
- 生活者の最大の敵は「虚偽」
- 広告は「遮断される」
- ネイティブ広告は是か非か
- 第3章 広告に代わる「つぎのコミュニケーション」
- 「企業からのアプローチ」の3条件
- 「PR」は関係性をつくるもの
- PR的コミュニケーションは“郷”の現状にそっている
- PR的コミュニケーションのリスク
- じつは広告もPR化している
- 「ファクト」が客観性をもたらす
- 拡散するのは「利他」の気持ちから
- 「だれ」には「場」と「人」がある
- PR的コミュニケーションは「共創」
- 第4章 広告をやめた企業はこうやって売り上げをあげる
- 「モノ」から「コト」へ
- モノを欲しがらない人たち
- 「コト」で表現する
- 仲間の存在をたしかめる「つながり消費」
- 自分の幸せをたしかめる「幸せ確認消費」
- 自分の可能性をさぐる「非日常消費」
- 「いいね!」は主観的評価
- 「AIDMA」「AISAS」、そして……
- ソーシャルメディア時代は「PLSA」モデル
- 「Simulation (評価)」は4つの視点から
- シャンパンタワー型コミュニケーション戦略
- 肝心なのは「最初のグラス」の選び方
- ホットセグメントを探す2つの手がかり
- 「アンバサダー」ではなく「オピニオンリーダー」
- 「3つの機会」で「コト消費」を起こす
- 第5章 科学を武器にしたPR的コミュニケーションの可能性
- 「3K」に「科学」が加わったPR
- 「生活者の本音」はなかなか表面化しない
- ソーシャルメディアは「声」の宝庫
- メディア×生活者=検索数
- PLSAモデルの効果を分析するには
- 競合との比較は「Perception (認知・認識)」で分析
- 検索するのは「興味をもったから」
- 「Simulation(評価)」は4つの視点それぞれに分析
- 「A」にいたる期間に注意
- 「売れる“打ち手”」は予測できる
- 世界の注目は「PR分析ツール」
- おわりに ── 「信頼」が競争軸になる時代