デジタルマーケティングを取り巻く環境が急激に変化している。スマートフォン普及率の高まりとともに、リアルな体験とデジタルの体験がシームレスにつながりつつある状況下で、企業はどのようにブランディングを進めていけばいいのか? スターバックスコーヒージャパンの長見明氏と、ネット通販でブランディングに取り組んでいるオイシックスの奥谷孝司氏に語り合ってもらった。
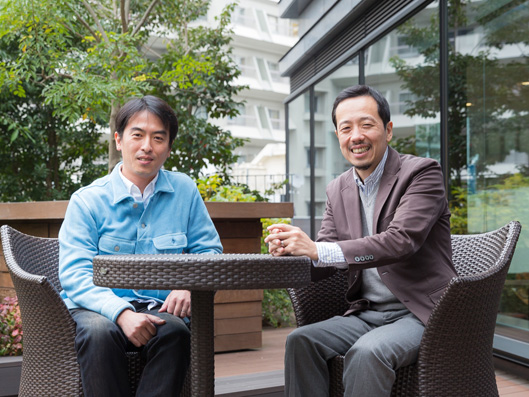
良い体験は一気にブランドに結びつく可能性がある

マーケティングコミュニケーション本部
デジタル戦略部 部長 長見 明氏
長見「ブランドのファン」って簡単に言いますが、人がどうやってその状態までたどり着くのかの分析は、ブランディングを行うにあたってとても重要です。食べ物は想像がつくんですよ。理屈の前に、僕は「体」が判断している部分が大きいと思っています。
僕は若いときに食品のPRをやっていました。PRやマーケティングコミュニケーションって、普通は機能的なメリットで興味を持ってもらい、情緒に訴えて、最後に自分事化してもらいます。食品の場合、マーケティングコミュニケーションの機能的な訴求は、栄養豊富であるとか、美味しいとか、無農薬で安心安全というところから入っていきます。
もう15年以上前の話ですが、高級スーパーで5,000円や10,000円するようなメロンを作っている農家さんにお会いする機会がありました。今はどうなっているか分かりませんが、当時、メロンは、完全無農薬栽培は難しい作物で、十数回農薬を散布するのが一般的だとうかがいました。メロンは、口の中が少しピリッとする印象がありませんか。あれは、農薬の影響なんだというのがその農家さんのお話でした。その農家さんの場合、ほとんど農薬を使わずにメロンを作っていたんです。
そういう機能的な話は分かりやすいので、もっとそういう話を聞きたいと思って「どこが他のメロンと違うんですか?」と聞いてみると「食べてみて、わかるから」と言われました。作っているものに自信を持っている農家さんはだいたいそうなんですが、決まって「食べてみて」って言われます。それで食べてみた。食べた瞬間に「あ、これ最高!」となりました(笑)。最初から最後まで、飽きることなくとろけるように甘くて、説明を求めた僕でさえ「これは説明不要だな」と思った。良い体験は、機能や情緒をすっ飛ばして、一気にブランドに結びつく可能性があると思うんです。

統合マーケティング部 部長
Chief Omni-Channel Officer
奥谷 孝司氏
奥谷たしかに、Macブランドの熱烈なファンに「iPhoneの何がいいの?」って聞くと、「とにかくいいんですよ。すごくかわいくて」とか言われるんですけど、何も合理的な説明がないですよね。
長見化粧品のコミュニケーションも同じです。表面的にとらえると、この成分がよくて、美白効果がどうとか、スペックと効果の塊のような世界が広がっているのに、ユーザーに「何がいいの?」と聞くと、「すごくいいから」と目をキラキラさせてオススメされる。
「いい」と言っている人の説明も、最初は機能から入るんですが、ひととおり説明したあと、「食べてみて」「使ってみて」となって、結局「いい」という言葉にすべて集約されています。完全にファンの人はいつだって目を輝かせながら「いい」っていうところから入るんですよ。合理的説明をすっ飛ばしたこの現象が何なのかといえば、僕は「体験」だと思うんです。体験って何?っていうと、僕は、体が心地よいと判断したものだと思っていて、そして、あるブランドでの体験の積み重ねが、ブランドへの信用につながります。
体験がブランドに結びつくのは理想的
長見これも聞いた話なのですが、魚は、食べられるものと食べられないものを、記憶ではなく、体で判断するのだそうです。とにかく、目の前のものを口に入れてみて、食べられないと分かるとプッと吐き出すというのを繰り返す。魚でも、人間でも、知識がなくても、体によいものは美味しく感じますし、生まれたときから体がそういうことをよく知っていると思うんです。

飲食店でも、音楽や座った感じの心地よさ、隣の席との距離感、適度な暗さを保った照明、これらが総合的に「心地いい」という体験として、体が判断していると思うんです。この「体験」がマーケティングコミュニケーションをすっ飛ばしてブランディングに結びつく重要な要素になっていて、この謎に僕は取り憑かれ続けています。
奥谷その話すごいおもしろいなと思う。私は、大学院での研究が買物価値研究でした。商品には機能性と快楽性があって、どうしてもまずは機能的なことから語りたがる。しかし結局は体験で、快楽性がある方が勝ってしまう。食べ物のECは、体験してもらうのが難しい。食べれば分かるんだけども、その前にまずネットで買わなければならない。
しかし、買い物体験をジョイフルにするのはけっこう難しい。それに挑戦することで、新しい買い物体験が提供できたらけっこう面白いんじゃないかなと思っています。
たとえば、スーパーに行っても、自分や家族がトマトが嫌いなら、ほぼトマトは買わないですよね。だけど、オイシックスはトマトに自信があって、トマトが嫌いな子供でも食べたら絶対好きになる。うちの子もトマトは嫌いなんですが、オイシックスのトマトは食べるんです。フルーツトマトは小さくて甘いから、単にフルーツみたいだよと言っているんですが(笑)。だけど本当に食べる。でも、トマトが嫌いなお客様にトマトを薦めるような後押しは、ECではなかなかできない。
「オイシックスで薦められたトマトは美味しくて甘くて、トマト嫌いの子供でも食べることができた」というのは、体験がブランドに結びつくという意味では理想的です。それをいかにWebでの買い物の場でやってあげられるか、ちょっと対話的要素を採り入れたECになってくると、けっこう最先端で面白い売場になるんじゃないかなと思っているんです。
長見僕の場合は、メディアで体験を伝えることは諦めているんです。店舗という舞台があるから、体験の舞台に誘導することで、デジタルでできる仕事の大部分は完了していると思っている。ですので、どこかにストック型のコンテンツを置いておいて、すでに体験して、ブランドを信用してくれているエバンジェリスト(伝道師)が他の人にお勧めするときの合理的な説明として使ってもらえるようにはしたいとは思っています。エバンジェリストはだいたい女性で、オススメ上手。「もう、すごいの!」って。「すごいの!」の言い方がスゴイ。
奥谷おっしゃるとおり、食品は五感を刺激するので、熱量が乗りやすい。一方でファッションは、身に付けたときに注目された、褒められたというのが体験として重要視されているような気がします。ただこれがクチコミとしてすごく難しいのは、自分から「カワイイって言われた」とか「ステキって褒められて嬉しかった」とは書けないわけです。誰かから聞かれて、答える。ファッションの場合は、人に言ってもらいたい。人間と共に、with C(Customer)になった瞬間、何かが出てくるんですね。食べて美味しいと思う体験と、着た自分が外に出て、素敵って言われる体験。

長見ある撮影モデルの女の子が「お気に入りです」って言って着ていた服が、表参道にしかないブランドのものでした。なんでそこがいいのって聞いたら、希少性がポイントで、そこのブランドの服を着ていると「それどこで買ったの?」と聞かれる。それがたぶんその子にとっての価値なんだと。自分らしく見えることは、その子にとっては人が着ていない服を着ていることも大きな要素。これはわかりやすいですよね。
――普通、商品やサービスについてコメントするときは、自分とその商品・サービスという関係をベースにコメントを書こうとするけれども、アパレルの場合はそうじゃないということですか?
奥谷買った後の詳細を、合理的に説明したり、言語化して書く人は少ないように見えます。料理だったら「食べて美味しい」のインプロバイゼーションが見えるんだけれども、洋服の場合、普通のブランドでのクチコミは難しい。でもファッショニスタ的な表現はあり得るじゃないですか。ZOZOTOWNとか、その辺うまくやってますね。
コミュニケーションの熱量とブランドの関係とは?
長見こないだちょっといい寿司屋に行ったんです。ちょっと懐が痛むくらいに高かったんですけど、むちゃくちゃ美味かったんですよ。1貫1貫が全部板さんの創作料理みたいな感じで、とにかく口に入れるまで味の想像がつかない。口に入れるごとに驚きがある。こういう話を聞くと、ちょっと行きたくなるじゃないですか。実体験があるときって、勧め方にも熱が入りますよね。ソーシャルメディア上の投稿だったとしても、熱が入るはずなんですよ。友達からのレコメンドが効くのは、第三者には分からないその熱量をテキストから感じられるからだと思うんです。
奥谷B to Cなコミュニケーションにはあんまり熱量がないけれども、B with Cなコミュニケーションには熱量がある。そのBはブランドでも、ビジネスでもいいですが、熱量があるコメントは個人的に伝わる。そこはスゴイ大事だなと思います。
スマホの普及によって、ブランドとお客さん、またお客さんとお客さんが直接、すぐにつながる時代になってきています。最初の話に戻ると、食べてみてとか、いいのよが、いろいろなかたちでつながるようになってきているから、そのつながりをどうブランド価値の増加につなげていくかというのはけっこう大事だと思います。
ブランドというのは、人間にとって何か根源的なものなんです。もうスターバックスで何年も美味しいコーヒーを飲んできているのに、今だって新しいブランドのお店ができればそこでコーヒーを飲んでみたい。野菜なんてもう何千年、何万年も食べているけれど、それでもオイシックスの野菜が美味しそうだと聞けば食べてみたくなる。
――スターバックスのように、日本国内だけで1000店舗以上あると、デジタルのコミュニケーションが刹那的になっていくときでも、ブランディングには強みを発揮するのでしょうか?
長見ここでも、僕の場合は、デジタルはきっかけ作りに徹して、お店でブランディングされればいいって割り切ってしまっています。リアルに体験を生み出せて、それが記憶として蓄積できるのは強いですよね。デジタルは、その分、どれだけたくさんの「きっかけ」を作れるかが勝負になります。
スターバックスが日本にやってきたとき、喫茶店文化がなかったアメリカと違って、日本の場合は、もともと喫茶店があった。かなり成熟したマーケットがあって、そこに対してどう入っていくかということだったので、日本の場合ものすごく差別化して、違う喫茶店というものを演出していって、今のポジションがある。その後に、いろんなナショナルチェーンがコーヒーの安売りを始めて、いったん落ちつき始めたときに、サードウェイブみたいなのが出てくる。小売業の楽しいところは、後からでも雨後の竹の子みたいに新しいライバルがガンガン出てくる。そういうところが楽しくもある。次の戦いがつねにある。ブランディングにも終わりがないのです。
奥谷小売りにはなかなか安泰がない。ブランドの話は瞬間では計れなくて、スターバックスがどれだけ大きくなっても、他の喫茶店はなくならない。むしろ市場が大きくなって、他社の参入も増えてくるし、他業種が参入してくることもある。市場が活況になればなるほど、最初に勝ちきった企業が積み重ねてきた良質な残存ブランド価値が逆に際立つかもしれない。企業は、そういうことも期待してブランディングしていると思います。時代が変わっても変わらないゆるぎない思い、その最大公約数が変わらず、背骨が通ったブランドであれば、それがどう臨機応変に変わっても、軸がぶれずに生き残れる感じがします。
[後編に続く]
























