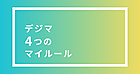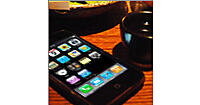■ことの発端はモバイルゲームのスマート化

「ことの発端はスマート化っていうことなんだけど、僕は今年、2010年はケータイ電話が“賢くなって”スマートフォンに行く流れと、PCが“余計なものをそぎ落として”スマートブックに行く流れが同時に起きて、その『スマートデバイス』とでも呼べるようなものがクロスオーバーする年だと考えているんだ」
S氏「賢いスマートと、痩せるスマートね」
A子「スマートには、2つの意味があるわけですね」

「この一見、逆方向の進化が同時に起きていることから、スマート化という流れはおそらく単一の完成したデバイスへ向かっていると言っていい。その1つの形がたとえば『iPad』だったりする」
S氏「でも……iPadは……ショージキどうなの? デカすぎない?」
A子「大きすぎですよね」

iPad

「iPadは確かに究極の答じゃないかもしれないけど、次のステップを踏み出すためには非常に重要な製品だと思うよ」
S氏「まあ斬新ではあるよね」
A子「でもiPadだけで仕事が全部できるなら、逆にMacBookがデカすぎるって感じるかも」

「まあiPadは置いといて、これがスマート化という現象だと思っているのね。『スマートなデバイスとはなにか?』という問いにみんなで答えている。しかも、それが小さいほうから大きいほうへという流れと、大きいほうから余分なものを取り除いて小さく、という、見た目は逆のベクトルの流れが同時に発生してる」
S氏「ダウンサイジングと高機能化が同時に発生しているわけね」

「そして同じことが、たぶん今ゲームにも起きてる」
A子「mixiアプリとか?」
S氏「ソーシャルゲームねえ……。確かにおもしろいっちゃあ、おもしろいんだけど……」

「進化の歴史でいうと、コンピュータゲームは、いわばメモリ上に“どれだけ宇宙を詰め込めるか”という歴史だった。表現手段が向上してモノクロのドットしかなかった時代から、カラー化、ハイレゾ(高精細)化、ワイヤーフレーム、ポリゴン、テクスチャ、プログラマブルシェーダーと進化してきた」
S氏「その結果、仕事がいつになっても終わらない(笑)。正直、最先端のCGテクニックはコードとしては理解できるけど、理論として理解するのはキツくなってきたなあ」

「ところがゲーム性を見てみると、どんどん単純化されていっているんだよね。海外の主流である一人称視点のシューティングゲーム(FPS)を見てみると、ルールはあってないようなもの。体感的にルールを理解するような仕組みになっていて、基本的には『死ぬな、殺せ』という原則しかない」
S氏「まあそういう単純ところがウケてる原因なんだろうけどね。日本だとまだまだ流行んないよなあ」

「え、シューティングゲームやらないの?」
S氏「いや、大好きだけど(笑)。でも、他人には勧められないよね。やっぱり。男の子の趣味っぽい感じ。A子さんとか、戦争ゲームとか別に興味ないでしょ」
A子「私、プレステのゲームとか、すぐ酔っちゃうからできないんですよねー」