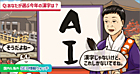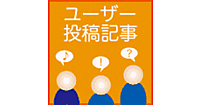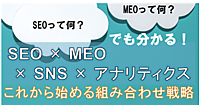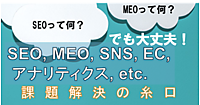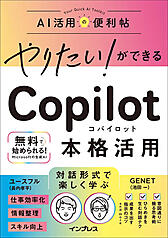全 648 記事中 601 ~ 648 を表示中
新着記事
編集部からのおしらせ
生成AIの入門書『やりたい!ができる Copilot本格活用』を3名様にプレゼント
12月19日 10:00
セミナー満足度 年間ランキングTop20【2025年 Web担当者Forum主催イベント】
12月18日 7:05
花王、三菱電機、パナソニックコネクトなどが登壇!2/4 オンライン開催 デジタルマーケターズサミット 2026 Winter【広告主・マーケター限定】
12月17日 14:00
【歳末&新春キャンペーン】Web担メルマガが50%OFF! 13.5万人超が購読する「Web担ウィークリー」
12月17日 10:00
AIの企業導入ガイドブック『生成AI「戦力化」の教科書』を3名様にプレゼント
12月12日 10:00
すべて見る