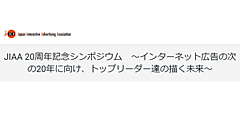「コクヨの役員だったらGPTで何する?」で語られた活用アイデアとは?
コクヨが生成AIの実践教育プログラム「GPT-Lab」を社員向けに実施。16個の生成AI業務アプリをビジネスサイドの社員たちが開発した。
2024年5月22日 7:00
多くの企業が生成AIの活用を模索する中、コクヨでは、人材教育・実践プログラム「KOKUYO DIGITAL ACADEMY(コクヨ デジタル アカデミー)」から生まれた、GPTアイデアの実践経験の場「GPT-Lab(ジーピーティー ラボ)」の第1期成果発表会が2024年4月11日、東京・品川オフィス「THE CAMPUS」で開催された。
第一部では、参加者59名(5チーム)による生成AI活用事例の成果発表会が行なわれ、第二部では、社外ゲストを迎えて「コクヨの役員だったらGPTで何する?」をテーマにパネルディスカッションが実施された。

第一部:発表会
社内研修プログラムで非エンジニア社員たちが16個の「生成AI業務アプリ」を開発
「GPT-Lab」は、GPTアイデアの実践経験の場として、コクヨグループ社員向けのデジタル人材教育・実践プログラム「KOKUYO DIGITAL ACADEMY」(2023年6月に開校)の一環として行われたもの。
一般的な企業研修では、「研修で学んだことを業務に活かしきれない」という課題がある。この課題に対して「GPT-Lab」では、講義で得た知識を使って、オフィス家具の製品企画やBtoB通販での営業など、さまざまな事業に携わる生成AI業務アプリのプロトタイプを非エンジニアである社員たちが作るという企画だ。
今回の発表会に参加したのは59名(A~Eの5チーム)。各チーム2~3つのテーマで発表し、アイデアは全部で16個あった。
誠実な変態賞という賞を受賞した、「没入会議サマライザー」は、音声認識技術とLLM(Large language Models:大規模言語モデル)を用いて、議事録作成業務や会議評価を自動化するアプリで、さまざまな部門で活用できる。
日本経済新聞社の小林氏は、「部門や事業を横断して使えるアイデアが多くあったので、大変刺激を受けました」と語り、また、「1つのアプリで複数の課題を解決する視点」があったことを賞賛した。
トラスコ中山の数見氏は、GPTでお客様の課題を解決するという視点をもつことの大切さに注目。「今日の発表でよく出てきた言葉が『お客様』でした」と話した。

第二部
社外ゲストが、経営者目線でコクヨに提案!
成果発表会後に行われたパネルディスカッションのテーマは、「コクヨの役員だったらGPT(Generative Pre-trained Transformer)で何する?」だ。
- 富士通株式会社 執行役員 EVP CDXO、CIO 福田譲氏
- トラスコ中山株式会社 取締役 経営管理本部 本部長 兼 デジタル戦略本部 本部長 兼 オレンジブック本部 本部長 数見篤氏
- 日本経済新聞社 プラットフォーム推進室 マーケティング&グロースG部長 小林秀次氏
- J.フロント リテイリング株式会社 執行役常務 デジタル戦略統括部長 兼 株式会社大丸松坂屋百貨店 取締役 林直孝氏
- 東京大学大学院 教授 田中謙司氏
- コクヨ株式会社 Executive Adviser of AI strategy、株式会社カウネット 社外取締役 野口竜司氏
- コクヨ株式会社 執行役員 ビジネスサプライ事業本部長、株式会社カウネット 代表取締役社長 宮澤典友氏
パネリストから出されたアイデアのうち、当日の参加者からの人気投票で上位だったものが次の3つだった。
- 俺の/私のラグノート
- 会議AI
- 式神AI
新製品発売⁉ 「俺の/私のラグノート」
「コクヨの役員だったら新製品を出したい」と語る富士通の福田氏の提案は、個人の外部記憶脳として使える「ラグ(RAG:Retrieval-Augmented Generation)ノート」。参加者による人気投票で1位となったアイデアだ。
以前に読んだ本の内容、恩師から聞いた言葉など、ふと思い出そうとしても思い出せない経験は誰にでもあるだろう。そうした気になったことをアプリ「ラグノート」に書いておくことで、いつでも思い出せる仕組みをつくったらおもしろいのではないか、というものだ。
ただし、このアプリには弱点があるという。もはや自分では何も覚えようとしなくなることだ。そこで、「たまには穴あき問題などでリマインドしてくれる機能があると、人間とAIとが共生する文具になると思います」と学習機能も付加価値として提案した。
「勉強・学習の定義を変えていけるポジションにいらっしゃるのがコクヨさん。ラグノートはベストセラーになると思いますので、ぜひ製品化をお願いします!」と福田氏。笑顔で製品化をアピールしていた。
しゃべり過ぎている人を注意してくれる「会議AI」
「『没入会議サマライザー』に、ファシリテーション能力をプラスしてほしい」と語るのは、J.フロント リテイリングの林氏だ。没入会議サマライザーは先述したように、音声認識技術やLLMによって、自動で議事録を作成したり、会議を評価したりするアプリ。
そのアプリに、会議を仕切って、しゃべりすぎている人には会議途中でも注意するファシリテーターを入れてほしいという。これは、さまざまな企業で欲しいアプリなのではないだろうか。人気投票で2位となった。
KPIに設定する!?「式神AI」
「陰陽師は式神に花をとってきてもらったりしていますよね」と話す東京大学の田中氏のアイデアは、「式神AI」だ。陰陽師は式神をさまざまな目的に使っているが、田中氏は、「陰陽師に代わってAIで式神のプログラムを作るとよい」という。1人が活動する24時間は、3人だと72時間になる。式神が多ければ多いほど、1日で行えることが増えていくわけだ。
そこで田中氏は、「式神が何人いるかをKPIとして、経営の視点と人事の視点で増やしていくといいのでは?」と語り、さらに「特級式神を作った人を評価するのもいいですね」と提案。人気投票で3位となった。
素敵なアイデアに会場が盛り上がる中、コクヨの野口氏は次のように語り、パネルディスカッションを締めた。
生成AI以前のAIでは、実現できないことが多かったのが現実でした。しかし現在では、実現できることが増えたと実感しています。どんどん新しいAIをつくって世の中に出していきたいと思います(野口氏)
「GPT-Lab」受賞アイデア
パネルディスカッション後には授賞式が行なわれた。業務改善・利用人数・効果の観点で優れ、かつすぐにでも業務利用可能なアイデアには「Quickwin賞」、システム連携などの開発が必要ではあるものの、Quickwin賞同様優れたアイデアには「Moonshot賞」、ダイレクトな効果の大小問わず何らかの価値を突き詰めたアイデアには「誠実な変態賞」、そしてコクヨグループ社員によるオンライン投票でもっとも票数が多かったアイデアには「オーディエンス賞」の4つの賞が贈られた。
競合品拾い出しAI(Quickwin賞・オーディエンス賞)
LLM(Large language Models:大規模言語モデル)を用いて、お客様の既存製品に相当するコクヨ製品情報を検索し、営業担当者に提案するアプリ。テーマ設定の観点や実現性、拡張性が評価され、Quickwin賞とオーディエンス賞を獲得。
顧客ニーズ発見AI(Moonshot賞)
写真内容を画像処理AIでテキスト化して蓄積。LLMを用いて蓄積情報から新商品のアイデアの元となる企画案を生成するアプリ。顧客への提案アイデアの幅を広げることができる点が評価され、Moonshot賞を獲得。
没入会議サマライザー(誠実な変態賞)
音声認識技術とLLMを用いて、議事録作成業務・会議評価を自動化するアプリ。

富士通の福田氏が、「四角いタイヤの荷車を押すのが仕事だとすると、テクノロジーは四角いタイヤを丸くすること。自動化技術が進んでいる今では、人間がやることは荷車を押す仕事ではなく、押さなくてよくすることが仕事だと思います」と話していたことが印象深かった。テクノロジーは、現場での課題、経営層が考える課題、そのさまざまな課題の解決をもたらすと同時に、これまでの仕事の枠組みをまったく変えてしまう可能性があると感じたイベントだった。