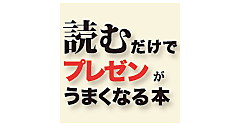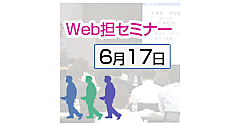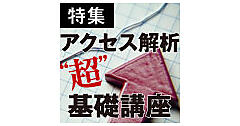「見た目」や「検索エンジンで○位」ではなくユーザー視点で客観的に調べ直すための指標
「見た目」や「検索エンジンで○位」ではなく
ユーザー視点で客観的に調べ直すための指標

株式会社 環
営業統括部 リーダー
ホームページ診断書を始めたきっかけは?
自社のサイトが本当に良いのか悪いのかを定量的に測る手法をだれでも簡単に使えるようにと考えて作りました。「サイトが良いのか悪いのか」を判断するためには、ライバル企業だとか、目的が同じ他のサイトを見ながら同じ基準で評価し、それと自分のサイトを比較して判断できるように作ってあります。
今はみなさんアクセス解析をしてサイトのパフォーマンスを評価していると思うのですが、アクセス解析でわかるのはページビュー数だとかユーザー数だとか、訪問者がたどった動線という「結果」なんですよね。でも、その結果には出ない部分もあるはずなので、アクセス解析データと併せて判断する指標として作りました。
どんな風に使ってほしい?
どこか競合と比較して、自分のサイトが優れているのか劣っているのかを、改めて実感してほしいですね。
見た目のビジュアルデザインで「何となく良い」だとか、SEOで順位が上がった下がったで一喜一憂するのではなく、ユーザー視点で客観的に調べることで、自社サイトに弱点がないかを改めて見直してほしいです。最初にウェブサイトを作ったときは気にしていても、少しずつサイトをいじっていくうちに、基本的な要素がうっかり失われてしまうこともありますから。
また、ウェブサイトのリニューアルをするときなどに、制作会社がちゃんとこういった点を理解しているかをチェックするためにも使えますね。発注する側が的確に判断できるようにする土台に使ったり、または制作会社を見極めるために質問する素材として使うのもいいでしょう。
もちろん、診断するのはサイトを改善するための準備ですから、結果をみて問題のある点は修正していかなきゃ意味がないです。このホームページ診断に含まれている項目は基本的なことばかりなので、細かくチェックしていって全部クリアするようにしたいですね。もちろん、サイトの規模感や改修の費用対効果によって優先度は付けるべきですが。
何点とれば合格でしょうか?
点数に関しては、及第点とか合格点という考え方はとっていません。漏れている点がないかをチェックする用途で使ってほしいですね。
リニューアル時の要件検討や他社との比較をするための入り口としては、特に何点で合格という考えではなくなりますね。診断で外側をチェックして、その後アクセス解析で内側をチェックして、そこからリニューアルに進むことが多いです。
実際に、当事者が認識していなかった問題点を診断書で明らかにして他社と比べることで「あ、うち悪いんだね」と現状を認識できた例も多いです。
ちゃんとできていて当然の部分をまず押さえたうえで、ユーザー視点に基づいたリニューアルを行う土台ですから、強いて合格点を設定するとしたら……満点でしょうか。
なぜ環がホームページ診断を?
そもそも環のビジネスの軸は、アクセス解析をもとにしたウェブサイトのトータルソリューションの提供です。制作、リスティング広告、LPO、ユーザービリティなど、コンサルティング全般を行っています。「使い勝手の良いウェブサイト」の足回りを全部そろえられるように、システム開発も自社で行う態勢をもっています。
以前からアクセス解析とあわせてホームページ診断はやっていたのですが、2007年ごろにアクセス解析とサイト制作という2つの仕事の軸が近づいてきたので、改めてホームページ診断という形でまとめ直したのです。アクセス解析を使った定量的な解析による現状分析は以前から得意だったんですが、デザインや要素などの定性的な部分に関して、このメソッドで強化した形ですね。
制作会社が基本を理解しているかチェックしたり質問したりするのにも使えますよね
株式会社 環
http://www.kan-net.com/
2000年2月に制作会社として設立され、「アクセス刑事」をはじめとする各種ツールを提供してきた環は、ウェブサイト制作とアクセス解析サービスを中心とし、さらにLPO、SEMやシステム開発なども併せて提供することで、企業サイトで「結果を出す」ことを旨として活動している。 2003年1月からは、7つの大学・研究所との産学共同研究により、消費者行動マーケティングにつなげていくための基礎研究を行っている。 現在同社が提供する代表的なサービスとしては、次のようなものがある。
- シビラ――アクセス解析サービス
- シビラオプティマイゼーション――LPOツール
- アクセス刑事(デカ)Pro2――低価格版アクセス解析