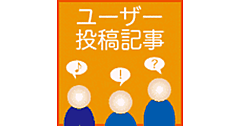また、編集部はこの内容について正確性を保証できません。
中華圏は範囲が広いです。
各地それぞれに言語があることは皆さまもご存知かと思います。例えば、上海語、四川語などです。
今、私たちが認知している中国語は、実は北京語に基づいています。北京語は中国大陸、台湾などでは主要言語として使われています。私の出身地、香港は北京語も通じますが、香港粤語(広東語)が主に使われている言語です。
今回は香港粤語(広東語)と北京語の違いを紹介してみます。
実は清の時代のはじめは、中国の標準語は北京語ではありませんでした。
しかし、時間が経って、北京語が徐々に主要の言語になりました。国の管理を強化するため、雍正帝は北京語を標準語にする政策を制定しました。そして、1920年代に、多くの人の努力で北京語を元に現代標準漢語が誕生しました。現代標準漢語(北京語)では51の声母、39の韻母があったと言われていて、4つの声調があります。
一方、広東語は20の声母、94の韻母、9つの声調があります。
現代標準漢語(北京語)と違って、広東語は多くの古代漢語が残っています。そして、清の時代からイギリスとの接触が多く、広東語の中には、英語の影響も見られます。例えば、「符碌」(意味:僥倖)・発音は「フールッ」(語源:fluke)・北京語で言うと「侥幸(ヂィアォシィン)」、「杯葛」(意味:ボイコット)・発音は「ブイコッ」(語源:Boycott)・北京語で言うと「抵制(ディーヂィー)」、「忌廉」(意味:クリーム)・発音は「ゲイニム」(語源:Cream)・北京語で言うと「奶油(ナァィヨウ)」など。

また、以下は北京語と広東語(香港粤語)のいくつかの例です。
▼続きはこちら▼
https://citrusjapan.co.jp/column/cj-column/w011_201909.html