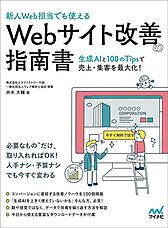Insight for WebAnalytics
企業Facebookページでファン数100未満が46%、Facebook利用者の7割弱がFacebook友達30人以下 など
企業Facebookページでファン数100未満が46%、Facebook利用者の7割弱がFacebook友達30人以下
2011/9/27のIMJモバイルのリリースから。http://www.imjmobile.co.jp/news/report_20110927-318.html
米Facebookの曜日別訪問シェア、土日に高くなる傾向
2011/9/27のHitwiseのブログから。
http://weblogs.hitwise.com/heather-dougherty/2011/09/facebook_where_we_reach_out_wh.html
ブラジルのSNS、Facebookが強いがOrkutの伸びが急
2011/9/27のcomScore Data Mineから。http://www.comscoredatamine.com/2011/09/orkut-leads-social-networking-market-in-brazil-but-facebook-growing-fast/
2011/9Facebook利用者数が最も伸びた国はブラジル、300万人、12%増
2011/9/27のsocialbakersの記事から。http://www.socialbakers.com/blog/258-top-growing-countries-on-facebook-in-september/
米アップルの噂サイト、製品発表に先行して利用が急増
2011/9/27のcompeteのブログから。
http://blog.compete.com/2011/09/27/is-october-4th-time-for-the-5th-iphone/
2011/9/27のIMJモバイルのリリースから。http://www.imjmobile.co.jp/news/report_20110927-318.html
米Facebookの曜日別訪問シェア、土日に高くなる傾向
2011/9/27のHitwiseのブログから。
http://weblogs.hitwise.com/heather-dougherty/2011/09/facebook_where_we_reach_out_wh.html
ブラジルのSNS、Facebookが強いがOrkutの伸びが急
2011/9/27のcomScore Data Mineから。http://www.comscoredatamine.com/2011/09/orkut-leads-social-networking-market-in-brazil-but-facebook-growing-fast/
2011/9Facebook利用者数が最も伸びた国はブラジル、300万人、12%増
2011/9/27のsocialbakersの記事から。http://www.socialbakers.com/blog/258-top-growing-countries-on-facebook-in-september/
米アップルの噂サイト、製品発表に先行して利用が急増
2011/9/27のcompeteのブログから。
http://blog.compete.com/2011/09/27/is-october-4th-time-for-the-5th-iphone/
2011Q2国内携帯電話出荷台数は前年同期比15.2%減の822万台、スマートフォン出荷台数比率は、45.5% など
2011Q2国内携帯電話出荷台数は前年同期比15.2%減の822万台、スマートフォン出荷台数比率は、45.5%
2011/9/27のIDC Japanのリリースから。http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110927Apr.html
民生用モバイル位置情報ビジネス市場、2015年に1,470億円
2011/9/27のシード・プランニングのリリースから。http://www.seedplanning.co.jp/press/2011/2011092701.html

2011/9/27のIDC Japanのリリースから。http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20110927Apr.html
民生用モバイル位置情報ビジネス市場、2015年に1,470億円
2011/9/27のシード・プランニングのリリースから。http://www.seedplanning.co.jp/press/2011/2011092701.html
米検索専門エンジンの検索数は伸びるも、バーティカル検索は停滞 など
米検索専門エンジンの検索数は伸びるも、バーティカル検索は停滞
2011/9/27のcomScore Voicesから。http://blog.comscore.com/2011/09/searcher_intent_why_vertical_s.html
2011/8米検索エンジンシェア、AOL含めたGoogleベースは68.3%
2011/9/27のcompeteのブログから。http://blog.compete.com/2011/09/27/august-2011-us-search-market-share-report/
2011/9/24の週の米検索エンジンシェア、Googleが65.78%。http://www.hitwise.com/us/datacenter/main/dashboard-23984.html
2011/9/24の週の豪検索エンジンシェア、Googleが93.77%http://www.hitwise.com/au/datacentre/main/dashboard-1706.html
2011/9/27のcomScore Voicesから。http://blog.comscore.com/2011/09/searcher_intent_why_vertical_s.html
2011/8米検索エンジンシェア、AOL含めたGoogleベースは68.3%
2011/9/27のcompeteのブログから。http://blog.compete.com/2011/09/27/august-2011-us-search-market-share-report/
2011/9/24の週の米検索エンジンシェア、Googleが65.78%。http://www.hitwise.com/us/datacenter/main/dashboard-23984.html
2011/9/24の週の豪検索エンジンシェア、Googleが93.77%http://www.hitwise.com/au/datacentre/main/dashboard-1706.html
米69%の人が地方新聞は既にないと言うも、地域情報を得るのにそれ程影響はない など
米69%の人が地方新聞は既にないと言うも、地域情報を得るのにそれ程影響はない
2011/9/26のInternet & American Life Projectのリリースから。http://www.pewinternet.org/Reports/2011/Local-news.aspx
2015年にブルーレイプレーヤが105百万台出荷
2011/9/26のIn-Statのリリースから。
http://www.instat.com/press.asp?ID=3267&sku=IN1104965ME

2011/9/26のInternet & American Life Projectのリリースから。http://www.pewinternet.org/Reports/2011/Local-news.aspx
2015年にブルーレイプレーヤが105百万台出荷
2011/9/26のIn-Statのリリースから。
http://www.instat.com/press.asp?ID=3267&sku=IN1104965ME
米2011/8スマートフォン購入者、Android比率が56% など
米2011/8スマートフォン購入者、Android比率が56%
2011/9/26のNielsenのブログから。http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/in-u-s-market-new-smartphone-buyers-increasingly-embracing-android/
米スマートフォン利用者数の性別トレンド、25-34歳が2011/7に2,230万人に
2011/9/26のcomScore Data Mineから。http://www.comscoredatamine.com/2011/09/u-s-smartphone-audience-growth-by-age-segment/

2011/9/26のNielsenのブログから。http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/in-u-s-market-new-smartphone-buyers-increasingly-embracing-android/
米スマートフォン利用者数の性別トレンド、25-34歳が2011/7に2,230万人に
2011/9/26のcomScore Data Mineから。http://www.comscoredatamine.com/2011/09/u-s-smartphone-audience-growth-by-age-segment/
米Google+の利用がソーシャルネットワークカテゴリーの第3位に浮上 など
米Google+の利用がソーシャルネットワークカテゴリーの第3位に浮上
2011/9/26のHitwiseのブログから。
http://weblogs.hitwise.com/heather-dougherty/2011/09/google_opens_the_floodgates_to.html
米インターネットラジオのPandora.com、1,200万人に利用者を伸ばす
2011/9/26のcompeteのブログから。http://blog.compete.com/2011/09/26/pandoras-box-of-marketing-mobile-seo-facebook-music/
北米のTwitter利用者はWindows利用者シェアが9割を超え、Google+利用者は7割に満たない
2011/9/26のChitika Insightsの記事から。http://insights.chitika.com/2011/social-media-and-operating-systems-tweeters-love-windows-plusers-and-stumblers-love-mac/
北米Windows8のシェア、9/15-9/17の3日間は上昇もそれ以降は停滞
2011/9/26のChitika Insightsの記事から。
http://insights.chitika.com/2011/is-windows-8-the-window-into-microsofts-future-or-decline/

2011/9/26のHitwiseのブログから。
http://weblogs.hitwise.com/heather-dougherty/2011/09/google_opens_the_floodgates_to.html
米インターネットラジオのPandora.com、1,200万人に利用者を伸ばす
2011/9/26のcompeteのブログから。http://blog.compete.com/2011/09/26/pandoras-box-of-marketing-mobile-seo-facebook-music/
北米のTwitter利用者はWindows利用者シェアが9割を超え、Google+利用者は7割に満たない
2011/9/26のChitika Insightsの記事から。http://insights.chitika.com/2011/social-media-and-operating-systems-tweeters-love-windows-plusers-and-stumblers-love-mac/
北米Windows8のシェア、9/15-9/17の3日間は上昇もそれ以降は停滞
2011/9/26のChitika Insightsの記事から。
http://insights.chitika.com/2011/is-windows-8-the-window-into-microsofts-future-or-decline/
「アトリビューション」は今年の流行語だけど簡単ではなさそう [週刊IFWA 2011/8/29]
定期メルマガの巻頭コラムのアーカイブです。メルマガの登録はこちら↓からどうぞ。
http://ibukuro.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html
■ 「アトリビューション」は今年の流行語だけど簡単ではなさそう
今年に入って、Google アナリティクスの動きが激しいですが、新しいGoogleアナリティクス(バージョン5)のレポート画面で、マルチチャネルという機能が全員に正式リリースされたというアナウンスがありました。
http://analytics.blogspot.com/2011/08/introducing-multi-channel-funnels.html
この機能は、「コンバージョン」したセッションの過去の接触媒体(参照元)の履歴を表示するというものです。そのため少なくとも「目標設定」をしておくことが必要ですし、「目標の値」あるいは「eコマースでの収益」などの値を入れておかないと価値換算での評価ができません。
広告効果測定系のツールの一部で既に提供している機能だと思いますが、コンバージョンまでのプロセスを「広告サイトA→検索連動型広告B→」といった具合で、ファーストタッチ(最初の広告接触)からラストタッチ(コンバージョンに至った広告)まで表示するようなレポートが代表的なアウトプットになります。
表示の粒度は「有料広告」「オーガニック検索」「ソーシャル ネットワーク」「参照元サイト」「メール」「フィード」「ノーリファラー」などとなっているのですが、自分のサイトの事情によってこの分類や、その内容をカスタマイズすることができます。さらに検索のところは、キーワード別に表示をすることまで可能です。
私なんぞは、こういうデータを見るだけでも可能性を感じてワクワクする訳ですが、一方でこれらを具体的にどう活かしていくのか、簡単に活かせるものなのだろうかというところが最も大事です。
そんな状況なので最近はアクセス解析イニシアチブのクローズの分科会でアトリビューション(貢献)分析について隔週くらいで勉強会を行っています。アクセス解析の経路分析ほどではないにしても、接触履歴は発散するし、単に結果を眺めるだけでは何も生み出しません。
やはり仮説検証型というか、まず問題意識を持ってそれからデータを見るというのが、最低限の活用条件になるのではないかと再確認した次第です。そのためには自分のサイトの事情に応じた初期設定やカテゴリー分け、広告の手動パラメータの付与といったがカスタマイズが重要で、はじめが肝心というのは同じです。
その上で、本当に施策に落とし込めるような発見ができるのかというのは簡単ではなさそうだというのが、正直なところです。
http://ibukuro.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html
■ 「アトリビューション」は今年の流行語だけど簡単ではなさそう
今年に入って、Google アナリティクスの動きが激しいですが、新しいGoogleアナリティクス(バージョン5)のレポート画面で、マルチチャネルという機能が全員に正式リリースされたというアナウンスがありました。
http://analytics.blogspot.com/2011/08/introducing-multi-channel-funnels.html
この機能は、「コンバージョン」したセッションの過去の接触媒体(参照元)の履歴を表示するというものです。そのため少なくとも「目標設定」をしておくことが必要ですし、「目標の値」あるいは「eコマースでの収益」などの値を入れておかないと価値換算での評価ができません。
広告効果測定系のツールの一部で既に提供している機能だと思いますが、コンバージョンまでのプロセスを「広告サイトA→検索連動型広告B→」といった具合で、ファーストタッチ(最初の広告接触)からラストタッチ(コンバージョンに至った広告)まで表示するようなレポートが代表的なアウトプットになります。
表示の粒度は「有料広告」「オーガニック検索」「ソーシャル ネットワーク」「参照元サイト」「メール」「フィード」「ノーリファラー」などとなっているのですが、自分のサイトの事情によってこの分類や、その内容をカスタマイズすることができます。さらに検索のところは、キーワード別に表示をすることまで可能です。
私なんぞは、こういうデータを見るだけでも可能性を感じてワクワクする訳ですが、一方でこれらを具体的にどう活かしていくのか、簡単に活かせるものなのだろうかというところが最も大事です。
そんな状況なので最近はアクセス解析イニシアチブのクローズの分科会でアトリビューション(貢献)分析について隔週くらいで勉強会を行っています。アクセス解析の経路分析ほどではないにしても、接触履歴は発散するし、単に結果を眺めるだけでは何も生み出しません。
やはり仮説検証型というか、まず問題意識を持ってそれからデータを見るというのが、最低限の活用条件になるのではないかと再確認した次第です。そのためには自分のサイトの事情に応じた初期設定やカテゴリー分け、広告の手動パラメータの付与といったがカスタマイズが重要で、はじめが肝心というのは同じです。
その上で、本当に施策に落とし込めるような発見ができるのかというのは簡単ではなさそうだというのが、正直なところです。
コミュニケーション能力を上げていこう [週刊IFWA 2011/8/22]
定期メルマガの巻頭コラムのアーカイブです。メルマガの登録はこちら↓からどうぞ。
http://ibukuro.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html
■ コミュニケーション能力を上げていこう
先週Google アナリティクスの「セッション」の定義が変更するという話をしました。仕様解説の続編をする積りはないのですが、Googleらしく、ちょっと変わったロジックであるということが真相のようです。
Google アナリティクスの場合は無料のツールですから仕方ないとしても、サービス提供側の情報提供のあり方について考えさせられました。私がよくお話するのは、こういうデータは最初の設定とか、言葉の定義とか計算式が大事で、それがしっかりしていないと判断を誤る事にもなりかねません。
今回のGoogleからの発表(Google Analytics公式ブログ(英語版))を見ると、説明不足の感は否めません。「これこれは含みます」と一例だけ示されても全貌は不明のままで、これは疑問を生むだけです。何が含まれ、何は含まないという定義を示してくれないとダメだと思います。
いくら技術の会社だと言っても、プロダクトマーケティングの責任者が、正確な情報を発信しなければならないと思います。
ということで、タイトルの話題に入るのですが、企業側の発表だけに止まらず、あらゆる仕事・プライベートで、思いを正しく伝える能力というのが、生きていく上での根本的に必要な技術だと考えています。
コミュニケーションが下手だと、無用な質問や疑問、疑惑や信用不安で、発信している本人にも返ってくることになるので、中途半端な伝え方や情報提供は双方にとってデメリットです。「お前の言っていることわからない」と平気で指摘してくれる友人や同僚が傍に居ればよいですが、いつまでもそんな周り人間に期待することは無理です。
私は下記を心掛けています。この10年、「言った言わない、聞いてない」的なトラブルは殆どありませんが、ちょっと怠ると起こってしまうものです。
・情報を網羅して発信する
・聞き手(受取手)の立場になって文書や言い方を考える
・場面や手段に応じた適切な応対をする
・オンラインだけで処理せず、面と向かって話をする
・確認のメモを共有する
・期限前に再確認する
ITリテラシーみたいなこと以前に、コミュニケーション・リテラシーからまず習得すべき方も多いように感じます。自分の場合は、社会人になって3年くらいで、先輩の方法を見習ったり、失敗をすることで習得してきたような気がしますが、コミュニケーションについて、体系的に教わったことは記憶にありません。
皆さんはどうやって習得されてきましたか?
http://ibukuro.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html
■ コミュニケーション能力を上げていこう
先週Google アナリティクスの「セッション」の定義が変更するという話をしました。仕様解説の続編をする積りはないのですが、Googleらしく、ちょっと変わったロジックであるということが真相のようです。
Google アナリティクスの場合は無料のツールですから仕方ないとしても、サービス提供側の情報提供のあり方について考えさせられました。私がよくお話するのは、こういうデータは最初の設定とか、言葉の定義とか計算式が大事で、それがしっかりしていないと判断を誤る事にもなりかねません。
今回のGoogleからの発表(Google Analytics公式ブログ(英語版))を見ると、説明不足の感は否めません。「これこれは含みます」と一例だけ示されても全貌は不明のままで、これは疑問を生むだけです。何が含まれ、何は含まないという定義を示してくれないとダメだと思います。
いくら技術の会社だと言っても、プロダクトマーケティングの責任者が、正確な情報を発信しなければならないと思います。
ということで、タイトルの話題に入るのですが、企業側の発表だけに止まらず、あらゆる仕事・プライベートで、思いを正しく伝える能力というのが、生きていく上での根本的に必要な技術だと考えています。
コミュニケーションが下手だと、無用な質問や疑問、疑惑や信用不安で、発信している本人にも返ってくることになるので、中途半端な伝え方や情報提供は双方にとってデメリットです。「お前の言っていることわからない」と平気で指摘してくれる友人や同僚が傍に居ればよいですが、いつまでもそんな周り人間に期待することは無理です。
私は下記を心掛けています。この10年、「言った言わない、聞いてない」的なトラブルは殆どありませんが、ちょっと怠ると起こってしまうものです。
・情報を網羅して発信する
・聞き手(受取手)の立場になって文書や言い方を考える
・場面や手段に応じた適切な応対をする
・オンラインだけで処理せず、面と向かって話をする
・確認のメモを共有する
・期限前に再確認する
ITリテラシーみたいなこと以前に、コミュニケーション・リテラシーからまず習得すべき方も多いように感じます。自分の場合は、社会人になって3年くらいで、先輩の方法を見習ったり、失敗をすることで習得してきたような気がしますが、コミュニケーションについて、体系的に教わったことは記憶にありません。
皆さんはどうやって習得されてきましたか?
「実践ソーシャル・メディア・マーケティング 戦略・戦術・効果測定の新法則」を読んだ
本書は2010年4月にWileyから出版された「Social Media Metrics: How to Measure and Optimize Your Marketing Investment (New Rules Social Media Series)」の日本語訳本である。しばらく洋書を読むのが億劫だった時期にあたったためか、原書は読んでいなかったので、日本語版で読ませてもらった。
英語のタイトルを素直に翻訳すると「実践ソーシャル・メディア・マーケティング 戦略・戦術・効果測定の新法則」という日本語のタイトルは違和感があるが、まあよいだろう。計測という視点で貫かれているものの、ソーシャル・メディア・マーケティングについて順序立てて追っていく構成になっているので。
それは目次を見てもらえれば感じてもらえるだろう。ただ、各種測定ツールの紹介オンパレードを期待しているのであれば、そういう方にはお勧めしない。個別のツールについての紹介などは殆どないからだ。実は私もそういうものが結構ある本なのかと思って読み始めたのだがそうではなかった。
もちろん基本的な計測指標は沢山羅列されているし解説もしているが、KPI大全集みたいな構成でもない。あくまでも原則を大雑把に追っていき、自分にあった計測手段と指標を考える上で網羅的に概観している本だ。なので表層的な計測テクニックを期待しているような方にもお勧めしない。
この手の本が翻訳されることは少ないと思っていたのだが、昨今のソーシャル流行りが要因かはわからないが、翻訳本が原書から1年もしないでリリースされたのはよい知らせだ。Jim Sterneと言えば、米アクセス業界で第一人者として知られる一人だ。
彼のそういった原則本はワクワクするようなものでもないが、味がある。第8章には組織への浸透的な話まである。個人的には翻訳で300ページにも満たず、多少物足りなさがなかったというのが正直な感想だが、関係者には必読書となるだろう。
<目次>
序章:まずは基本原則の理解から
第1章:目標を設定する
第2章:ユーザーの注目をひく
第3章:影響力を知る
第4章:感情を汲む、人の気持ちを読む
第5章:行動を促す
第6章:メッセージを聞く
第7章:結果を出す
第8章:社内を発奮させる
第9章:そしてこれから
発行:朝日新聞出版
著者:Jim Sterne
訳者:酒井 泰介
定価:2,200円+税
約270ページ
関連リンク:
書評ページをまとめた
英語のタイトルを素直に翻訳すると「実践ソーシャル・メディア・マーケティング 戦略・戦術・効果測定の新法則」という日本語のタイトルは違和感があるが、まあよいだろう。計測という視点で貫かれているものの、ソーシャル・メディア・マーケティングについて順序立てて追っていく構成になっているので。
それは目次を見てもらえれば感じてもらえるだろう。ただ、各種測定ツールの紹介オンパレードを期待しているのであれば、そういう方にはお勧めしない。個別のツールについての紹介などは殆どないからだ。実は私もそういうものが結構ある本なのかと思って読み始めたのだがそうではなかった。
もちろん基本的な計測指標は沢山羅列されているし解説もしているが、KPI大全集みたいな構成でもない。あくまでも原則を大雑把に追っていき、自分にあった計測手段と指標を考える上で網羅的に概観している本だ。なので表層的な計測テクニックを期待しているような方にもお勧めしない。
この手の本が翻訳されることは少ないと思っていたのだが、昨今のソーシャル流行りが要因かはわからないが、翻訳本が原書から1年もしないでリリースされたのはよい知らせだ。Jim Sterneと言えば、米アクセス業界で第一人者として知られる一人だ。
彼のそういった原則本はワクワクするようなものでもないが、味がある。第8章には組織への浸透的な話まである。個人的には翻訳で300ページにも満たず、多少物足りなさがなかったというのが正直な感想だが、関係者には必読書となるだろう。
<目次>
序章:まずは基本原則の理解から
第1章:目標を設定する
第2章:ユーザーの注目をひく
第3章:影響力を知る
第4章:感情を汲む、人の気持ちを読む
第5章:行動を促す
第6章:メッセージを聞く
第7章:結果を出す
第8章:社内を発奮させる
第9章:そしてこれから
発行:朝日新聞出版
著者:Jim Sterne
訳者:酒井 泰介
定価:2,200円+税
約270ページ
関連リンク:
書評ページをまとめた
米OS別クリック率、iPad、Android2.2が高い など
米OS別クリック率、iPad、Android2.2が高い
2011/9/23のChitika Insightsの記事から。
http://insights.chitika.com/2011/which-operating-systems-are-most-valuable-to-publishers/
米Google+利用者のブラウザ、Chrome比率が高い
2011/9/23のChitika Insightsの記事から。
http://insights.chitika.com/2011/what%E2%80%99s-the-most-popular-browser-on-your-site-it-matters/

2011/9/23のChitika Insightsの記事から。
http://insights.chitika.com/2011/which-operating-systems-are-most-valuable-to-publishers/
米Google+利用者のブラウザ、Chrome比率が高い
2011/9/23のChitika Insightsの記事から。
http://insights.chitika.com/2011/what%E2%80%99s-the-most-popular-browser-on-your-site-it-matters/
Above the fold(ファーストビュー)の広告クリック率が0.484%なのに対して、Belowは0.334% など
Above the foldの広告クリック率が0.484%なのに対して、Belowは0.334%
2011/9/22のChitika Insightsの記事から。http://insights.chitika.com/2011/the-importance-of-ad-placement-location-location-and-location/
米2011/8オンライン動画サイト利用、Google(YouTube)は1ヶ月で平均5.7時間閲覧
2011/9/22のcomScoreのリリースから。http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/9/comScore_Releases_August_2011_U.S._Online_Video_Rankings
2011/9/22のChitika Insightsの記事から。http://insights.chitika.com/2011/the-importance-of-ad-placement-location-location-and-location/
米2011/8オンライン動画サイト利用、Google(YouTube)は1ヶ月で平均5.7時間閲覧
2011/9/22のcomScoreのリリースから。http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/9/comScore_Releases_August_2011_U.S._Online_Video_Rankings
ソーシャルネットワーク利用、アジアは利用者ベースで世界の32.5%なのに利用時間シェアは16.5% など
ソーシャルネットワーク利用、アジアは利用者ベースで世界の32.5%なのに利用時間シェアは16.5%
2011/9/22のcomScore Data Mineから。http://www.comscoredatamine.com/2011/09/social-networking-visitation-and-engagement-by-region/
米役職が高いほど、仕事場は職場に限定されない
2011/9/22のForrester Researchのリリースから。http://www.forrester.com/ER/Press/Release/0,1769,1380,00.html
2011/9/22のcomScore Data Mineから。http://www.comscoredatamine.com/2011/09/social-networking-visitation-and-engagement-by-region/
米役職が高いほど、仕事場は職場に限定されない
2011/9/22のForrester Researchのリリースから。http://www.forrester.com/ER/Press/Release/0,1769,1380,00.html
2011年世界のメディアタブレット販売台数は6,360万台、2015年には3.3億台に など
2011年世界のメディアタブレット販売台数は6,360万台、2015年には3.3億台に
2011/9/22のGartnerのリリースから。
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1800514
世界のタブレット出荷台数、2016年には2.5億台に
2011/9/22のJuniper Researchのリリースから。http://www.juniperresearch.com/viewpressrelease.php?pr=260
2011/8国内PC出荷統計、台数ベースで対前年同月比107.3%、金額ベースで91.7%
2011/9/22のJEITAの統計資料から。http://www.jeita.or.jp/japanese/stat/pc/2011/

2011/9/22のGartnerのリリースから。
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1800514
世界のタブレット出荷台数、2016年には2.5億台に
2011/9/22のJuniper Researchのリリースから。http://www.juniperresearch.com/viewpressrelease.php?pr=260
2011/8国内PC出荷統計、台数ベースで対前年同月比107.3%、金額ベースで91.7%
2011/9/22のJEITAの統計資料から。http://www.jeita.or.jp/japanese/stat/pc/2011/
インターネットユーザーのスマートフォン所有率は全体で18.9%、男性20代では3人に1人 など
インターネットユーザーのスマートフォン所有率は全体で18.9%、男性20代では3人に1人
2011/9/22のビデオリサーチインタラクティブのリリースから。http://www.videoi.co.jp/release/20110922_2.html
2011Q2インドの携帯電話出荷台数、対前年同期比6%増、スマートフォンはどう68%増
2011/9/22のIDCのリリースから。
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prIN23051811
2011/9/22のビデオリサーチインタラクティブのリリースから。http://www.videoi.co.jp/release/20110922_2.html
2011Q2インドの携帯電話出荷台数、対前年同期比6%増、スマートフォンはどう68%増
2011/9/22のIDCのリリースから。
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prIN23051811
もしも、「NTTドコモ」を解析するなら(中)
Web担当者Forumの2011/9/22の記事をどうぞ。
http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2011/09/22/11136
関連リンク:
もしも、「NTTドコモ」を解析するなら(上)
もしも、「東京ガス」を解析するなら
もしも、「えきねっと」を解析するなら(前半)
もしも、「よみうりランド」と「としまえん」を解析するなら
もしも、「三井記念病院」を解析するなら
もしも、「帝京大学医学部附属溝口病院」を解析するなら
もしも、「日本相撲協会」を解析するなら
もしも、「浦和レッズ」を解析するなら
もしも、「家庭用太陽電池」を比較検討するなら(後半:京セラを調べる)
もしも、「家庭用太陽電池」を比較検討するなら(前半:シャープのサンビスタを調べる)
もしも、「デジタルカメラ」を比較検討するなら(後半:パナソニックのルミックスを調べる)
もしも、「デジタルカメラ」を比較検討するなら(前半:カシオのエクシリムを調べる)
もしも、「ベルリッツ」を解析するなら(後半:体験レッスンの申し込み)
もしも、「ベルリッツ」を解析するなら(前半:検索からコース詳細ページまで)
もしも、「ライフネット生命保険」を解析するなら(後半:見積もりから申し込みまで)
もしも、「ライフネット生命保険」を解析するなら(前半:検索から商品案内まで)
もしも、「@nifty」を解析するなら(後半:検索から申し込みまで)
もしも、「@nifty」を解析するなら(前半:収益構造から対象ユーザーを想定する)
もしも、「ヤマハ発動機」を解析するなら
もしも、「ドクターシーラボ」を解析するなら(後半)
もしも、「ドクターシーラボ」を解析するなら(前半)
もしも、「川崎市」を解析するなら(後半)
もしも、「川崎市」を解析するなら(前半)
もしも、「ANA」を解析するなら(後半)
もしも、「ANA」を解析するなら(前半)
もしも、三菱東京UFJ銀行サイトを解析するなら(後半)
もしも、三菱東京UFJ銀行サイトを解析するなら(前半)
もしもtoyota.jpを解析するなら(後半)
もしもtoyota.jpを解析するなら(前半)
旧連載分のWeb担当者Fourmの記事はこちら
http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2011/09/22/11136
関連リンク:
もしも、「NTTドコモ」を解析するなら(上)
もしも、「東京ガス」を解析するなら
もしも、「確定申告サイト」を解析するなら (後半)
もしも、「確定申告サイト」を解析するなら (前半)もしも、「DODA」を解析するなら(後半)
もしも、「DODA」を解析するなら (前半)
もしも、「えきねっと」を解析するなら(後半)もしも、「えきねっと」を解析するなら(前半)
もしも、「よみうりランド」と「としまえん」を解析するなら
もしも、「三井記念病院」を解析するなら
もしも、「帝京大学医学部附属溝口病院」を解析するなら
もしも、「日本相撲協会」を解析するなら
もしも、「浦和レッズ」を解析するなら
もしも、「家庭用太陽電池」を比較検討するなら(後半:京セラを調べる)
もしも、「家庭用太陽電池」を比較検討するなら(前半:シャープのサンビスタを調べる)
もしも、「デジタルカメラ」を比較検討するなら(後半:パナソニックのルミックスを調べる)
もしも、「デジタルカメラ」を比較検討するなら(前半:カシオのエクシリムを調べる)
もしも、「ベルリッツ」を解析するなら(後半:体験レッスンの申し込み)
もしも、「ベルリッツ」を解析するなら(前半:検索からコース詳細ページまで)
もしも、「ライフネット生命保険」を解析するなら(後半:見積もりから申し込みまで)
もしも、「ライフネット生命保険」を解析するなら(前半:検索から商品案内まで)
もしも、「@nifty」を解析するなら(後半:検索から申し込みまで)
もしも、「@nifty」を解析するなら(前半:収益構造から対象ユーザーを想定する)
もしも、「ヤマハ発動機」を解析するなら
もしも、「ドクターシーラボ」を解析するなら(後半)
もしも、「ドクターシーラボ」を解析するなら(前半)
もしも、「川崎市」を解析するなら(後半)
もしも、「川崎市」を解析するなら(前半)
もしも、「ANA」を解析するなら(後半)
もしも、「ANA」を解析するなら(前半)
もしも、三菱東京UFJ銀行サイトを解析するなら(後半)
もしも、三菱東京UFJ銀行サイトを解析するなら(前半)
もしもtoyota.jpを解析するなら(後半)
もしもtoyota.jpを解析するなら(前半)
旧連載分のWeb担当者Fourmの記事はこちら
インターネット広告出稿時にはインターネット広告到達者の30.6%が広告を認知
2011/9/22のビデオリサーチインタラクティブのリリースから。http://www.videoi.co.jp/release/20110922.html
ビデオリサーチインタラクティブ、オールアバウト、NTTレゾナント、日本マイクロソフト、ヤフーは、インターネット広告効果に関する共同調査プロジェクト「ネット広告バリューインデックス プロジェクト」の調査結果データを更新した。
本プロジェクトではインターネット広告認知やブランディング効果等、“インターネット広告の露出自体の効果”を検証して効果の基準値を作成することを目的としている。調査結果データの発表は2008年4月、2009年12月に続き、今回で3期目。
■調査結果データより
<インターネット広告効果の基準値>
・インターネット広告出稿時にはインターネット広告到達者の30.6%が広告を認知
・タレント/キャラクターをクリエイティブに使用した場合の認知率は、非使用にくらべ12ポイントアップ
・広告認知者の65.2%が広告内容を理解
・インターネット広告出稿により、広告到達者のメッセージ理解は広告非到達者の1.22倍、広告商品の購入/利用意向は1.15倍に
・広告到達回数の増加と共にインターネット広告認知/ブランディング効果は拡大(広告効果最大化のポイントとなる広告到達回数は“12回”)
・2,000万インプレッション出稿時の広告認知者数は228万人、商品購入/利用喚起者数は71万人
<調査結果より得られた知見>
・調査時期別でみると、広告到達回数がインターネット広告認知率に与える影響はより強力になっている
・広告サイズの拡大や広告クリエイティブのリッチ化の一層の浸透(注)などにより、広告認知者における広告内容の理解度、広告商品の購入/利用喚起やサイトアクセス意向などが上昇しており、インターネット広告効果は拡大傾向
・その他、インターネット広告とテレビ広告を連動した広告出稿は、お互いの広告認知にプラスの影響を与え合っていることが確認
とのことだ。

ビデオリサーチインタラクティブ、オールアバウト、NTTレゾナント、日本マイクロソフト、ヤフーは、インターネット広告効果に関する共同調査プロジェクト「ネット広告バリューインデックス プロジェクト」の調査結果データを更新した。
本プロジェクトではインターネット広告認知やブランディング効果等、“インターネット広告の露出自体の効果”を検証して効果の基準値を作成することを目的としている。調査結果データの発表は2008年4月、2009年12月に続き、今回で3期目。
■調査結果データより
<インターネット広告効果の基準値>
・インターネット広告出稿時にはインターネット広告到達者の30.6%が広告を認知
・タレント/キャラクターをクリエイティブに使用した場合の認知率は、非使用にくらべ12ポイントアップ
・広告認知者の65.2%が広告内容を理解
・インターネット広告出稿により、広告到達者のメッセージ理解は広告非到達者の1.22倍、広告商品の購入/利用意向は1.15倍に
・広告到達回数の増加と共にインターネット広告認知/ブランディング効果は拡大(広告効果最大化のポイントとなる広告到達回数は“12回”)
・2,000万インプレッション出稿時の広告認知者数は228万人、商品購入/利用喚起者数は71万人
<調査結果より得られた知見>
・調査時期別でみると、広告到達回数がインターネット広告認知率に与える影響はより強力になっている
・広告サイズの拡大や広告クリエイティブのリッチ化の一層の浸透(注)などにより、広告認知者における広告内容の理解度、広告商品の購入/利用喚起やサイトアクセス意向などが上昇しており、インターネット広告効果は拡大傾向
・その他、インターネット広告とテレビ広告を連動した広告出稿は、お互いの広告認知にプラスの影響を与え合っていることが確認
とのことだ。
「トルネード」を読んだ
ITの技術会社でもサービス提供会社でもないので、自分が直接的に役に立つことはないのだが、マーケティング戦略を考えるケース・スタディーとしては非常に興味深く読めた。もちろん技術の進歩などが激しいITマーケットならではのケースなので、汎用的にマーケティングを学びたい方は、一つのケース・スタディーでしかないという位置付けで読んだ方がいい。
「キャズム」のわかり易さのインパクトに比べれば、話は多少複雑になって、ボウリング・レーン、トルネードなどという言葉が加わってくるのだが、各ステージにおける陥りがちな行動とあるべき姿など、具体的な行動指針も整理されており、このマーケットに精通している筆者ならではの物語となっている。
<目次>
第一部:市場を知りつくして、「超成長」を遂げるとき
第1章:トルネードとは何か
第2章:キャズム---飛躍の前の試練を越える
第3章:ボウリング・レーン---「ニッチ」で連鎖反応を
第4章:トルネード---ひたすら売って勝利せよ
第5章:メイン・ストリート---「勝者の壁」を攻略する
第6章:自分の立ち位置を正確につかむために
第二部:最強の戦略を練り上げ、夢を現実にする
第7章:戦略的パートナーシップの意義と問題点
第8章:優位に立つための必須条件
第9章:間違いだらけのポジショニング
第10章:実行のための社内体制強化法
発行:海と月社
著者:ジェフリー・ムーア
訳者:中山 宥
定価:1,800円+税
約330ページ
関連リンク:
書評ページをまとめた
「キャズム」のわかり易さのインパクトに比べれば、話は多少複雑になって、ボウリング・レーン、トルネードなどという言葉が加わってくるのだが、各ステージにおける陥りがちな行動とあるべき姿など、具体的な行動指針も整理されており、このマーケットに精通している筆者ならではの物語となっている。
<目次>
第一部:市場を知りつくして、「超成長」を遂げるとき
第1章:トルネードとは何か
第2章:キャズム---飛躍の前の試練を越える
第3章:ボウリング・レーン---「ニッチ」で連鎖反応を
第4章:トルネード---ひたすら売って勝利せよ
第5章:メイン・ストリート---「勝者の壁」を攻略する
第6章:自分の立ち位置を正確につかむために
第二部:最強の戦略を練り上げ、夢を現実にする
第7章:戦略的パートナーシップの意義と問題点
第8章:優位に立つための必須条件
第9章:間違いだらけのポジショニング
第10章:実行のための社内体制強化法
発行:海と月社
著者:ジェフリー・ムーア
訳者:中山 宥
定価:1,800円+税
約330ページ
関連リンク:
書評ページをまとめた
中南米のソーシャルネットワーク、Facebookが9,100万人利用で圧倒的 など
中南米のソーシャルネットワーク、Facebookが9,100万人利用で圧倒的
2011/9/21のcomScore Data Mineから。http://www.comscoredatamine.com/2011/09/top-social-networking-sites-in-latin-america/
インターネット利用者のFacebook利用率が高い国、フィリピン、トルコ、チリがトップ3
2011/9/21のcomScore Data Mineから。http://www.comscoredatamine.com/2011/09/top-markets-for-facebook-by-percent-reach/
2016年に世界で17億人がモバイルでソーシャルネットワークを利用
2011/9/21のABI Researchのリリースから。http://www.abiresearch.com/press/3776-Over+1.7+Billion+Mobile+Social+Networking+Users+in+2016+Means+Facebook+Needs+Its+Own+Operating+System
2011/9/21のcomScore Data Mineから。http://www.comscoredatamine.com/2011/09/top-social-networking-sites-in-latin-america/
インターネット利用者のFacebook利用率が高い国、フィリピン、トルコ、チリがトップ3
2011/9/21のcomScore Data Mineから。http://www.comscoredatamine.com/2011/09/top-markets-for-facebook-by-percent-reach/
2016年に世界で17億人がモバイルでソーシャルネットワークを利用
2011/9/21のABI Researchのリリースから。http://www.abiresearch.com/press/3776-Over+1.7+Billion+Mobile+Social+Networking+Users+in+2016+Means+Facebook+Needs+Its+Own+Operating+System
2011/8米ウェブサイト利用、Back to School需要で教育情報や本のサイトの利用が増加 など
2011/8米ウェブサイト利用、Back to School需要で教育情報や本のサイトの利用が増加
2011/9/21のcomScoreのリリースから。http://www.comscore.com/content/download/10249/173097/file/comScore%20Media%20Metrix%20Ranks%20Top%2050%20U.S.%20Web%20Properties%20for%20August%202011.pdf
米Twitterの短縮URLのt.co利用が急増
2011/9/21のcompeteのブログから。
http://blog.compete.com/2011/09/21/is-short-the-new-black/
2011/9/21のcomScoreのリリースから。http://www.comscore.com/content/download/10249/173097/file/comScore%20Media%20Metrix%20Ranks%20Top%2050%20U.S.%20Web%20Properties%20for%20August%202011.pdf
米Twitterの短縮URLのt.co利用が急増
2011/9/21のcompeteのブログから。
http://blog.compete.com/2011/09/21/is-short-the-new-black/
確認済み
1 時間 32 分 ago
ウェブアナリスト 宏美のブログ。WebAnalyticsの3Cデータと関連情報を提供。一つはcompetitor、市場マクロデータや競合データ。一つはcompany、自社のアクセス解析データ。最後はcustomer、ユーザー行動データ。数値の一人歩きをさせたくないので、詳しくは原典と各調査方法を確認のこと。Unknownnoreply@blogger.comBlogger9007125
Insight for WebAnalytics フィード を購読